新選組・土方歳三を中心に取り上げるブログ。2004年大河ドラマ『新選組!』・2006正月時代劇『新選組!! 土方歳三最期の一日』……脚本家・制作演出スタッフ・俳優陣の愛がこもった作品を今でも愛し続けています。幕末関係のニュースと歴史紀行(土方さんに加えて第36代江川太郎左衛門英龍、またの名を坦庵公も好き)、たまにグルメねた。今いちばん好きな言葉は「碧血丹心」です。
二日続けて記事をアップするのは久しぶりです。
岩手
「復興助太刀」 新選組が集結 宮古で全国サミット
岩手
「復興助太刀」 新選組が集結 宮古で全国サミット
岩手県宮古市で5日、第12回全国新選組サミットが始まった。幕末に活躍した新選組の全国の同好会10団体や地元有志ら120人が集まって演武などを繰り広げ、会場を沸かせた。
初日は宮古駅前広場で、鍬ケ崎小の児童が大漁祝い唄でサミットを歓迎。参加者は土方歳三ら新選組隊士の装束をまとって演武を披露し、「誠」の旗を掲げて商店街をパレードした。
宮古湾は1869年、土方ら旧幕府軍が新政府軍に海上戦を挑んだ「宮古湾海戦」の舞台となった。その縁もあり、昨年12月にサミットの開催地に決定。東日本大震災でいったん立ち消えになったが、震災復興の応援の場にもしようと、関係者の後押しで開催にこぎ着けた。地元有志代表で、宮古観光協会の沢田克司会長は「全国の同好会から宮古を元気づけたいという言葉をもらった。仲間との絆が強まったと感じている」と話した。
サミットは6日、宮古湾海戦の戦没者、震災の犠牲者を海上から弔う供養をする。
月一回ペースになってしまいましたが、山内先生の連載が自分的にツボな人物を取り上げているのでまとめます。
岩手
新撰組ファン、宮古に集まれ 5、6日に全国サミット
あれっ?み~んな土方歳三 宮古で写真展
静岡
幕末のパン 江川坦庵の製法書もとに再現…静岡
江川英龍の功績のごくごく一部だと思いますが、話題になるのは嬉しいです。
京都
近藤勇 直筆の「英雄論」初公開 東山・霊山歴史館
山口
奇兵隊祭:幕末の志士らを慰霊 吟詠や勇壮な剣舞も披露--下関・桜山神社 /山口
コラム
【幕末から学ぶ現在(いま)】
(133)東大教授・山内昌之 松平定敬(上)
【幕末から学ぶ現在(いま)】
(134)東大教授・山内昌之 松平定敬(下)
【幕末から学ぶ現在(いま)】
(135)東大教授・山内昌之 市川三左衛門
【幕末から学ぶ現在(136)】
吉田松陰・番外編(上) 東大教授・山内昌之
エンターテインメント
ミュージカル「薄桜鬼 斎藤一編」 来春、美少年たちが乱舞
美少年といわれるとちょっと引きます……『薄桜鬼』斎藤一は青年だと思うので(笑)。
”薄桜鬼”がアクションゲームとなって登場!PSP「薄桜鬼 幕末無双録」2012年2月23日発売
岩手
新撰組ファン、宮古に集まれ 5、6日に全国サミット
新撰組ファンが一堂に集う「第12回全国新選組サミットin宮古」は5、6の両日、宮古市内で開かれる。震災の影響で開催が危ぶまれたが、関係団体などの協力で復興支援事業として実現。チャンバラや土方歳三の子孫によるトークショーなど子どもから大人まで楽しめる。
オープニングセレモニーは5日、同市宮町1丁目の宮古駅で行われる。女性パフォーマンス集団が、新撰組と敵軍に分かれてチャンバラを行う「殺陣(たて)パフォーマンス」や全日本刀道連盟の真剣を使った演武などが繰り広げられる。
鍬ケ崎小体育館では、新撰組副長の土方歳三の子孫、土方愛さんと幕末好き歴史アイドル小日向えりさんによるトークショーを開催する。
例年、新撰組と関わりのある地域で開かれ、県内での開催は初めて。宮古市では1869(明治2)年、旧幕府軍と明治新政府軍による宮古湾海戦が繰り広げられた。
【写真=5、6の両日開かれる新選組サミットのポスター。さまざまなイベントが予定されている】
あれっ?み~んな土方歳三 宮古で写真展
新撰組の土方歳三に扮(ふん)した写真を応募する「土方歳三・写真コンテストin宮古」の作品展は6日まで、宮古市の宮古駅前総合観光案内所で開かれている。
作品展は5、6の両日に同市で開催される「第12回全国新選組サミットin宮古」(実行委主催)関連のイベント。
全国各地から応募のあった23点を展示。どの作品も、洋装姿の土方歳三へのなりきり具合が際立つ。土方は、明治初期の宮古湾海戦(1869年)に参戦しており宮古とも縁がある。
先月開かれた審査会で、埼玉県の男性が最優秀賞を受賞した。受賞写真のモデルは、サミット初日に行われる「新選組パレード」の先頭を歩く予定だ。
宮古観光協会の山口惣一事務局長は「応募者それぞれの本気度がよく出た作品と思う」と作品を見つめる。
【写真=土方歳三へのなりきりぶりがユニークな写真展】
静岡
幕末のパン 江川坦庵の製法書もとに再現…静岡
日本で初めて兵糧用のパンを製造し、「パン祖」と呼ばれる幕末の韮山代官、江川坦庵(たんなん)(太郎左衛門英龍)が記したパンの製法書が新たに見つかり、静岡県函南町の製パン会社「石渡食品」が再現した。
まだ試作段階だが、同社は、坦庵が1842年(天保13年)に兵糧用のパンを初めて試作したとされる日にちなんで「パンの日」と制定された、来年の「4月12日」の発売を目指して、改良を重ねている。
新たに見つかった製法書は、「カーネルコックカステイラ」と名付けられたパンのもの。すでにポルトガルから伝わっていたカステラを意味する「カステイラ」に、当時アジア地域で活躍していたオランダの外交官「カーネルコック」の名前を付けたと思われる。
製法書は昨年8月に発見され、日付などは入っていないが、坦庵の直筆。縦66ミリ、横55ミリの円形で、厚さ1センチほどにこんもりと盛り上がった完成イメージとともに、「麦粉百六十目 砂糖四十目 玉子(たまご)五ツ」(1目は3・75グラム、小麦粉600グラム、砂糖150グラム)という材料や、「右三味水にてこね、焼なべにて焼」「焼ナベに油を引(ひき) 狐(きつね)色に焼申候(やきもうしそうろう)」という作り方が墨で記されている。
同社は、今年7月下旬に試作品を製作。8月1日からグランシップ(静岡市駿河区)で開催された展覧会「江川坦庵とゆかりの人々」(県など主催)で、来館者500人に配布した。
江川家に伝わる史料を保管している「江川文庫」(伊豆の国市)の職員、橋本敬之さん(59)によると、坦庵の作ったパンの製法書としては、部下から坦庵に宛てられた書簡が以前から保管されていた。そこに書かれているパンは、小麦と塩を使用し、乾パンのような固さとさっぱりした塩味で1年以上日持ちするもので、これを兵糧用に作ったと見られている。
これに対し、「カーネルコックカステイラ」は、さくさくとした食感でパンというよりお菓子に近い味わい。試作した同社の石渡浩二社長(60)は「当時は砂糖が貴重品のうえ、砂糖を使うと日持ちしなくなるので、兵糧には向かない。日持ちして備蓄しやすい小麦と塩を使う製法が広まったのではないか」と見ている。
石渡社長は「カーネルコックカステイラは、現代風に砂糖の量を増やすなどのアレンジを加えて作ろうと思う。地元の人に親しまれる商品に仕上げたい」と話している。
(2011年10月25日 読売新聞)
江川英龍の功績のごくごく一部だと思いますが、話題になるのは嬉しいです。
京都
近藤勇 直筆の「英雄論」初公開 東山・霊山歴史館
新選組局長として有名な幕末の剣豪、近藤勇が「英雄論」を記した直筆の漢詩が、京都市東山区の霊山歴史館で初公開され、注目を集めている。「まことに英雄の心中を理解できるならば、英雄ではないことが英雄である」との内容が達筆で書かれており、読書家でもあった近藤の実直な人柄が伝わる。
■京で発見 商家へ借金の返礼?
縦136センチ、横60センチの紙に七言絶句の詩形で書かれ、掛け軸に仕立てられている。広島県の医師が京都市内の古美術店で見つけ、霊山歴史館に鑑定を依頼。木村幸比古学芸課長は、数点見つかっている近藤の他の漢詩と筆跡や落款が酷似することから真筆とした。
漢詩は、前半で「人に知られず暮らすべき。議論するばかりの俗人と同じではいけない」と姿勢を論じ、後半は「英雄」の文字を3度繰り返している。詩の脇に添えられた「有感作」の言葉から本心を表現した詩とみられ、「剣客士 近藤書」と記されていた。
木村学芸課長は「目立とうとせず、行動する生きざまの大切さを説くことで、議論に熱心だった当時の倒幕派の志士を皮肉ったのではないか」とみる。
同館によると、近藤が文久3(1863)年に京都入りし、市中警備を担う新選組の拝命を受けるまでの間に、給金がなく、商家から軍資金を借りていた時期があり、今回の漢詩も借金の返礼として書かれた可能性があるという。
特別展「龍馬と土佐の衝撃」(12月26日まで)に合わせて公開する。土佐勤王党盟主の武市半平太が切腹時に使った短刀や、その時の血痕が残る襦袢(じゅばん)など幕末の史料約100点も並んでいる。
月曜休館。霊山歴史館TEL075(531)3773。
山口
奇兵隊祭:幕末の志士らを慰霊 吟詠や勇壮な剣舞も披露--下関・桜山神社 /山口
幕末、長州など各地で起きた戦争や紛争で亡くなった奇兵隊士らを祭る下関市上新地町の桜山神社で4日、第29回奇兵隊祭が厳かに執り行われた。旧下関市の45歳以下の神職が集まる下関青年神職会(野村正和会長)が主催した。
桜山神社は、長州藩が諸外国と戦った下関戦争(1863~64)の犠牲者を弔うため、長州藩士の高杉晋作(1839~67)が創建した。その後の倒幕運動で亡くなった志士をはじめ、幕末の思想家、吉田松陰(1830~59)ら396人を祭っている。
神事では、西日本地区屈指の吟詠コンクールとして知られる毎日吟士権大会審査員で、湖舟流吟剣詩舞道江湖会宗家、一木湖舟さんが「おくれても おくれても また君たちに ちかひしことを あにわすれめや」と、晋作が亡き隊士らにささげた歌を高らかに朗詠。妻江舟さんも勇壮な剣舞を披露。明治維新を待たずに散っていった志士らの御霊(みたま)を慰めた。【尾垣和幸】
コラム
【幕末から学ぶ現在(いま)】
(133)東大教授・山内昌之 松平定敬(上)
政治家の連携と牽制
民主党政権の二元外交の危険がささやかれている。前原誠司政調会長と玄葉光一郎外相との、アメリカや韓国での発言の微妙なズレを危惧する人も多い。
しかし、子細に観察すれば、2人の間には外交理念や政策をめぐる齟齬(そご)というよりも、経験や知識の差からくる格の違いが二元外交めいた印象を与えていることがすぐ分かる。
玄葉氏は、10月に韓国を訪問し金星煥(キム・ソンファン)外交通商相と会談したときに「日韓は死活的利益を共有している」という不用意な発言をした。竹島問題や「従軍慰安婦」といった外交懸案をかかえている2国が同盟国でもないのに、「死活的利益を共有」するはずもない。
それでいながら、8月に韓国の憲法裁判所による元慰安婦の個人補償請求権に関する判断を受けた韓国政府の対応に、「請求権問題は解決済み」という紋切り型の回答をした。これは“政治主導”を自負する政党の政治家らしくない。そこで韓国政府は慰安婦問題の国連提訴の準備を進め、問題の国際化を図ろうとしたわけだ。
玄葉氏は訪韓してもこの問題を解決できなかった。そこで次に訪韓した前原政調会長は、「人道的な観点から考える余地がないか、お互い知恵を出し合い静かな環境で議論したい」と述べて外交的解決への道筋を示したのである。元外交官の佐藤優氏が述べるように、「静かな環境」とは慰安婦問題を国際化しないという意味なのだ。これこそ民主党が本来目指す外交の“政治主導”というべきであろう。こうした踏み込みは、どれほど優秀であっても職業外交官には越軌(えっき)になるからだ。
page: 2
見習うべき兄弟の相互補助
佐藤氏は、両者の外交技能を兵隊の位に直せば、玄葉氏が下士官、前原氏が将官だと厳しく言い切っている。ただ玄葉氏の知性と闊達(かったつ)さを考えればもちろん士官は間違いなく、前線の部隊指揮官と帷幄(いあく)にある高級指揮官の感覚、大隊長と師団長の職位感覚の差くらいでもあろうか。
この差は、謙虚さや経験の積み重ねの有無に起因するものだ。謙虚さというのは、同じ松下政経塾8期生としての意地やライバル心にこだわらず、外交では一日の長のある前原氏に兄事し、時にはその経験に頼るのも大事ということだ。この点で見習うべきは、幕末に京都の治安警護の任にあたった会津藩主松平容保(かたもり)と桑名藩主松平定敬の兄弟による連携と相互補助であろう。
京都守護職の容保と京都所司代の定敬は、美濃国高須藩(岐阜県海津市)藩主松平義建(よしたつ)の実子であり、外に養子に出された。兄の尾張藩主徳川慶勝(よしかつ)、一橋家の養子となった茂栄(もちはる)とともに「高須四兄弟」と呼ばれる。いずれも“子柄”のいいという表現がぴったりくる、気品と才気にあふれた兄弟であった。
定敬は、松平定信(老中、8代将軍吉宗の孫)で知られる白河・桑名松平家へ養子に入った後、元治元(1864)年に京都所司代に任命された。すでに実兄の松平容保(会津藩主)は文久2(1862)年に京都守護職になっており、元治元年には一橋慶喜(よしのぶ)も禁裏御守衛総督(きんりごしゅえいそうとく)に任じられていた。いずれも新設の職である。その直後、文久3年の将軍家茂(いえもち)の上洛以来、京都警固の任にあった定敬も京都所司代に任命された。
page: 3
徳川幕府の草創期に設けられた京都所司代は、2代目の板倉勝重の治績で知られた重職であり、並の町奉行職ではない。京都の治安維持、朝廷・公家の監察、西国大名の監視、五畿内と近江、丹波、播磨8カ国の民政が当初の職務であった。
とくに初期は家康、秀忠、家光がたびたび上洛したために、所司代は将軍の権威を上方にあまねく広げて朝廷に睨(にら)みをきかせる職でもあった。民生の権限が京都町奉行へ委譲された後、所司代は大坂城代を経て幕府老中に上りつめる譜代大名のキャリアパスの一部となる。
しかし、この職掌の変化が京都所司代の治安維持機能を低下させた結果、所司代と町奉行の警察機能だけでは尊皇攘夷(じょうい)派浪士の跳梁跋扈(ちょうりょうばっこ)を取り締まれず、守護職が置かれたのである。
京都の治安と外交は「会桑」
とはいえ、いずれも会津藩と桑名藩という溜間(たまりのま)、すなわち江戸城内の将軍に近い高位席次、黒書院溜之間(くろしょいんたまりのま)に伺候(しこう)した代表的家門・譜代大名の精鋭部隊が直接京都に進駐し、その最高責任者が実の兄弟であったという重みは大きい。こうして幕末の京都の治安と外交は、江戸の将軍老中の手を離れて、京都で独自の勢力を形成する会津と桑名の両藩、略して「会桑」、一橋慶喜も加えて「一会桑(いちかいそう)」と呼ばれる権力によって担われることになった。
page: 4
「会桑」や兄弟の連携は、時に藩の利害を伴う相互牽制(けんせい)で複雑さを帯びるが、それは同じキャリアパターン(松下政経塾)をもつ者同士が協力しながら時には反発する政治の宿命に共通するともいえよう。(やまうち まさゆき)
◇
【プロフィル】松平定敬
まつだいら・さだあき 弘化3(1847)年、美濃(岐阜県)高須藩主松平家の七男として生まれる。伊勢(三重県)桑名藩主松平家に養子に入り安政6(1859)年に家督相続。元治元(1864)年、京都所司代となり京都の治安維持にあたる。戊辰戦争では主戦論を説くが敗北。明治2(1869)年、伊勢の津藩に預けられ、5年に許された。41年死去。
【幕末から学ぶ現在(いま)】
(134)東大教授・山内昌之 松平定敬(下)
敗者復活戦の美学
伊勢国(三重県)桑名藩主・松平定敬(さだあき)は、テロの跳梁跋扈(ちょうりょうばっこ)する京の都で所司代を務めた。兄の会津藩主松平容保(かたもり)が京都守護職を引き受けたのと同じく、天皇の座所と市街地を守る治安維持のためである。
鳥羽伏見の戦いで敗れても、東国大名の兄、容保であれば、京都を引き揚げて会津という国元に下がればよい。しかし京に近い桑名となれば、そうもいかない。
柏崎に移り抵抗覚悟
徳川慶喜(よしのぶ)の姦計(かんけい)にたばかられ無理やりに大坂城を捨て江戸表(えどおもて)に連れていかれた定敬は、この“敵前逃亡”を恥とした。戦闘意欲は衰えなくても、徹底抗戦を貫く力は桑名藩の留守方には残っておらず、定敬の帰国も困難であった。
事実、新政府軍の来襲を恐れた桑名の国元は、先代当主の遺児・万之助(後の定教(さだのり))を跡目に立て恭順することを決める。そこで定敬は、桑名藩の分領である越後国(新潟県)柏崎に移って抵抗する覚悟を固めた。
柏崎には、藩中興の祖たる松平定信が白河藩主だった時分から陣屋が置かれていた。桑名本領の石高は5万石なのに、柏崎領は6万石を誇っていた。しかも、米どころ越後の分領の実高は7万石以上だったという。そこで100名の藩士たちは定敬に従って、ロシア船コリヤ号に乗り柏崎を目指したのである。
page: 2
横浜を出帆した船には、会津藩士100名、長岡藩士150名も乗っており、北越戦線でやがて活躍する長岡藩のガットリング機関砲2門はじめ、大量の武器弾薬を満載していたらしい。
この時、ひとまず江戸に残留した藩士のなかには、やがて雷神隊を指揮して新政府軍をさんざんに打ち破る立見(たつみ)鑑三郎(尚文(なおふみ))もいた。
24歳の立見が率いた75人の雷神隊はじめ、致人(ちじん)隊や神風隊など350人ほどの桑名勢は、佐川官兵衛の会津隊、旧幕府歩兵差図役頭取だった古屋佐久左衛門の衝鋒(しょうほう)隊と並んで奥羽越で精強をうたわれた兵力にほかならない。北越戦争では桑名勢の活躍によって「官賊」はしばしば潰走を余儀なくされた。主人定敬の面目躍如というべきであろう。
定敬は北越と会津の2つの戦線で実兄、容保と一緒に新政府軍と戦ってきたが、ついに別れの時がきた。戦況思わしくなく、容保は自分を「阿兄(あけい)」(兄を親しんで呼ぶ敬称)と呼び慕ってきた実弟を会津籠城に付き合わせ桑名藩の社稷(しゃしょく)を危うくすることに忍びなかった。
このために定敬は、会津を去って仙台に向かい榎本武揚の幕府艦隊に身を投じて箱館へ渡った。
page: 3
ところが、本藩では家督の継承も無事に済ませ本領も安堵(あんど)されたのに、前藩主がいつまでも弓を引いていると聞こえも悪いどころでない。“朝敵”として藩全体に累が及ぶかもしれない。そこで桑名藩家老の酒井孫八郎はひそかに横浜から箱館に渡り、主君、定敬を説き帰順を勧めた。この結果、定敬はアメリカの蒸気船に坐乗(ざじょう)して箱館を去り、榎本軍降伏の当日に横浜に入った。まもなく尾張藩を通して新政府に帰順の意を伝えたのである。
卑怯未練、少しもなく
定敬は、将軍慶喜の恭順後も戦い続けたのだから、徳川恩顧の義理を十二分に尽くしたつもりであった。また、幕末以来ずっと戦い抜いてきた薩長への意地も貫いた気分だったに違いない。定敬の姿勢や覚悟には、どこを捜しても卑怯(ひきょう)未練な点は少しもない。また、明治10(1877)年に起こった西南戦争では、旧桑名藩士を率いて出征し薩摩人と思う存分に戦うこともできた。会津人ひいては実兄の容保と同じく、“戊辰の復讐(ふくしゅう)”を果たしたともいえる。さしずめ“朝敵回り持ち”ともいうべき不思議な縁を感じたはずである。
作家の中村彰彦氏は、『闘将伝』(文春文庫)のなかで、「前譴(ぜんけん)を償い報効を表わさんとする旧桑名藩士は、旧臣立見尚文に従ってすべからく義勇奉公すべし」という趣旨の定敬の一文を紹介している。
page: 4
定敬の許可を得て三重県に出張した立見は、450人の募集者を得たが、そのうち桑名人の応募は304人であった。
また、会津藩領を含む福島県からは1136人が応募している。桑名と会津の両藩出身者で全国の応募者1万3千人の1割以上を占めたのである。“賊徒”や“朝敵”と名指しをされた者たちの深い恨みは、貴種の松平定敬と容保の兄弟にも共通していたに違いない。
定敬は兄の後を継いで日光東照宮宮司の職を襲い、やがて従二位に叙せられて死没するのだから、まずまず以(もっ)て瞑(めい)すべしともいうべき生涯であった。立見は西南戦争終盤の城山攻略戦の最前線で最大の功労者となり、桑名人の名声を高からしめた。
このように“敗者復活戦”がそれなりに機能していたのが日本人の隠れた歴史的美徳である。
尊敬されるリーダーは
さて、政権交代を余儀なくされた自民党には浪々の日々が続く。果たして自民党は敗者復活を果たせるのだろうか。定敬や容保のように部下や民から慕われ尊敬されるリーダーを試練のうちに育てられるのだろうか。野党としての精彩の欠如が気になるところだ。(やまうち まさゆき)
【幕末から学ぶ現在(いま)】
(135)東大教授・山内昌之 市川三左衛門
「政治のねじれ」の厳しさ
「ねじれ」とはもともと、数学で空間内の2本の直線が平行でなく、交わっていない状態を指すようだ。つまり同一平面に2直線が乗れない場合の互いの位置関係を意味した。この用語は、いまの政界では衆議院の多数派たる政権与党が参議院では少数派になり、野党が多数派を占める不規則な状態をもっぱら指す。「ねじれ国会」においては、与党の法案が参議院を通らず政権運営が袋小路に陥ることが多い。
平成19年の参議院選挙以後に常態化した「ねじれ国会」は、自民党の安倍晋三元首相や福田康夫元首相の退陣につながることになった。二院制の議会がこうした状態をまったく想定していなかったとは言いきれない。
そもそも、離合集散が習いの政治では与野党間に外交安全保障や財政金融政策などをめぐってねじれが生じることが珍しくない。綱領をもたない民主党内部では日米同盟すら否定しかねない首相も出るありさまであり、かえって与野党の一部が政策面で近づくねじれが現れている。
党争が恒常化した水戸藩
幕末で政治的なねじれが恒常化していたのは、水戸藩であろう。その藩主徳川斉昭(なりあき)は宗家の社稷(しゃしょく)を守るべき御三家の一員でありながら、尊皇攘夷(じょうい)派の首魁(しゅかい)としてことごとに幕府の開国外交の足を引っ張る異様さであった。そもそも天皇中心の国家をつくるということは、政権を委任された幕府の威信と地位を相対的に低めることになるのだが、この矛盾をついに解決しきれず、幕末の水戸藩は凄惨(せいさん)な内部党争の末に自壊してしまった。
page: 2
水戸藩のねじれは政治構造だけでなく、藩士の人間関係にも悲劇をもたらした。なかでも、天狗(てんぐ)党などの尊攘派から保守派門閥と忌み嫌われた市川三左衛門の立ち位置は、ねじれの矛盾の中心にいた故の悲劇で特徴づけられる。
彼は小納戸頭、小姓頭、馬廻(うままわり)頭、大寄合(おおよりあい)頭などの要職を歴任し、門閥の諸生(しょせい)党のリーダーとして天狗党はじめ尊攘過激派と対立する宿命にあった。尊攘派による改革を牽引(けんいん)した徳川斉昭の死去後、藩主慶篤(よしあつ)は藩論の分裂を抑えきれず、いまや伝説の域に入った藩内抗争は激しさを増す一方であった。
政治のねじれは、筑波山を占拠する天狗党など過激派の動きを鎮静化しながら水戸藩の一体性を回復しようとした藩主名代の常陸宍戸藩主、松平頼徳の奇妙な役割にも象徴されている。本来なら頼徳は、水戸城にいちはやく入り市川らを謹慎蟄居(ちっきょ)させる慶篤の意向を伝えて挙藩一致の姿勢を固めるべきなのに、武田耕雲斎(こううんさい)ら激派の供(とも)を許し藤田小四郎ら天狗党が軍列に従う既成事実をやむなく追認してしまった。
討伐すべき対象の天狗党と一緒になって水戸城の国家老たちを罷免する動きを示し藩兵とも戦うはめになったのだから、これ以上の政治のねじれはないだろう。市川はこのねじれを幸いに、支藩の藩主たる頼徳が天狗党に通牒(つうちょう)しているとして、幕府に強い処分を要求する。この結果、頼徳は切腹を命じられた。頼徳は何の因果で名代でありながら死を賜(たま)わったのか、自分の運命を呪うような気分であったろう。
page: 3
「忠が不忠になるぞ悲しき」
市川は幕府の援助を受けて天狗党を敗走させた後、執政として藩の最大実力者となったが、よいことばかりではない。天狗党の家族まで処刑した市川は、大政奉還から鳥羽伏見の戦いにいたる政治情勢の急展開と、水戸藩出身の将軍慶喜の水戸謹慎による政治構造の逆転で、思いがけず野党の立場に落とされた。これもねじれなのである。
市川に言わせるなら、諸生党対天狗党の対立といっても藩内の主権をめぐる争いであり、自分たちは京都の朝廷や官軍に弓引くものでないという気分があった。しかし、政治の全国性を見ない屁理屈というものである。このあたりの市川の心理状態は、穂積忠氏の最新作『忠が不忠になるぞ悲しき』(日新報道)にもよく描かれている。
京都では天狗党の別動隊ともいうべき本圀寺(ほんこくじ)党が慶喜を一貫して警護していたが、鳥羽伏見の敗戦以後は官軍としての旗幟(きし)を鮮明にし、故郷の水戸に迫る勢いを示した。水戸に来る官軍が薩長や他藩の部隊なら市川も恭順していたかもしれない。しかし、凄惨な血の復讐(ふくしゅう)が待っている運命を甘受する気は更々なかった。
市川は、諸生党を率いて水戸を脱出、奥羽と越後の各地を転戦して新政府軍と戦う。諸生党の勇敢な戦いは戊辰戦争の隠れたクライマックスである。会津落城後の落魄(らくはく)ぶりと悲惨な境遇には驚きを禁じえない。
行き場のない市川らはまたしても水戸へ帰還し、藩校弘道館に拠(よ)りながら水戸城の本圀寺党らと「弘道館戦争」を展開した。市川は2人の息子を失いながら下総方面へ敗走して、勢力としての諸生党は壊滅した。
page: 4
この後、江戸に潜伏した市川は、藩の捕吏に縛されて水戸へ移送され逆磔(さかばっつけ)の極刑に処された。血が逆流して意識を失うまで逆さ吊りにし、また正常位に戻して意識を回復させるサイクルを繰り返す残酷な刑である。市川三左衛門の辞世は、政治が本当にねじれた場合の厳しさを現代人にも教えるかのようだ。
君がため捨つる命は惜しまねど忠が不忠になるぞ悲しき(やまうち まさゆき)
◇
【プロフィル】市川三左衛門
いちかわ・さんざえもん 文化13(1816)年、水戸藩士の家に生まれる。大寄合頭、家老など藩の要職を歴任。元治元(1864)年の天狗党の乱では、佐幕派の諸生党を率いて天狗党関係者を徹底的に弾圧し、自ら執政となり藩の実権を握る。戊辰戦争では各地を転戦した末、国外逃亡を図るが捕らえられ、明治2(1869)年に処刑された。
【幕末から学ぶ現在(136)】
吉田松陰・番外編(上) 東大教授・山内昌之
教えながら学ぶ人
晩秋の10月も押し迫ってから長州萩に出かけてきた。萩博物館で「世界史のなかの吉田松陰」と題して講演するためである。
萩は現在でも、古地図さながらに由緒ある街並みと武家屋敷のたたずまいを残している。この静かで穏やかな住人に接すると、幕末に狂気をはらむエネルギーを発散させた長州人と共通するものがないかに見える。萩市役所や博物館の皆さんはどこまでも物静かで親切このうえもない人たちだからである。
しかし、講演が終わって質疑に移ると、穏健な萩人の内面にひそむ歴史への誇りと先人への奥ゆかしい尊敬心がにじみ出てくる。こと歴史となると、人びとは熱く過去を語り現在に及ぶのである。なかでも「松陰先生」と必ず敬称をつけるのがならいの地では、松陰への敬愛の念が自然ににじみ出てくる人も多く、職業柄歴史上の人物を呼び捨てにする私などはいかにも“異邦人”めいた存在というほかない。それでも、外から来た人間、それもイスラムや中東を本来の専門とする学者の松陰論を虚心坦懐(きょしんたんかい)に聞いてくれるあたりに萩人の懐の深さがあるといえよう。
松陰の生きた時代は、環太平洋戦略的経済連携協定(TPP)への加盟交渉への参加すら逡巡(しゅんじゅん)し、円高・金融不安に揺れながら、まかりまちがえば沖縄県民の離反を招きかねない日米関係の歪(ゆが)みが進行する現在と共通する点も少なくない。
松陰は、外国人の圧迫で日本が消滅しかねない危機の深化のなかで、日本史と世界史が人びとの日常生活から外交安全保障に至る多領域で切迫した危機を最初に意識した日本人の一人である。
page: 2
明治維新の精神的指導者、吉田松陰の肖像 (国立国会図書館蔵)
焦りにも似た義務感
浦賀にペリーの黒船到来と聞くと、松陰は矢も盾もたまらず夜に船を出したが船脚は遅く、風も潮も思わしくなく翌朝10時にやっと品川に着いた。すぐに上陸し陸路で目的地に向かい、夜10時にたどり着いた。
この行動力こそ現代人が松陰から学ぶべき点である。船の方が理屈では早く着き、身体にも疲れが残らないはずだ。しかし自分だけの楽や、わがままを求めないのが松陰なのだ。
風も潮流も順調でなく思いや気だけはせく一方である。それでも、浦賀に寸秒も遅れずに見るべきものがあると信じるからこそ、自分の目で見届けたいのだ。何をおいても気迫が理屈に勝るのが松陰なのである。
自分の見聞が一秒でも遅れるなら、国の滅びもそれだけ早まると考えるのが松陰の発想であった。この焦りにも似た義務感が松陰に陸路をとらせ昼夜兼行の強行軍となった原因である。松陰も初めて見た蒸気船の威容に度肝を抜かれた。
松陰は、日本の台場(砲台)にある大砲の数もすこぶる少ないと地団太(じだんだ)を踏んでくやしがる。こうした混乱状況で松陰の師筋たる佐久間象山と塾生たちも多数集まってきたが、「議論紛々に御座候」と師たちも周章狼狽(しゅうしょうろうばい)するありさまが手にとるように分かる。松陰が幕府の老中など門閥大名はもとより象山とも違うのは、国際情勢など冷静に分析し、何故に日本がかかる事態に陥ったのかを学び、何をなすべきかを検討するあたりであろう。松陰といえば熱情をすぐに連想するが、緻密な冷静さでも際立っていたのである。
page: 3
明治維新の精神的指導者、吉田松陰の肖像 (国立国会図書館蔵)
東アジアの国際戦略
松陰は、遅れた軍事力を抱えたまま国際政治のパワーポリティクスに対面した日本が外国軍艦の襲来に対処できる道筋を考えた。第一は西洋兵学の採用による軍事的近代化と貿易勧業による富国強兵への道である。第二は、「帝国主義の時代」が近づく19世紀半ばの東アジアで国際戦略を作りあげることだった。
松陰は、養家の吉田家が山鹿流兵学を教える師範であり、軍事戦略にも関心を示したのも当然である。吉田寅次郎こと松陰は、わずか10歳で藩校明倫館で兵学を講義し、11歳で御前講義をした神童の誉れ高い少年であった。それでいて才に溺れ傲慢になることもない。西洋式の大砲や軍艦の購入や製造から洋式訓練や陣立の導入、外国語教育の実施など説く方向は多岐に渡っていた。
松陰は人に向かって説教するだけでなく、自らも西洋兵法を学ぶことを決意した。懸案があれば、教師でありながら生徒として新たに学ぼうとするのだ。松陰の底知れぬ謙虚さはいつも向学心に結びつくのである。TPPの問題などに直面して狼狽する政治家に必要なのは、松陰のように「教えながら学ぶ」「学びながら教える」といった柔軟な姿勢であろう。(やまうち まさゆき)
◇
【プロフィル】吉田松陰
よしだ・しょういん 文政13(1830)年、長州(山口県)藩士の家に生まれる。藩校明倫館を経て、諸国を遊学。佐久間象山に蘭学や砲術を学ぶ。安政元(1854)年、停泊中のペリー艦隊に乗り込み密航を訴えるが、拒絶され投獄。出獄後、萩で「松下村塾」を開き、高杉晋作ら明治維新で活躍する人材を多く育てた。安政6(1859)年、安政の大獄により江戸で処刑された。
エンターテインメント
ミュージカル「薄桜鬼 斎藤一編」 来春、美少年たちが乱舞
美少女たちの躍動が見られる映画があれば、美少年たちの熱い戦いを見られる舞台もある。エンターテインメント企業のマーベラスAQL(東京都品川区)が来年春に開催予定の「ミュージカル 薄桜鬼(はくおうき) 斎藤一編」は、人気の恋愛シミュレーションゲームで、テレビアニメーション化もされた作品の舞台版。原作では新選組の隊士たちが闇の存在を相手に戦うストーリーのなかに、隊士たちの過去や、互いの関係が描かれ、女性ファンを引きつけた。
ミュージカルは、殺陣のシーンが評判の劇団「30-DELUX」とのコラボレーションで展開。斎藤一役に松田凌(りょう)、沖田総司役に廣瀬大介と、ともに20歳の若手俳優を起用して、アクションもあれば歌もダンスもある情熱のステージを繰り広げる。
「斎藤一役をやらせていただけると聞いたとき、頭の中で整理がつかないくらいうれしかった」と松田。「うれしい気持ちだけでは演じられない。責任を果たせるように頑張りたい」と、大役への強い意欲を見せた。廣瀬は「課題は殺陣。歌もダンスも演技も未熟だが、殺陣は初めての挑戦になるので、沖田総司と思ってもらえるよう頑張る」と、沖田役に向かう決意を示した。
(谷口隆一、写真も/SANKEI EXPRESS)
美少年といわれるとちょっと引きます……『薄桜鬼』斎藤一は青年だと思うので(笑)。
”薄桜鬼”がアクションゲームとなって登場!PSP「薄桜鬼 幕末無双録」2012年2月23日発売
ばったばったとなぎ倒す、爽快アクションここに開幕。
アイデアファクトリーより、PSP専用ソフト「薄桜鬼 幕末無双録」が2012年2月23日に発売される。
同作品は、アドベンチャーゲーム「薄桜鬼 新選組奇譚」をモチーフにした爽快アクションゲーム。プレイヤーは、薄桜鬼に登場する新選組の隊士となって、新選組を勝利に導く事になる。
また、公式webサイトでゲーム画面のスクリーンショットも公開されている。
なお、「薄桜鬼 幕末無双録」」の価格は通常版6,090円(税込)、限定版8,190円(税込)。
【記事:フェイトちゃん】
今月は3回も鈴本に通えた。神奈川音楽堂の談春師匠も聴けた。だから満足……と言い切れないのは、仕事の都合で有楽町朝日ホールの談春独演会のチケットを友人に譲った無念がちょっと残っているから^_^;。
国立西洋美術館「ゴヤ展」を見たついでに、上野公園内の彰義隊の墓に手を合わせ、上野藪そばで昼食、アメ横をぶらぶらして、最後は鈴本演芸場の夜席。今日は橘屋文左衛門師匠がトリ。
バリトン声に弱い自分、ドスのきいた文左衛門師匠の声を聴きたくなって。
けい木「寿限無」
林家木久扇師匠の前座さんだとか。若者だなぁ。
朝太「子ほめ」
権助が「このぶんじゃ山は雪だんべえ」と言う小咄から、子ほめへ。真打に抜擢が決まっただけあって、余裕たっぷりの「子ほめ」。自分にはちょっと、演技過剰な感じがしたけど。
仙三郎社中「太神楽」
寄席の吉右衛門こと仙三郎師匠の土瓶芸、毎回どきどきします。
三之助「黄金の大黒」
たぶん生でも聴いたことがあるはずなのだが、あまり自分には刺さらないネタだった。三之助さんの噺でやっと楽しめたかな。
菊丸「宗論」
息子が入れあげる教会に来日した神父の名前がクリスチャンディオールルイヴィトンだったり、ちょこちょこと手を入れてくれているので楽しんだ。物まねが入った歌手が誰だったのか、よくわからなかったけど(^_^;)。
ホンキートンク「漫才」
何度も聴いてるけど、漫才の中ではロケット団に次いで笑わせてくれる。
はん治「ぼやき居酒屋」
はん治さんはほとんどこれしか聴いてない。でも鉄板。
雲助「身投げ屋」
初めて聴いた。さすが五街道雲助、何を聴いても安心して心身を任せられる。
中入り
カンジヤママイム「パントマイム」
大人のメルヘン、ピノキオならぬヒノキオが面白かった。
五明楼玉の輔「ざいぜんごろう」?
大半は落語家の噂話。池袋演芸場で数少ないお客さんを相手にした時とか、落語家二世たちの生態とか、定番だけどやっぱり笑わせる。正蔵三平兄弟と木久蔵くんの小咄は、鉄板。
そして、患者さんに癌を告知しなければならない、頼りない医者の話に。癌を初めて告知するお医者さんが、看護師さんのアドバイスに従って、患者さんの脈を取りながら「がんもどき」とか「ガンジー」とか言葉を投げかけて反応を見るって展開。
ぺぺ桜井「ギター漫談」
「禁じられた遊び」を弾きながら演歌を歌えるって、やはり、凄い。
橘屋文左衛門「天災」
聴いたことがあるような気がしていたが、どうやら文左衛門師匠の「天災」は初めてだったらしい。「っぴらごめんねぇ」「表ぇ出ろ」が口癖の、とんでもなく喧嘩っ早い八五郎が笑える。それを引き立てる辛抱強い紅羅坊奈丸先生の落ち着きっぷりがおかしい。
そして、ぺぺ師匠の「……さよなら」を二回も仕込む器用さ。
わはは、気持ち良く帰宅できました。
国立西洋美術館「ゴヤ展」を見たついでに、上野公園内の彰義隊の墓に手を合わせ、上野藪そばで昼食、アメ横をぶらぶらして、最後は鈴本演芸場の夜席。今日は橘屋文左衛門師匠がトリ。
バリトン声に弱い自分、ドスのきいた文左衛門師匠の声を聴きたくなって。
けい木「寿限無」
林家木久扇師匠の前座さんだとか。若者だなぁ。
朝太「子ほめ」
権助が「このぶんじゃ山は雪だんべえ」と言う小咄から、子ほめへ。真打に抜擢が決まっただけあって、余裕たっぷりの「子ほめ」。自分にはちょっと、演技過剰な感じがしたけど。
仙三郎社中「太神楽」
寄席の吉右衛門こと仙三郎師匠の土瓶芸、毎回どきどきします。
三之助「黄金の大黒」
たぶん生でも聴いたことがあるはずなのだが、あまり自分には刺さらないネタだった。三之助さんの噺でやっと楽しめたかな。
菊丸「宗論」
息子が入れあげる教会に来日した神父の名前がクリスチャンディオールルイヴィトンだったり、ちょこちょこと手を入れてくれているので楽しんだ。物まねが入った歌手が誰だったのか、よくわからなかったけど(^_^;)。
ホンキートンク「漫才」
何度も聴いてるけど、漫才の中ではロケット団に次いで笑わせてくれる。
はん治「ぼやき居酒屋」
はん治さんはほとんどこれしか聴いてない。でも鉄板。
雲助「身投げ屋」
初めて聴いた。さすが五街道雲助、何を聴いても安心して心身を任せられる。
中入り
カンジヤママイム「パントマイム」
大人のメルヘン、ピノキオならぬヒノキオが面白かった。
五明楼玉の輔「ざいぜんごろう」?
大半は落語家の噂話。池袋演芸場で数少ないお客さんを相手にした時とか、落語家二世たちの生態とか、定番だけどやっぱり笑わせる。正蔵三平兄弟と木久蔵くんの小咄は、鉄板。
そして、患者さんに癌を告知しなければならない、頼りない医者の話に。癌を初めて告知するお医者さんが、看護師さんのアドバイスに従って、患者さんの脈を取りながら「がんもどき」とか「ガンジー」とか言葉を投げかけて反応を見るって展開。
ぺぺ桜井「ギター漫談」
「禁じられた遊び」を弾きながら演歌を歌えるって、やはり、凄い。
橘屋文左衛門「天災」
聴いたことがあるような気がしていたが、どうやら文左衛門師匠の「天災」は初めてだったらしい。「っぴらごめんねぇ」「表ぇ出ろ」が口癖の、とんでもなく喧嘩っ早い八五郎が笑える。それを引き立てる辛抱強い紅羅坊奈丸先生の落ち着きっぷりがおかしい。
そして、ぺぺ師匠の「……さよなら」を二回も仕込む器用さ。
わはは、気持ち良く帰宅できました。
去年のこの時期に同じ会場で聴いた談春師の「居残り佐平次」の素晴らしさが今でも忘れられず、今回もチケット確保。5列目、むっちゃ端っこだったけど、去年の最後列よりはずっといい。

「出来心」春太
春太さん、なかなかの美男です。
昔から大好きなネタ。「昔から落語に出てくる泥棒は大したものは出てきませんで」……このマクラの辺で笑わせるなんて、なかなかやるじゃん。←ハマ言葉(^_^;)
「裏は花色木綿」連呼で客席を沸かせます。しばらく見ないうちに、随分巧くなったと思います。
「長短」談春
ここのところ寄席通いが続いていたので、「演者ひとり15分、トリ30分」の時間配分に慣れてきたかなというところ。マクラだけで15分たっぷりな談春師、久しぶりだったけど、やっぱり聴かせてくれるからねぇ。
去年もここで演じたけど、坂道を上ってきてここまで来て下さってありがとうございます的な口上。私は野毛の方から散歩してきたので紅葉坂は上がってなかったけど、道路工事とかで歩きにくい上に雨も降って(開演時は止んでいたけど)、そんな思いをして来てくださった皆様に来てよかったと思わせる高座にしたいと意欲を語る。去年の「居残り佐平次」並みの意欲でしょうか、どきどき。
この落語会には通な方が多くて、自分は春太の「出来心」は前座にしてはなかなかだと思ったけど、意地でも笑わないと歯を食いしばってる方がいらっしゃる。「オレぁ小三治の三十代の『出来心』を聴いてんだ」ってところでしょうか……ってところで笑わせて。
今週は青森、仙台の公演に加えて被災地で落語会をやって来られて、風邪を引いてしまい、ビタミン剤や解熱剤やいろいろ飲んで、幸せな気分になっておられるそうです(要するにハイってことですね^_^;)。喉の調子は良くないとあらかじめお断り。
この会場の音響のよさから、今回の被災地での会場の音響係のおっさんの話に転じる。港町で落語は受けないらしいです。浪花節は大受けなんだけど、気性の荒い漁師には落語は独り言にしか聞こえないらしい。ちょっととんちんかんな音響係のおっさんに振り回された公演だったようだけど、おっさんは談春師の落語はなかなかよかったと言ってくれたそうな(笑)。
あと、厚生年金会館の取り壊しの時に、倉庫で昔の名人の写真を何点も掘り出したというエピソードも聞いたなぁ。
そんな感じでたっぷりなマクラの後に、何が来るかと思えば「長短」ですよ。談春さんの「長短」は必殺ですからね。
京みやげの和菓子をいただいた長さんの、食べるのに長いことながいこと。菓子をふたつに割って白あんなのを確認し、半分このどちらが重いかを両手ではかり、ようやく口に入れたと思ったら指の間からむにって出てきたあんこを舌で舐め取る(°°;)。
そして、タバコの吸い方について講釈たれる短さんに、何度も怒らないかと確認しつつ、ようやく、タバコの火玉が袂に入って袂が燃えてるという説明が長いのなんの。短さんのたもとが半分燃えてなくなっちゃったよ^_^;。
マクラと「長短」で30分余りという、たっぷり談春。
中入り
「文七元結」談春
風邪で体調が悪いというのに、中入り後登場してすぐに「文七元結をやります」と宣言して会場を沸かせる。
でもすぐには入らない。名人論をひとくさり。名人とはナンバーワンでありオンリーワンでもあるということ、今の落語会はそういう意味で衆目の一致する名人はいないのではないかと言う。これって「平成の名人」を目指す談春さんだからこそ言える言葉だと思う。そして、この最前列に並ぶ方々ひとりひとりに今の名人は誰かと聞いたら、皆さん違う答えを言うでしょうと。例に出したのは、談志、志の輔、昇太(爆笑が起きる)、志らく(何ともいえぬ口調で、また爆笑)……エトセトラ。
去年の有楽町よみうりホールで聴いた「文七元結」より、さらにこってり。特に、今日は佐野槌の女将の説教が数倍増しの濃さ。マクラの名人論を思い起こさせる中で、文七が博打にのめりこむのは左官の道で名人級ともなると自らの仕事に対しても目が肥えるだけに孤独なのだろうという指摘は、名人を目指す談春師自身の孤高な戦いを想起させる。そして「あんたはそういう風に生まれついたのだから、覚悟おし」と釘を刺す女将に、談春師の覚悟のほども見える。こんだけ女将にやりこめられた上に、お久ちゃんのけなげな心根に触れてしまったら、長兵衛親方だって博打から足を洗うしかないね。
言葉数多くたたみかけるように語りこむことで聴く者の脳に映像のように場面を思い起こさせる談春師、暮れも押し迫った吾妻橋にモヤが立ちこめて、そんな橋の上で身投げをしようとする商家の勤め人・文七と左官の長兵衛の場面が私の脳裏に映像で浮かんできました。文七の、五十両を見知らぬ若者にくれてやる理屈のこねっぷりに、ただもぉ涙涙。ただもぉ、俺の目の前で死ぬな、生きろというだけのために、娘が命かけてつくった五十両を投げ出してしまう、この馬鹿さ加減……(;o;)。
後半は、おっかぁのすさまじさに、爆笑。そして、お約束の大団円に、心が温まる。
ブラボー。去年の「佐平次」に並ぶ名演。
「出来心」春太
春太さん、なかなかの美男です。
昔から大好きなネタ。「昔から落語に出てくる泥棒は大したものは出てきませんで」……このマクラの辺で笑わせるなんて、なかなかやるじゃん。←ハマ言葉(^_^;)
「裏は花色木綿」連呼で客席を沸かせます。しばらく見ないうちに、随分巧くなったと思います。
「長短」談春
ここのところ寄席通いが続いていたので、「演者ひとり15分、トリ30分」の時間配分に慣れてきたかなというところ。マクラだけで15分たっぷりな談春師、久しぶりだったけど、やっぱり聴かせてくれるからねぇ。
去年もここで演じたけど、坂道を上ってきてここまで来て下さってありがとうございます的な口上。私は野毛の方から散歩してきたので紅葉坂は上がってなかったけど、道路工事とかで歩きにくい上に雨も降って(開演時は止んでいたけど)、そんな思いをして来てくださった皆様に来てよかったと思わせる高座にしたいと意欲を語る。去年の「居残り佐平次」並みの意欲でしょうか、どきどき。
この落語会には通な方が多くて、自分は春太の「出来心」は前座にしてはなかなかだと思ったけど、意地でも笑わないと歯を食いしばってる方がいらっしゃる。「オレぁ小三治の三十代の『出来心』を聴いてんだ」ってところでしょうか……ってところで笑わせて。
今週は青森、仙台の公演に加えて被災地で落語会をやって来られて、風邪を引いてしまい、ビタミン剤や解熱剤やいろいろ飲んで、幸せな気分になっておられるそうです(要するにハイってことですね^_^;)。喉の調子は良くないとあらかじめお断り。
この会場の音響のよさから、今回の被災地での会場の音響係のおっさんの話に転じる。港町で落語は受けないらしいです。浪花節は大受けなんだけど、気性の荒い漁師には落語は独り言にしか聞こえないらしい。ちょっととんちんかんな音響係のおっさんに振り回された公演だったようだけど、おっさんは談春師の落語はなかなかよかったと言ってくれたそうな(笑)。
あと、厚生年金会館の取り壊しの時に、倉庫で昔の名人の写真を何点も掘り出したというエピソードも聞いたなぁ。
そんな感じでたっぷりなマクラの後に、何が来るかと思えば「長短」ですよ。談春さんの「長短」は必殺ですからね。
京みやげの和菓子をいただいた長さんの、食べるのに長いことながいこと。菓子をふたつに割って白あんなのを確認し、半分このどちらが重いかを両手ではかり、ようやく口に入れたと思ったら指の間からむにって出てきたあんこを舌で舐め取る(°°;)。
そして、タバコの吸い方について講釈たれる短さんに、何度も怒らないかと確認しつつ、ようやく、タバコの火玉が袂に入って袂が燃えてるという説明が長いのなんの。短さんのたもとが半分燃えてなくなっちゃったよ^_^;。
マクラと「長短」で30分余りという、たっぷり談春。
中入り
「文七元結」談春
風邪で体調が悪いというのに、中入り後登場してすぐに「文七元結をやります」と宣言して会場を沸かせる。
でもすぐには入らない。名人論をひとくさり。名人とはナンバーワンでありオンリーワンでもあるということ、今の落語会はそういう意味で衆目の一致する名人はいないのではないかと言う。これって「平成の名人」を目指す談春さんだからこそ言える言葉だと思う。そして、この最前列に並ぶ方々ひとりひとりに今の名人は誰かと聞いたら、皆さん違う答えを言うでしょうと。例に出したのは、談志、志の輔、昇太(爆笑が起きる)、志らく(何ともいえぬ口調で、また爆笑)……エトセトラ。
去年の有楽町よみうりホールで聴いた「文七元結」より、さらにこってり。特に、今日は佐野槌の女将の説教が数倍増しの濃さ。マクラの名人論を思い起こさせる中で、文七が博打にのめりこむのは左官の道で名人級ともなると自らの仕事に対しても目が肥えるだけに孤独なのだろうという指摘は、名人を目指す談春師自身の孤高な戦いを想起させる。そして「あんたはそういう風に生まれついたのだから、覚悟おし」と釘を刺す女将に、談春師の覚悟のほども見える。こんだけ女将にやりこめられた上に、お久ちゃんのけなげな心根に触れてしまったら、長兵衛親方だって博打から足を洗うしかないね。
言葉数多くたたみかけるように語りこむことで聴く者の脳に映像のように場面を思い起こさせる談春師、暮れも押し迫った吾妻橋にモヤが立ちこめて、そんな橋の上で身投げをしようとする商家の勤め人・文七と左官の長兵衛の場面が私の脳裏に映像で浮かんできました。文七の、五十両を見知らぬ若者にくれてやる理屈のこねっぷりに、ただもぉ涙涙。ただもぉ、俺の目の前で死ぬな、生きろというだけのために、娘が命かけてつくった五十両を投げ出してしまう、この馬鹿さ加減……(;o;)。
後半は、おっかぁのすさまじさに、爆笑。そして、お約束の大団円に、心が温まる。
ブラボー。去年の「佐平次」に並ぶ名演。
久しぶりにまとめてみました。
北海道
咸臨丸で町おこしを 木古内サミットに全国200人
新選組サミット:維新期の海戦に思いはせ 「震災復興の力に」 宮古で11月 /岩手
茨城
東日本大震災 「志士の墓」修復 秋季大祭で記念碑 水戸・回天神社
東京
【街角モノがたり】「江戸四宿」の面影残る板橋
府中の大國魂神社で8日から奉祝行事 能や狂言、歌舞伎など披露
新潟
河井継之助の遺徳しのび144年祭 新潟・長岡市の栄凉寺
京都
新選組:局長、近藤勇直筆の掛け軸 京都市内で発見
広島
幕末「神機隊」の歩み紹介
高知
龍馬ふるさと博:JR高知駅前の新パビリオン好評 「龍馬伝・幕末志士社中」 /四国
樋口真吉:新写真見つかる 戊辰戦争前?刀差し、立ち姿 /高知
長崎
洋食屋事始 「自由亭」幕末のメニュー
エンターテインメント
ちば賞大賞の新鋭・桐村海丸の新連載は新撰組の草創期
江口洋介 : 映画「るろうに剣心」で斉藤一を演じる 香川照之と吉川晃司も出演決定
実写版るろ剣に吉川晃司、江口洋介、香川照之が剣心のライバル役で登場!
江口洋介が斉藤一……どんな感じだろう。問題は……蒼志様だな。
ブックレビュー
『新選組 敗者の歴史はどう歪められたのか』大野敏明著
6代目の描く山田方谷、前横浜税関総務部長が小説を出版/神奈川
コラム
【幕末から学ぶ現在(いま)】
(132)東大教授・山内昌之 近藤勇
「近藤は大久保大和、土方歳三(ひじかた・としぞう)は内藤隼人と改名した。これは、甲州人の歴史へのこだわりを察知し、武田家や甲州に縁のある大久保や内藤の姓をあえて称したためだという」……なるほど。
「東山道先鋒(とうさんどうせんぽう)総督府参謀だった土佐藩の乾(いぬい)退助は、信玄の宿老だった板垣信方(のぶかた)の死から320年にあたるため、甲斐源氏の流れを汲む板垣氏の苗裔(びょうえい)という家伝を示して板垣退助と姓を改めたのだ。この策で板垣は甲州人の支持を得て、勝沼の戦いで大久保大和こと近藤勇の甲陽鎮撫隊を撃破したという説もあるほどだ」……こっちは知ってましたが。
「 近藤は甲州での敗戦後、京都以来の同志、永倉新八や原田左之助らと訣別(けつべつ)し、旧幕府歩兵らを率いて下総国流山に屯集(とんしゅう)した。だが香川敬三率いる新政府軍に包囲され、やがて出頭、板橋宿まで連行された。そこで正体が見破られ、捕縛後に斬首されたことはよく知られている。しかし近藤にとって、甲州での勝ち戦さが成らなかったにせよ、人生の最期を故郷で晴れがましく送れたのは幸いであった」……山内先生、近藤勇に暖かい視点でありがとうございます。
北海道
咸臨丸で町おこしを 木古内サミットに全国200人
【木古内】日本初の太平洋横断を成し遂げた幕末14 件の軍艦「咸臨丸(かんりんまる)」が渡島管内木古内町の沖合に座礁沈没して今年で140年になることを記念し、全国のゆかりの地から関係者を集めた初の「咸臨丸全国まちづくりサミット」が24日、同町中央公民館で開かれた。
咸臨丸の建造国であるオランダ大使館からも含め約200人が参加した。
討論会では国内各地の代表者ら13人がそれぞれの取り組みを報告した後、木古内町サラキ岬沖に沈んでいるとみられる船体について議論した。
新選組サミット:維新期の海戦に思いはせ 「震災復興の力に」 宮古で11月 /岩手
新選組副長の土方歳三や日露戦争時の連合艦隊司令長官、東郷平八郎らが明日の日本を夢見て死闘を繰り広げた「宮古湾海戦」の舞台となった宮古市で11月、「第12回全国新選組サミット」が開かれる。新選組ゆかりの全国各地の同好会と宮古市の有志が東日本大震災復興の理想を掲げて開催するもので、海戦戦没者や震災犠牲者を洋上から弔う供養も予定されている。【鬼山親芳】
宮古開催は昨年11月、京都であったサミットで、宮古の関係者が宮古湾海戦の話をしたのがきっかけで内定していた。3月11日の大震災でいったんは立ち消えになったが、京都の関係者から「祇園祭は1000年に1度とされる貞観地震(869年)のあった時代に京の都に流行した疫病の汚れを払う復興の祈りが始まりだった」として震災復興のためにも宮古開催を望む声が出され、決定した。
宮古市では「宮古港海戦の会」(会長・沢田克司宮古観光協会長)が中心となってイベントを企画。初日の11月5日には宮古駅前広場で、鍬ケ崎小学校児童による大漁祝い唄で幕を開け、新選組隊士の装束をした一団が目抜き通りの末広町商店街をパレード。鍬ケ崎小や周辺では祇園囃子の演奏や土方歳三の末えいによるトークショーなどのほか、夜はホテルを会場に交流会を予定。鎮魂の洋上供養は最終日の6日に行われる。
沢田会長は「142年前、土方歳三らが宮古の海を駆け抜けていった歴史に思いをはせ、震災復興の力になってくれればうれしい」と話す。問い合わせは同会(電話0193・62・3632)。
==============
◇宮古湾(港)海戦
明治2(1869)年3月25日(新暦5月6日)、箱館に独自の政権を樹立した榎本武揚ら旧幕府軍の軍艦「回天」が宮古湾に停泊する新政府(官軍)の「甲鉄」ら艦船に急襲をかけた海戦。午前5時ごろから約30分間の白兵戦だったが、敗走した回天側に艦長の甲賀源吾ら17人、官軍側にも4人の計21人の死者が出た(「宮古・閉伊秘話」小島俊一著)。
茨城
東日本大震災 「志士の墓」修復 秋季大祭で記念碑 水戸・回天神社
東日本大震災で被害を受けた水戸市指定史跡「水戸殉難志士の墓」など回天神社(同市松本町)境内の復旧事業が終了し、14日に開かれる秋季大祭では「東日本大震災復旧記念碑」が建立される。震災でほぼ全てが倒壊した幕末志士の墓は約7カ月ぶりに復旧、関係者は安堵の表情を見せた。(三保谷浩輝)
◇
同神社は、幕末の安政の大獄や桜田門外の変、天狗(てんぐ)党の変、戊辰戦争などで亡くなった水戸藩に関係する志士らの霊を慰めるために建てられた。境内には昭和8年建立の「忠魂塔」や天狗党の変などで命を落とした志士らの墓、天狗党最後の地・敦賀(福井県)で一行が監禁された鰊蔵(にしんぐら)を移築した回天館などがある。
震災では、回天館は無事だったが、「忠魂塔」の笠石(かさいし)などが落下したほか、本殿を取り囲む玉垣が全壊。また、大正3年に建てられた「水戸殉難志士の墓」371基のうち4基を残して倒れ、破損した。
同神社代表役員の滝田昌生さん(79)は「被災であっちも駄目、こっちも…と、無残な状況におののいた」と振り返る。だが、4月には復旧事業を立ち上げ、秋季大祭を目指して順次工事を始めた。中でも志士の墓は、墓石が割れ、修復困難な10基を造り直すなどして今月4日に完成。約7カ月ぶりに371基がそろった。
墓石の完成で復旧作業は完了。秋季大祭では「惨禍を忘れず災害復旧記念の証とす」などと記した東日本大震災復旧記念碑を建立、除幕式が開かれる。碑は台座を含めて高さ約2メートル、幅約90センチ。題字は天狗党の一勢力に名を連ねた水戸藩士の遺族で、本紙「正論」メンバーの田久保忠衛・杏林大学名誉教授が書いた。
滝田さんは「復旧できてホッとした。これで明治維新回天の業の礎となった先人の思いを継承し、日本の国をよくする足がかりにできる」と話している。
東京
【街角モノがたり】「江戸四宿」の面影残る板橋
JR埼京線で池袋の次が板橋。駅近くから北に延びる旧中山道は近代的な商店街に変貌しているが、地名の起こりになった橋「板橋」や新選組・近藤勇の墓碑など、名所旧跡に事欠かない。
板橋は品川(東海道)、千住(日光・奥州街道)、内藤新宿(甲州街道)と並ぶ「江戸四宿」の一つ。昔の旅人は徒歩だったが、現在は地下鉄の都営三田線が移動に便利だ。新板橋から志村坂上へ北上して地上に出ると、国指定史跡「志村一里塚」がある。江戸日本橋から3番目の一里塚で、今も当時と同じ場所に立っている。
板橋本町まで戻り、縁切榎を目指して南へ。悪縁切りを祈願する樹木として、3代目の今も信仰を集める。絵馬には配偶者や兄弟姉妹、職場の同僚との縁切りを願う強い思いが込められ、その切実さに胸を突かれる。
石神井川に架かる板橋は、古くは源頼朝が渡ったとも伝えられる。現在はコンクリート製だが、木目調の欄干と木々の緑が調和して落ち着いたたたずまいを見せる。桜の季節にはたくさんの人が訪れるという。
旧道の適度な道幅は人に優しい。行き交う自転車や歩く人々には、どこかのんびりとしたムードが漂い、並走する中山道(国道17号)の騒がしさは、まるで別世界の出来事のよう。
橋の南から区役所前付近までが、一番にぎやかな仲宿商店街。江戸時代にも宿場で一番栄えた場所だが、「今も昔と変わっていないんだよね」と喫茶店のママさんは笑って話してくれた。
短い旅の最後、板橋駅前の「むすびのけやき」に良縁をお願いした。歩き疲れて偶然口にした菓子店「はちや」の蜜蜂焼は絶品。これもご縁だろうか。
【メモ】いたばし観光センターには、初代の縁切榎が保管されている。悪縁を切りたい人は念には念を入れたい。
府中の大國魂神社で8日から奉祝行事 能や狂言、歌舞伎など披露
建立から1900年を迎えた大國魂神社(東京都府中市宮町)で8日から3日間、奉祝行事として能、狂言、歌舞伎などさまざまな郷土芸能が披露される。
8日は前橋市指定無形文化財の「総社神楽」、台東区指定無形文化財の小野雅楽会による雅楽、10日はあきる野市に伝わる農村芸能の秋川歌舞伎や能、狂言などが演じられる。
このほか、今年は江戸末期の新選組局長、近藤勇が同神社で天然理心流宗家の襲名披露をしてから150年目にあたり、これを記念して9日午後0時半から、近藤の生家の子孫ら12人による天然理心流の奉納演武が披露される。
同神社では室町時代や江戸時代などに奉納され、宝物殿に所蔵している刀、脇差などの刀剣17本を初めて一般公開している。公開は30日まで。
新潟
河井継之助の遺徳しのび144年祭 新潟・長岡市の栄凉寺
戊辰戦争で新政府軍に徹底抗戦した長岡藩の家老、河井継之助(1827-1868)の没後144年祭の法要が9日、継之助の眠る新潟県長岡市東神田の栄(えい)凉(りょう)寺でしめやかに営まれ、市民ら約40人が継之助の遺徳をしのんだ。
継之助は藩財政を再建、フランス式調練を取り入れるなど軍を近代化。武装中立を唱えるが、戊辰戦争では軍事総督となり、1度は奪われた長岡城の奪還に成功したものの、その際に左ひざを負傷。再び城を奪われ、落ちのびる途中、会津・塩沢村(現福島県只見町)で死去した。現在の暦で10月1日だった。
法要は河井継之助記念館友の会主催で、長岡藩牧野家17代当主の牧野忠昌さんが祭文を読みあげ、「不当なる要求を突きつけた新政府軍に敢然と戦いを挑んだ」と継之助をしのび、戦いの犠牲になった継之助や当時の長岡の人たちの冥福を祈った。
河井家8代当主で、継之助のひ孫にあたる河井弘安さん(49)も東京都内から駆けつけて墓前に手を合わせ、「144年たち、今も皆さまから慕われていることはありがたい。本人も長岡のために尽くして良かったと思っているのではないか」と話していた。
京都
新選組:局長、近藤勇直筆の掛け軸 京都市内で発見
幕末の京都で活躍した新選組局長、近藤勇(1834~68)直筆の掛け軸が京都市内で見つかったことが分かった。「英雄」をテーマにした自作の漢詩で、近藤が活動資金調達のために豪商などから金を借りる際にお礼として書いたものと見られる。近藤直筆の掛け軸は数点しか見つかっておらず、近藤の人間像を知るうえで貴重な発見という。
掛け軸は縦196センチ、横63センチ(書は縦136センチ、横60センチ)。同市内の美術店が08年に大阪府内で入手して所蔵していたものを今月、広島県尾道市の医師が購入した。幕末を中心とした歴史博物館「霊山(りょうぜん)歴史館」(京都市東山区)に持ち込まれ、木村幸比古・学芸課長(幕末史)が筆跡や落款(らっかん)などから真筆と判定した。
書の詳しい内容は未解明だが、「英雄」に対する心情を披露し、最後に「剣客士 近藤書」と書かれている。
木村課長によると、近藤らが関東から入洛(にゅうらく)した文久3(1863)年ごろに書かれた掛け軸(東京国立博物館所蔵)と形式などが似ており、同時期の書と見られる。同年、近藤らは武功を評価されて「新選組」の名を与えられ、倒幕運動の過激派志士の取り締まりに当たった。大阪や京都の豪商らから強引に金を借り、こうした書を残すことがあったという。
木村課長は「漢学者の頼山陽(らいさんよう)の書を好み、まねをしていた近藤の筆跡に間違いない。憧れの武士となって意気揚々としていた当時の近藤の様子が伝わってくる」と話している。【花澤茂人】
広島
幕末「神機隊」の歩み紹介
江戸時代末期の倒幕運動に加わった、東広島市の「神機隊」関連資料の展示会「東広島の明治維新」が27日、同市西条町御薗宇のフジグラン東広島2階の市民ギャラリーで始まった。10月2日まで。無料。
神機隊は幕末に志和町で結成され、農家の若者たち約1200人が入隊した。規律案や入隊希望者の推薦状などの資料に加え、主催する東広島郷土史研究会の会員が作った地図や年表を含む計54点を展示。時代の激動が庶民にも浸透していたことがうかがえる。
午前10時~午後6時(最終日は午後5時まで)。
【写真説明】神機隊に関する資料に見入る来場者
高知
龍馬ふるさと博:JR高知駅前の新パビリオン好評 「龍馬伝・幕末志士社中」 /四国
◇ブーム逃さんぜよ
◇来場者数15万人へ、土佐の魅力アピール
昨年放送されたNHK大河ドラマ「龍馬伝」の反響で、空前の“龍馬ブーム”となった高知県。今年3月からは新観光イベント「志国高知 龍馬ふるさと博」が始まった。7月に高知市のJR高知駅前にオープンした新パビリオン「龍馬伝・幕末志士社中」は、今月17日で来場者が5万人に達し、好評を得ている。また、ご当地アイドル「土佐おもてなし勤王党」が結成されるなど、龍馬ブームの流れを止めてなるものかと、今年も県は観光事業に力を入れている。【倉沢仁志】
年間来場者数15万人を目指す新パビリオンには「龍馬伝」の撮影で使用された生家セットが設置され、室内に水を引くなどして龍馬の生まれ育った家を忠実に再現した造りになっている。この他、龍馬を演じた福山雅治さんら各俳優の着用した衣装なども展示されている。
JR高知駅前にある特設ステージでは「土佐おもてなし勤王党」や「よさこいおもてなし隊」が定期的にミュージカルや踊りを披露し、観光客に高知の魅力をアピール。さらに土佐勤王党結成150周年を記念し、JR高知駅前に坂本龍馬、武市半平太、中岡慎太郎の「3志士像」を期間限定で設置して盛り上げている。
10月1、2両日には、高知の食を味わってもらう企画「土佐豊穣祭」として、県内の素材を使ったB級グルメの出店ブースが3志士像近くに並ぶ。
樋口真吉:新写真見つかる 戊辰戦争前?刀差し、立ち姿 /高知
坂本龍馬と親交があった土佐藩下級役人の樋口真吉(1815~70年)の新しい写真が30日、見つかった。四万十市立郷土資料館が子孫から預かっていたものを徳島大学の渋谷雅之名誉教授(69)が確認した。【真明薫】
新しく見つかった写真は立ち姿で、右手に乗馬用の鞭(むち)を持ち、長い刀を左に差している。ガラス板を使った縦10センチ横7・5センチの湿板写真。顔や刀の長さが酷似し、撮影した場所のじゅうたんの模様、足下の石畳などから慶応4(1868)年4月ごろに横浜市内で撮影されたものらしい。真吉が53歳ごろのもので、戊辰戦争に行く前に撮影したとみられる。
真吉は土佐・中村(現四万十市)生まれで、剣豪としても知られ、幡多郡の志士らの代表的存在。龍馬を少年期から目にかけ、隠れ家の手配をしたり、脱藩した龍馬に大阪で会い1両を渡すなどしたとされる。
長崎
洋食屋事始 「自由亭」幕末のメニュー
「長崎で今日のクリーニング店を開業しています」。さらに「日本人として最初の西洋式洗濯屋」だったと続く。
草野丈吉(1840~86)について、玄孫(やしゃご)の草野敏彦さん(77)(大阪)が述べている談話(「日本の『創造力』」第3巻所収)は意外だった。
丈吉らの小伝を記した私家版の「暁霞生彩(ぎょうかせいさい)」(星丘重一氏・編)にあるらしい。
幕末、長崎・出島のオランダ人にボーイとして雇われた丈吉が習い覚えた西洋式の洗濯のわざを生かし、文久3年(1863年)に外国船の乗組員を相手に洗濯業を始めたというのだ。
「なかでも丈吉がもっとも影響を受けたのはデ・ウィットのところにいたころでしょう」
大阪市史編纂(へんさん)所長の堀田暁生さん(65)は、月刊誌に長期連載した「大阪開化自由亭物語」をはじめ、大阪の近代史の一ページを彩った丈吉の研究を四半世紀重ねてきた人だ。
挙げたのは当時のオランダ総領事の名である。17歳で出島出入りの日本人商人に奉公した丈吉は2人のオランダ人を経て、そのデ・ウィットに雇われた。
「料理、客をもてなす態度も仕込まれたでしょうね」。丈吉は江戸へも随行したようだ。農家出身の若者には洗濯屋、そして、やがて洋食屋の草分けとして名を残すことにつながる濃密な西洋体験の連続だったろう。
◎
デ・ウィットの帰国後、丈吉は伊良林(長崎市)の実家に戻り、所帯を持って洗濯屋に。ほどなくして西洋料理の専門店「良林亭」も開く。
洋食屋の誕生には五代才助(友厚)のすすめがあったと伝えられる。五代は、長崎においてはグラバーらとも親交があった薩摩藩士。薩英戦争などあわただしい時代に、丈吉とのどんな出会いがあったのだろうか。
ともあれ五代が所望し食べたとされる西洋料理は、鮮魚のフライ、冷肉薫製、精肉の焼き肉、生野菜などだったようだ。
その伊良林を、敏彦さんも4年前歩いた。住宅の密集する坂道に「良林亭跡」の看板がある。〈六畳一間の部屋で、6人以上のお客様はお断りだった〉当時の様子も記されている。
良林亭はまもなく場所を移し、「自遊亭」「自由亭」と改称。長崎奉行らも訪れたそうだ。
丈吉は慶応4年(68年)、土佐の後藤象二郎の求めで大阪へ向かい、山内容堂公にもかわいがられたという。そのころ、大阪に設けられた外国人止宿所の司長を任される。外国官権判事で、大阪にいた五代の依頼だったとみられている。
西洋料理とクリーニング技術の習得が「ホテル経営につながった」。敏彦さんの談話(前掲書)に添えられた指摘はよくうなずけた。
◎
明治10年(77年)には神戸で、明治天皇に自由亭の西洋料理が献じられた。その献立を載せた新聞記事が「自由亭物語」に登場する。〈ロブスタサラド(海老 花玉子 チシャ)〉、〈ゲンパイ(鴨 山鴨 鰻 鶉 豚 牛)〉などである。
翌11年、丈吉は再び長崎市で自由亭を開く。店は諏訪神社前。12年には、長崎を訪れた前米大統領、グラント将軍も自由亭の料理を食したという。
「伊太利国皇族接待日誌」というメニューのコピーを、「現代の名工」のシェフ坂本洋司さん(64)(長崎市)がみせてくれた。これも同じ年、自由亭の調理だそうだ。
〈フライコローツキ〉はコロッケ、〈マカラニチイス〉がマカロニグラタンなど、現代につながる料理名がおもしろい。
「丈吉はトップクラスの料理人」と坂本さんは絶賛する。堀田さんによれば、英国の外交官アーネスト・サトウ編集の旅行案内にも、大阪・中之島の自由亭ホテルの食事、サービスは優秀と紹介されているそうだ。
長崎市歴史民俗資料館長の永松実さん(60)も丈吉にひかれる一人だ。「食を通じて著名な人たちとこれほどのつながりをもった丈吉は、もっと知られていい人物ですよ」
一昨年12月から昨年2月にかけて資料館で、「西洋料理店の魁 草野丈吉展」を開いた。オランダの船で丈吉が訪れたとされる北海道・函館にも立ってみた。丈吉の物語をまとめたい思いが強くなったという。
元高校教師の敏彦さんには、生い立ちを描いた著書「くるみの木」がある。そこでも、祖母が丈吉の孫で、一方の祖父は学者であったという系譜を大切にみつめている。後継ぎのなかった草野家の姓は父親が継いだ。だが、丈吉の味が子孫につながることはなかった。
開化を彩ったホテル
幕末の文久3年といえば、丈吉が長崎に洋食屋を開いた年だが、そのころ、開港地の横浜にレストランやバーのあるホテルが建てられた、と「日本のホテル小史」(村岡實・著)にある。
東京では、築地ホテルが慶応3年(1867年)に起工、完成は翌年8月だった。暖炉やベランダなども備えられていたそうだ。それからまもなく、大阪にも「外国人止宿所」が設けられた。長崎の人・丈吉は、その外国人向けホテルの司長、〈ジェネラル・マネージャー〉(前掲書)となる。
「大阪の歴史71」(大阪市史料調査会発行)所収の堀田さんの論考は、明治2年(69年)の英字新聞の広告から止宿所が当初から「自由亭ホテル」と名乗っていたと指摘している。その後、自由亭は西洋料理を調理できる場として名声を得ながら、5店舗に拡大。大阪・中之島にも14年、自由亭ホテルが開業した。
19年、丈吉が急病で亡くなった後、長女の錦(きん)が後を継ぎ、28年に大阪ホテル東店、29年に同西店を開業させたが、錦を支えた星丘安信の没後、32年に売却。草野家と西洋料理とのかかわりも途絶えてしまう。
「ホテル小史」に戻ると、明治3、4年に、長崎では4軒のホテルが相次いで開業し、好評だったと記されている。どのホテルにもボウリングやビリヤードといったレジャー施設がすでに整えられていたというのが興味深い。
「150年前の料理」再現
グラバー邸の一室に料理の模型がずらりと並んでいる。「150年前の西洋料理」と題し、坂本さんら料理人たちが当時の正月料理をこしらえ、模型にして残したものだ。2003年のこと。自由亭の献立記録などを参考にしたという。
その後も時折、幕末・明治の西洋料理を再現する機会がある。「これは3年ほど前」と坂本さんが差し出した写真には、おいしそうな料理が盛られていた。一つずつ、「現代の名工」に解説してもらった。
手前はロストルヒス。タイの塩焼きだ。前列を左へ、まずケレーフトソップ。伊勢エビを二つに割ってタマネギやパン粉などを詰め、ボートル(バター)で揚げ、ブイヨンを入れた白ブドウ酒で煮る。次のブラートルボックは野牛の股(もも)丸焼きで味つけは塩、コショウ、酢。左端のブラートルエンゲホーゲルは鴨(かも)肉の丸焼き。
奥の列には、ホウレンソウとゆで卵のスペナーンや、シカ肉を焼くハルトベーストなど。豪華そうだが、坂本さんによれば「オランダの素朴な料理」という。
(2011年9月27日 読売新聞)
エンターテインメント
ちば賞大賞の新鋭・桐村海丸の新連載は新撰組の草創期
本日10月6日に発売されたモーニング45号(講談社)にて、「しおかぜ」で第59回ちばてつや賞一般部門大賞を受賞した桐村海丸の短期集中連載「とんがらし」がスタートした。
「とんがらし」は新撰組22 件隊士の若き日々を描く物語。第1話では沖田総司と原田左之助の出会いが描かれた。
このほか今号では、うえやまとち「クッキングパパ」の江戸時代編「遠山のくっ金さん」を収録。巻頭カラーでは、同心1ヶ月分の給料で作れる、江戸時代のご馳走を再現したグルメ企画が行われている。
江口洋介 : 映画「るろうに剣心」で斉藤一を演じる 香川照之と吉川晃司も出演決定
俳優の佐藤健さん主演で実写映画化される「るろうに剣心-明治剣客浪漫譚-」(大友啓史監督)の追加キャストが4日、発表され、俳優の江口洋介さんが旧幕府軍・新撰組三番隊組長の斉藤一を演じることが明らかになった。また、歌手で俳優の吉川晃司さんが浮浪(はぐれ)人斬り・鵜堂刃衛役、俳優の香川照之さんが悪の親玉・武田観柳役で出演することも発表された。江口さんは、作品について「今まで経験したことのない大友監督の撮影方法に新たな可能性を感じ、僕自身どう仕上がるのかが、今から楽しみでいます。きっと今までにないエンターテインメントをご披露できるのではないかと思いますので、ご期待ください」とコメントを寄せている。
「るろうに剣心」は、94~99年に「週刊少年ジャンプ」(集英社)で連載され、コミックスは全28巻で累計5000万部以上を発行した大ヒットマンガ。幕末に「人斬り抜刀斎」として恐れられた緋村剣心(ひむら・けんしん)が、明治維新後「不殺(ころさず)」を誓った流浪人(るろうに)として、さまざまな人たちとの出会いや、宿敵との戦いをへて、新たな時代の生き方を模索していくという物語で、映画では主人公の剣心を佐藤さん、ヒロイン・神谷薫を女優の武井咲さん、剣心を慕う美人女医の高荷恵を女優の蒼井優さんが演じる。大河ドラマ「龍馬伝」を手がけ、4月に20年間在籍したNHKを退局した大友監督がメガホンを取る。
江口さんが演じる斉藤一は、新撰組を経て、明治維新後は明治政府の警官となり、密偵として暗躍する……という原作でも人気のキャラクター。江口さんは、作品の舞台について「明治になり国から魂である刀を奪われた。そんな人間たちが明治という時代をどう生き抜いていくのかが、この作品には詰まっている」と話し、「『るろうに剣心』を通して日本人が生きてきたルーツみたいなものを少しでもスクリーンの中から感じとってもらえればと思う」と作品への思いを語っている。
また、吉川さんは、鵜堂刃衛について「敵味方の分別を忘れただひたすらに切りまくるは、己にふさわしい死に場所を得るためか。そのまとう寂しさに“ゾクッ”とさせられながら演じられる幸せ。奇々怪々です!」とコメント。「龍馬伝」から引き続き大友監督作品に出演する香川さんは「監督からは『新しい悪、ただの悪ではないもの』を目指すと言われて、役作りと同時に、いろいろな小道具だったり、メークだったり、髪の毛だったり、衣装だったり、外見の造作には非常にこだわっています。観柳は自由勝手に生きた人なので、僕も作品の中で自由に振る舞えればいいなと思っています」と意気込みを話している。
製作はワーナー・ブラザース映画で、12年夏に公開予定。(毎日新聞デジタル)
実写版るろ剣に吉川晃司、江口洋介、香川照之が剣心のライバル役で登場!
単行本全28巻の累計発行部数が5000万部を超える剣客漫画を実写映画化した『るろうに剣心』に、吉川晃司、江口洋介、香川照之が出演することがわかった。
本作の物語は、明治維新のために伝説の人斬りとして生きてきた剣心が、維新以後、殺さずの誓いをたて、町から町へ流浪の旅をしているというところから始まる。吉川、江口、香川は、緋村剣心(佐藤健)の前に立ちはだかる最強のライバルたちを演じる。
吉川晃司は、ただただ人を殺すことを楽しみ、己の欲望を満たすために金で人斬りを請け負っていた浮浪人斬りの鵜堂刃衛を演じる。吉川は「敵・味方の分別を忘れ、ただひたすらに斬りまくるは、己に相応しい死に場所を得るためか。そのまとう寂しさに、ゾクッとさせられながら演じられる幸せ。奇々怪々です!」と出演の喜びを語った。ただの殺人鬼ではなく、独自の殺しの美学を持つなど、剣心とは対照的な最凶キャラクターを演じる吉川のその圧倒的な存在感に今から期待が寄せられる。
維新時代に新政府の人斬りである剣心と対峙する旧幕府軍・新撰組三番隊組長・斎藤一を演じるのは江口洋介。維新後は明治政府の警察官となるが、剣心たちとは決して相容れない孤高のダークヒーローを熱演する。「江戸時代の頃、侍は刀を魂と信じて生きていた。それが明治になり、国から魂である刀を奪われた。そんな人間たちが明治という時代をどう生き抜いていくのかが、この作品には詰まっている。『るろうに剣心』を通して日本人が生きてきたルーツみたいなものを少しでもスクリーンの中から感じとってもらえれば」と本作の魅力を語る。初参加となる大友組については、「今まで経験したことのない大友監督の撮影方法に新たな可能性を感じ、僕自身、どう仕上がるのかが今から楽しみ。きっと今までにないエンターテインメントをご披露できるのではないか」と話しており、どのような化学反応を起こすかにも注目だ。
香川照之が演じるのは、高荷恵(蒼井優)を手下として利用し、薫(武井咲)が師範代を務める神谷道場を乗っ取ろうとし、さらに新政府に代わって自分の帝国を築こうとする悪の親玉・武田観柳だ。蒼井同様、大河ドラマ「龍馬伝」から引き続いて大友組に参加が決まった香川は、「監督からは『新しい悪、ただの悪ではないもの』を目指すと言われ、役作りと同時に、色々な小道具やメイク、髪の毛や衣裳など、外見の造作には非常にこだわっています。観柳は自由勝手に生きた人なので、僕も作品の中で自由に振る舞えれば良いなと思う」とコメントを寄せた。原作の持つ冷徹で不気味なキャラクターをどう演じるのか、香川版観柳への期待が高まると共に、観柳邸でのガトリングガンを使用したアクションシーンが実写でどう表現されているかも大きなポイントになるだろう。【Movie Walker】
江口洋介が斉藤一……どんな感じだろう。問題は……蒼志様だな。
ブックレビュー
『新選組 敗者の歴史はどう歪められたのか』大野敏明著
新選組ブームだそうだ。新選組をテーマにした映画やテレビドラマ、あるいは小説は、数多く作られてきたが、著者は、それらの多くは歪められ、史実とは異なっているという。例えば池田屋事件は警察行動であったとする。「局中法度書」は本当にあったのか。松原忠司の死の真相は。分裂してからも行動をともにした高台寺党など。
さらには土方歳三戦死後の新選組局長が、明治になってから切腹した話、十番組長の原田左之助が満州に行き、馬賊になったという説、沖田総司の姉が中国の大連で亡くなっていたことなど、テレビドラマからでは分からない新選組の物語が、あくまで史実にこだわってふんだんにつづられる。(じっぴコンパクト新書・800円)
6代目の描く山田方谷、前横浜税関総務部長が小説を出版/神奈川
徳川幕府の政治指南役として15代将軍・慶喜や筆頭老中・板倉勝静(かつきよ)を支えた改革派の学者・山田方谷(ほうこく)(1805~1877)の生涯を通じて、幕末の政権交代のドラマをつづった「小説 山田方谷の夢」(明徳出版社、2415円)が出版された。
作者は方谷の6代目にあたる野島透・財務省関東財務局総務部長(50)。執筆は前任の横浜税関総務部長(2009年7月~11年7月)の時代で「開港の地である横浜で生麦事件など歴史の現場に接し、先祖を振り返る気持ちが高まったことが理由」という。
方谷は備中松山藩(現岡山県高梁(たかはし)市一帯)の藩主・勝静の下、財務大臣役を担って破綻状態にあった藩財政を立て直した。信頼を失った旧藩札の一斉焼却処分と新藩札の発行、鉄をはじめとした特産品の育成、農民の現金収入につながる河川改修など大規模公共事業の実施―といった七大政策は、財政再建のお手本として語り継がれている。
藩政改革の功を評価され、勝静とともに幕政に携わった。大政奉還の案文も手掛けたという。方谷と新選組2 件のつながりなど、多彩な人間模様を交え先祖の功績をまとめた野島氏は「難局に立ち向かう幕末の人々の姿は、震災復興に臨む私たちに勇気を与えてくれる」と話している。
コラム
【幕末から学ぶ現在(いま)】
(132)東大教授・山内昌之 近藤勇
■甲州人と甲陽鎮撫隊
甲州(甲斐)はいまの山梨県である。その政治風土は独特な気風をもっているようだ。
そのせいか甲州は政党政治家でも、自民党幹事長を務めた故金丸信氏や、参院議員でありながら民主党幹事長に就任した輿石東氏など、野党との間にも太いパイプをもち、国会対策にも熟達する政党人を生んできた。
◆国会対策に熟達の政党人
輿石氏の人脈の広さも相当のものらしい。小沢一郎氏との深い関係がある一方、前原誠司氏との仲も悪くないようだ。それでいて、小沢氏の党員資格停止処分の見直しに慎重であり、旧社会党や日教組の出身らしく「機関決定」を尊重する衆議一決のルールにも忠実である。政治家を外貌や印象だけで判断してはならない。存外に輿石氏は“懐が深い”のかもしれない。
もちろん甲州が格別に閉鎖的であるとか、甲州人が排他的というわけではない。しかし、同じ内陸国でも「近江」(近い海)という琵琶湖をもつ江州(滋賀県)とも違う山がちの地として、武田信玄が隣国の塩攻めで苦しんだ過去もある。鮑(あわび)の煮貝(にがい)などの保存加工された海産物に蛋白(たんぱく)質を頼る、海のない国ぶりが人びとに忍耐を教え、戦国時代に「甲軍」と畏怖された精強さや粘り強さを甲州人に与えたのかもしれない。
江戸時代でも、将軍綱吉から松平姓を賜った柳沢吉保(よしやす)の時代を例外として、甲州は天領か将軍一門の知行地であった。甲州人の耐久力を支えてきた要因として、武田信玄や徳川家康や将軍家に直轄統治されたというプライドの高さも無視できない。
◆歴史へのこだわりを察知
実際に幕末の慶応4(1868)年3月、鳥羽伏見で敗れて江戸に戻った近藤勇ら新選組が甲陽鎮撫隊(こうようちんぶたい)と名を改め甲州を目指したとき、いまや若年寄格となった近藤は大久保大和、土方歳三(ひじかた・としぞう)は内藤隼人と改名した。これは、甲州人の歴史へのこだわりを察知し、武田家や甲州に縁のある大久保や内藤の姓をあえて称したためだという。
面白いのは新政府軍のほうも同様だったことだ。東山道先鋒(とうさんどうせんぽう)総督府参謀だった土佐藩の乾(いぬい)退助は、信玄の宿老だった板垣信方(のぶかた)の死から320年にあたるため、甲斐源氏の流れを汲む板垣氏の苗裔(びょうえい)という家伝を示して板垣退助と姓を改めたのだ。この策で板垣は甲州人の支持を得て、勝沼の戦いで大久保大和こと近藤勇の甲陽鎮撫隊を撃破したという説もあるほどだ。
近藤の甲陽鎮撫隊は、70人余の新選組に加え新規募集の浅草弾左衛門の配下約200名の陣容であったが、大砲2門と小銃500挺(ちょう)ではあまりにも火力に乏しく、軍資金5千両も武州三多摩の近藤や土方の故郷などで豪遊を繰り返すうちに乏しくなった。なにしろ若年寄や寄合になったというのだから、故郷に錦を飾りながら道々で歓待を受けたのも無理はない。
そのうちに、空城だった甲府城の接収が板垣退助らの東山道軍に先んじられたのだからたまらない。いまの甲州市(旧勝沼町)で野戦に打って出たが、甲陽鎮撫隊の戦意は乏しく、兵器も優勢な新政府軍に撃破され1日たらずで壊滅してしまった。甲陽鎮撫隊は国境の上野原まで退却後、めいめいばらばらに江戸まで潰走する始末であった。
近藤は甲州での敗戦後、京都以来の同志、永倉新八や原田左之助らと訣別(けつべつ)し、旧幕府歩兵らを率いて下総国流山に屯集(とんしゅう)した。だが香川敬三率いる新政府軍に包囲され、やがて出頭、板橋宿まで連行された。そこで正体が見破られ、捕縛後に斬首されたことはよく知られている。しかし近藤にとって、甲州での勝ち戦さが成らなかったにせよ、人生の最期を故郷で晴れがましく送れたのは幸いであった。
◆粘りと忍耐で果たせるか
輿石氏も参院から党幹事長になるのは、政党人としてこれ以上に名誉なことはない。その重責を甲州人らしい粘りと忍耐力で果たせるのか、甲陽鎮撫隊と若年寄格で舞い上がった近藤のように肝心の修羅場で力を発揮できないのか。野田政権の肝を握る輿石氏の力量が試される日々が続く。(やまうち まさゆき)
◇
【プロフィル】近藤勇
こんどう・いさみ 天保5(1834)年、武蔵国(東京都)多摩に生まれる。天然理心流の剣術を学び、文久3(1863)年、幕府の浪士隊に加わって京都に行き、新選組を結成。隊内の粛清を経て局長となり、反幕派を取り締まる。慶応4(1868)年の鳥羽・伏見の戦いののち江戸に退き、甲府へ進軍するが敗北。同年、捕らえられて斬首された。
「近藤は大久保大和、土方歳三(ひじかた・としぞう)は内藤隼人と改名した。これは、甲州人の歴史へのこだわりを察知し、武田家や甲州に縁のある大久保や内藤の姓をあえて称したためだという」……なるほど。
「東山道先鋒(とうさんどうせんぽう)総督府参謀だった土佐藩の乾(いぬい)退助は、信玄の宿老だった板垣信方(のぶかた)の死から320年にあたるため、甲斐源氏の流れを汲む板垣氏の苗裔(びょうえい)という家伝を示して板垣退助と姓を改めたのだ。この策で板垣は甲州人の支持を得て、勝沼の戦いで大久保大和こと近藤勇の甲陽鎮撫隊を撃破したという説もあるほどだ」……こっちは知ってましたが。
「 近藤は甲州での敗戦後、京都以来の同志、永倉新八や原田左之助らと訣別(けつべつ)し、旧幕府歩兵らを率いて下総国流山に屯集(とんしゅう)した。だが香川敬三率いる新政府軍に包囲され、やがて出頭、板橋宿まで連行された。そこで正体が見破られ、捕縛後に斬首されたことはよく知られている。しかし近藤にとって、甲州での勝ち戦さが成らなかったにせよ、人生の最期を故郷で晴れがましく送れたのは幸いであった」……山内先生、近藤勇に暖かい視点でありがとうございます。
小三治師匠がトリの鈴本を見たいということで、行ってきました。
さん坊「真田小僧」
こみち「高砂や」
女流の中で一番うまい、こみちさん。豆腐の呼び声風な「たかーさごや」が楽しい。
仙三郎社中 太神楽
福治「堀の内」
文左衛門「のめる」
ハチ公と半公のキャラづくりがうまく、スピード感あふれる攻防。さらに携帯電話が鳴ったとこにもツッコミが速い。いいなぁ、文左衛門。
ロケット団 漫才
やっぱり漫才の若手の中では突出している。北の国からネタが一番受ける。
小燕枝 「小言幸兵衛」
心中の場面が笑えた。
世津子 マジック
今日も大成功。
琴調 講談「愛宕の春駒」
中入り
紫文 三味線漫談
今日は面白かった。大物の師匠の前だと燃えるタイプ?
小三治「転宅」
石川五右衛門についてひとしきり解説。転宅の間抜けな泥棒が、小三治にかかると、何てかわいい。情けなくて、にくめない。
さん坊「真田小僧」
こみち「高砂や」
女流の中で一番うまい、こみちさん。豆腐の呼び声風な「たかーさごや」が楽しい。
仙三郎社中 太神楽
福治「堀の内」
文左衛門「のめる」
ハチ公と半公のキャラづくりがうまく、スピード感あふれる攻防。さらに携帯電話が鳴ったとこにもツッコミが速い。いいなぁ、文左衛門。
ロケット団 漫才
やっぱり漫才の若手の中では突出している。北の国からネタが一番受ける。
小燕枝 「小言幸兵衛」
心中の場面が笑えた。
世津子 マジック
今日も大成功。
琴調 講談「愛宕の春駒」
中入り
紫文 三味線漫談
今日は面白かった。大物の師匠の前だと燃えるタイプ?
小三治「転宅」
石川五右衛門についてひとしきり解説。転宅の間抜けな泥棒が、小三治にかかると、何てかわいい。情けなくて、にくめない。
トリの小三治師匠が出ないとは言え、土曜日の夜の鈴本がこんなに空いているのは初めて(汗)。市馬師匠が代演なのに、くすん。
ちょっと落語のラインナップが少ない番組だったけど、このメンバーなら、悪くないと思うんだけど。
なな子「子ほめ」
正蔵の前座だったのね(°°;)←何を驚いている^_^;。
仙三郎社中 太神楽
上野にパンダが来たことを記念に、パンダを傘回し(^^)。
遊一「元犬」
舌出してはぁはぁしているところが、いっちゃってる感じでした^_^;。
歌武蔵「相撲部屋外伝」
毎回毎回時事ネタが盛り込まれていて楽しい。
遊平かほり 漫才
たぶん初めて。夫婦漫才。
小燕枝 「強情灸」
自分は寄席にいるんだなぁとしみじみする一時をありがとうございます。
世津子 マジック
今日も大成功。ジョブズ死去がトップページの日経新聞を細かくちぎって、なでしこジャパン優勝のスポーツ紙に変えたマジックは楽しい。
琴調 「浜野矩随」
やっぱり、このネタは講談で聴く方が違和感ない。落語で聴くと、息子が職人として世に出るかどうかのために自害をはかる母の存在が重た過ぎるんだな……。
中入り
ホンキートンク 漫才
見るたびに微妙に話題が変わっているのがわかる。市馬師匠の直前の出番で歌うのはまずかろうと思う(爆)のだけど、昭和の歌謡曲が得意な市馬師匠にはネタがわかるまい^_^;。
市馬 「大工調べ」
わーい、「大工調べ」たっぷり、大岡越前のお取り調べも聴けて、サゲは「だいくはとうりゅう、しらべをごろうじろ(細工はりゅうりゅう、仕上げをごろうじろ)」ときた。
与太郎の一言一言に、座席が湧く。癒やしのオーラ出しまくりです、市馬師匠……今日も元気をいただきました、ごちそうさまです。
ちょっと落語のラインナップが少ない番組だったけど、このメンバーなら、悪くないと思うんだけど。
なな子「子ほめ」
正蔵の前座だったのね(°°;)←何を驚いている^_^;。
仙三郎社中 太神楽
上野にパンダが来たことを記念に、パンダを傘回し(^^)。
遊一「元犬」
舌出してはぁはぁしているところが、いっちゃってる感じでした^_^;。
歌武蔵「相撲部屋外伝」
毎回毎回時事ネタが盛り込まれていて楽しい。
遊平かほり 漫才
たぶん初めて。夫婦漫才。
小燕枝 「強情灸」
自分は寄席にいるんだなぁとしみじみする一時をありがとうございます。
世津子 マジック
今日も大成功。ジョブズ死去がトップページの日経新聞を細かくちぎって、なでしこジャパン優勝のスポーツ紙に変えたマジックは楽しい。
琴調 「浜野矩随」
やっぱり、このネタは講談で聴く方が違和感ない。落語で聴くと、息子が職人として世に出るかどうかのために自害をはかる母の存在が重た過ぎるんだな……。
中入り
ホンキートンク 漫才
見るたびに微妙に話題が変わっているのがわかる。市馬師匠の直前の出番で歌うのはまずかろうと思う(爆)のだけど、昭和の歌謡曲が得意な市馬師匠にはネタがわかるまい^_^;。
市馬 「大工調べ」
わーい、「大工調べ」たっぷり、大岡越前のお取り調べも聴けて、サゲは「だいくはとうりゅう、しらべをごろうじろ(細工はりゅうりゅう、仕上げをごろうじろ)」ときた。
与太郎の一言一言に、座席が湧く。癒やしのオーラ出しまくりです、市馬師匠……今日も元気をいただきました、ごちそうさまです。
最近は落語ブログ化している気がする当ブログですが、管理人の白牡丹はiPhoneアプリで薄桜鬼待受絵草子土方歳三版を購入し、三木眞一郎さんの土方ヴォイスに毎日励まされて仕事しております。
もう10年以上も毎週木曜日に買っている「週刊モーニング」で、新選組ものが連載開始となりました。
「とんがらし」桐村海丸
ちば賞大賞の新鋭・桐村海丸の新連載は新撰組の草創期
……総司よりも左之助がお子ちゃまな作品は初めてかも知れない(^_^;)。
もう10年以上も毎週木曜日に買っている「週刊モーニング」で、新選組ものが連載開始となりました。
「とんがらし」桐村海丸
ちば賞大賞の新鋭・桐村海丸の新連載は新撰組の草創期
本日10月6日に発売されたモーニング45号(講談社)にて、「しおかぜ」で第59回ちばてつや賞一般部門大賞を受賞した桐村海丸の短期集中連載「とんがらし」がスタートした。
「とんがらし」は新撰組隊士の若き日々を描く物語。第1話では沖田総司と原田左之助の出会いが描かれた。
このほか今号では、うえやまとち「クッキングパパ」の江戸時代編「遠山のくっ金さん」を収録。巻頭カラーでは、同心1ヶ月分の給料で作れる、江戸時代のご馳走を再現したグルメ企画が行われている。
……総司よりも左之助がお子ちゃまな作品は初めてかも知れない(^_^;)。
三連休、談笑さん出演「笑神降臨」に喬太郎・談笑の二人会に、とどめは談笑独演会@にぎわい座。こんなに談笑さんに浸って明日から普通に勤め人に戻れるのか自分……(汗)。
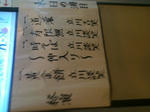
初めて前座の吉笑くん聴きました。
ネタは昨日喬太郎師がトリでかけた「道灌」です。
特に柳家の前座さんは最初に覚えるネタとして開口一番にかける「道灌」ですが、前座のうちはまるまる覚えたのをリズムとメロディを再現できるように復唱できればいいのだそうです。お客さんを笑わそうとするより、リズムとメロディを身につけることが大事な修行だとか。
でも、たかだかライブ歴3年弱のあたしですが、吉笑さんについては自信をもって「前座レベルじゃねぇ」と感じました。リズムとメロディは入門10ヶ月の前座と思えないぐらい緩急が自由自在だし、ちょっとしたことで笑いを取る余裕もある。
入門10ヶ月だろうと11ヶ月だろうと、これだけできているのなら、二つ目に昇進賛成です。それに、立川流は広小路以外に寄席がないので、前座では修行の場が限られます。さっさと二つ目になって、揉まれて芽を出してね。
「寿限無」立川談笑
談笑師匠、昨日の喬太郎師との二人会の様子もちらりと伺わせつつ、名前にまつわるマクラを振ります。相撲のしこ名とか。これは、ひょっとして。
……わーい、談笑版「寿限無」初めてです。時々ちらっと放送禁止用語が混じっていたのは私の気のせいかも知れません(爆)。「ジュテームジュテーム」は、最近、白鳥さん版もありますが、それ以降が談笑版はもっとエロい、というか、下ネタ(^_^;)。
「時そば」立川談笑
一席やった後に高座を立たず、おしゃべりを続ける談笑師。ということは、中入り前にもう一席だな(ガッツポーズ)。
もぉ、昨日の高座の前に「新角」で食べたコロッケそばがまずかったとか、中野北口の「かさい」のそばが想像を絶するほどすっごいってマクラだったら……アレ以外ないですね(^_^;)。
でも、ちょっと寄り道して、下北半島の「九艘泊」は津軽弁で「くそどまり」と自分たちの地名を呼んでるとか、沖縄の人たちは台風が来るとドライブに出るとか、三島のドライブインのおじいちゃんはマイペースだとか、蕎麦ねたからちょっとだけ外しておいて、来ましたね。
陰々滅々な時そば、また聴けて嬉しい〜(^^)。
中入り
「黄金餅」立川談笑
このラインナップで後半は「品川心中」とか「居残り佐平次」とかないだろうなぁと思いつつ(聴きたかったなぁ、談笑版で)、突入したらやっぱり「黄金餅」だった。
関西に14年住んでたけど通天閣には一度も観光していない自分が言うのも何だけど、でも大阪の串揚げは美味しいと思う。ちなみに日本食になれていない外人さんも大喜び、食べやすいのよ。
で、ずっしり重い談笑版の中入り後のネタとしては、いいと思う。下谷から始まって麻布までの言い立て、ちょこっとだけ噛んだけど、はっきり発音することを優先してごまかさなかったのはよかったと思うし、今の世界では上野御徒町から都営地下鉄大江戸線で麻布十番まで一本ってのが、いいよね。
遠火の近火で焼かれた西念さんの遺体がどんなもんだったか想像したくはないのですが、腹から取り出した黄金を元手に菓子屋を開いて儲けたって馬鹿話で終わらせないのが談笑さんだよね。因果は巡る……ってところで、ぞくっとさせておしまい。
ぱちぱちぱち。また近々、吉笑さんと談笑さん、見たいです。
初めて前座の吉笑くん聴きました。
ネタは昨日喬太郎師がトリでかけた「道灌」です。
特に柳家の前座さんは最初に覚えるネタとして開口一番にかける「道灌」ですが、前座のうちはまるまる覚えたのをリズムとメロディを再現できるように復唱できればいいのだそうです。お客さんを笑わそうとするより、リズムとメロディを身につけることが大事な修行だとか。
でも、たかだかライブ歴3年弱のあたしですが、吉笑さんについては自信をもって「前座レベルじゃねぇ」と感じました。リズムとメロディは入門10ヶ月の前座と思えないぐらい緩急が自由自在だし、ちょっとしたことで笑いを取る余裕もある。
入門10ヶ月だろうと11ヶ月だろうと、これだけできているのなら、二つ目に昇進賛成です。それに、立川流は広小路以外に寄席がないので、前座では修行の場が限られます。さっさと二つ目になって、揉まれて芽を出してね。
「寿限無」立川談笑
談笑師匠、昨日の喬太郎師との二人会の様子もちらりと伺わせつつ、名前にまつわるマクラを振ります。相撲のしこ名とか。これは、ひょっとして。
……わーい、談笑版「寿限無」初めてです。時々ちらっと放送禁止用語が混じっていたのは私の気のせいかも知れません(爆)。「ジュテームジュテーム」は、最近、白鳥さん版もありますが、それ以降が談笑版はもっとエロい、というか、下ネタ(^_^;)。
「時そば」立川談笑
一席やった後に高座を立たず、おしゃべりを続ける談笑師。ということは、中入り前にもう一席だな(ガッツポーズ)。
もぉ、昨日の高座の前に「新角」で食べたコロッケそばがまずかったとか、中野北口の「かさい」のそばが想像を絶するほどすっごいってマクラだったら……アレ以外ないですね(^_^;)。
でも、ちょっと寄り道して、下北半島の「九艘泊」は津軽弁で「くそどまり」と自分たちの地名を呼んでるとか、沖縄の人たちは台風が来るとドライブに出るとか、三島のドライブインのおじいちゃんはマイペースだとか、蕎麦ねたからちょっとだけ外しておいて、来ましたね。
陰々滅々な時そば、また聴けて嬉しい〜(^^)。
中入り
「黄金餅」立川談笑
このラインナップで後半は「品川心中」とか「居残り佐平次」とかないだろうなぁと思いつつ(聴きたかったなぁ、談笑版で)、突入したらやっぱり「黄金餅」だった。
関西に14年住んでたけど通天閣には一度も観光していない自分が言うのも何だけど、でも大阪の串揚げは美味しいと思う。ちなみに日本食になれていない外人さんも大喜び、食べやすいのよ。
で、ずっしり重い談笑版の中入り後のネタとしては、いいと思う。下谷から始まって麻布までの言い立て、ちょこっとだけ噛んだけど、はっきり発音することを優先してごまかさなかったのはよかったと思うし、今の世界では上野御徒町から都営地下鉄大江戸線で麻布十番まで一本ってのが、いいよね。
遠火の近火で焼かれた西念さんの遺体がどんなもんだったか想像したくはないのですが、腹から取り出した黄金を元手に菓子屋を開いて儲けたって馬鹿話で終わらせないのが談笑さんだよね。因果は巡る……ってところで、ぞくっとさせておしまい。
ぱちぱちぱち。また近々、吉笑さんと談笑さん、見たいです。
よみうりホールを満員にする顔合わせ。わくわくしちゃう♪
テレビカメラ入ってる(WOWOWらしい)のに放送禁止用語飛ばしまくりのキョン師と談笑師。全編放送はないでしょうね、ライブ万歳(笑)。
開口一番「時そば」立川こしら
広瀬さんに言わせると「下手だけど面白い」こしら初体験。
何だろう、たとえば白鳥さんとか談笑さんのようなひねりもないのに、今どきのお兄ちゃんっぽいこしらが普通に「時そば」やってるのがおかしい。
喬太郎「ほんとのこというと」
テレビカメラが入っているのに、これをかけるかキョン師っ(爆)。
ゆみこが彼氏の家族に挨拶に行って歓待されるのだけど、こんないい家族のところに嫁に行けないと号泣。唐揚げよりもナルト丸かじりが好き、と聞いてお父さんは弟に5000円分のナルトを買いに出す。次は、こんないい弟さん、自分の弟はヤクまみれで売人になりさがって……家族、弟をシンナー買いに出す。さらに次は、こんないい妹さん、自分の妹はデリヘル嬢(妙にリアリティのある、池袋のなんとかって店名)……家族、妹を援交に出す。
あげくの果ては、ゆみこ、「あなた、優しすぎて……(以下略)」。
談笑「粗忽長屋」
ネタだしは「粗忽長屋」だけど中身はもちろん談笑版「粗忽だらけ長屋」。
マクラは読売ホール近くの「新角」という立ち食いそば屋にはじまり、中野北口「かさい」、杉並「小ばやし」、と何だか行ってみたいような行ってみたくないような蕎麦屋の話。さらに、下北半島の九艘泊なる地での体験、沖縄では台風が来るとドライブに行こうという人々の気質、静岡県の三島で入った食堂のおじいちゃんのマイペースなオーダー処理の仕方と、爆笑なマクラの後に、本編。
そして、「キ××イ」「創×学×」と放送禁止用語をかっちり入れる(ツイッターねただと、WOWOW収録は談笑師匠目当てだって話を後で聞いたのですが^_^;)。
相変わらず、粗忽だらけ。オチはオレじゃなくて「お前だー」って(°°;)。
(中入り)
談笑「イラサリマケー」
テレビカメラが入っていたら、ないだろうなと思っていたのに、まさかの「イラサリマケー」(爆)。談笑師匠、ステキすぎる(笑)。冒頭は堂々「東×見×録」「月××」の悪口だし。
「オスメス」「エロエロ」は「ネコミにイマダメ、ユビクライにテサバキ」中略「いかないと、しろうとたいかい」。金馬が得意とした「居酒屋」の改作、炸裂。
喬太郎「道灌」
トリで「道灌」取れるのが噺家の理想とは聞くが、キョン師、割と普通に「道灌」やって、聞かせてくれたと思う(時にはしーんとさせ、時には爆笑させ)。でも確か途中にやっぱり放送禁止用語入っていた気がする(^_^;)。
座談
MCはぴあの戸塚さん。こしら曰く「話を壊す」というが、談笑・喬太郎の前には話を振るのもびびっているような。キョン師と談笑師が暴走するのを止められるはずもなく(爆)。
クライマックスはキョン師の「3分でやれる芝浜」こと「ブルーライト横浜」の替え歌。さらに「芝浜」ならぬ「芝カマ」のアイディアを披露。これには、改作落語を武器にする談笑師もたじたじな感じ。
キョン師の師匠であるさん喬師匠が「けれんはいけません」と大手町落語会の楽屋で(誰に言うともなく、でも誰に言ったかわかるような様子で)言った直後に談笑師がかけたのが「片棒・改」と知って、喝采。「ミッキー!」とかやって、下げた楽屋でさん喬師匠が鬼のような表情だったとか(苦笑)……。
キョン師曰く、弟子入りした時から言われ続けながら新作落語とかやっているそうだから、談笑師も引き続き持論の落語論を発展し続けて欲しい。
それにしてもキョン師、自由自在に高座で寝転んで色っぽいポーズとったり、半分でんぐり返ってみたり、自在ですねぇ。
テレビカメラ入ってる(WOWOWらしい)のに放送禁止用語飛ばしまくりのキョン師と談笑師。全編放送はないでしょうね、ライブ万歳(笑)。
開口一番「時そば」立川こしら
広瀬さんに言わせると「下手だけど面白い」こしら初体験。
何だろう、たとえば白鳥さんとか談笑さんのようなひねりもないのに、今どきのお兄ちゃんっぽいこしらが普通に「時そば」やってるのがおかしい。
喬太郎「ほんとのこというと」
テレビカメラが入っているのに、これをかけるかキョン師っ(爆)。
ゆみこが彼氏の家族に挨拶に行って歓待されるのだけど、こんないい家族のところに嫁に行けないと号泣。唐揚げよりもナルト丸かじりが好き、と聞いてお父さんは弟に5000円分のナルトを買いに出す。次は、こんないい弟さん、自分の弟はヤクまみれで売人になりさがって……家族、弟をシンナー買いに出す。さらに次は、こんないい妹さん、自分の妹はデリヘル嬢(妙にリアリティのある、池袋のなんとかって店名)……家族、妹を援交に出す。
あげくの果ては、ゆみこ、「あなた、優しすぎて……(以下略)」。
談笑「粗忽長屋」
ネタだしは「粗忽長屋」だけど中身はもちろん談笑版「粗忽だらけ長屋」。
マクラは読売ホール近くの「新角」という立ち食いそば屋にはじまり、中野北口「かさい」、杉並「小ばやし」、と何だか行ってみたいような行ってみたくないような蕎麦屋の話。さらに、下北半島の九艘泊なる地での体験、沖縄では台風が来るとドライブに行こうという人々の気質、静岡県の三島で入った食堂のおじいちゃんのマイペースなオーダー処理の仕方と、爆笑なマクラの後に、本編。
そして、「キ××イ」「創×学×」と放送禁止用語をかっちり入れる(ツイッターねただと、WOWOW収録は談笑師匠目当てだって話を後で聞いたのですが^_^;)。
相変わらず、粗忽だらけ。オチはオレじゃなくて「お前だー」って(°°;)。
(中入り)
談笑「イラサリマケー」
テレビカメラが入っていたら、ないだろうなと思っていたのに、まさかの「イラサリマケー」(爆)。談笑師匠、ステキすぎる(笑)。冒頭は堂々「東×見×録」「月××」の悪口だし。
「オスメス」「エロエロ」は「ネコミにイマダメ、ユビクライにテサバキ」中略「いかないと、しろうとたいかい」。金馬が得意とした「居酒屋」の改作、炸裂。
喬太郎「道灌」
トリで「道灌」取れるのが噺家の理想とは聞くが、キョン師、割と普通に「道灌」やって、聞かせてくれたと思う(時にはしーんとさせ、時には爆笑させ)。でも確か途中にやっぱり放送禁止用語入っていた気がする(^_^;)。
座談
MCはぴあの戸塚さん。こしら曰く「話を壊す」というが、談笑・喬太郎の前には話を振るのもびびっているような。キョン師と談笑師が暴走するのを止められるはずもなく(爆)。
クライマックスはキョン師の「3分でやれる芝浜」こと「ブルーライト横浜」の替え歌。さらに「芝浜」ならぬ「芝カマ」のアイディアを披露。これには、改作落語を武器にする談笑師もたじたじな感じ。
キョン師の師匠であるさん喬師匠が「けれんはいけません」と大手町落語会の楽屋で(誰に言うともなく、でも誰に言ったかわかるような様子で)言った直後に談笑師がかけたのが「片棒・改」と知って、喝采。「ミッキー!」とかやって、下げた楽屋でさん喬師匠が鬼のような表情だったとか(苦笑)……。
キョン師曰く、弟子入りした時から言われ続けながら新作落語とかやっているそうだから、談笑師も引き続き持論の落語論を発展し続けて欲しい。
それにしてもキョン師、自由自在に高座で寝転んで色っぽいポーズとったり、半分でんぐり返ってみたり、自在ですねぇ。
カレンダー
| 10 | 2025/11 | 12 |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
カテゴリー
最新記事
(10/19)
(09/13)
(07/16)
(03/25)
(03/24)
最新コメント
[12/14 白牡丹(管理人)]
[12/14 ゆーじあむ]
[11/08 白牡丹(管理人)]
[11/07 れい]
[01/21 ゆーじあむ]
[11/15 白牡丹@管理人]
[11/15 ゆーじあむ]
[05/25 長谷川誠二郎]
[07/23 白牡丹@管理人]
[07/23 伊藤哲也]
最新TB
ブログ内検索
アーカイブ
最古記事
カウンター
プロフィール
HN:
白牡丹
性別:
非公開
自己紹介:
幕末、特に新選組や旧幕府関係者の歴史を追っかけています。連絡先はmariachi*dream.com(*印を@に置き換えてください)にて。
リンク
アクセス解析
Livedoor BlogRoll
本棚
