新選組・土方歳三を中心に取り上げるブログ。2004年大河ドラマ『新選組!』・2006正月時代劇『新選組!! 土方歳三最期の一日』……脚本家・制作演出スタッフ・俳優陣の愛がこもった作品を今でも愛し続けています。幕末関係のニュースと歴史紀行(土方さんに加えて第36代江川太郎左衛門英龍、またの名を坦庵公も好き)、たまにグルメねた。今いちばん好きな言葉は「碧血丹心」です。
ニッカンスポーツコムと日刊スポーツ紙面の連動企画「日本史なんでもランキング」、第4回は「あなたの好きな新選組隊士」ランキングです。
あなたの好きな新選組隊士
さっそく一票投じました。好きな隊士の選択は躊躇ありませんでしたが、好きな理由を書くのに30分以上迷いました……惚れた理由を言葉で説明するのは難しいものですね(汗)。
隊士名を「あいうえお」順で並べているので、筆頭が伊東甲子太郎であるのがなかなか新鮮。芹沢派とか高台寺党とか、なかなか充実したリストだと思います。史実にもとづいたフィクションでのイメージが先行しているんじゃないかと思われる隊士名が入っているところは若干気になるところですが、投票結果がどう出るか。
あなたの好きな新選組隊士
さっそく一票投じました。好きな隊士の選択は躊躇ありませんでしたが、好きな理由を書くのに30分以上迷いました……惚れた理由を言葉で説明するのは難しいものですね(汗)。
隊士名を「あいうえお」順で並べているので、筆頭が伊東甲子太郎であるのがなかなか新鮮。芹沢派とか高台寺党とか、なかなか充実したリストだと思います。史実にもとづいたフィクションでのイメージが先行しているんじゃないかと思われる隊士名が入っているところは若干気になるところですが、投票結果がどう出るか。
趣味が同じというのは意外に難しい。萌えの方向や暑苦しさが微妙に違うと、かえって「えっ!?(;゜ロ゜)」ということがあるからだ。
『萌えよ幕末女子』、そういう意味でこわごわ手に取ったが、ツボったツボった(爆)。「新番組」を「新選組」と読み違えるとか、観光ガイドが時々いい加減な知識だったりするとツッコミを入れるとか、実家の墓よりお慕いしている墓にお参りする回数がやたら多いとか。伊東甲子太郎が暗殺された木津屋橋の碑を捜して京都の人に道を聞いたらマイナー過ぎて地元の人もわからないとか。佐幕派ファンで松平容保は「容保様」「容保公」なのに徳川慶喜は「よしのぶ」だったり(「けいき」に加えて「二心公」「豚一公」も使いますが)。
佐幕派のイラストに新選組のおなじみの面々はもちろん、伊庭八郎、酒井玄蕃、星恂太郎、立見鑑三郎、細谷十太夫を配しているところがいいです。山川大蔵(小編の山川大蔵と龍馬と谷干城が出てくるマンガがよかった)もいいですね。
佐幕派と倒幕派という分け方になると掲載しにくいけど、伊東甲子太郎も当時の人たちが美男子と語り残してますよん♪
そして、ドラマ化された新選組ものの俳優さんから改めて新選組にキャスティングする企画、この人選が自分の好みとどんぴしゃりだったのには驚いた(苦笑)……原田泰造as近藤勇、山本耕史as土方歳三、中川勝彦(しょこたんのパパ)as沖田総司、堺雅人as山南敬助、遠藤憲一as永倉新八、山本太郎as原田左之助、オダギリジョーas斎藤一、中野誠也as山崎丞。左之助は史実で美形だと言い伝えられているのでビジュアルは他の方でもと思うものの、山本太郎が後に馬賊になりそうなキャラっぷりがよかった。欄外に生田斗馬as藤堂平助、佐々木蔵之介as伊東甲子太郎(ここは谷原章介がマイベストなんですが……玉木宏でも見てみたい)、向井理as河合耆三郎、伊勢谷友介as大石鍬次郎、豊川悦司as芹沢鴨(もうちょっと骨太い人がいいと思うけど)……ますますイケメン新選組だなぁ。新見錦は相澤一之さん希望♪
龍馬は内野聖陽さんと江口洋介さんの間で悩むところです。
昨日買った志の輔午前様らいぶ『三軒長屋』を見ながら。
山形
清河八郎 再評価の動き
東京
幕末動乱、幕開けの地桜田門 「桜田門外」の官庁街
品川・立会川の龍馬像が20歳に若返り-除幕式に島崎和歌子さんも
福井
福井藩と竜馬のかかわり浮き彫り 県文書館で幕末を紹介の企画展
京都
龍馬と新選組の熱き思い、京の街ではじける
兵庫
和田岬砲台 勝海舟が指導、龍馬も見たぜよ 金具など部品公開
米国
北米初の邦人入植地保存へ 会津出身「若松コロニー」
史実
「大警視」川路利良、鳥羽・伏見の戦いをつづる
山形
清河八郎 再評価の動き
「町人無礼切り」覆す新資料
旧清川村(現庄内町)出身で、尊皇攘夷運動などに携わった幕末の志士・清河八郎(1830~63年)が今年生誕180年を迎えたのを記念して、東京都内で来月5日、シンポジウムが開催される。地元からはバスツアーが企画され、山形大の山本陽史教授が、清河の再評価をテーマに基調講演を行う。清河の活動歴に暗い影を落としていた「酔って町人を切り、幕府に追われた」との通説を覆す新資料も見つかるなど、区切りの年に故郷の偉人を見直す動きが広がっている。
清河は若くして江戸に学び、文武両道を修めた才人で、新撰組の前身で尊皇攘夷を目指す「浪士組」を結成するなど尊皇攘夷、倒幕運動の先駆けとして活躍した。
新資料は、東京都千代田区の区立四番町歴史民俗資料館が数年前に収集した北町奉行所の同心・山本啓助の手帳。全6冊ある手帳のうちの一つに、逃亡する清河を追って新潟や山形などに出張した様子が記されている。
山本の手帳では、清河が町人を切ったとされる1861年5月20日の前日に、南北の町奉行所で清河ら8人を捕まえる命令が出され、打ち合わせをする記述があったという。今年3月、同資料館で手帳を活字化した際に発覚した。
日本近世史の研究をしている早稲田大非常勤講師の西脇康さん(54)は、「無礼を働いたとされる町人は清河を捕まえる手先だと考えられる。危機を察した清河は逃げたが、捕まえ損なった奉行所が失敗を隠そうと、清河が酔って一般の町民を切ったという話にすり替えたのでは」と推測する。
庄内町にある清河八郎記念館の斎藤清館長(80)も、「造り酒屋に生まれた清河が町人を切るほど酔うはずがないと思っていた。『町人無礼切り』の汚名が晴れてうれしい」と話している。
来月5日に大正記念館(東京都江東区)で行われるシンポジウムでは、山本教授が「清河八郎『回天の門』を再評価する」と題して基調講演を行うほか、山本教授や斎藤館長らによるパネルディスカッションも予定。6日には清河塾跡や北辰一刀流を学んだ千葉周作道場跡など、ゆかりの地を巡る見学会も行われる。
シンポジウムと見学会には庄内町からのバスツアーも企画されている。参加費は宿泊料なども含めて1人3万3000円。問い合わせや申し込みは日本海トラベル(0234・43・4312)へ。
(2010年11月14日 読売新聞)
東京
幕末動乱、幕開けの地桜田門 「桜田門外」の官庁街
幕府の大老、井伊直弼を水戸、薩摩浪士が暗殺した1860年の大事件を描く新作映画「桜田門外ノ変」。幕末動乱の幕開けを見届けた旧江戸城の桜田門(東京都千代田区)は、外国人観光客ら多くの人々でにぎわう。
映画の大老襲撃シーンは血みどろの激闘だ。大沢たかおさん演じる現場指揮官の関鉄之介がいたのは、今の桜田門交差点辺り。井伊家の彦根藩邸は約400メートル西の国会前庭にあったという。雪の中、かごで登城中だった直弼を“怪優”伊武雅刀さんが熱演。断末魔にあえぐ顔に無念がにじむ。
現在の“門外”には、「桜田門」の異名を持つ警視庁本部がそびえ、霞が関の中央官庁街が広がる。片側4車線の桜田通りは歩道も広々。農林水産省の前はカツラ、財務省はヒマラヤスギと多彩な街路樹も楽しめる。
襲撃の前夜、浪士18人が気勢を上げた品川の妓楼は跡形もないが、当日朝に集合した愛宕神社(東京都港区)は健在だ。86段の「男坂」を上った境内には「桜田烈士」の碑。呼応して挙兵するはずの薩摩藩が沈黙し、鉄之介が「桜田烈士か…」と劇中で自嘲(じちょう)する。
神社のある愛宕山の山頂は、東京23区内の自然地形の山では最も高い標高26メートル。勝海舟が西郷隆盛を誘って市中を見渡し、江戸城の無血開城をかけ合ったとの逸話が残る。
20分も歩けば桜田門。映画の終盤、官軍を率いて入城する西郷がつぶやく。「ここからでごわす。あっという間でござった」。決死の“義挙”から8年。歴史を変えた浪士たちの熱情を思った。
【ちなミニ】
愛宕神社境内の「和食T」は、東京産の食材にこだわる人気店。定番ランチ「愛宕丼」は、低脂肪のブランド鶏肉「東京しゃも」を使った親子丼に野菜汁などが付いて1500円。
品川・立会川の龍馬像が20歳に若返り-除幕式に島崎和歌子さんも
京急立会川駅前の品川区立北浜川児童遊園(品川区東大井2)で11月13日、「20歳の龍馬銅像除幕式」が行われた。
これまで設置されていた龍馬像は、高知市より寄贈されたプラスチック製。NHK大河ドラマ「龍馬伝」の影響で龍馬ブームとなり、立会川に訪れる観光客が増えたことから、地元有志がブロンズ像の制作を企画した。中心メンバーは東京京浜ロータリークラブ。
坂本龍馬が19歳の時、立会川の土佐藩が築いた浜川砲台で警備に加わったという説が残っていることから、新しい銅像は「20歳の龍馬像」。
除幕式には、若き日の龍馬を一目見ようと多くの人が詰め掛け、児童遊園前の商店街は見物客であふれ返った。濱野健品川区長、高地市商工観光部の古味勉部長、幕末史研究家の小美濃清明さんほか、ゲストには「龍馬伝」で坂本龍馬の兄嫁役を演じた島崎和歌子さんが登場した。
「多くの方にご協力いただき、この日を迎えられて感無量。品川の新しい名所となれば」とスピーチしたのは、東京京浜ロータリークラブの井上忠道会長。岡崎誠也高地市長の代読を務めた古味さんは「『龍馬伝』を契機に、龍馬にゆかりのある街同士が相互に協力していきたい。ぜひ高知の皆様にもお越しいただければ」とアピール。島崎さんが「私も坂本龍馬のような人を探したい。今日も探しに来たが、なかなか見当たらない」と、見物客の笑いを誘う場面も。
品川区在住で主婦の山本さんは「除幕式があると聞いて見に来たが、こんなに大勢の人がいるとは思わなかった。新しい龍馬像はりりしくてかっこよくなった」とほほ笑む。
龍馬像を富山の工場から運んだ運送事業を展開するハーツ(南大井5)の山口裕詮さんは、「銅像は520キロで、運搬距離は約440キロメートル。クレーン付きのトラックで往復12時間かけて運び、銅像を台座に差し込むのが大変だった。これを機に、地元・立会川がますます盛り上がれば」と期待を寄せる。
新しいブロンズ像設置によってプラスチック製の龍馬像は、土佐藩の下屋敷跡にある区立浜川中学校に移動した。
福井
福井藩と竜馬のかかわり浮き彫り 県文書館で幕末を紹介の企画展
幕末52件維新期の福井藩士が書いた書簡や手紙などに焦点を当てた福井県文書館の企画展「知られざる幕末維新 福井藩士の記録」が12月23日まで、福井市の同館で開かれている。未刊行の書簡集や史料を中心に展示してあり、松平春嶽と坂本竜馬のかかわりや、重要な役割を担いつつあった福井藩の実情などが浮かび上がる構成となっている。
原本24点、パネル5点、複製本53冊を展示。目付・青山小三郎の京都滞在時の記録「上京中日記」や、情報収集に当たっていた探索方・山本龍二郎(後の関義臣)の書簡「風雪書」などが展示されている。
県内初公開となる「上京中日記」は、1863(文久3)年6~8月の記録。竜馬が勝海舟の代理として京都の福井藩邸を訪れ春嶽の上京を促したのに対し、春嶽が藩を挙げて上京し武力で開国か鎖国か解決する考えであることを伝えたところ、竜馬が大変喜んだ―など、興味深い内容が記されている。
また、4千冊以上ある「大日本維新史料稿本」の中から、中老・中根雪江の「枢密備忘」を抜粋し紹介。春嶽の側近だった中根の記録から、春嶽の日々の政治的行動がうかがい知れる内容となっている。同館の吉田健・古文書調査専門員は「文久2年12月に竜馬のほか、高杉晋作や武市半平太、桂小五郎らが春嶽公に会いに来たが、実際に話をできたのは竜馬のみと記述されている。竜馬の考え方はこのとき既に高杉ら尊皇攘夷派と違い、春嶽と近かったと考えられる」と推測。また、最初は竜馬の名前を間違えて記述してあることなどから「春嶽と竜馬が初めて会ったのはこの時だろう」とも指摘する。
11月25日からは展示を入れ替え、ペリー来航時の緊迫した状況を伝える「遺愛帖(ちょう)」、春嶽側近による「御用日記」などの原本を紹介する。
京都
龍馬と新選組の熱き思い、京の街ではじける
幕末京都さながらに、坂本龍馬と新選組それぞれの熱い思いを引き継いだ二つのイベントが13日、京都市内で行われた。「龍馬よさこい10」では学生たちが「坂本龍馬に届け」と力強く踊り、「全国新選組サミット」(14日)の参加者たちはサミットを前に隊士の装いで京のまちを練り歩いた。
「龍馬よさこい10」は学生の実行委と霊山社中が開き、今年で3回目。昨年の倍の43チーム約1700人の学生が全国から集まり、高知の「よさこい踊り」や京都の「京炎そでふれ」などの創作踊りを市内3会場で披露した。
京都三条会商店街(中京区)では学生たちが「せい」「やー」と声を張り上げて踊りながら商店街を行進、熱気に包まれた。
「全国新選組サミット」は京都市では2回目の開催で、14日に壬生寺(同区)で開かれる。13日は、土方歳三が生まれた東京都日野市など新選組ゆかりの地の関係者ら16団体53人が集まり、壬生寺から三条通の池田屋跡まで歩いた。
羽織や鉢金を身に着けた一行が道中で「えい、えい、おー」と勝ちどきをあげると、道行く人は写真を撮って笑顔を見せていた。
兵庫
和田岬砲台 勝海舟が指導、龍馬も見たぜよ 金具など部品公開
【兵庫】幕末に外国船を攻撃する目的で作られた和田岬砲台(神戸市兵庫区)を解体修理で取り外した金具などが来月18日、同区の兵庫公会堂で公開される。神戸市教委は「砲台が完成した1864年は、神戸海軍操練所が設置された年。建設中の砲台を坂本龍馬も間違いなく見ていた」と話している。
発表した市教委によると、三菱重工業神戸造船所内にある同砲台は直径約15メートル、高さ約12メートルの円形で、勝海舟の指導で完成。幕末期の建物には珍しく木造建築に鉄製のボルトやくぎなどが使われるなど西洋技術を模倣しており、修理後は元に戻されるために部品が間近で見られるのは今回が唯一の機会という。内部は木造、外部は花崗岩製の2階建てで、11カ所から大砲を放つことが可能だが、実際に大砲が配置されたかは不明。現在は国の史跡に指定されている。
同砲台は木造部が腐敗したため07年度から文化庁と県、同市の補助で同社が初の本格的な解体修理工事を開始し、13年3月に終了する予定。公開は午後1時~2時半で、砲台を設置する台場に詳しい東京都品川区立品川歴史館の学芸員による講演会などもある。
定員200人。参加には応募が必要で、往復はがきに「砲台講演会希望」と記し、参加者全員(最大3人)の住所▽氏名▽電話番号と、返信用はがきに返信先の住所と氏名を記入し、〒652-8570 兵庫区まちづくり課「砲台講演会」係まで(住所は不要)。今月19日必着。【吉川雄策】
米国
北米初の邦人入植地保存へ 会津出身「若松コロニー」
【ロサンゼルス共同】米カリフォルニア州の自然保護団体アメリカン・リバー・コンサーバンシー(ARC)は12日までに、1869年に福島県からの移民団が移住した北米最初の日本人入植地「若松コロニー」(同州ゴールドヒル)の跡地を、保存のため買い取ったことを明らかにした。
ARCは、入植者は米国の農業や技術などの進歩に貢献したと指摘。「若松コロニーの物語は(北米大陸初の英国人の永続的な入植地)ジェームズタウンや(英国のピルグリム・ファーザーズを乗せた)メイフラワー号(をめぐる歴史)と同じぐらい感動的だ」と強調した。跡地は、将来的に公園や博物館にする計画という。
入植者は戊辰戦争204件(68~69年)で敗れた会津藩の出身者らで、コロニーでは養蚕業や農業が行われたが、数年で崩壊。71年に19歳で亡くなった女性の墓や家畜小屋などが残っている。
資金集めには地元日系人団体なども協力したという。
史実
「大警視」川路利良、鳥羽・伏見の戦いをつづる
旧薩摩藩士で近代警察の父、「大警視」川路利良
かわじとしよし
が、鳥羽・伏見の戦い(1868年)に従軍した未発表の陣中書簡が、東京都内の川路家に残されていることが分かった。
砲弾飛び交う戦場の生々しい様子や、次々に倒れる戦友への思いなどが活写されている。
書簡は約2・8メートルの長さ(縦約16センチ)があり、開戦から2日がたった1月5日の戦闘から記述されている。川路は当時、35歳で足軽部隊の「兵具方
ひょうぐがた
一番隊長」を務めていた。
最大の激戦となった石清水八幡宮(京都府八幡市)の戦いでは、大砲の弾が飛ぶ中、長州軍などと共に「馬追いのごとく」突撃し、幕府軍を敗走させた。
書簡では、「世の中に戦ほど面白いものはない。戦も上手になったので討ち死にすることはないから心配しないでほしい」と自信を見せ、「江戸城へ乗りこみ徳川慶喜
よしのぶ
の首をとる」と意気込む様子も記されている。
大坂城の慶喜が江戸へ船で逃げたあとに、郷里の薩摩へ書き送ったらしい。
磯田道史・茨城大准教授(幕末史)は「薩摩人は基本的に寡黙だが、この書簡では親類の死を『愁嘆
しゅうたん
限りなき候』と後から書き加えるなど、感情を交え生き生きとした描写があり、とても貴重」と話している。
川路利良(川路利永さん提供)
◆川路利良=1834~79年。戊辰戦争で活躍し、維新後、新政府に東京の治安維持担当に登用される。明治5年(1872年)に近代警察制度を学ぶためにヨーロッパへ渡り、帰国後の74年に東京警視庁が創設されると大警視(警視総監)となった。西南戦争では、官軍として西郷隆盛率いる薩摩軍と戦った。
(2010年11月13日12時54分 読売新聞)
土曜の午後、まったりと志の輔らくご。1500人収容の会場は満員でした。昼夜で3000人の観客を動員してしまう志の輔師匠、さすがです。
しのすけドットコム 第3回日の出寄席 公演情報
1. 開口一番「牛ほめ」立川志の彦
前座修行3年目だそうです。1500人の観客の前で高座に上がって、どんな気持ちだったでしょうね。一通りやり遂げましたが、やはり笑いどころは少ないかな。
2.「ディアファミリー」立川志の輔
尖閣諸島での事件、横浜のAPECなど時事ネタをひとくさり。
わーい、「ディアファミリー」ライブで聴くのは初めて。勤続30周年の日に早帰りするお父さんを待つ家族の元に、まず宅急便(用意していたクラッカーをここで全部使ってしまう)。その宅急便の巨大な箱から出てきたのは、狩猟を趣味とする社長からお父さんに送られた、鹿の頭部の剥製。ほら、アメリカ映画とかに山荘の暖炉のある居間に飾られてる、立派な角のついた、アレですよ。とまどい、見なかったことにしておこうと箱のふたを閉じたところに、お父さん帰宅。
公団住宅のどこにそんな鹿の頭部を置くのかと、お父さんも悩む。でも、どんなに自分の意に沿わないものでも、30年間の自分のサラリーマン生活を記念して送られたものをすぐに処分する気にもなれない。で、押し入れに収納しようとすると、ジューサーミキサーとか、もちつき器とか、お母さんの美顔器(ローンまだ終わってない)、息子のスノボとかサーフボードとか、娘の雛飾りとか、昔懐かしいぶら下がり健康棒とか、出てくる出てくる。鹿の頭を収納するスペースを巡って、お母さんが嫁入りした時に持ってきた秘蔵の『サザエさん』全70巻との全面対決となり、夫婦は破綻寸前に……(汗)。
ゲラゲラ笑いが止まらない〜。そして、中入りになって、斜め後ろの女性客から「すいません、笑い声が大きくて気になってしょうがないんです。控えてくれませんか」と注意を受けてしまった……ええっ、志の輔らくごを聞いて笑うのを抑えてくれと言われても(汗)。
中入り
3. ゲスト 長唄三味線&トーク 松永鉄九郎
めくりがなかったので確かではないけど、もらったチラシの写真から判断して、たぶんゲストはこの方。
松永鉄九郎 公式サイト
以前の公演で、グループというかユニットでゲスト出演された方ではないかな。志の輔さんのファンで楽屋に出入りしているうちにゲスト招待されたと自己紹介されてました。
歌舞伎の中で出てくる音曲について軽妙なトークで解説しながら演奏するというスタイル。佃という曲は隅田川の流れを表しているとか、大ざつまは舞台の場面転換につかわれるとか、とても勉強になりました。落語家の出囃子にも長唄の一部が使われていたりする(佃は談笑さんの出囃子ですね、野球拳の方が多いですし、最近はときどきミッション・インポッシブルだったりしますが)ので、親近感。
4. 「柳田格之進」立川志の輔
マクラは先週のにぎわい座でも聞いた長崎公演の楽屋噺ですが、前回のシーボルト記念館での話はなかったです。同じようなマクラなんで「え、でも志の輔師匠のことだから、先週と同じ『新版しじみ売り』ってことはないよな」と思ったら……わーい、志の輔版「柳田格之進」。
Wikipedia 柳田格之進
志の輔さんは、いきなり、店の主人に預けた五十両を捜しに来る番頭さんと、江戸で一二を争う質屋の主人との会話から。そこで、囲碁が趣味の主人が離れで碁友達で浪人の柳田格之進と碁を打っている最中に主人に手渡した五十両がなくなっていたという事情が判明。
浪人ながら高潔な柳田の人柄に感じ入った主人は、柳田を疑う番頭に釘を刺す。しかし、三十年も主人に仕えてきた自分よりも、たった十日ばかり碁を打つ相手として離れに通い始めた貧乏浪人が信用されることに納得できず、番頭は柳田の住む長屋を訪ね、かまをかける。
疑われたことに激怒する柳田だが、武士の誇りと体面を傷つけられるよりはと切腹を決意し、金を用立てておくから明日昼に取りに来るよう番頭に言い渡す。それを聞いていた娘のきぬ、父が切腹するよりもと、自分が吉原に身売りすると申し出る。
翌日、番頭の話を聞いた主人は真っ青になって柳田の長屋を番頭と共に訪れたが、すでに引き払った後だった。
そして、年末のすす払いで、離れの額の裏から五十両が見つかる。主人が厠に立つ時に、ここに置いたままになっていたのを失念したのだ。番頭は柳田に「万が一あの五十両が見つかったら、自分の汚い首を差し上げる。それで足りないなら、旦那様の首も差し上げる」と豪語していたものだから、真っ青になる。
年明けて年始回りをしていた番頭、湯島の切り通しですれ違った立派な着物の侍に声をかけられる。何と、仕官かなって江戸留守居役になった柳田格之進。再会を祝って一献と誘われるも気が気でなく、五十両みつかったことを告げて頭を下げる。柳田は翌日店を訪ねると約束。
首を差し出すことを予測して眠れぬ夜を過ごした番頭、柳田が娘きぬ(志の輔さんの落語では子細は説明されなかったが、吉原にいったん身売りしたところを仕官かなった父に請け出されたのだろう)立ち会いで主人もろとも首を打たれる覚悟をする。主人と番頭がお互いをかばう場面に、柳田は代わりに、「手が誤って」主人が大切にしていた碁盤をまっぷたつに。もう一度主人と番頭に刀を向けるところを娘のきぬが「果たされました」と止め、柳田は「さすが柳田の娘」と娘を褒める。
演者によって、娘きぬは吉原で病没していたり、正気を失っていたところを助け出されて番頭の必死の看病で正気を取り戻して番頭と夫婦になったり(同性としては、この展開はどうよと首をかしげるのだが)、落髪していたり、いろいろ。今日の志の輔さん版ではやや説明不足だったけど、吉原から請け出され、柳田の遺恨を果たす場に見分役として立ち会ったと思われる。彼らのせいで自分が負った苦難を、主従の思いに免じて赦すという、菩薩だなぁと感じられる役柄。
柳田の潔癖な武士らしい人柄とか、主人が柳田に傾倒することに嫉妬する番頭はちょっとマンガチックにして嫌らしさを消すとか、志の輔らくごらしい出来。
今日も堪能しました、ありがとうございました。次回はパルコかな……今日も満員だったのでチケット取りは困難を極めると思いますが、頑張ります。
しのすけドットコム 第3回日の出寄席 公演情報
1. 開口一番「牛ほめ」立川志の彦
前座修行3年目だそうです。1500人の観客の前で高座に上がって、どんな気持ちだったでしょうね。一通りやり遂げましたが、やはり笑いどころは少ないかな。
2.「ディアファミリー」立川志の輔
尖閣諸島での事件、横浜のAPECなど時事ネタをひとくさり。
わーい、「ディアファミリー」ライブで聴くのは初めて。勤続30周年の日に早帰りするお父さんを待つ家族の元に、まず宅急便(用意していたクラッカーをここで全部使ってしまう)。その宅急便の巨大な箱から出てきたのは、狩猟を趣味とする社長からお父さんに送られた、鹿の頭部の剥製。ほら、アメリカ映画とかに山荘の暖炉のある居間に飾られてる、立派な角のついた、アレですよ。とまどい、見なかったことにしておこうと箱のふたを閉じたところに、お父さん帰宅。
公団住宅のどこにそんな鹿の頭部を置くのかと、お父さんも悩む。でも、どんなに自分の意に沿わないものでも、30年間の自分のサラリーマン生活を記念して送られたものをすぐに処分する気にもなれない。で、押し入れに収納しようとすると、ジューサーミキサーとか、もちつき器とか、お母さんの美顔器(ローンまだ終わってない)、息子のスノボとかサーフボードとか、娘の雛飾りとか、昔懐かしいぶら下がり健康棒とか、出てくる出てくる。鹿の頭を収納するスペースを巡って、お母さんが嫁入りした時に持ってきた秘蔵の『サザエさん』全70巻との全面対決となり、夫婦は破綻寸前に……(汗)。
ゲラゲラ笑いが止まらない〜。そして、中入りになって、斜め後ろの女性客から「すいません、笑い声が大きくて気になってしょうがないんです。控えてくれませんか」と注意を受けてしまった……ええっ、志の輔らくごを聞いて笑うのを抑えてくれと言われても(汗)。
中入り
3. ゲスト 長唄三味線&トーク 松永鉄九郎
めくりがなかったので確かではないけど、もらったチラシの写真から判断して、たぶんゲストはこの方。
松永鉄九郎 公式サイト
以前の公演で、グループというかユニットでゲスト出演された方ではないかな。志の輔さんのファンで楽屋に出入りしているうちにゲスト招待されたと自己紹介されてました。
歌舞伎の中で出てくる音曲について軽妙なトークで解説しながら演奏するというスタイル。佃という曲は隅田川の流れを表しているとか、大ざつまは舞台の場面転換につかわれるとか、とても勉強になりました。落語家の出囃子にも長唄の一部が使われていたりする(佃は談笑さんの出囃子ですね、野球拳の方が多いですし、最近はときどきミッション・インポッシブルだったりしますが)ので、親近感。
4. 「柳田格之進」立川志の輔
マクラは先週のにぎわい座でも聞いた長崎公演の楽屋噺ですが、前回のシーボルト記念館での話はなかったです。同じようなマクラなんで「え、でも志の輔師匠のことだから、先週と同じ『新版しじみ売り』ってことはないよな」と思ったら……わーい、志の輔版「柳田格之進」。
Wikipedia 柳田格之進
志の輔さんは、いきなり、店の主人に預けた五十両を捜しに来る番頭さんと、江戸で一二を争う質屋の主人との会話から。そこで、囲碁が趣味の主人が離れで碁友達で浪人の柳田格之進と碁を打っている最中に主人に手渡した五十両がなくなっていたという事情が判明。
浪人ながら高潔な柳田の人柄に感じ入った主人は、柳田を疑う番頭に釘を刺す。しかし、三十年も主人に仕えてきた自分よりも、たった十日ばかり碁を打つ相手として離れに通い始めた貧乏浪人が信用されることに納得できず、番頭は柳田の住む長屋を訪ね、かまをかける。
疑われたことに激怒する柳田だが、武士の誇りと体面を傷つけられるよりはと切腹を決意し、金を用立てておくから明日昼に取りに来るよう番頭に言い渡す。それを聞いていた娘のきぬ、父が切腹するよりもと、自分が吉原に身売りすると申し出る。
翌日、番頭の話を聞いた主人は真っ青になって柳田の長屋を番頭と共に訪れたが、すでに引き払った後だった。
そして、年末のすす払いで、離れの額の裏から五十両が見つかる。主人が厠に立つ時に、ここに置いたままになっていたのを失念したのだ。番頭は柳田に「万が一あの五十両が見つかったら、自分の汚い首を差し上げる。それで足りないなら、旦那様の首も差し上げる」と豪語していたものだから、真っ青になる。
年明けて年始回りをしていた番頭、湯島の切り通しですれ違った立派な着物の侍に声をかけられる。何と、仕官かなって江戸留守居役になった柳田格之進。再会を祝って一献と誘われるも気が気でなく、五十両みつかったことを告げて頭を下げる。柳田は翌日店を訪ねると約束。
首を差し出すことを予測して眠れぬ夜を過ごした番頭、柳田が娘きぬ(志の輔さんの落語では子細は説明されなかったが、吉原にいったん身売りしたところを仕官かなった父に請け出されたのだろう)立ち会いで主人もろとも首を打たれる覚悟をする。主人と番頭がお互いをかばう場面に、柳田は代わりに、「手が誤って」主人が大切にしていた碁盤をまっぷたつに。もう一度主人と番頭に刀を向けるところを娘のきぬが「果たされました」と止め、柳田は「さすが柳田の娘」と娘を褒める。
演者によって、娘きぬは吉原で病没していたり、正気を失っていたところを助け出されて番頭の必死の看病で正気を取り戻して番頭と夫婦になったり(同性としては、この展開はどうよと首をかしげるのだが)、落髪していたり、いろいろ。今日の志の輔さん版ではやや説明不足だったけど、吉原から請け出され、柳田の遺恨を果たす場に見分役として立ち会ったと思われる。彼らのせいで自分が負った苦難を、主従の思いに免じて赦すという、菩薩だなぁと感じられる役柄。
柳田の潔癖な武士らしい人柄とか、主人が柳田に傾倒することに嫉妬する番頭はちょっとマンガチックにして嫌らしさを消すとか、志の輔らくごらしい出来。
今日も堪能しました、ありがとうございました。次回はパルコかな……今日も満員だったのでチケット取りは困難を極めると思いますが、頑張ります。
今日の午後は志の輔らくご♪
北海道
【白老】元陣屋の立役者 三好監物の生涯が漫画に
雑記帳:戊辰戦争の縁「登別・白石カレンダー」
北海道坂本龍馬記念館15日に開館1年
山形
清河八郎生誕180年の節目に完成 庄内・清河神社、善意が支えた屋根改修
福島
会津っぽが温泉街ガイド「アルクべ東山」
茨城
シンポ:「桜田門外の変」映画化が縁 水戸浪士ら子孫14人100年ぶり集結 /茨城
栃木
カメラ8000台、東京へ 閉館した益子の博物館所蔵品
東京
社告:北斎生誕250年特別展 23日まで、長野・小布施で開催中 /東京
神奈川
「写真の開祖・上野彦馬」展:13・14日、産業能率大で /神奈川
新潟
新潟大神宮:会津藩士慰霊碑を修復 建立120年、関係者70人が除幕式 /新潟
京都
龍馬も通った花街、組合解散前に「石畳」整備
町の歴史資料館で幕末・維新激動期の大山崎紹介
京大、竜馬の手紙公開 薩長「両方の志」に配慮
兵庫
みみより情報:展覧会「幕末を翔けぬけた人々」 川西市で28日まで /兵庫
和田岬砲台の金具初公開 築造当時の工法知る貴重な資料 兵庫
幕末の動乱語る 和田岬砲台史料を初公開
岡山
新選組サミット初参加 県内の団体 岡山との縁アピール
福岡
上野彦馬賞フォトコンテスト:あすから作品展 九産大美術館で準備作業 /福岡
佐賀
偉人伝出版を「七賢人しおり」で応援=佐賀県書店組合
コラム
【幕末から学ぶ現在(いま)】(87)東大教授・山内昌之 水野忠徳
【次代への名言】非常の師弟編(30)
北海道
【白老】元陣屋の立役者 三好監物の生涯が漫画に
幕末の白老元陣屋ゆかりの仙台藩士三好監物の生涯が、漫画になった。仙台市で暮らす、やしゃごの三好彰さん(59)が監修した。白老発展の礎を築いた監物の横顔を分かりやすく紹介している。
白老元陣屋は、ロシアの南下政策に対抗する北の警備拠点。幕府の命で仙台藩士が派遣され、三好監物は2代目御備頭(おそなえがしら)を1857年から務めた。当初陣屋は、勇払(苫小牧市)に、との命令を、実地調査を行った監物らの進言で白老に変更された、というエピソードもある。
タイトルは「三好監物物語~仙台藩蝦夷地へ・激動の幕末史」。B6判、42ページ。監物が白老元陣屋に赴任するまでに始まり、前半は、藩士が寒さと食料不足に苦しみながら警護に当たった様子を描いている。後半は帰藩後の監物。信念を貫く言論で大老・井伊直弼の怒りを買い、藩内で少数派の尊皇攘夷論を唱えて命を狙われたこともあった。1868年、54年の生涯を閉じる。自害だった。
三好彰さんは、仙台市内で耳鼻咽喉科クリニックを営む。1988年から毎年、白老を訪れて子供たちの耳鼻科健診を行うなどまちとのかかわりを持ち続けている。「三好監物物語」は、2007年に白老元陣屋資料館に寄贈した医学漫画から抜粋し、編集した。
彰さんは「監物の生涯を多くの町民に知ってもらい、歴史的関係を共有する白老と仙台の友好発展につなげてほしい」と話している。漫画は150部ほど用意し、資料館で無料配布している。問い合わせは仙台藩白老元陣屋資料館 電話0144(85)2666。
雑記帳:戊辰戦争の縁「登別・白石カレンダー」
姉妹都市の宮城県白石市と北海道登別市は、初めて共同で2011年の「登別・白石カレンダー」を作製した。白石は「白石城」、登別は「登別温泉・地獄谷」など自慢の観光名所を紹介している。
戊辰(ぼしん)戦争(1868~69年)で敗北した白石城主が、新天地を求めて北海道に渡り開拓した土地が登別の基礎になったという。登別市が今年1月、「11年は合同で作製しよう」と、白石市に持ち掛けた。
カレンダーは1部1000円。付属のはがきを送ると、抽選で両市の協賛企業提供の特産品が当たるプレゼントも。両市は「歴史的なつながりを大事にし、1年といわず末永く協力したい」。【豊田英夫】
北海道坂本龍馬記念館15日に開館1年
函館西部地区の新観光名所「北海道坂本龍馬記念館」(末広町8)が、15日で開館1年を迎える。これまでの来場者数は6万人を突破。観光客だけでなく、市民にも愛される地域施設に成長した。同記念館の三輪貞治館長(46)は「今までは館の意義を知ってもらう期間。これからはステージアップさせて、社会教育事業や観光振興などにも寄与していきたい」と2年目に向けて力を込める。
現在放送中のNHK大河ドラマ「龍馬伝」の人気や昨今の幕末ブーム、箱館奉行所のオープンなどの相乗効果もあり、連日多くの人たちが詰めかける同記念館。これまでのボランティアスタッフに加え、今年10月からは林洋二理事(50)が札幌から函館へ転居。解説案内などを通して館の運営を支えるなど来場者の受け入れ態勢を手厚くした。さらに、展示品を増やすなど飽きさせない工夫も凝らしている。
三輪館長と林理事はこの1年を振り返り「たくさんの出会いに恵まれた年だった。地元の人たちの温かさにも触れることができた」と話す。今後は感謝の心と龍馬の遺志を伝えようと、子どもたちを対象にした龍馬塾を開き、社会教育や人材育成にも力を入れる。
14日には、開館1周年記念で同記念館向かいに製作された「坂本龍馬像」の除幕式を皮切りに、「龍馬祭」を年末まで開催。多数のイベントも企画中で、同祭を契機により地域に根ざした記念館を目指していく。
同館では、銅像基金賛同者を募集している。詳しくは同館電話0138-24-1115まで。
山形
清河八郎生誕180年の節目に完成 庄内・清河神社、善意が支えた屋根改修
清河神社(正木尚文宮司)=庄内町清川=の、老朽化に伴う屋根改修工事が無事完了した。地域住民が昨年10月に実行委員会(松田広委員長)を設立し、これまで募金活動を展開。神社に祭られている幕末の志士・清河八郎(1830~63年)の全国のファンらも善意を寄せた。7日に竣工(しゅんこう)式典が行われた。
式典には地元住民ら約140人が出席。清河八郎顕彰会の斎藤清会長や松田委員長が「清河生誕180周年の節目の年に屋根を改修することができ、この上ない喜びを感じている」とあいさつ。正木宮司は「神社を後世まで引き継ぐことができるようになった。県内外の協力者に感謝している」と述べた。
実行委によると、清川の住民や清河ファンら延べ618の個人・団体が賛同し、計1173万円の善意を寄せた。総工事費は1135万円。5月に工事に着工し、敷き詰められていた瓦をすべて取り除いて鉄製の鋼板にふき替え、8月に完成した。
地域住民らが出席した竣工式典
清川出身の八郎を祭る同神社は、地元小学生がみこ舞を披露する例大祭(5月)など、住民にとってなじみのイベントが開かれている。1933(昭和8)年の創建以降、改修したことがなく、屋根の腐食による雨漏りが年々悪化、改修が急務となっていた。
福島
会津っぽが温泉街ガイド「アルクべ東山」
「会津っぽと・そぞろ歩き・体感散策ウオーク・いにしえアルクベ東山」が7日、会津若松市東山地区で開かれた。
県内外から参加した約200人が地元のボランティアガイドの案内で歴史のまちを巡り、ウオーキングを楽しんだ。
東山温泉観光協会、いにしえ夢街道協議会、NPO法人会津地域連携センターなどが組織する実行委員会の主催で、県地域づくり総合支援事業の補助金を受けて実施した。
参加者は10班に分かれ、ボランティアガイドの先導で東山温泉旅館共同駐車場をスタート。
東山温泉街を抜けて会津藩主松平家墓所に向かい、新選組隊長近藤勇の墓がある天寧寺や会津藩祖保科正之公の菩提(ぼだい)寺である大龍寺などを訪ねた。
この日の会津若松市は朝方こそ冷え込んだものの、快晴に恵まれ、美しい紅葉が参加者を迎えた。
ボランティアガイドの説明も彩りを添え、歴史ファンや家族連れらは秋の東山路を満喫していた。
茨城
シンポ:「桜田門外の変」映画化が縁 水戸浪士ら子孫14人100年ぶり集結 /茨城
◇ルーツ再確認
幕末の大老暗殺事件「桜田門外の変」に加わった水戸浪士らの子孫14人が10日、水戸市三の丸の県立図書館でのシンポジウムで集結した。事件の映画化を通じ、縁を持った歴史愛好家が呼び掛けて実現。子孫らは自らのルーツを再確認するとともに、事件後途切れていた仲間意識をあたためた。
主催したのは、同事変研究同好会(会長=中村康雄・那珂歴史同好会会長)。三上靖彦・「桜田門外ノ変」映画化支援の会事務局長らが機運作りに奔走していたのに刺激を受け、歴史資料や関係者の調査をする中で、子孫らと知り合った。中村会長によると、事件から50年目の1910年、靖国神社で約500人が参加して記念式典があり、浪士らの子孫も顔を合わせたが、これだけの人数の子孫が集まるのはそれ以来100年ぶり。
シンポジウムでは那珂市歴史民俗資料館の仲田昭一館長が「桜田門外の変と時代背景」という演題で基調講演。水戸藩は徳川家でありながら朝廷と幕府の君臣関係に基づき、朝幕対立の際には朝廷側につくことが光圀公の時代からの家訓だったこと、彦根藩は朝廷監視役としての自負があったこと、幕末は朝廷と幕府の力のバランスが変化していったことなどを説明した。
その後のパネルディスカッションでは三上氏や、井伊直弼公の首を切り落としたとされる薩摩藩浪士の有村次左衛門のひ孫、有村幸三さん(64)=神奈川県茅ケ崎市=も加わり、映画の感想などを語り合った。有村さんは「曽祖父の斬(き)り合いシーンは見ていてゾッとした」と話しながらも、子孫らが集まったことに「いきなり親類が増えたよう」と顔をほころばせていた。【山崎明子】
栃木
カメラ8000台、東京へ 閉館した益子の博物館所蔵品
昨年7月、惜しまれつつ閉館した益子町の「ペンタックスカメラ博物館」の所蔵品が、東京都千代田区の「日本カメラ博物館」に移されていたことが分かった。ファンから「今後どうなるのか」と心配された、貴重なコレクション。新たな場所で命脈を保つことになった。
東京に移されたのは、世界各国のカメラ約8千点と古写真などの蔵書だ。コレクションの中には1860年代に製造され、幕末から明治の写真店に置かれていた大型の木製カメラや、ドイツ・ライカ社の1920年代の貴重品「1(B)」などの名機も含まれる。
ペンタックスカメラ博物館は67年に東京で開館。93年には規模拡大のため、工場がある益子町に移された。運営するHOYAペンタックスは事業縮小にともなって昨年6月に閉鎖を発表し、所蔵品の引受先を探していた。同社や日本カメラ博物館によると、自社製の試作機など一部を除いて、所蔵品は5月までに日本カメラ博物館を運営する「日本カメラ財団」に売却されたという。
日本カメラ博物館は、古今東西のカメラ1万点以上を収蔵する国内最大級のカメラ博物館。ペンタックスコレクションの合流により一部に重複する機種もあるものの、展示内容はより充実することになる。現在、整理が進められており、30日からの特別展「ポラロイド・カメラ展」では一部が展示される予定だという。
日本カメラ博物館学芸員の山本一夫さん(40)は「これだけのコレクションはバラバラになるともう集まらない。絶対に散逸させてはいけない、という思いから引き受けることが決まった」と話している。明治期の木製カメラなどは常設展に組み込まれることが決まっているほか、将来的には「ペンタックス博物館展」として特別展を開くことを検討しているという。(矢吹孝文)
東京
社告:北斎生誕250年特別展 23日まで、長野・小布施で開催中 /東京
江戸中期から幕末にかけて活躍した絵師、葛飾北斎の生誕250年を記念した特別展「『富士と桜』展-画狂人北斎と中島千波の世界」(北斎館主催、毎日新聞社など共催)が、長野県小布施町の北斎館、高井鴻山記念館、おぶせミュージアム・中島千波館の3館で11月23日まで開かれています。「冨嶽三十六景」や「北斎漫画」で知られる北斎が晩年に滞在した小布施に、肉筆、版画、摺物(すりもの)、版本など280点余りが展示されています。
また、特別イベントとして、11月13日(土)午後1時から同町の北斎ホールで、「歴史小説家高橋克彦・日本画家中島千波が語る北斎-江戸と現在」をテーマにした特別対談もあります。
3館の開館時間は午前9時~午後5時。入館は閉館の30分前。入館料は北斎館=大人500円、高校生300円▽鴻山記念館=同300円、150円▽中島千波館=同500円、250円。3館とも中学生以下無料。3館共通の特別展入館券は大人1000円、高校生500円。問い合わせは、北斎館(電話026・247・5206)。
神奈川
「写真の開祖・上野彦馬」展:13・14日、産業能率大で /神奈川
◇坂本龍馬の立位像写真も
日本初の営業写真館を開いた上野彦馬(1838~1904年)のおいが創立した産業能率大の湘南キャンパス(伊勢原市上粕屋)で、館撮影の坂本龍馬らの写真展「産業能率大学と写真の開祖・上野彦馬」が13、14日に開かれる。同大は「激動の時代に思いをはせ、彦馬から続く進取の精神を感じ取ってほしい」と来場を呼びかけている。【井崎憲】
絵師の家に生まれた彦馬はほぼ独学で撮影術を学んだ。幕末の志士やニコライ2世ら外国要人、当時の風俗などを撮影し、横浜の下岡蓮杖(れんじょう)と並んで日本ではカメラマンの祖とされる。1862(文久2)年、長崎に写真館「上野撮影局」を開設。龍馬の肖像写真で最も有名な、懐手に立つポーズの「立位像」もここで撮影された。
彦馬の養育も受けたおいの故・上野陽一氏は東京帝国大を卒業後、米国の科学的管理法を「能率学」と邦訳したマネジメント思想の先駆者で、大学前身の産業能率短大を1950年に設立した。
今年はNHK大河ドラマ「龍馬伝」が放映されており、大学祭のある両日、立位像(複写)の他、当時来日した外国人や風景など大学で収蔵していた彦馬ゆかりの写真約50点を同キャンパス図書館で展示することが決まった。
14日の同キャンパスでは、陽一氏の長男で古写真にも造詣が深い産能大最高顧問・一郎氏が大学と彦馬について講演、彦馬撮影の写真スライドを交えて当時の風俗も解説する。
◇所蔵の50点を展示
同大図書館の関郁夫館長は「ビジネスのイメージが強い大学だが、新しいモノを目指すDNAが受け継がれていることを内外の人に知ってほしい」と話している。
写真展は13日が午前10時半~午後4時、14日は午後5時まで。一郎氏の講演は午後2時半から1号館205号教室で。同教室では、龍馬伝を執筆した脚本家、福田靖さんの講演(14日午後1~2時)もある。いずれも入場無料。問い合わせは同大図書館(0463・92・2218)。
新潟
新潟大神宮:会津藩士慰霊碑を修復 建立120年、関係者70人が除幕式 /新潟
戊辰(ぼしん)戦争(1868~69年)で戦場になった新潟で戦死した会津藩士を弔うため、明治時代に新潟大神宮(新潟市中央区西大畑町)に建てられた慰霊碑が修復され、3日、除幕式が行われた。碑建立から今年は120年の節目に当たり、新潟、福島県会津若松市の関係者約70人が出席し、歴史を語り継いでいくことを誓い合った。
戊辰戦争では東北、越後の諸藩が奥羽越列藩同盟を結び、薩長などと戦い敗れた。慰霊碑は1890(明治23)年、墓も作ることを許されなかった会津藩戦死者を慰霊するため、新潟に移り住んだ会津藩の生き残りが地元の人の協力を得て建立した。「殉節之碑」と名が付けられたが、明治政府の目をおそれ、神社片隅の目立たない場所に建てられた。
長い歳月がたち、碑にひびが入り、碑文の字も見えにくくなったため、新潟市内の有志が寄付を募り、修復事業に取り組んだ。一新された碑は高さ2・2メートルで、境内の見やすい場所に移された。碑文には会津藩が賊軍の汚名を着せられ、明治後も苦難の道を歩んだことが刻まれている。
除幕式には、碑の伝承活動に取り組んでいる新潟市民のほか、菅家一郎・会津若松市長らが出席。120年前の碑建立に尽くした旧会津藩士の子孫という斎藤兵市郎さん(79)=新潟市東区=は「碑は新潟と会津のきずなの象徴。これを機会に市民に広く知ってもらい、交流を深めていきたい」と感慨深げに話した。【小川直樹】
京都
龍馬も通った花街、組合解散前に「石畳」整備
かつて花街として栄えた京都市下京区の島原で、石畳風に舗装された道路が完成した。
坂本龍馬ら幕末の志士が通い、太夫らも華やかに行き交ったが、戦後は衰退。近く解散する「島原貸席お茶屋業組合」が、「風情と文化の薫りを石畳にとどめ、多くの人に散策してほしい」と整備した。
島原は江戸時代初期、遊郭としてでき、中期には与謝蕪村ら文化人による「島原俳壇」が多くの作品を生み出した。幕末には龍馬や新撰組を率いた近藤勇らも訪れ、にぎわったという。
しかし、終戦後に約100軒あったお茶屋は激減し、今では1軒だけになった。解散を決めた組合は、閉鎖した歌舞練場の跡地の売却収入を使って、これまでに「島原大門」の修復や文芸碑の建立などを行ってきた。今回、清算事業の最後に約4500万円で道路を整備することにした。
「角屋もてなしの文化美術館」付近の延長910メートルの路上に、乳白色の加工セメントを薄く塗り、表面を削って四角の切れ込みを入れ、御影石を敷き詰めたような風合いに仕上げた。7日は記念式典を開き、太夫らが通り初めを行う。
(2010年11月13日10時16分 読売新聞)
町の歴史資料館で幕末・維新激動期の大山崎紹介
「幕末・維新期の大山崎」と題した企画展が、京都府大山崎町大山崎の町歴史資料館で開かれている。1864年の「禁門の変」で敗れた長州藩の志士たちが天王山で自決する姿を描いた絵や、町や社寺の被災ぶりを記した文書など約60点が並ぶ。
激動期の大山崎の様子を伝えようと資料館が催した。家々が燃え、兵馬が駆け回り、町人が逃げまどうなど、禁門の変で戦場となった京都の騒乱を克明に書いた絵が展示されている。薩摩、会津両藩と戦った長州藩の真木和泉の肖像画や、真木ら17人の志士が使ったとされる弁当箱、敗走後に17人が天王山で自刃する姿を描いた絵も並んでいる。
さらに、会津藩が大山崎を砲撃した際、観音寺(山崎聖天)の僧が本堂の仏像を池に入れて隠し、柳谷(現長岡京市)を経て逃げる様子を記録した史料や、戦火を逃れて避難した住民に、同藩が戦闘終了後、帰還を呼び掛けた木製の高札も展示されている。
このほか、維新後の廃仏棄釈の影響で、現在の大阪府島本町山崎にあった「西観音寺」が、神社への変更を余儀なくされたという史実も写真などで紹介している。訪れた人々は、激動期の大山崎の様子を思い浮かべながら展示品を眺めていた。28日まで。大人300円、小中生は無料。
京大、竜馬の手紙公開 薩長「両方の志」に配慮
「急成ハかへりて両方の志通しかね候へハ」(急ぐとかえって両方の志が通じかねる)。薩長同盟の橋渡しをした坂本竜馬が関係者にあてた手紙が13日、京都大総合博物館(京都市)の特別展で公開された。21日まで。
同盟成立の約3カ月前に当たる慶応元(1865)年10月に書かれており、同博物館の岩崎奈緒子教授は「大詰めの協議を慎重に進めようとする竜馬の意向がうかがえる」と話している。
手紙は竜馬と長州藩のパイプ役を務めた長府藩(長州の支藩)の藩士印藤聿にあてたもの。「両方より道也義也と論を吹合候よふニなれハ、かへりてがいを生し」(両方が道理だ義だと言い合うようでは障害が生まれる)、「談笑中ニともに宜を求め候よふでなけれハ、とても大成ハなりかたく」(談笑の中で互いに友好を求めるようでなければ大きな成功はない)などとつづっている。
手紙は明治時代の政治家品川弥二郎が、幕末1605件期に活躍した志士らを追悼するため京都につくった「尊攘堂」に収蔵された後、京都大に寄贈された。
兵庫
みみより情報:展覧会「幕末を翔けぬけた人々」 川西市で28日まで /兵庫
◇所蔵資料50点を展示--大阪青山歴史文学博物館
◇幕府の軍艦「開陽丸」の絵や横井小楠自筆「国是十二条」
NHK大河ドラマ「龍馬伝」の舞台にもなっている幕末の動乱の時代に活躍した人々の軌跡を追う展覧会「幕末を翔(か)けぬけた人々」が、川西市長尾町の大阪青山歴史文学博物館で開かれている。
展覧会では、同館が所蔵する資料約50点が展示されている。幕末に徳川幕府の軍艦であった「開陽丸」の絵のほか、坂本龍馬が新しい時代の日本の方針を提案した「船中八策」に大きな影響を与えたと言われる横井小楠の「国是十二条」の自筆原本など、幕末に活躍した人々の肉筆が多数、出展されている。
同館の外観はかつて付近にあった山下城の復元をイメージした城郭建築で、ひときわ異彩を放っている。また、最上階には展望室が作られており、能勢妙見山などの山並みが一望できるという(雨天時は閉室)。
28日まで。入館時間は午前10時から午後4時半まで。月曜は休館。入館料は一般600円、65歳以上500円、大学生400円、高校生300円、中学生以下無料。問い合わせは同館(072・790・3535)。
和田岬砲台の金具初公開 築造当時の工法知る貴重な資料 兵庫
昭和初期以来、約80年ぶりの“平成の大修理”が進む和田岬砲台(神戸市兵庫区)で、内部の木造部分の解体に伴い取り外された建築部材や金具が12月18日、同区の兵庫公会堂で初めて公開される。木造の柱や梁(はり)の結合などに使用された金具類は、築造当時の建築工法を知る貴重な資料。修理後の組み立て工事で再び使用されるため“最初で最後”の公開になる。
建築部材が取り外されたのは築造以来初めて。同砲台は西洋の築城技術を参考に、伝統的な日本の建築工法を駆使して建てられており、当時の最先端の技術が垣間見える。取り外された部材はボルトやナット、釘(くぎ)など数百点で、このうち約50点が公開される。
公開に合わせ、神戸市教委などが12月18日午後1時半から4時まで、兵庫公会堂で歴史講演会を開く。公開後、東京都品川区立品川歴史館学芸員の冨川武史氏による講演がある。
同砲台は幕末に、外国艦船の来襲に備えて、軍艦奉行の勝海舟が築造した。三菱重工業神戸造船所の敷地内にあり、同社が所有している。大正10年に県下の第1号史跡に指定された。今回の大がかりな解体修理は平成24年度末に終了する予定。
講演会、公開(午後1時~2時半)とも無料だが、講演会は往復はがきによる申し込みが必要。申し込み締め切りは11月19日。定員は200人で超えた場合は抽選する。問い合わせは兵庫区まちづくり課((電)078・511・2111)。
幕末の動乱語る 和田岬砲台史料を初公開
外国船が日本沖に姿を現し始めた幕末期、勝海舟の提言を受けて江戸幕府が造った要塞(よう・さい)「和田岬砲台」(神戸市兵庫区)の建築部材や金具類が12月18日、神戸市兵庫区の兵庫公会堂で初公開される。最新の西洋技術を模倣して苦労しながら造った跡がうかがえる貴重な史料だ。(日比野容子)
和田岬砲台は、大阪湾岸の警備のため築造された四つの要塞のうちの一つ。夙川の河口にある西宮砲台も現存しているが、砲台内部が当時の姿のまま残っているのは和田岬砲台だけで、県第1号の国史跡に指定されている。
勝海舟が「神戸海軍操練所」を創設した1864年に完成。市教委文化財課は「海舟の弟子だった坂本龍馬も足を踏み入れたに違いない」と推測する。函館・五稜郭のような星形土塁に囲まれた円筒形の砲台外郭部は、花崗岩(か・こう・がん)製。2階建ての2階部分に大砲発射用の11の窓を備えるが、4年後の神戸開港で必要性が薄れ、使われることはなかった。
砲台の解体修理事業は、所有者の三菱重工が文化庁、県、神戸市の補助金を受けて2007年度から始まった。砲台内の柱や梁(はり)がシロアリや浸水によって腐食が進んだためで、来年度から老朽化した部材を入れ替えて組み立て直す。総事業費は約5億6千万円で、2013年3月に終わる予定だ。
今回展示するのは約50点。中でも興味深いのは、築造以来外されたことのないクギ、ネジ、ボルトなど、木と木を組み合わせて固定するのに使った金具類だ。神戸大大学院工学研究科の足立裕司教授(近代建築史)は「日本古来の木組み技術で建造することが可能だったにもかかわらず、当時最新と考えられていた西洋技術を何とか採り入れようとした跡が読み取れる重要な史料」と指摘する。
当日は午後1時~同2時半の公開に合わせて午後1時半~同4時、修理工事についての報告と東京都品川区立品川歴史館学芸員の冨川武史さんが砲台築造の歴史的背景に迫る講演「江戸湾防備から摂海防備へ~品川御台場から見た和田岬砲台~」をする。
講演の聴講には申し込みが必要。往復はがきに住所、氏名、電話番号を書き、今月19日必着で、〒652・8570 兵庫区まちづくり課「砲台講演会」係まで申し込む。詳しくは同課(078・511・2111内線214)、または市教委文化財課(078・322・5799)へ。
岡山
新選組サミット初参加 県内の団体 岡山との縁アピール
県内の新選組ファン、隊士の子孫らでつくる「岡山新選組準備会」が13、14日に京都市で開催される「第11回全国新選組サミット」に初めて参加する。隊士にふんした参加者が京の町を練り歩くパレードにも加わる予定で、会員は「岡山が新選組との縁が深いことをPRしたい」と楽しみにしている。
同準備会は、今年4月に発足。現在、会員は10~80代の男女28人で、定期的に会合を持つなど新選組について学んでいる。
サミットは、新選組にちなんだまちづくりを進めようと、京都市、福島県会津若松市などゆかりの地で毎年開催。今回は全国の愛好者グループなどから100人以上が参加。パレードのほか、各団体の活動発表、史跡見学、専門家の講演などが予定されている。
同準備会は、20人以上の隊士を送り出したという岡山と新選組のかかわりをアピールするとともに、他地域のファンと交流を深めようと参加を決めた。
同準備会は会員を募集中。問い合わせは、同準備会ホームページ(http://okayamashinsengumi.web.fc2.com)。
福岡
上野彦馬賞フォトコンテスト:あすから作品展 九産大美術館で準備作業 /福岡
第11回上野彦馬賞九州産業大学フォトコンテスト(同大、毎日新聞社主催)の作品展が13日から東区の同大美術館で始まるのを前に、搬入作業が11日から始まった。作品展は28日まで。入場無料。
計2574点の応募作から選ばれた一般部門29点、高校生・中学生部門75点の入賞作を展示。最高賞の上野彦馬賞を受賞した九州産業大1年、知念愛佑美さん=福岡市=の「祖母の日課」(カラー5枚組み)や、ジュニア大賞の八代白百合学園高3年、中西彩さん=熊本県八代市=の「猛暑日」など、若手写真家たちの感性が光る作品がそろった。
また、企画展として、上野彦馬が活躍した幕末~明治期に撮影された写真展も同時開催。萩博物館(山口県萩市)が所蔵する高杉晋作や伊藤博文の肖像写真など50点が展示される。【徳野仁子】
〔福岡都市圏版〕
佐賀
偉人伝出版を「七賢人しおり」で応援=佐賀県書店組合
佐賀県教育委員会が「佐賀偉人伝」シリーズを11月から順次出版することを受け、佐賀県書店商業組合が「佐賀七賢人しおり」を作成し た。幕末・明治期の県出身者7人、1枚で1人ずつ紹介するもので、偉人伝をPR。県内の書店で無料でもらえる。
しおりは計7万枚作成。大隈重信や佐野常民ら「佐賀の七賢人」それぞれの写真が載っているほか、経歴や功績などを簡単に紹介してい る。組合に加盟している約60店舗で希望者に無料配布される。
同組合は「ふるさとの偉人は名前は知っていても中身は忘れがち。幕末明治の偉人に改めて関心を持ってもらいたい」(岩永藤房理事長) と説明。「今年は国民読書年ということもあり企画した」という。
佐賀偉人伝は、幕末・明治期に活躍した県出身者を紹介するシリーズ。「鍋島直正」が11月に出版されるのを皮切りに、5年間で七賢人を含 む15人程度を対 象に15冊程度が出版される。郷土教育や観光に活用されるほか、「九州・山口の近代化産業遺産群」の世界遺産登録に向け県民意識の高揚を 図る目的もある。【もぎたて便】
(2010/11/10-09:00)
コラム
【幕末から学ぶ現在(いま)】(87)東大教授・山内昌之 水野忠徳
■「屏風外相」の見識と胆力
いつの時代でも閣老や首相には、肝心の政策について関係者の質問にきちんと答えられない者がいる。
幕末の老中でいえば、米国公使ハリスの金銀貨幣の品位量目に関する問いに窮した間部詮勝(まなべ・あきかつ)の例が想い起こされる。返答につまった間部は、日本では大名たる者、金銀の事情に通じる必要もなく、幕府では勘定奉行、藩には家老がいて処理するので、ここにいる勘定奉行に聞いてくれと珍答を返した。さしものハリスも、日本では財政金融の根本原理を知らないで総理が務まるのかと絶句したというのだ。
折から出張中のオマーンで菅直人首相の表情をNHKで観たが、その生気の無さに愕然(がくぜん)とした。菅首相を間部と比較するのは、平成の日本人にとって辛(つら)いことである。
しかし、首相が国会答弁や記者会見で見せる自信なげな表情に接すると切なくなる。予算委員会で答弁する仙谷由人官房長官の迫力と存在感が増すのも致し方ない。首相の発言が不安な今日、政権維持のために官房長官が前面に出る機会も増えるのは仕方がないからだ。
◆最後まで戦い抜いた生涯
幕末でも閣老が外国公使と交渉する時には、とても素人の老中に任せられないので、「屏風(びょうぶ)」の後に隠れて談判の要領をふきこむ黒衣(くろこ)めいた顧問格もいた。「屏風水野」の異名で知られる水野忠徳こと痴雲(ちうん)である。水野は、鎖国の不可を悟った最初の幕府官僚であるが、改革を唱えながらも軽挙妄動を排した穏健慎重な面をもっていた。
しかし、その保守的合理主義は剛直な胆力に支えられている。修好通商条約で神奈川開港を約しながら横浜を選定して外国から抗議を受けた時も、居留民の安全や貿易の利便から横浜が勝るとかわしたのも水野である。また、金銀貨の同種同量交換を公平に解決しようと苦労したのも彼にほかならない。しかも時に屏風の後から表へ姿を現す水野の凄(すご)みは胆力や度胸も並でない点にあった。
文久3(1863)年の老中小笠原長行(ながみち)の率兵入京の戦略を描いたのは水野忠徳らしく、この武力クーデターによって一挙に尊皇攘夷(じょうい)派を朝廷や京から一掃しようとした。ひょっとして念頭には、北条義時が後鳥羽上皇らを廃した承久の変の先例もあったのかもしれない。将軍家茂(いえもち)の命によって水野らの野心的な計画は挫折し、幕威の衰微はますます明らかになるが、謹慎処分を受けた彼はこれで屈しなかった。鳥羽伏見の戦いに負けても、水野は江戸城の評定(ひょうじょう)で徹底抗戦を主張した。将軍慶喜(よしのぶ)の恭順を機に隠居し武蔵布田宿(ふだしゅく)に移住した水野は、まもなく慶応4(1868)年7月に絶命した。まさしく、憤死したというべきであろう。
◆苦しい中でも国土守る
水野は日本の政治外交の基礎になる多くの仕事を果たした。長崎奉行としてオランダから軍艦を購入し、海軍伝習所の開設など日本海軍の礎をつくったのも水野である。特筆すべきは、ペリー来航で米英2国が領有の野心を抱いた小笠原諸島への侵略を阻止するために、島へわざわざ渡航し日本の領土権を宣言したのだ。
幕府が苦しい時世でも、琉球(沖縄)や蝦夷地(北海道)の国境を守るべきだという水野の主張について、属僚として働いた福地源一郎(桜痴(おうち))はこう語る。「これを忽(ゆるが)せに附し去るべからずと切論し外国のために我国の版図を侵略せらるるの恐れありと痛議したるは、数回に止(とどま)らざりけり」(『幕末政治家』)
すでに屏風の後から姿を現して政権の主役となった感のある仙谷官房長官には、小笠原について「日本の版図たる事を分明に定めたり」と評価された水野の見識に倣(なら)いながら、中国に過剰な敬語を使わず豪胆に尖閣問題などの難局を打開してほしいものだ。(やまうち まさゆき)
◇
【プロフィル】水野忠徳
みずの・ただのり 文化7(1810)年または12年生まれ。禄高500石の旗本だったが、老中阿部正弘の抜擢(ばってき)を受けて嘉永5(1852)年に浦賀奉行。長崎奉行、外国奉行なども歴任し、各国との条約交渉など外交の一線に立った。公武合体策に反対したが容(い)れられず、文久2(1862)年に隠居し、痴雲と号した。その後も、尊皇攘夷派の打倒と幕府の権威回復に奔走したが挫折。慶応4(1868)年、幕府崩壊後ほどなく没した。
【次代への名言】非常の師弟編(30)
■「思想が時代に先立つ者は、守旧派から阻害されることになる。しかし、先立つ者がいなければ、後生はどうして覚醒(かくせい)できるのか」(勝海舟)
幕末・維新期における幕臣の雄、勝海舟は、洋学者・佐久間象山の門弟の一人である。また、勝の妹、順子が象山の正妻に迎えられたから、干支(えと)でひと回り年下ながら、勝は象山の義兄にあたる。
「いかにもおれは天下の師だというように、厳然と構えこんで、漢学者が来ると洋学をもって威(おど)しつけ、洋学者が来ると漢学をもって威しつけ、ちょっと書生が訪ねて来ても、じきに叱(しか)り飛ばすという風でどうも始末にいけなかったよ」
勝の象山評だ。身内をほめることに対する江戸っ子特有の“照れ”があると思う。というのも、象山の遭難を「国家のため、痛憤胸間に満つ」と嘆き、象山の主著『省●録(せいけんろく)』が明治になって出版されたとき、費用を工面し、冒頭の序文をつづって追悼したのが勝だったからだ。
「自分は人の知りえないことを知り、人のできないことができる。この天恵を自分のためだけに用い、天下のために用いなければ、天に背くその罪は重い」
『省●録』の一節。確かに自信家である。しかし、報いられることが少なかったにもかかわらず、彼が一心に、その非常の才のすべてを危機にあった国を救うためにささげたことも事実である。
まな弟子の吉田松陰が至誠の人なら、象山は覇気の人だった。そしてこの師弟はともに、時代にさきがけたがために、ついに維新を目にすることはなかった。(文化部編集委員 関厚夫)
●=侃の下に言
明日は全国各地で紅葉狩りに絶好のお天気だそう。小春日和ですって。
北海道
【白老】元陣屋の立役者 三好監物の生涯が漫画に
山形
清河八郎生誕180年の節目に完成 庄内・清河神社、善意が支えた屋根改修
茨城
シンポ:「桜田門外の変」映画化が縁 水戸浪士ら子孫14人100年ぶり集結 /茨城
京都
町の歴史資料館で幕末・維新激動期の大山崎紹介
兵庫
みみより情報:展覧会「幕末を翔けぬけた人々」 川西市で28日まで /兵庫
幕末の動乱語る 和田岬砲台史料を初公開
岡山
新選組サミット初参加 県内の団体 岡山との縁アピール
北海道
【白老】元陣屋の立役者 三好監物の生涯が漫画に
幕末の白老元陣屋ゆかりの仙台藩士三好監物の生涯が、漫画になった。仙台市で暮らす、やしゃごの三好彰さん(59)が監修した。白老発展の礎を築いた監物の横顔を分かりやすく紹介している。
白老元陣屋は、ロシアの南下政策に対抗する北の警備拠点。幕府の命で仙台藩士が派遣され、三好監物は2代目御備頭(おそなえがしら)を1857年から務めた。当初陣屋は、勇払(苫小牧市)に、との命令を、実地調査を行った監物らの進言で白老に変更された、というエピソードもある。
タイトルは「三好監物物語~仙台藩蝦夷地へ・激動の幕末史」。B6判、42ページ。監物が白老元陣屋に赴任するまでに始まり、前半は、藩士が寒さと食料不足に苦しみながら警護に当たった様子を描いている。後半は帰藩後の監物。信念を貫く言論で大老・井伊直弼の怒りを買い、藩内で少数派の尊皇攘夷論を唱えて命を狙われたこともあった。1868年、54年の生涯を閉じる。自害だった。
三好彰さんは、仙台市内で耳鼻咽喉科クリニックを営む。1988年から毎年、白老を訪れて子供たちの耳鼻科健診を行うなどまちとのかかわりを持ち続けている。「三好監物物語」は、2007年に白老元陣屋資料館に寄贈した医学漫画から抜粋し、編集した。
彰さんは「監物の生涯を多くの町民に知ってもらい、歴史的関係を共有する白老と仙台の友好発展につなげてほしい」と話している。漫画は150部ほど用意し、資料館で無料配布している。問い合わせは仙台藩白老元陣屋資料館 電話0144(85)2666。
山形
清河八郎生誕180年の節目に完成 庄内・清河神社、善意が支えた屋根改修
清河神社(正木尚文宮司)=庄内町清川=の、老朽化に伴う屋根改修工事が無事完了した。地域住民が昨年10月に実行委員会(松田広委員長)を設立し、これまで募金活動を展開。神社に祭られている幕末の志士・清河八郎(1830~63年)の全国のファンらも善意を寄せた。7日に竣工(しゅんこう)式典が行われた。
式典には地元住民ら約140人が出席。清河八郎顕彰会の斎藤清会長や松田委員長が「清河生誕180周年の節目の年に屋根を改修することができ、この上ない喜びを感じている」とあいさつ。正木宮司は「神社を後世まで引き継ぐことができるようになった。県内外の協力者に感謝している」と述べた。
実行委によると、清川の住民や清河ファンら延べ618の個人・団体が賛同し、計1173万円の善意を寄せた。総工事費は1135万円。5月に工事に着工し、敷き詰められていた瓦をすべて取り除いて鉄製の鋼板にふき替え、8月に完成した。
地域住民らが出席した竣工式典
清川出身の八郎を祭る同神社は、地元小学生がみこ舞を披露する例大祭(5月)など、住民にとってなじみのイベントが開かれている。1933(昭和8)年の創建以降、改修したことがなく、屋根の腐食による雨漏りが年々悪化、改修が急務となっていた。
茨城
シンポ:「桜田門外の変」映画化が縁 水戸浪士ら子孫14人100年ぶり集結 /茨城
◇ルーツ再確認
幕末の大老暗殺事件「桜田門外の変」に加わった水戸浪士らの子孫14人が10日、水戸市三の丸の県立図書館でのシンポジウムで集結した。事件の映画化を通じ、縁を持った歴史愛好家が呼び掛けて実現。子孫らは自らのルーツを再確認するとともに、事件後途切れていた仲間意識をあたためた。
主催したのは、同事変研究同好会(会長=中村康雄・那珂歴史同好会会長)。三上靖彦・「桜田門外ノ変」映画化支援の会事務局長らが機運作りに奔走していたのに刺激を受け、歴史資料や関係者の調査をする中で、子孫らと知り合った。中村会長によると、事件から50年目の1910年、靖国神社で約500人が参加して記念式典があり、浪士らの子孫も顔を合わせたが、これだけの人数の子孫が集まるのはそれ以来100年ぶり。
シンポジウムでは那珂市歴史民俗資料館の仲田昭一館長が「桜田門外の変と時代背景」という演題で基調講演。水戸藩は徳川家でありながら朝廷と幕府の君臣関係に基づき、朝幕対立の際には朝廷側につくことが光圀公の時代からの家訓だったこと、彦根藩は朝廷監視役としての自負があったこと、幕末は朝廷と幕府の力のバランスが変化していったことなどを説明した。
その後のパネルディスカッションでは三上氏や、井伊直弼公の首を切り落としたとされる薩摩藩浪士の有村次左衛門のひ孫、有村幸三さん(64)=神奈川県茅ケ崎市=も加わり、映画の感想などを語り合った。有村さんは「曽祖父の斬(き)り合いシーンは見ていてゾッとした」と話しながらも、子孫らが集まったことに「いきなり親類が増えたよう」と顔をほころばせていた。【山崎明子】
京都
町の歴史資料館で幕末・維新激動期の大山崎紹介
「幕末・維新期の大山崎」と題した企画展が、京都府大山崎町大山崎の町歴史資料館で開かれている。1864年の「禁門の変」で敗れた長州藩の志士たちが天王山で自決する姿を描いた絵や、町や社寺の被災ぶりを記した文書など約60点が並ぶ。
激動期の大山崎の様子を伝えようと資料館が催した。家々が燃え、兵馬が駆け回り、町人が逃げまどうなど、禁門の変で戦場となった京都の騒乱を克明に書いた絵が展示されている。薩摩、会津両藩と戦った長州藩の真木和泉の肖像画や、真木ら17人の志士が使ったとされる弁当箱、敗走後に17人が天王山で自刃する姿を描いた絵も並んでいる。
さらに、会津藩が大山崎を砲撃した際、観音寺(山崎聖天)の僧が本堂の仏像を池に入れて隠し、柳谷(現長岡京市)を経て逃げる様子を記録した史料や、戦火を逃れて避難した住民に、同藩が戦闘終了後、帰還を呼び掛けた木製の高札も展示されている。
このほか、維新後の廃仏棄釈の影響で、現在の大阪府島本町山崎にあった「西観音寺」が、神社への変更を余儀なくされたという史実も写真などで紹介している。訪れた人々は、激動期の大山崎の様子を思い浮かべながら展示品を眺めていた。28日まで。大人300円、小中生は無料。
兵庫
みみより情報:展覧会「幕末を翔けぬけた人々」 川西市で28日まで /兵庫
◇所蔵資料50点を展示--大阪青山歴史文学博物館
◇幕府の軍艦「開陽丸」の絵や横井小楠自筆「国是十二条」
NHK大河ドラマ「龍馬伝」の舞台にもなっている幕末の動乱の時代に活躍した人々の軌跡を追う展覧会「幕末を翔(か)けぬけた人々」が、川西市長尾町の大阪青山歴史文学博物館で開かれている。
展覧会では、同館が所蔵する資料約50点が展示されている。幕末に徳川幕府の軍艦であった「開陽丸」の絵のほか、坂本龍馬が新しい時代の日本の方針を提案した「船中八策」に大きな影響を与えたと言われる横井小楠の「国是十二条」の自筆原本など、幕末に活躍した人々の肉筆が多数、出展されている。
同館の外観はかつて付近にあった山下城の復元をイメージした城郭建築で、ひときわ異彩を放っている。また、最上階には展望室が作られており、能勢妙見山などの山並みが一望できるという(雨天時は閉室)。
28日まで。入館時間は午前10時から午後4時半まで。月曜は休館。入館料は一般600円、65歳以上500円、大学生400円、高校生300円、中学生以下無料。問い合わせは同館(072・790・3535)。
==============
◇プレゼント
この展覧会のチケットを2枚1組で10人にプレゼントします。はがきに「幕末展チケット希望」と書き、郵便番号、住所、氏名、電話番号も記入して、〒660-0892 尼崎市東難波町5の16の29、毎日新聞阪神支局みみより情報係へ。17日まで必着。応募多数なら抽選します。
幕末の動乱語る 和田岬砲台史料を初公開
外国船が日本沖に姿を現し始めた幕末期、勝海舟の提言を受けて江戸幕府が造った要塞(よう・さい)「和田岬砲台」(神戸市兵庫区)の建築部材や金具類が12月18日、神戸市兵庫区の兵庫公会堂で初公開される。最新の西洋技術を模倣して苦労しながら造った跡がうかがえる貴重な史料だ。(日比野容子)
和田岬砲台は、大阪湾岸の警備のため築造された四つの要塞のうちの一つ。夙川の河口にある西宮砲台も現存しているが、砲台内部が当時の姿のまま残っているのは和田岬砲台だけで、県第1号の国史跡に指定されている。
勝海舟が「神戸海軍操練所」を創設した1864年に完成。市教委文化財課は「海舟の弟子だった坂本龍馬も足を踏み入れたに違いない」と推測する。函館・五稜郭のような星形土塁に囲まれた円筒形の砲台外郭部は、花崗岩(か・こう・がん)製。2階建ての2階部分に大砲発射用の11の窓を備えるが、4年後の神戸開港で必要性が薄れ、使われることはなかった。
砲台の解体修理事業は、所有者の三菱重工が文化庁、県、神戸市の補助金を受けて2007年度から始まった。砲台内の柱や梁(はり)がシロアリや浸水によって腐食が進んだためで、来年度から老朽化した部材を入れ替えて組み立て直す。総事業費は約5億6千万円で、2013年3月に終わる予定だ。
今回展示するのは約50点。中でも興味深いのは、築造以来外されたことのないクギ、ネジ、ボルトなど、木と木を組み合わせて固定するのに使った金具類だ。神戸大大学院工学研究科の足立裕司教授(近代建築史)は「日本古来の木組み技術で建造することが可能だったにもかかわらず、当時最新と考えられていた西洋技術を何とか採り入れようとした跡が読み取れる重要な史料」と指摘する。
当日は午後1時~同2時半の公開に合わせて午後1時半~同4時、修理工事についての報告と東京都品川区立品川歴史館学芸員の冨川武史さんが砲台築造の歴史的背景に迫る講演「江戸湾防備から摂海防備へ~品川御台場から見た和田岬砲台~」をする。
講演の聴講には申し込みが必要。往復はがきに住所、氏名、電話番号を書き、今月19日必着で、〒652・8570 兵庫区まちづくり課「砲台講演会」係まで申し込む。詳しくは同課(078・511・2111内線214)、または市教委文化財課(078・322・5799)へ。
岡山
新選組サミット初参加 県内の団体 岡山との縁アピール
県内の新選組ファン、隊士の子孫らでつくる「岡山新選組準備会」が13、14日に京都市で開催される「第11回全国新選組サミット」に初めて参加する。隊士にふんした参加者が京の町を練り歩くパレードにも加わる予定で、会員は「岡山が新選組との縁が深いことをPRしたい」と楽しみにしている。
同準備会は、今年4月に発足。現在、会員は10~80代の男女28人で、定期的に会合を持つなど新選組について学んでいる。
サミットは、新選組にちなんだまちづくりを進めようと、京都市、福島県会津若松市などゆかりの地で毎年開催。今回は全国の愛好者グループなどから100人以上が参加。パレードのほか、各団体の活動発表、史跡見学、専門家の講演などが予定されている。
同準備会は、20人以上の隊士を送り出したという岡山と新選組のかかわりをアピールするとともに、他地域のファンと交流を深めようと参加を決めた。
同準備会は会員を募集中。問い合わせは、同準備会ホームページ(http://okayamashinsengumi.web.fc2.com)。
明日は全国各地で紅葉狩りに絶好のお天気だそう。小春日和ですって。
北海道
【白老】元陣屋の立役者 三好監物の生涯が漫画に
山形
清河八郎生誕180年の節目に完成 庄内・清河神社、善意が支えた屋根改修
茨城
シンポ:「桜田門外の変」映画化が縁 水戸浪士ら子孫14人100年ぶり集結 /茨城
京都
町の歴史資料館で幕末・維新激動期の大山崎紹介
兵庫
みみより情報:展覧会「幕末を翔けぬけた人々」 川西市で28日まで /兵庫
幕末の動乱語る 和田岬砲台史料を初公開
岡山
新選組サミット初参加 県内の団体 岡山との縁アピール
北海道
【白老】元陣屋の立役者 三好監物の生涯が漫画に
幕末の白老元陣屋ゆかりの仙台藩士三好監物の生涯が、漫画になった。仙台市で暮らす、やしゃごの三好彰さん(59)が監修した。白老発展の礎を築いた監物の横顔を分かりやすく紹介している。
白老元陣屋は、ロシアの南下政策に対抗する北の警備拠点。幕府の命で仙台藩士が派遣され、三好監物は2代目御備頭(おそなえがしら)を1857年から務めた。当初陣屋は、勇払(苫小牧市)に、との命令を、実地調査を行った監物らの進言で白老に変更された、というエピソードもある。
タイトルは「三好監物物語~仙台藩蝦夷地へ・激動の幕末史」。B6判、42ページ。監物が白老元陣屋に赴任するまでに始まり、前半は、藩士が寒さと食料不足に苦しみながら警護に当たった様子を描いている。後半は帰藩後の監物。信念を貫く言論で大老・井伊直弼の怒りを買い、藩内で少数派の尊皇攘夷論を唱えて命を狙われたこともあった。1868年、54年の生涯を閉じる。自害だった。
三好彰さんは、仙台市内で耳鼻咽喉科クリニックを営む。1988年から毎年、白老を訪れて子供たちの耳鼻科健診を行うなどまちとのかかわりを持ち続けている。「三好監物物語」は、2007年に白老元陣屋資料館に寄贈した医学漫画から抜粋し、編集した。
彰さんは「監物の生涯を多くの町民に知ってもらい、歴史的関係を共有する白老と仙台の友好発展につなげてほしい」と話している。漫画は150部ほど用意し、資料館で無料配布している。問い合わせは仙台藩白老元陣屋資料館 電話0144(85)2666。
山形
清河八郎生誕180年の節目に完成 庄内・清河神社、善意が支えた屋根改修
清河神社(正木尚文宮司)=庄内町清川=の、老朽化に伴う屋根改修工事が無事完了した。地域住民が昨年10月に実行委員会(松田広委員長)を設立し、これまで募金活動を展開。神社に祭られている幕末の志士・清河八郎(1830~63年)の全国のファンらも善意を寄せた。7日に竣工(しゅんこう)式典が行われた。
式典には地元住民ら約140人が出席。清河八郎顕彰会の斎藤清会長や松田委員長が「清河生誕180周年の節目の年に屋根を改修することができ、この上ない喜びを感じている」とあいさつ。正木宮司は「神社を後世まで引き継ぐことができるようになった。県内外の協力者に感謝している」と述べた。
実行委によると、清川の住民や清河ファンら延べ618の個人・団体が賛同し、計1173万円の善意を寄せた。総工事費は1135万円。5月に工事に着工し、敷き詰められていた瓦をすべて取り除いて鉄製の鋼板にふき替え、8月に完成した。
地域住民らが出席した竣工式典
清川出身の八郎を祭る同神社は、地元小学生がみこ舞を披露する例大祭(5月)など、住民にとってなじみのイベントが開かれている。1933(昭和8)年の創建以降、改修したことがなく、屋根の腐食による雨漏りが年々悪化、改修が急務となっていた。
茨城
シンポ:「桜田門外の変」映画化が縁 水戸浪士ら子孫14人100年ぶり集結 /茨城
◇ルーツ再確認
幕末の大老暗殺事件「桜田門外の変」に加わった水戸浪士らの子孫14人が10日、水戸市三の丸の県立図書館でのシンポジウムで集結した。事件の映画化を通じ、縁を持った歴史愛好家が呼び掛けて実現。子孫らは自らのルーツを再確認するとともに、事件後途切れていた仲間意識をあたためた。
主催したのは、同事変研究同好会(会長=中村康雄・那珂歴史同好会会長)。三上靖彦・「桜田門外ノ変」映画化支援の会事務局長らが機運作りに奔走していたのに刺激を受け、歴史資料や関係者の調査をする中で、子孫らと知り合った。中村会長によると、事件から50年目の1910年、靖国神社で約500人が参加して記念式典があり、浪士らの子孫も顔を合わせたが、これだけの人数の子孫が集まるのはそれ以来100年ぶり。
シンポジウムでは那珂市歴史民俗資料館の仲田昭一館長が「桜田門外の変と時代背景」という演題で基調講演。水戸藩は徳川家でありながら朝廷と幕府の君臣関係に基づき、朝幕対立の際には朝廷側につくことが光圀公の時代からの家訓だったこと、彦根藩は朝廷監視役としての自負があったこと、幕末は朝廷と幕府の力のバランスが変化していったことなどを説明した。
その後のパネルディスカッションでは三上氏や、井伊直弼公の首を切り落としたとされる薩摩藩浪士の有村次左衛門のひ孫、有村幸三さん(64)=神奈川県茅ケ崎市=も加わり、映画の感想などを語り合った。有村さんは「曽祖父の斬(き)り合いシーンは見ていてゾッとした」と話しながらも、子孫らが集まったことに「いきなり親類が増えたよう」と顔をほころばせていた。【山崎明子】
京都
町の歴史資料館で幕末・維新激動期の大山崎紹介
「幕末・維新期の大山崎」と題した企画展が、京都府大山崎町大山崎の町歴史資料館で開かれている。1864年の「禁門の変」で敗れた長州藩の志士たちが天王山で自決する姿を描いた絵や、町や社寺の被災ぶりを記した文書など約60点が並ぶ。
激動期の大山崎の様子を伝えようと資料館が催した。家々が燃え、兵馬が駆け回り、町人が逃げまどうなど、禁門の変で戦場となった京都の騒乱を克明に書いた絵が展示されている。薩摩、会津両藩と戦った長州藩の真木和泉の肖像画や、真木ら17人の志士が使ったとされる弁当箱、敗走後に17人が天王山で自刃する姿を描いた絵も並んでいる。
さらに、会津藩が大山崎を砲撃した際、観音寺(山崎聖天)の僧が本堂の仏像を池に入れて隠し、柳谷(現長岡京市)を経て逃げる様子を記録した史料や、戦火を逃れて避難した住民に、同藩が戦闘終了後、帰還を呼び掛けた木製の高札も展示されている。
このほか、維新後の廃仏棄釈の影響で、現在の大阪府島本町山崎にあった「西観音寺」が、神社への変更を余儀なくされたという史実も写真などで紹介している。訪れた人々は、激動期の大山崎の様子を思い浮かべながら展示品を眺めていた。28日まで。大人300円、小中生は無料。
兵庫
みみより情報:展覧会「幕末を翔けぬけた人々」 川西市で28日まで /兵庫
◇所蔵資料50点を展示--大阪青山歴史文学博物館
◇幕府の軍艦「開陽丸」の絵や横井小楠自筆「国是十二条」
NHK大河ドラマ「龍馬伝」の舞台にもなっている幕末の動乱の時代に活躍した人々の軌跡を追う展覧会「幕末を翔(か)けぬけた人々」が、川西市長尾町の大阪青山歴史文学博物館で開かれている。
展覧会では、同館が所蔵する資料約50点が展示されている。幕末に徳川幕府の軍艦であった「開陽丸」の絵のほか、坂本龍馬が新しい時代の日本の方針を提案した「船中八策」に大きな影響を与えたと言われる横井小楠の「国是十二条」の自筆原本など、幕末に活躍した人々の肉筆が多数、出展されている。
同館の外観はかつて付近にあった山下城の復元をイメージした城郭建築で、ひときわ異彩を放っている。また、最上階には展望室が作られており、能勢妙見山などの山並みが一望できるという(雨天時は閉室)。
28日まで。入館時間は午前10時から午後4時半まで。月曜は休館。入館料は一般600円、65歳以上500円、大学生400円、高校生300円、中学生以下無料。問い合わせは同館(072・790・3535)。
==============
◇プレゼント
この展覧会のチケットを2枚1組で10人にプレゼントします。はがきに「幕末展チケット希望」と書き、郵便番号、住所、氏名、電話番号も記入して、〒660-0892 尼崎市東難波町5の16の29、毎日新聞阪神支局みみより情報係へ。17日まで必着。応募多数なら抽選します。
幕末の動乱語る 和田岬砲台史料を初公開
外国船が日本沖に姿を現し始めた幕末期、勝海舟の提言を受けて江戸幕府が造った要塞(よう・さい)「和田岬砲台」(神戸市兵庫区)の建築部材や金具類が12月18日、神戸市兵庫区の兵庫公会堂で初公開される。最新の西洋技術を模倣して苦労しながら造った跡がうかがえる貴重な史料だ。(日比野容子)
和田岬砲台は、大阪湾岸の警備のため築造された四つの要塞のうちの一つ。夙川の河口にある西宮砲台も現存しているが、砲台内部が当時の姿のまま残っているのは和田岬砲台だけで、県第1号の国史跡に指定されている。
勝海舟が「神戸海軍操練所」を創設した1864年に完成。市教委文化財課は「海舟の弟子だった坂本龍馬も足を踏み入れたに違いない」と推測する。函館・五稜郭のような星形土塁に囲まれた円筒形の砲台外郭部は、花崗岩(か・こう・がん)製。2階建ての2階部分に大砲発射用の11の窓を備えるが、4年後の神戸開港で必要性が薄れ、使われることはなかった。
砲台の解体修理事業は、所有者の三菱重工が文化庁、県、神戸市の補助金を受けて2007年度から始まった。砲台内の柱や梁(はり)がシロアリや浸水によって腐食が進んだためで、来年度から老朽化した部材を入れ替えて組み立て直す。総事業費は約5億6千万円で、2013年3月に終わる予定だ。
今回展示するのは約50点。中でも興味深いのは、築造以来外されたことのないクギ、ネジ、ボルトなど、木と木を組み合わせて固定するのに使った金具類だ。神戸大大学院工学研究科の足立裕司教授(近代建築史)は「日本古来の木組み技術で建造することが可能だったにもかかわらず、当時最新と考えられていた西洋技術を何とか採り入れようとした跡が読み取れる重要な史料」と指摘する。
当日は午後1時~同2時半の公開に合わせて午後1時半~同4時、修理工事についての報告と東京都品川区立品川歴史館学芸員の冨川武史さんが砲台築造の歴史的背景に迫る講演「江戸湾防備から摂海防備へ~品川御台場から見た和田岬砲台~」をする。
講演の聴講には申し込みが必要。往復はがきに住所、氏名、電話番号を書き、今月19日必着で、〒652・8570 兵庫区まちづくり課「砲台講演会」係まで申し込む。詳しくは同課(078・511・2111内線214)、または市教委文化財課(078・322・5799)へ。
岡山
新選組サミット初参加 県内の団体 岡山との縁アピール
県内の新選組ファン、隊士の子孫らでつくる「岡山新選組準備会」が13、14日に京都市で開催される「第11回全国新選組サミット」に初めて参加する。隊士にふんした参加者が京の町を練り歩くパレードにも加わる予定で、会員は「岡山が新選組との縁が深いことをPRしたい」と楽しみにしている。
同準備会は、今年4月に発足。現在、会員は10~80代の男女28人で、定期的に会合を持つなど新選組について学んでいる。
サミットは、新選組にちなんだまちづくりを進めようと、京都市、福島県会津若松市などゆかりの地で毎年開催。今回は全国の愛好者グループなどから100人以上が参加。パレードのほか、各団体の活動発表、史跡見学、専門家の講演などが予定されている。
同準備会は、20人以上の隊士を送り出したという岡山と新選組のかかわりをアピールするとともに、他地域のファンと交流を深めようと参加を決めた。
同準備会は会員を募集中。問い合わせは、同準備会ホームページ(http://okayamashinsengumi.web.fc2.com)。
談春さん、「紅葉坂の佐平次」以来、ますます乗りに乗ってる気がする。先月の「九州吹き戻し」@横浜にぎわい座もなかなかだったので、平日夜に東京湾を半周してにぎわい座まで駆けつけるのは大変なんですが(汗)今回も駆けつけました。
大正解。大ネタ2本、どちらも爆笑の連続でした。談笑さんの芸をたっぷり堪能して、ほこほこと暖かい幸福感に包まれた家路でした。

1. 開口一番「鮑のし」こはる
わーい、久しぶりのこはるちゃん。女性としては声が低いということもあるかと思いますが、身につけた話芸の力なんでしょう、こはるちゃんには女性が落語をやっている違和感をまったくといっていいほど感じません。
でも「権助魚」に比べると「鮑のし」はやっぱり難しいんだろうなぁ。ちょっと難しい課題に取り組んでます感がありました。前座さんでも二つ目近い(談春さんはいつでも推薦すると言っているそうです、ただ家元が最終審査する落語立川流の二つ目のハードルは相当に高そうです)こはるさんとなると、あちこちで笑いを取るだけのレベルではあるのですが。甚兵衛さんキャラは難易度が高そうですし、魚屋の鮑に関する啖呵もあるし。
2. 「二階ぞめき」談春
談春師、最近マクラが長くなってきてませんか。小三治師に追いつこうというるわけではないと思いますが(苦笑)、以前に比べて、いろいろなマクラを楽しんでいる印象です。
まずはこはるちゃんの髪型をいじる。こはるちゃんはいつでも二つ目OKといいつつ、最近家元が元気なんで家元による「前座→二つ目」昇進試験をクリアするのは大変だぞ、と。
次は横浜周辺の戒厳令の中をよくいらっしゃいました、的なネタ。APECで厳戒態勢だし、昨日は異臭騒ぎがあったし。その異臭、汚水が自然発酵したらしい……って、どんな汚水なんだ横浜ってツッコミ入れて大爆笑。
立川流の門下なのでトラブルは慣れっこ、特に家元と志らくが一緒の時は、ということで、家元が皇居の近く(国立小劇場か国立演芸場?)で高座に上がった時にちょうど皇太子殿下のパレードがあって、あの近辺を大きな荷物抱えてネタをぶつぶつつぶやいて歩いていたら何度も警官に呼び止められて荷物検査をされた。風呂敷包みの中は着物、職業を聞かれて「落語家です」と答えたら何となく生暖かい目(あれ、何となくいたわるような、だったかな?)で見られたとか。
ふっとマクラに振りたい話があったんだけど、今の話をしているうちに忘れちゃった(爆)、思い出したら中入り後とか言ってたけど……結局思い出せなかったのか、中入り後はまったくマクラなしでしたねぇ(^_^;)。
その後はディズニーランドの話だったかな。そこから十代に通い弟子になっていた頃、大山のスナックに好きな女性がいて通っていたんだけど競輪もやっていたので帰宅する電車賃をけちって戸田まで2時間ほどを歩いて帰宅していたそうだ。そして、その途中、バブルの時代でもあったので、途中に中南米から働きに来ていたキレイなおねえさんたちの立っている道を通り抜けることが続いたそうで。度々通ると会話するようになったり、いつもいる女性を見かけないと気にかかったりとか、その辺りがかつての吉原の冷やかしとか「ぞめき」の感覚でしょうねということで、予告されてた「二階ぞめき」の世界へ。
談春さんの高座は素直にとっても楽しめた。吉原を冷やかして歩くのが好きだという若旦那の気持ち、買い物も好きだけどウィンドウショッピングも好きだという女性に「あるある」ネタかも知れない(自分は短い時間で効率的な買い物をするのが好きなので、ウィンドウショッピングの趣味はないのですが)。
そして、吉原に好きな女がいるのなら、金の心配は要らない、落籍して囲ってしまいなさいと番頭にそそのかされるという、世の中の大半の殿方にとってはうはうはな境遇にある若旦那のロジックがふるってる。特定の女に入れ込んでいるわけじゃない、吉原そのものが好きなんだ。吉原を丸ごと見受けするならいいが、そうじゃないなら吉原通いはやめない、って主張。
現代に置き換えてみるとこんな感じですか、銀座のシャネルの商品を買い占めておきましたので銀座通いはおやめ下さいといわれたってやめないよ、銀座全部を買い占めたというなら話は別だ……(汗)。
でも金がうなるほどあるそうで、若旦那が居住している二階に吉原を再現しちゃうんですね。この馬鹿馬鹿しさが、まさに落語。そして、大工の熊公はじめ、腕に覚えがある職人が吉原再現プロジェクトXに共感して、広いとはいえ商家の二階に吉原の町並みがつくられてしまうという、馬鹿馬鹿しくもありえない落語設定。ところが、クラウドコンピューティングができてしまう今なら、ネット上で3Dの吉原を再現するRPGは簡単そう(爆)。
吉原再現ジオラマに興奮し、脳内妄想でひとりRPGしてしまう若旦那に爆笑しっ放しだったんですが……考えてみれば、深川江戸資料館の長屋再現スペースで落語さながらの長屋の住人たちを脳内妄想してうはうはしてる自分も、若旦那と似たもの同士です(爆)。
中入り後については、また、改めて。
大正解。大ネタ2本、どちらも爆笑の連続でした。談笑さんの芸をたっぷり堪能して、ほこほこと暖かい幸福感に包まれた家路でした。
1. 開口一番「鮑のし」こはる
わーい、久しぶりのこはるちゃん。女性としては声が低いということもあるかと思いますが、身につけた話芸の力なんでしょう、こはるちゃんには女性が落語をやっている違和感をまったくといっていいほど感じません。
でも「権助魚」に比べると「鮑のし」はやっぱり難しいんだろうなぁ。ちょっと難しい課題に取り組んでます感がありました。前座さんでも二つ目近い(談春さんはいつでも推薦すると言っているそうです、ただ家元が最終審査する落語立川流の二つ目のハードルは相当に高そうです)こはるさんとなると、あちこちで笑いを取るだけのレベルではあるのですが。甚兵衛さんキャラは難易度が高そうですし、魚屋の鮑に関する啖呵もあるし。
2. 「二階ぞめき」談春
談春師、最近マクラが長くなってきてませんか。小三治師に追いつこうというるわけではないと思いますが(苦笑)、以前に比べて、いろいろなマクラを楽しんでいる印象です。
まずはこはるちゃんの髪型をいじる。こはるちゃんはいつでも二つ目OKといいつつ、最近家元が元気なんで家元による「前座→二つ目」昇進試験をクリアするのは大変だぞ、と。
次は横浜周辺の戒厳令の中をよくいらっしゃいました、的なネタ。APECで厳戒態勢だし、昨日は異臭騒ぎがあったし。その異臭、汚水が自然発酵したらしい……って、どんな汚水なんだ横浜ってツッコミ入れて大爆笑。
立川流の門下なのでトラブルは慣れっこ、特に家元と志らくが一緒の時は、ということで、家元が皇居の近く(国立小劇場か国立演芸場?)で高座に上がった時にちょうど皇太子殿下のパレードがあって、あの近辺を大きな荷物抱えてネタをぶつぶつつぶやいて歩いていたら何度も警官に呼び止められて荷物検査をされた。風呂敷包みの中は着物、職業を聞かれて「落語家です」と答えたら何となく生暖かい目(あれ、何となくいたわるような、だったかな?)で見られたとか。
ふっとマクラに振りたい話があったんだけど、今の話をしているうちに忘れちゃった(爆)、思い出したら中入り後とか言ってたけど……結局思い出せなかったのか、中入り後はまったくマクラなしでしたねぇ(^_^;)。
その後はディズニーランドの話だったかな。そこから十代に通い弟子になっていた頃、大山のスナックに好きな女性がいて通っていたんだけど競輪もやっていたので帰宅する電車賃をけちって戸田まで2時間ほどを歩いて帰宅していたそうだ。そして、その途中、バブルの時代でもあったので、途中に中南米から働きに来ていたキレイなおねえさんたちの立っている道を通り抜けることが続いたそうで。度々通ると会話するようになったり、いつもいる女性を見かけないと気にかかったりとか、その辺りがかつての吉原の冷やかしとか「ぞめき」の感覚でしょうねということで、予告されてた「二階ぞめき」の世界へ。
談春さんの高座は素直にとっても楽しめた。吉原を冷やかして歩くのが好きだという若旦那の気持ち、買い物も好きだけどウィンドウショッピングも好きだという女性に「あるある」ネタかも知れない(自分は短い時間で効率的な買い物をするのが好きなので、ウィンドウショッピングの趣味はないのですが)。
そして、吉原に好きな女がいるのなら、金の心配は要らない、落籍して囲ってしまいなさいと番頭にそそのかされるという、世の中の大半の殿方にとってはうはうはな境遇にある若旦那のロジックがふるってる。特定の女に入れ込んでいるわけじゃない、吉原そのものが好きなんだ。吉原を丸ごと見受けするならいいが、そうじゃないなら吉原通いはやめない、って主張。
現代に置き換えてみるとこんな感じですか、銀座のシャネルの商品を買い占めておきましたので銀座通いはおやめ下さいといわれたってやめないよ、銀座全部を買い占めたというなら話は別だ……(汗)。
でも金がうなるほどあるそうで、若旦那が居住している二階に吉原を再現しちゃうんですね。この馬鹿馬鹿しさが、まさに落語。そして、大工の熊公はじめ、腕に覚えがある職人が吉原再現プロジェクトXに共感して、広いとはいえ商家の二階に吉原の町並みがつくられてしまうという、馬鹿馬鹿しくもありえない落語設定。ところが、クラウドコンピューティングができてしまう今なら、ネット上で3Dの吉原を再現するRPGは簡単そう(爆)。
吉原再現ジオラマに興奮し、脳内妄想でひとりRPGしてしまう若旦那に爆笑しっ放しだったんですが……考えてみれば、深川江戸資料館の長屋再現スペースで落語さながらの長屋の住人たちを脳内妄想してうはうはしてる自分も、若旦那と似たもの同士です(爆)。
中入り後については、また、改めて。
ちょっと出遅れ、国立演芸場に着いたのは開演から1時間たった19時半。モニターテレビで中継を鑑賞することに。
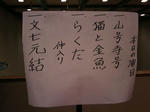
「らくだ」かかってる……かんかんのうの場面に間に合ってよかったというか、ここまで逃して口惜しいというか。
談笑版「らくだ」、かんかんのうじゃないです。40代半ば以上の人間には昔懐かしい歌謡曲です(笑)。死体背負って歌うのか、それを(汗)。
清めの酒を飲むうちに、丁目の半次におどされておろおろしていた屑屋の久六が酔っ払って半次を圧倒するところが聴き所。談笑版はこのあたりがちょっとくどいかも(チャレンジねたをかける国立演芸場の独演会ですから、これからでしょう)。
一般的なバージョンでは久六が剃刀でらくだの髪をそいで漬け物樽に詰め込むんだけど、談笑版では鰺切り包丁で……うわーん、怖い怖い(;o;)。
樽をかつぎ出すところで「片棒」ネタのギャグが出てくるところは笑えた。
八百屋と久六のやりとりでサゲなんだけど、前半聴いてなかったせいか、よくわからなかった(汗)。うぅ、談笑版をフルバージョンで聴く機会に埋め合わせよう。
☆★☆★
中入り後。ばくちで六両負けて寒い中を半纏一枚で放り出された男が……うわー、「らくだ」かけた後に「文七元結」、相変わらずチャレンジャーというかタフな談笑師。
ほとんど地の言葉なし(覚えている限りは一カ所だけ)。会話だけでテンポよく展開。
腕のよい左官だった長兵衛が酒と博打で身を持ち崩していくわけを、ちゃんと補ってくれている。長七という息子がいて、左官としても将来楽しみだったのだが、病でぽっくり逝ってしまった。先々の楽しみを失って自暴自棄になる長兵衛、というのは一応の納得感。
女性のキャラクターに割と配慮している談笑版、お久ちゃんと佐野槌の女将さんの造型にけっこう力を入れている(お兼は存在感薄いが)。
お久ちゃんは、自慢だった父親が荒れていくのを見ながら、兄と違って自分は左官になれないことを気に病み、好きだった父親を嫌いになる自分が許せず、吾妻橋のあたりで身投げをはかるところを佐野槌の女将に助けられ、身売りして貧しい我が家を立て直そうとする、という事情に。うーん、辻褄は合うけど、鬱展開だなぁ。
佐野槌の女将さんは、目配りだけで大物っぷりが伝わる感じ。でも、来年の暮れまではお久ちゃんを店に出さないと約束する場面で、一日でも過ぎたらもう遅いとたたみ込む談春版の女将を知っているだけに……談笑版にも吉原の大店を仕切る女将の遣り手ぶりを今後は期待したいところ。
お久ちゃんのけなげさと女将の説教に、腹をくくって左官として立ち直ることを約束する長兵衛。吾妻橋で通行人とぶつかって、懐を探ると、女将に借りた五十両がない。がっくりきて、たもとに石を入れ始める……おいおいおいっ、長兵衛が身投げをはかるのか談笑版はっ(汗)。間一髪、爆笑。ここは、うまい。
そこに、身投げをはかる若者が登場。掛け取りの帰りに五十両を盗まれたという若者に、お久ちゃんが吉原に身を置くことで借りた五十両をぽんとやってしまう文七の江戸っ子気質にどう説得力を持たせるか。談笑さん、そう来たか。余計かも知れないけど、お久ちゃんがかつての父親を自慢にしていたこと、その自分に戻るためには五十両をここで見知らぬ若者にくれてやるのだということを、もう少しだけ強めに匂わせると、さらにいいかも。
五十両を受け取った文七が戻った近江屋の主人、卯兵衛はなかなかの人物ぶりが伺えてグッド。ちょっとさもしい番頭とのやりとりが笑えた。「井戸の茶碗」とか「柳田格之進」とか踏まえたくすぐり、いいです!そしてまた、卯兵衛が長兵衛の長屋を訪れる場面、長兵衛と卯兵衛のやりとりもよかった。
今後またどこかで、さらに磨きをかけた談笑版「文七元結」聴きたいです。
☆★☆★
一旦幕を下ろしてまた上げてご挨拶。先日亡くなった弟弟子の談大さんの告別式が今日の昼過ぎにあったそうです。
訃報を聞いたのが日暮里寄席の楽屋だったこと。出演する立川流の皆さんが動揺しつつもお客様たちを笑わせることに務め、最後は20周年記念で三本締めをしたこと。落語家という商売はつくづく因果なものだと感じたこと。
兄弟子の文都さんが亡くなったのもちょうど一年前だったこと。
そして最後に、今日の告別式で家元が披露した弔辞の紹介……笑いつつも、ぐっと来ました。
9月末に古い友人が急逝したショックを思い出し、ほろりと来る挨拶でした。
☆★☆★
これで、国立演芸場、J亭@JTホール、月刊談笑@北沢タウンホールとみっつの談笑月例会を一応コンプリートしました。いま自分的に一番面白いのは月刊談笑かな……勤務地から下北沢まで1時間半はかかるので毎月行くのは難しそうですが。
「らくだ」かかってる……かんかんのうの場面に間に合ってよかったというか、ここまで逃して口惜しいというか。
談笑版「らくだ」、かんかんのうじゃないです。40代半ば以上の人間には昔懐かしい歌謡曲です(笑)。死体背負って歌うのか、それを(汗)。
清めの酒を飲むうちに、丁目の半次におどされておろおろしていた屑屋の久六が酔っ払って半次を圧倒するところが聴き所。談笑版はこのあたりがちょっとくどいかも(チャレンジねたをかける国立演芸場の独演会ですから、これからでしょう)。
一般的なバージョンでは久六が剃刀でらくだの髪をそいで漬け物樽に詰め込むんだけど、談笑版では鰺切り包丁で……うわーん、怖い怖い(;o;)。
樽をかつぎ出すところで「片棒」ネタのギャグが出てくるところは笑えた。
八百屋と久六のやりとりでサゲなんだけど、前半聴いてなかったせいか、よくわからなかった(汗)。うぅ、談笑版をフルバージョンで聴く機会に埋め合わせよう。
☆★☆★
中入り後。ばくちで六両負けて寒い中を半纏一枚で放り出された男が……うわー、「らくだ」かけた後に「文七元結」、相変わらずチャレンジャーというかタフな談笑師。
ほとんど地の言葉なし(覚えている限りは一カ所だけ)。会話だけでテンポよく展開。
腕のよい左官だった長兵衛が酒と博打で身を持ち崩していくわけを、ちゃんと補ってくれている。長七という息子がいて、左官としても将来楽しみだったのだが、病でぽっくり逝ってしまった。先々の楽しみを失って自暴自棄になる長兵衛、というのは一応の納得感。
女性のキャラクターに割と配慮している談笑版、お久ちゃんと佐野槌の女将さんの造型にけっこう力を入れている(お兼は存在感薄いが)。
お久ちゃんは、自慢だった父親が荒れていくのを見ながら、兄と違って自分は左官になれないことを気に病み、好きだった父親を嫌いになる自分が許せず、吾妻橋のあたりで身投げをはかるところを佐野槌の女将に助けられ、身売りして貧しい我が家を立て直そうとする、という事情に。うーん、辻褄は合うけど、鬱展開だなぁ。
佐野槌の女将さんは、目配りだけで大物っぷりが伝わる感じ。でも、来年の暮れまではお久ちゃんを店に出さないと約束する場面で、一日でも過ぎたらもう遅いとたたみ込む談春版の女将を知っているだけに……談笑版にも吉原の大店を仕切る女将の遣り手ぶりを今後は期待したいところ。
お久ちゃんのけなげさと女将の説教に、腹をくくって左官として立ち直ることを約束する長兵衛。吾妻橋で通行人とぶつかって、懐を探ると、女将に借りた五十両がない。がっくりきて、たもとに石を入れ始める……おいおいおいっ、長兵衛が身投げをはかるのか談笑版はっ(汗)。間一髪、爆笑。ここは、うまい。
そこに、身投げをはかる若者が登場。掛け取りの帰りに五十両を盗まれたという若者に、お久ちゃんが吉原に身を置くことで借りた五十両をぽんとやってしまう文七の江戸っ子気質にどう説得力を持たせるか。談笑さん、そう来たか。余計かも知れないけど、お久ちゃんがかつての父親を自慢にしていたこと、その自分に戻るためには五十両をここで見知らぬ若者にくれてやるのだということを、もう少しだけ強めに匂わせると、さらにいいかも。
五十両を受け取った文七が戻った近江屋の主人、卯兵衛はなかなかの人物ぶりが伺えてグッド。ちょっとさもしい番頭とのやりとりが笑えた。「井戸の茶碗」とか「柳田格之進」とか踏まえたくすぐり、いいです!そしてまた、卯兵衛が長兵衛の長屋を訪れる場面、長兵衛と卯兵衛のやりとりもよかった。
今後またどこかで、さらに磨きをかけた談笑版「文七元結」聴きたいです。
☆★☆★
一旦幕を下ろしてまた上げてご挨拶。先日亡くなった弟弟子の談大さんの告別式が今日の昼過ぎにあったそうです。
訃報を聞いたのが日暮里寄席の楽屋だったこと。出演する立川流の皆さんが動揺しつつもお客様たちを笑わせることに務め、最後は20周年記念で三本締めをしたこと。落語家という商売はつくづく因果なものだと感じたこと。
兄弟子の文都さんが亡くなったのもちょうど一年前だったこと。
そして最後に、今日の告別式で家元が披露した弔辞の紹介……笑いつつも、ぐっと来ました。
9月末に古い友人が急逝したショックを思い出し、ほろりと来る挨拶でした。
☆★☆★
これで、国立演芸場、J亭@JTホール、月刊談笑@北沢タウンホールとみっつの談笑月例会を一応コンプリートしました。いま自分的に一番面白いのは月刊談笑かな……勤務地から下北沢まで1時間半はかかるので毎月行くのは難しそうですが。
毎度、写真画像が横に寝ててすみません。
土曜の午後、にぎわい座でまったりと志の輔らくごを友と聴く。あぁ、幸せなひととき。
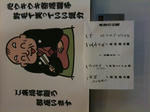
1.開口一番「つる」志の太郎
「立川志の輔6番目の弟子」と自己紹介してました。手元の『落語ファン倶楽部』最新号の「東西落語家現勢図」では5番目になってるんですが。志の輔さんの前座さんは最近入れ替わったのかな。
背が高くて、さらにとっても面長なのが印象的。先代の圓楽師匠と顔を並べて比較したい感じ(爆)。
初めて見る前座さんにしては口跡がきれいなので、下地があるのかも知れません。声の通りがよく、聴きやすいし。
前座噺おなじみの「つる」ですが……「つ〜っと来て、るっと止まる」の前に「つる〜っと来て、ぽいっと止まる」というバージョンもあるんですね。ここで笑わせてもらいました。
2. 「王子の狐」志の輔
まずは軽く時事ネタ。APEC会場となって全国から警官が配備されている横浜エリアにわざわざお越しいただいてありがとうございました、この時期にこのあたりでお巡りさんに道を聞くと首をひねられることが多いとか。
そしてホットな、尖閣諸島で海上巡視船に中国の漁船が突っ込んだ模様が収録されたビデオ画像がYouTubeにリークされ、それがテレビ報道されるということにツッコミを入れたマクラ。確かに、テレビに収録された画像をYouTubeやニコ動にアップすると著作権法違反で削除されるのに、YouTubeにアップされたビデオが昨日は一日中テレビを賑わせておりましたなぁ(汗)。
そして、APECの警備で全国から横浜に警察官が招集されているということは、北海道と九州の守りが薄くなっている、ロシアと中国が来るかも知れないぞ〜という、志の輔さんもやはり立川流の落語家さんだなぁと感じる一幕。
つい一昨日あたりの日本テレビの収録で王子稲荷(関東の稲荷神社の総社だそうです)に行って、座布団五枚敷いた「お石様」というものに出会ったというマクラ……「何か、いい回答したらしい」という『笑点』に引っかけた一言で爆笑してしまうんですが。漬け物石のような大きな石を、願い事しながら持ち上げて、すぐに持ち上げられたらすぐに願い事がかなうとか、持ち上げられなかったらなかなか願い事がかなわないとか。
山瀬まみさん「明日二日酔いになりませんように」と願って持ち上げようとしたら、うんともすんともいわない。志の輔さんが「王子稲荷の側の扇屋の卵焼きが美味しかったから、収録が終わったらスタッフがお土産で用意してくれますように」と願って持ち上げたら、すっと持ち上がったらしい。スタッフの力自慢が持ち上げても持ち上がらず、志の輔さんが願い事なしでもう一度持ち上げようとしたら今度はまったく動かなかったと……人の願いや祈りの気持ちが「火事場の馬鹿力」を生むのではないかという志の輔師匠のお話、ガッテンさせていただきました。
王子稲荷がマクラということで、予想通り「王子の狐」。子供時代に読んだ子供向けの落語入門本で読んだ覚えがある。
そう言えば、自分は品川区出身だけど、生まれたのは北区十条。母が、出産予定日には3週間ぐらいあるからと北区十条の実家を訪問した夜に、母をせっついて出てきたらしい(汗)。予定日通り生まれたら牡牛座だったろうに、せっかちに生まれて出たところからして牡羊座に生まれる宿命だったのだろう(苦笑)。
閑話休題。普通は人を化かすと言われている狐が、人にいっぱい喰わされるという噺。17〜8才の妙齢の美女「お玉ちゃん」に化けた狐が、実は子持ち。子狐を喰わせるために人を化かしてたのかと思うと、いっぱい喰わされてぼこぼこにされる展開にはちょっと涙ぐみそそう。サゲ近くで出てくる子狐が愛らしいのは、さすが志の輔さん。
(中入り)
3. テツandトモ
「志の輔noにぎわい」ではゲストが事前予告されていないことが多い。今回も事前知識なし。で、前座の志の太郎さんがめくりを上げた時に「テツandトモ」と表示された時、場内に軽いどよめきが。
「なんでだろう〜、なんでだろう〜、なぜだなんでだろう〜♪」のテーマソングとともに、テツandトモ登場。赤と青のジャージ、肩から腕に白2本線。
しょっぱなが、志の輔さんの高座のゲストだということで談志家元の物まね。形態模写も兼ねてて、なかなか。さらに戦場カメラマンの渡部陽一さんの物まねと入り混じるというむずかしい展開へ。
いくつかの漫談ネタをアクションと歌で聴かせて見せてくれるステージで、とても楽しかったです。
4.「新版しじみ売り」志の輔
九州地方を巡業したというマクラから入りました。かなりの部分は「ピーピングしのすけのふしあなから世間」コラムの「龍馬の母、現る」でカバーされていましたが、さすが志の輔さん、ライブに来たお客様へのサービスを忘れていません。
長崎巡業の折、龍馬ブームで沸き返る中を「シーボルト記念館」訪問。ガイドさんは「シーボルトに詳しい人」と「坂本龍馬に詳しい人」を選べるんだそうです。そして「シーボルトに詳しい人」のガイドで、記念館に車を運転してくれた、龍馬ブームに対してちょっと斜に構えた、「長崎はくんち第一だと思ってる」ような人のツッコミが秀逸な、シーボルト記念館でのあれこれ。
シーボルト事件のそもそもが、間宮林蔵なんですよ、って話、みなもと太郎の歴史大河マンガ『風雲児たち』の愛読者である自分には「うん、通説はそうだよね」という感じなんですが、志の輔さんの口を借りると『風雲児たち』キャラの伊能忠敬とかシーボルトとか間宮林蔵とか高橋景保とかが脳内イメージに沸き上がる……収集つけるのが大変でしたが(^_^;)、歴史は暗記物ではなくて沢山のストーリーが積み上がってこそ面白いのだと思います。
で、マクラで何となく予感がしていたわけです。歴史に名を残しながら人となりを知られていない人物がいる、というフリから入ると、「あ、来たかも♪」です。そして「おじさんおじさん」と子供の物売りが出てきたら(「ねずみ」の冒頭も似ていたと思うのだけど、脳内イメージでは子役が違う・爆)、冬のネタで「しじみ売り」かもと思うわけ。
ピンポーン♪。CDに収録された「しじみ売り」、今年の初めの寒い時期にヘビーローテーションで聴きましたから、パチパチと拍手です。
しじみ売りの少年、追っ払おうとする料亭の料理人、少年を気に入ってとりなそうとする大物風な職業不詳のおじさん、おじさんを「兄貴」と慕うちんぴら風の「熊」。おじさんに気に入られた少年が小生意気な口をきくと、熊が「小僧〜っ」とすごむんですよ。それを、おじさんが肩ポンして取りなすんですよ。
で、九歳の少年が寒い中を川に下りてシジミを取っては売っている身の上話をすると、「おじさん」には聞き覚えのある、箱根の宿のある事件につながり……やがて「おじさん」の身の上が明らかにされ……この人情噺で、このサゲ、完成度高いです。初「新版しじみ売り」ライブ、堪能しました。
「新版」とついているわけは、たとえば志ん生師匠版と、後半の展開が違うかららしいですね。志ん生版は、クマに身代わり自首させるという展開なんだとか(汗)。少年の姉と駆け落ちした相手が幸せになるという点はいいけど、親分が子分を身代わり出頭させるって、それでいいのかってツッコミ入りますよね。しかも、親分は磔獄門必至という大物盗賊なわけで。
そんな親分が、少年の身の上話から、自分が情けをかけた相手を、その情けゆえに小伝馬町の牢獄に投獄させる羽目になったと知り、死罪覚悟で自首を決意するという内面のドラマが「しじみ売り」の肝ですね。
自分が志の輔ファンに引き込んだ友人も、この展開でどんなサゲになるのかとはらはらしっ放しだっただけに、こう来るかと感嘆しきりでした。
志の輔師匠、ありがとうございました。自分は今月日の出寄席@国際フォーラムのチケット取ってますが、今日の友人は行けませんので、ふたりで手分けして年明けの志の輔らくご@パルコのチケットを取ろうねと誓い合いました。
土曜の午後、にぎわい座でまったりと志の輔らくごを友と聴く。あぁ、幸せなひととき。
1.開口一番「つる」志の太郎
「立川志の輔6番目の弟子」と自己紹介してました。手元の『落語ファン倶楽部』最新号の「東西落語家現勢図」では5番目になってるんですが。志の輔さんの前座さんは最近入れ替わったのかな。
背が高くて、さらにとっても面長なのが印象的。先代の圓楽師匠と顔を並べて比較したい感じ(爆)。
初めて見る前座さんにしては口跡がきれいなので、下地があるのかも知れません。声の通りがよく、聴きやすいし。
前座噺おなじみの「つる」ですが……「つ〜っと来て、るっと止まる」の前に「つる〜っと来て、ぽいっと止まる」というバージョンもあるんですね。ここで笑わせてもらいました。
2. 「王子の狐」志の輔
まずは軽く時事ネタ。APEC会場となって全国から警官が配備されている横浜エリアにわざわざお越しいただいてありがとうございました、この時期にこのあたりでお巡りさんに道を聞くと首をひねられることが多いとか。
そしてホットな、尖閣諸島で海上巡視船に中国の漁船が突っ込んだ模様が収録されたビデオ画像がYouTubeにリークされ、それがテレビ報道されるということにツッコミを入れたマクラ。確かに、テレビに収録された画像をYouTubeやニコ動にアップすると著作権法違反で削除されるのに、YouTubeにアップされたビデオが昨日は一日中テレビを賑わせておりましたなぁ(汗)。
そして、APECの警備で全国から横浜に警察官が招集されているということは、北海道と九州の守りが薄くなっている、ロシアと中国が来るかも知れないぞ〜という、志の輔さんもやはり立川流の落語家さんだなぁと感じる一幕。
つい一昨日あたりの日本テレビの収録で王子稲荷(関東の稲荷神社の総社だそうです)に行って、座布団五枚敷いた「お石様」というものに出会ったというマクラ……「何か、いい回答したらしい」という『笑点』に引っかけた一言で爆笑してしまうんですが。漬け物石のような大きな石を、願い事しながら持ち上げて、すぐに持ち上げられたらすぐに願い事がかなうとか、持ち上げられなかったらなかなか願い事がかなわないとか。
山瀬まみさん「明日二日酔いになりませんように」と願って持ち上げようとしたら、うんともすんともいわない。志の輔さんが「王子稲荷の側の扇屋の卵焼きが美味しかったから、収録が終わったらスタッフがお土産で用意してくれますように」と願って持ち上げたら、すっと持ち上がったらしい。スタッフの力自慢が持ち上げても持ち上がらず、志の輔さんが願い事なしでもう一度持ち上げようとしたら今度はまったく動かなかったと……人の願いや祈りの気持ちが「火事場の馬鹿力」を生むのではないかという志の輔師匠のお話、ガッテンさせていただきました。
王子稲荷がマクラということで、予想通り「王子の狐」。子供時代に読んだ子供向けの落語入門本で読んだ覚えがある。
そう言えば、自分は品川区出身だけど、生まれたのは北区十条。母が、出産予定日には3週間ぐらいあるからと北区十条の実家を訪問した夜に、母をせっついて出てきたらしい(汗)。予定日通り生まれたら牡牛座だったろうに、せっかちに生まれて出たところからして牡羊座に生まれる宿命だったのだろう(苦笑)。
閑話休題。普通は人を化かすと言われている狐が、人にいっぱい喰わされるという噺。17〜8才の妙齢の美女「お玉ちゃん」に化けた狐が、実は子持ち。子狐を喰わせるために人を化かしてたのかと思うと、いっぱい喰わされてぼこぼこにされる展開にはちょっと涙ぐみそそう。サゲ近くで出てくる子狐が愛らしいのは、さすが志の輔さん。
(中入り)
3. テツandトモ
「志の輔noにぎわい」ではゲストが事前予告されていないことが多い。今回も事前知識なし。で、前座の志の太郎さんがめくりを上げた時に「テツandトモ」と表示された時、場内に軽いどよめきが。
「なんでだろう〜、なんでだろう〜、なぜだなんでだろう〜♪」のテーマソングとともに、テツandトモ登場。赤と青のジャージ、肩から腕に白2本線。
しょっぱなが、志の輔さんの高座のゲストだということで談志家元の物まね。形態模写も兼ねてて、なかなか。さらに戦場カメラマンの渡部陽一さんの物まねと入り混じるというむずかしい展開へ。
いくつかの漫談ネタをアクションと歌で聴かせて見せてくれるステージで、とても楽しかったです。
4.「新版しじみ売り」志の輔
九州地方を巡業したというマクラから入りました。かなりの部分は「ピーピングしのすけのふしあなから世間」コラムの「龍馬の母、現る」でカバーされていましたが、さすが志の輔さん、ライブに来たお客様へのサービスを忘れていません。
長崎巡業の折、龍馬ブームで沸き返る中を「シーボルト記念館」訪問。ガイドさんは「シーボルトに詳しい人」と「坂本龍馬に詳しい人」を選べるんだそうです。そして「シーボルトに詳しい人」のガイドで、記念館に車を運転してくれた、龍馬ブームに対してちょっと斜に構えた、「長崎はくんち第一だと思ってる」ような人のツッコミが秀逸な、シーボルト記念館でのあれこれ。
シーボルト事件のそもそもが、間宮林蔵なんですよ、って話、みなもと太郎の歴史大河マンガ『風雲児たち』の愛読者である自分には「うん、通説はそうだよね」という感じなんですが、志の輔さんの口を借りると『風雲児たち』キャラの伊能忠敬とかシーボルトとか間宮林蔵とか高橋景保とかが脳内イメージに沸き上がる……収集つけるのが大変でしたが(^_^;)、歴史は暗記物ではなくて沢山のストーリーが積み上がってこそ面白いのだと思います。
で、マクラで何となく予感がしていたわけです。歴史に名を残しながら人となりを知られていない人物がいる、というフリから入ると、「あ、来たかも♪」です。そして「おじさんおじさん」と子供の物売りが出てきたら(「ねずみ」の冒頭も似ていたと思うのだけど、脳内イメージでは子役が違う・爆)、冬のネタで「しじみ売り」かもと思うわけ。
ピンポーン♪。CDに収録された「しじみ売り」、今年の初めの寒い時期にヘビーローテーションで聴きましたから、パチパチと拍手です。
しじみ売りの少年、追っ払おうとする料亭の料理人、少年を気に入ってとりなそうとする大物風な職業不詳のおじさん、おじさんを「兄貴」と慕うちんぴら風の「熊」。おじさんに気に入られた少年が小生意気な口をきくと、熊が「小僧〜っ」とすごむんですよ。それを、おじさんが肩ポンして取りなすんですよ。
で、九歳の少年が寒い中を川に下りてシジミを取っては売っている身の上話をすると、「おじさん」には聞き覚えのある、箱根の宿のある事件につながり……やがて「おじさん」の身の上が明らかにされ……この人情噺で、このサゲ、完成度高いです。初「新版しじみ売り」ライブ、堪能しました。
「新版」とついているわけは、たとえば志ん生師匠版と、後半の展開が違うかららしいですね。志ん生版は、クマに身代わり自首させるという展開なんだとか(汗)。少年の姉と駆け落ちした相手が幸せになるという点はいいけど、親分が子分を身代わり出頭させるって、それでいいのかってツッコミ入りますよね。しかも、親分は磔獄門必至という大物盗賊なわけで。
そんな親分が、少年の身の上話から、自分が情けをかけた相手を、その情けゆえに小伝馬町の牢獄に投獄させる羽目になったと知り、死罪覚悟で自首を決意するという内面のドラマが「しじみ売り」の肝ですね。
自分が志の輔ファンに引き込んだ友人も、この展開でどんなサゲになるのかとはらはらしっ放しだっただけに、こう来るかと感嘆しきりでした。
志の輔師匠、ありがとうございました。自分は今月日の出寄席@国際フォーラムのチケット取ってますが、今日の友人は行けませんので、ふたりで手分けして年明けの志の輔らくご@パルコのチケットを取ろうねと誓い合いました。
カレンダー
| 10 | 2025/11 | 12 |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
カテゴリー
最新記事
(10/19)
(09/13)
(07/16)
(03/25)
(03/24)
最新コメント
[12/14 白牡丹(管理人)]
[12/14 ゆーじあむ]
[11/08 白牡丹(管理人)]
[11/07 れい]
[01/21 ゆーじあむ]
[11/15 白牡丹@管理人]
[11/15 ゆーじあむ]
[05/25 長谷川誠二郎]
[07/23 白牡丹@管理人]
[07/23 伊藤哲也]
最新TB
ブログ内検索
アーカイブ
最古記事
カウンター
プロフィール
HN:
白牡丹
性別:
非公開
自己紹介:
幕末、特に新選組や旧幕府関係者の歴史を追っかけています。連絡先はmariachi*dream.com(*印を@に置き換えてください)にて。
リンク
アクセス解析
Livedoor BlogRoll
本棚
