新選組・土方歳三を中心に取り上げるブログ。2004年大河ドラマ『新選組!』・2006正月時代劇『新選組!! 土方歳三最期の一日』……脚本家・制作演出スタッフ・俳優陣の愛がこもった作品を今でも愛し続けています。幕末関係のニュースと歴史紀行(土方さんに加えて第36代江川太郎左衛門英龍、またの名を坦庵公も好き)、たまにグルメねた。今いちばん好きな言葉は「碧血丹心」です。
今日は友人と「志の輔らくごinACT」に行ってきます。twitterなどで演目を知ってしまった(汗)のですが、まだライブで聴いていない作品ばかりなので楽しみです。
福島
京都「容保桜」苗木を来春、若松に植樹
会津まつり:「藩公行列」が雨で初の中止 /福島
白虎隊士らを慰霊 若松で墓前秋季祭礼
神奈川
勝海舟の肖像画も披露 咸臨丸遣米150周年式典
石川
見る者圧倒 力強い書 羽咋・永光寺 山岡鉄舟の4点初公開
富山
そろばん侍、直之が記した幕末加賀藩 磯田氏が文書確認
兵庫
幕末の砲台保護へ 兵庫県教委が現地調査開始
広島
竜馬にふんして観光客ご案内
書簡や絵図で幕末の福山紹介
鳥取
鳥取城下の変化一目
佐賀
佐賀15人の偉人伝
長崎
これが本物 実録・坂本龍馬展・6 異国船図
腰掛け龍馬の写真10月公開 大浦慶の縁者から県が購入
鹿児島
西郷さんに一筆絵付け 鹿児島中央駅
福島
京都「容保桜」苗木を来春、若松に植樹
幕末に京都守護職上屋敷があった京都府庁旧本館中庭(上京区)の「容保(かたもり)桜」の苗木が来春にも会津若松市に植樹されることになり、命名者である京都府の桜守・佐野藤右衛門さんが24日、同市の鶴ケ城を訪れる。
容保桜は旧本館の中庭にあるヤマザクラのうちの1本で、オオシマザクラの特徴も併せ持つ珍しい品種であることが佐野さんの調査で分かっている。
府庁は京都守護職上屋敷跡地で、幕末に会津藩主・松平容保公が京都守護職を務めていたことから今春、佐野さんが「容保桜」と命名した。
桜守として知られる佐野さんは「容保桜」の種子から苗を育てていて、苗を容保公ゆかりの地である会津若松市に移植したいと申し出ている。
24日は佐野さん自ら桜の名所でもある鶴ケ城などを訪れ、植樹に最適な場所を探す。
佐野さんによって適地が決まれば、来春にも「容保桜」の植樹が行われる見通しという。
会津まつり:「藩公行列」が雨で初の中止 /福島
会津若松市の「会津まつり」で23日、メーン行事の「藩公行列」が雨天のため中止になった。事務局の会津若松観光物産協会によると、58回目で初の中止という。
同まつりは、戊辰戦争で鶴ケ城を明け渡した9月23日を中日にした3日間、戦死者の慰霊を兼ねて同城や中心市街地で開かれる同市の秋祭り。1953年に始まった。
今年も22日、子供たちによる稚児行列で開幕。しかし、雨が降り続き、23日も回復が見込めなかったため、事務局が同日朝、行列の中止を決めた。行列は、市民らが歴代の藩主や戊辰戦争を戦った白虎隊、娘子隊などにふんして、市内を行進する。今年は青森県むつ市など会津藩ゆかりの県外勢も含め、約460人が参加予定だった。【太田穣】
白虎隊士らを慰霊 若松で墓前秋季祭礼
戊辰戦争で散った白虎隊士ら少年武士の霊を慰める墓前秋季祭礼は24日、会津若松市の飯盛山で行われた。
会津弔霊義会の主催で毎年春と秋に催している。
神事で少年らを追悼した後、同会の芳賀公平理事長が「白虎隊士の『国や古里を守る』という精神を伝えていきたい」と祭文を読み上げた。
菅家一郎市長ら関係者が墓前に玉ぐしをささげた。
続いて多くの参拝者が見守る中、会津高剣舞委員会の生徒が厳かに伝統の剣舞を奉納した。
市中心部では同日、会津まつりのフィナーレを飾る日新館童子行列も繰り広げられ、武者姿などに扮(ふん)した子どもたちが行進した。
神奈川
勝海舟の肖像画も披露 咸臨丸遣米150周年式典
江戸時代末期の一八六〇(万延元)年、幕府の遣米使節団を乗せた咸臨丸の太平洋横断から百五十周年を祝う記念式典が二十五日、横須賀市本町で開かれた。操船を手伝うため咸臨丸に同乗した米海軍大尉のひ孫で、米国の陸軍大学で歴史学を教えているジョージ・ブルック三世さん(65)が、咸臨丸と日米交流をテーマに講演した。
ブルックさんの曾祖父ジョン・ブルック大尉は幕末当時、米海軍の測量技師として日本近海の海底調査のため来日。「日本人単独の初の太平洋横断」を目指す遣米使節団の操船技術を心配し、自ら同乗を申し出て幕府に許可されたという。
ブルック大尉は航海中に艦長の勝海舟と交流を深め、米国に到着後、海舟の肖像画を記念に描かせた。ブルック家が今も保管する肖像画は、スライドで映し出され、来場者から驚きの声が漏れた。 (新開浩)
石川
見る者圧倒 力強い書 羽咋・永光寺 山岡鉄舟の4点初公開
羽咋市酒井町、曹洞宗永光(ようこう)寺は二十三日から二十八日まで、所蔵する山岡鉄舟の書四点を特別公開する。能登半島広域観光協会が主催する能登ふるさと博事業の「能登秘宝めぐり」の一環。
山岡鉄舟は幕末から明治にかけて活躍した武士、政治家で、剣、禅、書の達人としても知られる。
同寺によると、書はそれぞれ縦百八十センチ、横九十五センチ。四点は「金毛」「獅子」「奮威」「出塵」と記されており、「金毛の獅子 威を奮い 出塵す」という禅語。明治時代、困窮していた同寺が鉄舟に書を依頼し、一八八六(明治十九)年に額や軸一万枚の寄進を受け寺の再建費用に充てたとされ、今回公開される四点は当時のもの。これまで公開はしておらず、初公開になるという。
屋敷智乗監寺(57)は「見るものを圧倒する力強さがある。気迫が伝わってくる」と話している。特別拝観料は五百円。 (島崎勝弘)
富山
そろばん侍、直之が記した幕末加賀藩 磯田氏が文書確認
映画「武士の家計簿」の原作者、磯田道史茨城大准教授は25日までに、加賀藩士・猪 山直之が最後の藩主・前田慶寧(よしやす)の発言を書き抜きした文書を、金沢市立玉川 図書館近世史料館で確認した。文書には、旧幕府軍と新政府軍が戦った鳥羽・伏見の戦い に出兵する藩士に対し、新政府軍と一戦する覚悟で粉骨を尽くすよう、慶寧が命じる場面 もある。幕末加賀藩の実態と、直之の忠実な仕事ぶりを示す史料として注目される。
磯田氏が確認した文書「御意之趣書抜(ぎょいのおもむきかきぬき)」には、14代藩 主慶寧が1854(嘉永(かえい)7)年1月から68(慶応4)年10月までに発言し た内容を抜粋して記してある。
表紙に書き手として「猪山」の名があり、猪山家の家計簿を研究する磯田氏は「筆跡か ら、藩主の御次執筆(おつぎしっぴつ)役(書記官)を務めた直之が記したものに間違い ない」と指摘した。
1868年の鳥羽・伏見の戦いでは、1月6日から8日にかけて藩軍の隊長らをグルー プ別に「御居間書院」に呼び出し、皇国のために内府公(15代将軍徳川慶喜(よしのぶ ))と協力し、軍を派遣する旨を伝えている。慶寧は「必ず一戦に及ぶだろうから、粉骨 を尽くして忠勤に励め」という趣旨の発破を掛けている。
鳥羽・伏見の戦いでの加賀藩の立ち位置については、本気で戦闘に参加する意思はなく 、深い縁戚(えんせき)関係にある徳川側に配慮して消極的に出兵したとの研究分析もあ るが、磯田氏は「薩長(さっちょう)と相まみえる覚悟だったことをはっきりさせる重要 な史料」と指摘した。
文書は明治に入り、直之が藩主の発言をまとめた資料を基に重要な部分を抜粋してあら ためて書き残したものとみられる。磯田氏は「新政府が権勢を振るっている時期、前田家 にとっては都合の悪い文書だったのではないか」と推測。それでも直之が書き残したこと について「歴史にうそをつかず、記録係としての仕事を忠実にこなそうとした。直之のま じめな性格が出ている」と話した。
兵庫
幕末の砲台保護へ 兵庫県教委が現地調査開始
兵庫県沿岸部に残る幕末の砲台、台場(だいば)跡について、県教育委員会が現地調査を始めた。文献などから、勝海舟ゆかりの和田岬砲台(神戸市兵庫区)など約50件があったとみられるが、国の史跡として保護されているのは4件のみ。県教委は「緊迫した歴史情勢や当時の海外知識が読み取れる歴史文化遺産」と位置づけ、今後3年で現状を把握し、保存活用に弾みをつけたい考えだ。
幕末の砲台、台場は強固な石垣や土塁で防護した要塞(ようさい)。県沿岸部では外国船の脅威が高まった1850~60年代、幕府のほか尼崎、明石、姫路、徳島、豊岡など諸藩が相次いで築造した。由良要塞本部(洲本市)のように明治時代に陸軍が築いたものもある。
しかし、国や地方自治体の文化財保護が長らく近世以前を中心に扱ってきたため、大正時代に和田岬砲台と西宮砲台(西宮市)、2006年に松帆(淡路市)、07年に舞子(神戸市垂水区)の台場跡が国史跡に指定されたのみ。ほかは保護対象ではないため、開発から遺跡を守るために行政が遺跡のある場所を示す地図に記載されていない例も多く、中には破壊されたものもある。
ところが近年、近代化の歩みを伝える遺産として国の評価が高まったことなどから、県教委文化財室は研究者らによる調査研究検討会を7月下旬に結成。現存する数さえ把握されていないため、淡路地域から調査を始めた。
県教委は「日本海と瀬戸内海の双方に面した兵庫県は多様な形状の砲台、台場がある“博物館”。調査の成果を住民に分かりやすく還元したい」と話している。
(仲井雅史)
広島
竜馬にふんして観光客ご案内
幕末の志士坂本竜馬にふんして10~11月に福山市鞆町で観光客と交流する「鞆龍馬おもてなし隊」の研修会が25日、福山市役所であった。
おもてなし隊は女性1人を含む市内の20~70代計20人。うち13人が研修会に参加した。市観光課の職員は「記念撮影には積極的に応じましょう」などと指導。名所や土産物を説明する際の想定問答も紹介した。
全員が現場で着る黒の羽織とはかまを試着。竜馬の写真を見ながら、襟元は詰めて、はかまのすそは低めにするなど、竜馬らしい着こなしを研究した。
おもてなし隊は、近くNHK大河ドラマ「龍馬伝」で鞆町を舞台としたシーンが放送されるのを受け、福山市などでつくる福山観光キャンペーン実行委員会が公募した。期間は10月2日から11月29日まで。毎週金曜日から月曜日までと祝日に、午前10時半から午後3時半まで2人が交代で町内を回る。
【写真説明】竜馬をイメージした衣装を試着するメンバー
書簡や絵図で幕末の福山紹介
企画展「幕末の福山藩」が、福山市丸之内の福山城博物館で開かれている。幕府の老中として日米和親条約を結び、開国に大きな役割を果たした7代藩主阿部正弘(1819~57年)を中心に紹介する。11月14日まで。
正弘が着た「紺糸菱綴五枚胴具足(こんいとひしつづりごまいどうぐそく)」、アメリカ使節との交渉について部下に指示した書簡など計約120点を展示している。幕府側として長州藩に敗れた第2次長州戦争、明治に入っては幕府を相手に戦った福山藩の歩みも絵図でたどる。
阿部家が藩主となった1710年から300年の記念展。月曜日休館。500円。同館=電話084(922)2117。
【写真説明】阿部正弘が着用したよろいなどに見入る来館者
鳥取
鳥取城下の変化一目
幕末地図と航空写真対比 やまびこ館
幕末の鳥取城下の精巧な測量図を、現代の航空写真と対比して見ることができる特別展「ここはご城下にござる」(読売新聞鳥取支局など後援)が、鳥取市上町の市歴史博物館「やまびこ館」で開かれている。10月31日まで。
測量図は、鳥取藩が1857~59年の安政年間に下級武士に作らせた「鳥取城下全図」(県立博物館所蔵)。2005年に市が撮影した航空写真を6メートル四方の樹脂シートに印刷して床いっぱいに広げ、分割してフィルムにコピーした城下全図と重ね合わせると、150年間のまちの変化が一目で分かる。
自分が住む地域にフィルムを重ねた来館者は、鳥取地震(1943年)や鳥取大火(52年)に遭いながらも幕末当時の道が残っていたり、堀が道路に姿を変えていたりすることに関心を示していた。
人口が増えた城下町で、藩がごみの回収や処理に悩んだり水道施設の整備に力を注いだりしたことを紹介する資料も展示。同市新町、小売業柴田太一さん(39)は「これまでにない視点で歴史を体感できる」と興味深そうに見入っていた。
10月9、30日の午後1時から学芸員による解説、同17日午後2時から講座がある。祝日の翌日と月曜は休み。問い合わせは、やまびこ館(0857・23・2140)。
(2010年9月24日 読売新聞)
佐賀
佐賀15人の偉人伝
県教委と佐賀城本丸歴史館(佐賀市)が、幕末~明治期に活躍した佐賀の偉人たちを、1人1冊ずつのシリーズで出版する事業に今年度から取り組んでいる。毎年度3冊出版し、5年間で15冊、計15人の偉人たちをとり上げる予定。郷土の偉人たちの業績を知ってもらい、地域の観光や文化振興に役立ててもらうのが狙いだ。(吉村治彦)
出版が決まっているのは、佐賀藩主の鍋島直正、北海道開拓に貢献した島義勇、日本赤十字社を創設した佐野常民、外務卿などを務めた副島種臣、教育制度を整備した大木喬任、司法制度の基礎を作った江藤新平、早稲田大学を創立した大隈重信の「佐賀の七賢人」と、画家として第1回の文化勲章を受けた岡田三郎助の8人。
郷土史家や学者らでつくる編集委員会が7月に開かれ、今年度は11月に鍋島直正、1月に大隈重信、3月に岡田三郎助を出版することが決まった。初回に鍋島直正を選んだのは、佐賀藩の近代化を主導し、多くの人材を育てた功績のためで、元佐賀大教授の杉谷昭・佐賀城本丸歴史館長が執筆する。同館によると、出版が決まった8人以外では、種痘普及を進めた伊東玄朴や東京駅の設計を担当した辰野金吾も有力という。
同館は今年度、来館者や県高齢者大学の受講生ら計約560人に、代表的な偉人30人の氏名と簡単な業績を記したアンケート用紙を利用し、興味のある偉人などを尋ねる調査を実施。大隈や江藤のほか、佐賀の砲術のリーダーだった平山醇左衛門や、知的障害児の教育に尽力した石井亮一は認知度が低いにもかかわらず、関心度は高かったという。編集委員会は今後、アンケートの結果を参考にしつつ、地域性も考えて残りの偉人を選定する方針。
本はA5判の112ページで、1冊千円の予定。全国の主要書店で販売する。また、紙の本だけではなく、電子書籍も発行し、インターネット上の電子書店で販売することも検討している。
出版事業を担当している本丸歴史館の古川英文副館長は「できるだけ読みやすいものにしたいが、最新の研究成果も盛り込みたい。日本の近代化に尽力した偉人に関心をもってもらい、地域の振興に利用してもらいたい」と話している。
長崎
これが本物 実録・坂本龍馬展・6 異国船図
妖怪に例えられた黒船
19世紀半ば、東アジア市場での自由貿易拡大を図る欧米列強の使節が長崎に来航するようになり、これを拒絶する徳川幕府との間で駆け引きが続いた。江戸から遠く離れた長崎での交渉は日数がかかるため、交渉はいつも不調に終わった。
嘉永6(1853)年、アメリカ東インド艦隊司令長官ペリーは、軍艦4隻を率いて江戸湾に近い浦賀へ寄航。長崎での交渉に限界を感じ、直接交渉を企図していた。このとき若き龍馬は江戸で剣術修行に励んでいた。周辺は緊迫し、龍馬も戦争のときには異国人の首を取ると意気込んでいた。この「黒船来航」が龍馬そして日本の運命を大きく変えることになる。
「異国船図」は、幕末の風刺画である。不気味に黒い煙をはきながら大砲を放ち、船首と船尾には鬼の顔が付いている。ペリー来航をきっかけに、幕府は欧米諸国と通商条約を結び貿易を開始する。しかし、この開国はインフレという経済混乱と、攘夷(じょうい)テロという治安悪化を招いた。社会不安をもたらした黒船来航は「異界からの妖怪」として庶民の心に映ったのである。
NHK大河ドラマ特別展「実録・坂本龍馬展」は10月2日~11月3日、長崎歴史文化博物館3階企画展示室で開催。問い合わせは同館(電095・818・8366)。
腰掛け龍馬の写真10月公開 大浦慶の縁者から県が購入
長崎歴史文化博物館(長崎市立山1丁目)は24日、幕末の長崎で活躍した女性商人大浦慶の縁者が所有していた坂本龍馬の写真など2枚を、10月に期間限定で公開すると発表した。
公開するのは、坂本龍馬と洋装の男性がそれぞれいすに腰掛けている写真。いずれも同時期に撮影されたとみられ、大浦家の親類に当たる長崎市の竹谷家が慶の遺品として保管していた。県が8月、同家から250万円で購入した。
龍馬の写真は縦7・7センチ、横4・8センチ。長崎歴文博は龍馬暗殺後の1868(慶応4)年ごろに焼き直されたものと推測している。
洋装の男性の写真は縦9・2センチ、横5・7センチ。同様の格好をした肖像写真が残っている海援隊士沢村惣之丞(そうのじょう)の可能性もあるとみて、今後調査を進める。
竹谷家所有の龍馬写真は昨年存在が明らかになり、龍馬と慶の交友関係を示唆する新資料として話題を呼んでいた。一般公開は初めてとなる。
写真は10月15~17日の3日間、「実録・坂本龍馬展」(10月2日から)で展示する。
鹿児島
西郷さんに一筆絵付け 鹿児島中央駅
鹿児島が生んだ幕末の偉人、西郷隆盛(1828-77)の命日に当たる24日、鹿児島市中央町のJR鹿児島中央駅の利用者に、西郷さんの似顔絵に一筆ずつ色を付けてもらうイベントがあった。
西郷隆盛の顕彰を続ける同市の市民グループ「城山林間研修会」(礒城泉会長)が十数年前から毎年続けている。これまでは、同市城山町の西郷銅像前や城山展望台で行っていたが、九州新幹線全線開通をにらみ、初めて中央駅で開いた。
今年の下絵は、西郷さんの顔と噴煙を上げる桜島のデザインに、全線開通で鹿児島と大阪を結ぶ「さくら」も新たに加わった。この日は、改札口前の通路の一角に下絵を飾り、買い物客や通勤・通学客にクレヨンを渡して、自由に色を付けてもらった。
礒会長は「新幹線開通でたくさんの観光客が鹿児島に来る。楽しみながら西郷さんの魅力を知ってもらいたい」と話した。完成した絵は、来年3月の全線開通に合わせ、中央駅に展示する予定という。
幕末ニュース、特別版というところで。
栃木
土方歳三に着目 「歴女呼び込め」
土方歳三 宇都宮にたどる
歴史愛好家ら22人ツアー
“土方歳三のヒミツ”に触れた 宇都宮でゆかりの場所めぐり
自分は土方ファンなんで、宇都宮城が「土方歳三が足に負傷した場所」として知られるより、「土方歳三が一日で陥落させた城」として知られて欲しいなぁ(すぐ取り返されたけど^_^;)。
栃木
土方歳三に着目 「歴女呼び込め」
新選組の土方歳三が宇都宮市内に残した足跡を巡る「うつのみやヒミツめぐりツアー」が23日、県内外から歴史好きの22人が参加して開かれた。宇都宮城址(じょうし)公園や簗瀬橋など、ゆかりの地をガイドつきで訪ねた。来月24日にも予定されている。(細見るい、樋口彩子)
ツアーを企画したのは、地域の活性化や魅力発信に取り組む「街づくり大学」と「宇都宮プライド創造ボランティア歴史歩き隊」。今年2月、集客のためのアイデアを練るなかで、「宇都宮でけがを負った新選組の土方歳三ならば、『歴女』を呼び込めるのではないか」と歴史ブームに着目。ツアーを実現させた。
土方歳三は1868(慶応4)年に起きた戊辰戦争で、旧幕府側の一軍を率いて宇都宮に入り、新政府軍の拠点だった宇都宮城を奪う攻防戦の先頭に立った。市内には複数の足跡が残るものの、現在では知る人が少なくなっているという。
このほど、そんな市内の11カ所のスポットを写真と説明つきで紹介したマップ「まち歩き地図『新選組土方歳三と幕末の宇都宮へタイムスリップ』」を「歴史歩き隊」が作成、3千部を作った。
この日、ガイドを務めたのも「歴史歩き隊」の荒瀬友栄(ともしげ)さん(31)。県内外から募った参加者は、新政府軍との激戦地となった宇都宮二荒山神社の大鳥居前に集合、宇都宮城址公園へ。その後、土方が指揮して戦った下河原門跡や簗瀬橋、土方が足を撃ち抜かれて重傷を負ったという松が峰門跡など約2キロのコースを2時間かけて巡った。
城址公園では、宇都宮新選組同好会のメンバーらが土方歳三と新選組隊士の衣装を着て登場。参加者は説明を聞いたあと記念撮影を楽しんだ。
参加者の一人、佐野市の高校生伊丹玲於奈さん(16)は「土方さんの登場には興奮した。歴史が好きという自分と同じ趣味の人が見つかるのもうれしい」。東京から来たという会社員高橋亜由さん(27)は「以前も宇都宮の街は歩いたが、説明を聞きながら歩けるのが楽しい」と笑顔で話した。
また、市内の中心部「オリオン通り」では、街づくり大学のメンバーが説明役に。紅茶専門店「Y’s tea」では、新選組の「誠」の旗をランチに飾るなど趣向を凝らした。
荒瀬さんは「歴史の初心者に向けたイベントとして、パワースポットなどの紹介も織り交ぜて親しみやすくした。県内外から人を呼んで、ギョーザだけにとどまらない宇都宮観光を楽しんでほしい」と話していた。
ツアー第2弾は、10月24日の「宇都宮城址まつり」でも予定されている。問い合わせは市都市ブランド戦略室(028・632・2129)。「まち歩き地図」は城址公園とオリオン通りの宮カフェで手に入る。
◆ ◆ ◆
【キーワード:土方歳三と宇都宮】 土方歳三(1835~1869)は新選組の副長として幕末を生きた。旧幕府側と明治新政府軍とが戦った戊辰戦争では、一軍を率いて宇都宮へ。新政府軍の拠点だった宇都宮城を奪おうと攻防戦の先頭に立った。城を取り戻そうとした新政府軍に敗れて負傷。その後、今市(現日光市)から会津に逃れ、函館の五稜郭で戦死した。享年35歳だった。
土方歳三 宇都宮にたどる
歴史愛好家ら22人ツアー
新選組の土方歳三とゆかりのある宇都宮市の歴史について知ってもらうイベント「うつのみやヒミツめぐりツアー」が23日、開かれた。歴史愛好家らが参加、幕末に思いをはせながら、「宇都宮城」などを見学した=写真=。
イベントは、市内の自営業者や会社員らでつくる市民団体「宇都宮街づくり大学」と、市の魅力をPRする「宇都宮プライド創造ボランティア」の歴史歩き隊のメンバーが企画。歴史歩き隊のメンバーが今月、歴女などの誘客向けに作成した観光マップを元に、新選組の副長、土方歳三に関係が深い市内各所を巡るという内容になっている。
雨にもかかわらず県内外から22人が参加。幕府軍を率い宇都宮に攻め上がった土方歳三が退却してきた兵士を切り捨てたとされる田川の「簗瀬橋」や、足を負傷したとされる宇都宮城の「松ヶ峯門」などを見学、宇都宮城では新選組にふんした市民との記念撮影も行われた。新選組が大好きで参加したという東京都板橋区、会社員横尾友香さん(27)は、「宇都宮観光は2度目だが、今回は、分かりやすく、詳しい説明があって良かった。しかも記念撮影も出来てすごく興奮している」と目を輝かせていた。
“土方歳三のヒミツ”に触れた 宇都宮でゆかりの場所めぐり
新撰組の土方歳三が宇都宮で戦っていたなんて-。宇都宮市への理解を深めてもらおうと、宇都宮街づくり大学(根本泰昌代表)は23日、市内にある土方ゆかりの場所をめぐる「うつのみやヒミツめぐりツアー」を開催した。
参加した歴史好きの市民ら22人は、ガイドの説明を受けながら、戊辰戦争で土方が攻撃した下河原門跡などを散策、幕末に思いをはせていた。宇都宮城址公園では土方ら新撰組に扮(ふん)した「宇都宮新撰組同好会」のメンバーらとの記念撮影も楽しんだ。宇都宮市竹林町、病院勤務、斎藤郁美さん(23)は「新撰組の小説を読んでも、宇都宮は出てこない。今まで知らなかったゆかりの地に行けて感激」と笑顔で話していた。
自分は土方ファンなんで、宇都宮城が「土方歳三が足に負傷した場所」として知られるより、「土方歳三が一日で陥落させた城」として知られて欲しいなぁ(すぐ取り返されたけど^_^;)。
ガタイがいいから、いかにも美丈夫です。竹中半兵衛って確か肺病で死ぬんですよね……山本耕史さんでは、とても肺病で死ぬように見えない(爆)。
高橋克典「男同士の大恋愛」 W主演の山本耕史に熱視線!
しかし、最大の突っ込みどころは↓でしょう。
相変わらず香取慎吾にぞっこんだと公言してます^_^;。
高橋克典「男同士の大恋愛」 W主演の山本耕史に熱視線!
しかし、最大の突っ込みどころは↓でしょう。
それぞれにとっての頼れる“軍師”は、山本が「時代劇で共演した香取慎吾君」とし、高橋は「『ちゃんとした仕事をしろ』と言ってくれる渡辺謙さんや、このドラマの監督」と話した。
相変わらず香取慎吾にぞっこんだと公言してます^_^;。
暑さ寒さも彼岸まで、お彼岸の中日になってようやく猛暑から解放されたようですね。秋が短くなるという予報で、春と秋が好きな自分はちょっと悲しいです。
宮城
土方歳三軸に描く戊辰戦争 「戦塵 北に果つ」
神奈川
大阪
高槻藩士が着用か 寄贈陣羽織を公開
兵庫
ブームに乗って 龍馬の和歌、風呂敷に 明石
山口
高杉晋作の書簡、きょうから公開 小郡文化資料館 山口
福岡
特別展:「村上仏山」の業績しのぶ 行橋市歴史資料館で生誕200年展 /福岡
佐賀
幕末と今・・・有田「今昔図」完成
コラム
【幕末から学ぶ現在(いま)】(80)東大教授・山内昌之 西郷隆盛(下)
文化芸能
西郷隆盛の側近「半次郎」映画公開 「鹿児島から世界へ発信」 榎木さん舞台あいさつ
宮城
土方歳三軸に描く戊辰戦争 「戦塵 北に果つ」
仙台・甲斐原さん作家デビュー
戊辰(ぼしん)戦争で最後まで新政府軍に抵抗した新撰組副長の土方歳三を軸に、東北、北海道などでの戦いを描いた小説「戦塵 北に果つ―土方歳三戊辰戦始末」(学研)が出版された。作者は仙台市在住の甲斐原康(かいばらこう)さん(63)で、今作品がデビュー作。「東北でも激戦が繰り広げられた。英雄の背後に名も無き人がいる。それぞれの思いをかけて戦った人が日本を作っていったことを知ってほしい」との思いを込めた。
大阪市出身の甲斐原さんは流通会社に勤務後、30年ほど前に仙台市の財団に転職し、仙台に居を構えた。市民センターや児童館の館長などを歴任し、今年3月、定年退職した。
仙台で暮らし始めた頃、散歩の途中で幕末の仙台藩士・玉蟲左太夫(たまむしさだゆう)の墓を訪れた。奥羽越列藩同盟の結成に尽力するなどし、責任を問われて切腹させられた玉蟲の生涯に触れ、東北での幕府軍と新政府軍の戦いを初めて身近に感じたという。
文献にもあたり、長年構想を練って執筆した同作品が昨年、歴史群像大賞(学研主催)の優秀賞に選ばれ、出版の運びとなった。
物語は土方を軸に、幕府軍に加わった元江戸の町火消し・佐吉を語り部に展開する。戦場で抜群の剣の冴(さ)えと統率力を示し、おじけづく味方を容赦なく切り捨てる冷徹さから戦鬼と呼ばれた土方。反面、平時は部下への優しい心配りを示す土方への、愛憎半ばする周囲の思いが描かれる。
仙台出身で、新撰組内の路線対立から切腹させられたとされる山南敬助も登場するほか、当時の国分町のにぎわいも再現される。
江戸を脱出後、幕府軍は負け続け、東北を北上する。新時代を前に揺らぐ人たちを前にしても、土方は自らが掲げた武士の道に殉じ、戦い続ける。
甲斐原さんは「土方は潔く、正義だが危うい。自分なりの誠を貫き、その誠に周りが巻き込まれていった」と分析している。
本は四六判256ページで1500円(税別)。
神奈川
「龍馬」講演会
「18歳当時の龍馬の考えについて−龍馬没後の土佐人の思想−」と題した公開講座が25日(土)市民会館で開催される。主催は相模原地域大学。14時から16時。講師は、「さがみ龍馬先生顕彰会」会長の溝渕誠之氏。幕末動乱期の龍馬の生き方を通じて、現代の私たちが学ぶべきものを探る。定員は先着150人。要資料代500円。希望者は本日23日中に、主催事務局(【電話】042・747・2913)へ。
大阪
高槻藩士が着用か 寄贈陣羽織を公開
高槻藩士が幕末に着用したとみられる陣羽織=写真=が高槻市教委に寄贈され、10月2日から同市城内町の市立しろあと歴史館で特別公開される。同館は「高槻藩に関する資料の多くは明治維新以降に散逸しており、藩士の陣羽織の実物を確認したのは初めて」と説明している。
同館によると、陣羽織「緋羅紗地八角(ひらしゃじはっかく)に桔梗紋(ききょうもん)」(身丈95・6センチ、肩幅54・6センチ)は当時、舶来の高級毛織物だった「羅紗(らしゃ)」の赤い生地を使い、背面に「八角に桔梗」の家紋がかたどられている。両肩に皮製の肩飾りがあり、西洋式軍服の影響で陣羽織に肩飾りをつけることが流行した幕末に作られたとみられる。
陣羽織を寄贈したのは熊本県菊陽町の飲食業石田雅陽(まさひ)さん(46)。石田家の墓は乾性(けんしょう)寺(高槻市天神町1丁目)にあり、陣羽織は藩士だった先祖のものと伝えられていた。幕末の高槻城下を描いた絵図に、石田姓の中堅武士の屋敷が三の丸にあることなどから、この人物の陣羽織だった可能性があるという。
同館の千田(ちだ)康治学芸員は「陣羽織は役職を持つ藩士が公用の外出時などに着用した。保存状態もよく、貴重な資料だ」と話している。
特別公開は同館の1階エントランスで10月2日から11月28日まで。無料。休館日は祝日を除く月曜と祝日の翌日。問い合わせは同館(072・673・3987)へ。
兵庫
ブームに乗って 龍馬の和歌、風呂敷に 明石
明石観光協会は、幕末の志士坂本龍馬が「明石にて」と題して詠んだ和歌をあしらった風呂敷を作成した。
「うき事を独明しの旅枕磯うつ波もあわれとぞ聞」。龍馬が神戸の海軍操練所で活動していた1863年ごろ、当時は明石藩の領内だった舞子砲台を訪れ、近くの旅館に泊まった際に詠んだとされる。「龍馬詠草」として京都国立博物館に所蔵されている。
風呂敷は紺色の71センチ四方で、坂本家の家紋である「組み合わせ角に桔梗紋」を添えている。同協会の榎本伸行専務理事は「遅ればせながら、龍馬ブームに参戦しました」。1800円。明石駅の観光案内所などで販売中。同協会TEL078・918・5080
(森本尚樹)
山口
高杉晋作の書簡、きょうから公開 小郡文化資料館 山口
幕末の長州藩で「正義派」と「俗論派」の攻防が激化してきた元治元(1864)年9月に高杉晋作が吉田松陰の兄、杉梅太郎に記した書簡が、山口市小郡文化資料館で22日から初公開される。
手紙が書かれたのは、長州藩が「禁門の変」を起こして幕府から征伐令が出され、さらに下関が四国艦隊の砲撃を受けた後のまさに激動の時期。書面では、高杉が藩から「石州口御軍政取計」という職を与えられようとしている状況などを、杉に報告している。杉と高杉は信頼関係が強く、たびたび手紙をやり取りしていたという。
こののち、急進的な正義派は衰退し、幕府に恭順を示す俗論派が主導権を掌握。高杉は、身の危険を感じて一時九州へ逃れる。
資料は、所有していた市内の収集家の遺族が平成6年、同資料館に寄贈。市教委の調査や整理を経て、同資料館で22日から10月31日まで開かれる企画展の中で初めて公開される。
福岡
特別展:「村上仏山」の業績しのぶ 行橋市歴史資料館で生誕200年展 /福岡
◇書、日記、手紙など108点
幕末から明治時代、上稗田村(現行橋市上稗田)に私塾「水哉(すいさい)園」を開き、優秀な門人を輩出した漢学者、村上仏山(ぶつざん)(1810~79年)の生誕200年記念特別展「村上仏山」(行橋市教委など主催)が、行橋市中央の市歴史資料館で開かれている。11月5日まで。火曜休館。
村上が残した書、日記、手紙、塾の教材、門下生の名簿など108点を展示。卒塾した門下生と飲んでは語った愛用の酒用ひょうたんもある。
村上は9歳の時、近くの神官から漢学を教わり26歳で水哉園を開いた。儒教を基に漢詩文を中心にした講義を展開し、明治の内相、末松謙澄(1855~1920年)や元号「昭和」を考案した宮内省編修官、吉田学軒(1866~1941年)ら約3000人が学んだ。
資料館の山中英彦館長は「日本の歴史を動かす人材を輩出した水哉園は、蔵春園(豊前市)などと並ぶ優れた私学校だった」と語る。
26日午後1時、同市大橋の市中央公民館で、村上のやしゃごで元高校教諭の村上良春さんらの記念講演(入場無料)▽10月24日は水哉園跡など村上ゆかりの地を巡る「ゆくはし探訪」(1000円、10月7日申し込み締め切り)もある。同館0930・25・3133。【降旗英峰】
〔京築版〕
佐賀
幕末と今・・・有田「今昔図」完成
古絵図手に住民調査 26日に歩こう会
江戸時代の有田と現在の有田町の違いが一目でわかる今昔図「新有田郷図」が完成した。同町のNPO法人「アリタ・ガイド・クラブ」(大橋康二理事長)と町歴史民俗資料館(尾崎葉子館長)が参加者を募り、約150年前の絵図を元に町を歩いて移り変わりをチェック、現在の地図に重ね合わせた。26日には新郷図を使った歩こう会を開く。
絵図は県立図書館(佐賀市)所蔵の「松浦郡有田郷図」。幕末の安政6年(1859年)、鍋島藩が作製した。現在の有田陶器市のメーン会場、内山地区を中心に描かれている。
調査には小学生から80歳代まで約60人が参加。地区を5ブロックに分けて「歩こう隊」を組織し、昨年11月から約5か月間、絵図を見ながら通りや住居、川の流れなどを確認した。
その結果、主要道路や川筋は幕末から大きく変わっておらず、絵図に残るほこらや鳥居なども正確に描かれていることがわかった。
新郷図は縦42センチ、横59センチ。現存するものは実線、未確認のものは点線で透明フィルムに印刷、現在の地図の上に置いて2枚重ねにしており、すでにない登り窯などの位置もわかる。
500部作製。巻物風にして、隊員が絵付けをした磁器の帯留めとヒモで結んでいる。1部1500円で同資料館などで販売。
「住民が地域を見つめ直す機会になったと思う。新郷図を観光にいかし、有田に元気を呼び込みたい」と同クラブ。歩こう会は参加無料。問い合わせは同クラブ(050・5539・5349)へ。
コラム
【幕末から学ぶ現在(いま)】(80)東大教授・山内昌之 西郷隆盛(下)
「正義」「正道」信じ生きた
菅直人首相を支える新たな顔ぶれはまことに味わい深い。留任した仙谷由人官房長官に加え、新任の岡田克也民主党幹事長と前原誠司外相は、“小沢一郎何するものぞ”という気概に溢(あふ)れた政治家たちである。この3人が時に揺れ動いた菅首相を叱咤(しった)激励しなければ、小沢陣営の気迫に菅陣営はたじろぎ苦杯を嘗(な)めていたかもしれなかった。
このトリオで、民主党代表選のさなかに尖閣諸島沖を侵犯した中国漁船による海上保安庁巡視船への不法行為を原理と原則に基づいて処理してもらいたい。もし鳩山由紀夫前首相と小沢一郎元幹事長のコンビであれば、法律に照らして正当な中国人船長の逮捕や起訴に踏み切るか否か、疑問も残ったのである。
◆主権や国威を忘れず
「友愛の海」で中国の勝手な跳梁(ちょうりょう)を許し抗議もしなかった鳩山氏や、多数の民主党議員を嬉々(きき)と胡錦濤国家主席との記念写真に応じさせた小沢氏と異なり、菅新政権の核の3人には、どの国が相手であろうと日本の主権と国民の安全を犯す行為に厳しく対処することを内外に闡明(せんめい)してもらいたいものだ。ここでも西郷隆盛の言葉を思い出さざるをえない。
「正道を踏み国を以(もっ)て斃(たお)るるの精神無くば、外国交際は全(まった)かる可(べ)からず。彼の強大に畏縮し、円滑を主として、曲げて彼の意に順従する時は、軽侮を招き、好親却(かえっ)て破れ、終に彼の制を受るに至らん」(岩波文庫『西郷南洲遺訓』一七)
西郷隆盛の遺(のこ)した文章のなかでも、この言葉ほど日本の外交環境を憂える者に勇気を与える表現はない。西郷の言葉は、国土交通相だった前原氏も高く評価した海上保安官たちの毅然(きぜん)とした対応や司法当局の自律性とさながら重なるかのようであり、日本人の耳朶(じだ)を打ってやまない。現代語に訳しても、西郷発言の格調の高さは変わらない。
正義のために正道を歩み、国家と一緒に倒れてもよい精神がなければ、外国との交際は満足にできない。その強大さに畏(かしこ)まって小さくなり、揉(も)めずに形だけすらすらと進めばよいと考えるあまり、主権や国威を忘れてみじめにも外国の意に従うならば、ただちに外国からあなどりを招く。その結果、かえって友好的な関係は終わりを告げ、最後には外国による命令を受けることになる。
外国に対し毅然と
小沢氏が好きな人物として西郷を挙げるのは心強い限りだが、西郷からは外国に対する毅然とした精神と姿勢も学んでほしいものだ。鳩山・小沢コンビにはアメリカにはことさら厳しく、中国には訳もなく甘いところがあった。ことに鳩山前首相は、その在任中に中国海軍が沖縄近辺海域を何度も示威航行し、日本の排他的経済水域で挑発行為を繰り返しても、抗議もせず不快感を表明するでもなかった。今度の事案でも自分の首相在任中には日中関係が良くなっていたと呑気(のんき)なことを語っている。
鳩山氏の姿勢は、「彼の強大に畏縮し、円滑を主として、曲げて彼の意に順従する」典型と言われても仕方がない。氏に「正道を踏み国を以て斃るるの精神」がないのを今更あげつらうつもりもない。しかし、アメリカから自立するポーズをどれほど取ろうとも、国益を毀損(きそん)し中国の「制を受るに至らん」危険を生むなら、何のための自主自立外交なのかという疑念が湧(わ)かないのだろうか。
対米外交で失敗した氏は対露外交で復権を狙っているという観測もある。しかし首相を退いた氏の最優先事項は、米軍普天間問題解決の下支えのために粘り強く働き、県民の素意と日米同盟の重要性を両立させる方策を探り名誉挽回(ばんかい)に努めることではないのか。氏の姿勢ではアメリカや中国に加えて、ロシアからも「軽侮」を招くことは必至であろう。
西郷は、「正義」や「正道」を人間の守るべき大事な価値と信じて生き抜いた。彼は、この2つを国際関係でも実現されるべき要素と確信していたからだ。この信念のためなら、自分の命も天にささげる覚悟をもっていたがために、その発言に気迫がみなぎっていたのである。ここにこそ現代の政治家と国民が西郷に学ぶべき点があるといえよう。(やまうち まさゆき)
文化芸能
西郷隆盛の側近「半次郎」映画公開 「鹿児島から世界へ発信」 榎木さん舞台あいさつ
幕末から明治初期にかけて「人斬(き)り半次郎」の異名で知られ、西郷隆盛を側近として支えた中村半次郎(桐野利秋)を描いた映画「半次郎」(五十嵐匠監督)の公開初日の18日、主演の俳優榎木孝明さん(54)=鹿児島県伊佐市出身=が、鹿児島市中央町の映画館「鹿児島ミッテ10」で舞台あいさつした。
2009年9月17日の撮影開始からちょうど1年。映画を企画した榎木さんは「やっとこの日が来ました。表現者の一人として鹿児島から何かを伝えたかった。この作品を鹿児島から世界へ発信できてうれしい」と笑顔であいさつ。会場を埋めた観衆350人から拍手がわき起こった。
ヒロイン役の白石美帆さんは「榎木さんの思いが現場のスタッフ、エキストラのみなさんに伝わり、いいものを作ろうと一丸になれました」と撮影を振り返った。
映画は、征韓論に敗れて隆盛とともに東京から郷里鹿児島に戻った半次郎が、隆盛を擁して決起、政府軍を相手に戦い抜き、壮絶な死を遂げる姿を描いている。18日から福岡、熊本、鹿児島で先行公開。来月9日から全国上映される。
暑さ寒さも彼岸までとはよく言われますが、彼岸入りの今日も30度(汗)。一週間で秋らしくなるかなー。
岩手
竜馬直筆の手紙、二戸で発見 下関の豪商あて資金相談か
茨城
幕末「水戸派」語る新選組まつり開幕 行方でシンポ
芹沢鴨たち水戸派、伊東甲子太郎・鈴木三樹三郎兄弟にスポットを当てたシンポジウムが大河ドラマ『新選組!』以降も続いているのは嬉しい限りです。
広島
福山藩主・阿部家ゆかりの品展示 福山城博物館で秋季特別展
香川
咸臨丸、太平洋横断から150年
高知
高知県文化財の屏風絵、貸出先が変色させ謝罪
長崎
表敬訪問:ジョン万次郎直系5代目・中濱さん、長崎市長を きょうから講演会 /長崎
岩手
竜馬直筆の手紙、二戸で発見 下関の豪商あて資金相談か
幕末の志士・坂本竜馬が長州・下関の豪商伊藤九三あてに送った手紙が、岩手県二戸市の民家で見つかり、高知県立坂本龍馬記念館(高知市)の三浦夏樹主任学芸員が18日、直筆と確認した。
三浦学芸員によると、手紙は縦24.6センチ、横33.2センチで、慶応3(1867)年3月13日に書かれたものとみられる。文末には独特の字体で書かれた「龍」の署名が確認できた。
竜馬直筆の手紙はこれまで、伊藤あてに書いた14通を含め141通確認されているが、東北で見つかるのは極めて珍しいという。
手紙は、長州藩の支藩だった長府藩の関係者と一緒に下関を訪問後、自分だけ下関を離れた後に執筆。ともに行動していたとみられる「野村老次子」という人物の宿泊先を知らせた上で、「ご用があればお尋ねください」と記している。
三浦学芸員は「現時点で詳細は分からないが、伊藤に資金面などで相談していた可能性がある」としている。伊藤は竜馬の支援者として知られ、資金面で活動を支えたり、自宅の一角を新婚だった竜馬に提供したりした。
手紙を所有しているのは二戸市内の女性で、夫方の祖父が譲り受けたという。女性が9月10日、盛岡市の石川啄木記念館に相談。龍馬記念館の三浦学芸員が鑑定を進めていた。
茨城
幕末「水戸派」語る新選組まつり開幕 行方でシンポ
「第6回なめがた新選組まつり」(行方市観光協会など主催)が18日、同市玉造甲の霞ケ浦ふれあいランドで始まった。初日は、シンポジウム「新選組水戸派談義~新選組と茨城の志士たちを語る~」が開かれた。19日は同市の法眼寺で芹沢鴨・平間重助追善供養、お梅顕彰碑除幕式、ふれあいランドでまちづくり市民劇団「玉造座」の公演などを行う。
新選組初代筆頭局長の芹沢鴨と、同副長助勤の平間重助は同市芹沢地区の出身。NHK大河ドラマ「新選組!」放送をきっかけに同市内で毎年、新選組に関するイベントが行われている。
シンポジウムで県立歴史館の永井博学芸課長は、「(幕末に大きな影響を与えた)水戸学は『尊皇攘夷(じょうい)をやるのは幕府』という考え方。決して幕府を否定することではない。新選組もある意味、その考え方」と指摘した。
かすみがうら市立郷土資料館の千葉隆司学芸員は、新選組に一時期所属した伊東甲子太郎・鈴木三樹三郎兄弟を生んだ志筑(かすみがうら市)の本堂家について説明した。
幕末史研究家のあさくらゆうさんは「新選組局長は、初代の芹沢鴨も最後の相馬主計も茨城出身。そのことをもっと発信すべき」と強調。「行方市玉造新選組まちづくりの会」の篠本圭司さんは「幕末、多くの人が遠くから集まって議論した。私たちも見習い、行政の垣根を越え、地域を盛り上げないといけない」などと話した。
芹沢鴨たち水戸派、伊東甲子太郎・鈴木三樹三郎兄弟にスポットを当てたシンポジウムが大河ドラマ『新選組!』以降も続いているのは嬉しい限りです。
広島
福山藩主・阿部家ゆかりの品展示 福山城博物館で秋季特別展
福山市丸之内の福山城博物館で18日、阿部家が1710年に福山藩主になって300年の節目を記念した秋季特別展「幕末101件の福山藩」が始まった。幕末から明治にかけての阿部家ゆかりの甲冑(かっちゅう)や古文書、絵図など約120点に入館者らが見入っている。11月14日まで。
阿部家は1869年まで10代にわたり福山藩主。特別展ではペリー来航(1853年)時、幕府の老中首座として日米和親条約を締結し、鎖国政策を転換した第7代阿部正弘ら歴代藩主の肖像画のほか、第9代正方が元服時に着た「紺糸威胴丸童具足(こんいとおどしどうまるわらべぐそく)」、第4代正倫が土をこねて作った茶わんなどが並ぶ。「箱館戦争出兵図」には現在の市章コウモリに似た指揮旗が描かれている。
10月3日午後2時から福寿会館(同市丸之内)で、萩博物館(山口県萩市)の道迫真吾主任研究員による「幕末101件における長州藩と福山藩」と題した記念講演会(無料)もある。
香川
咸臨丸、太平洋横断から150年
幕末の幕府の軍艦「咸臨丸」が太平洋横断に成功して今年で150年になるのを記念したイベント「咸臨丸と塩飽本島」が、丸亀市の本島で開かれている。勝海舟やジョン万次郎らと咸臨丸に乗り組んだ塩飽諸島の若者らを知ってもらおうと、地元住民らの実行委員会が計画した。
咸臨丸は1860年、日米修好通商条約の批准書交換のため太平洋を横断した。実行委によると、本島の石川政太郎、佐柳島の前田常三郎、広島の向井仁助ら塩飽諸島出身の水主(か・こ)35人が乗船したという。
塩飽勤番所では10月1日から、当時の本島を再現したジオラマ(縦1・5メートル、横2メートル)を展示。本島観光案内所では11月30日まで、咸臨丸の大型模型(縦2メートル、横3メートル)や絵画(縦1・8メートル、横3メートル)などが見られる。勤番所などでは講演会も。咸臨丸研究家木村秀雄さんの「咸臨丸の水主たち」(9月23日)、郷土史家入江幸一さんの「咸臨丸と塩飽」(10月24日)などが予定されている。
10月24日に本島港で水主の顕彰碑の除幕式がある。問い合わせは本島市民センター(0877・27・3222)へ。
高知
高知県文化財の屏風絵、貸出先が変色させ謝罪
「絵金」の名で知られる幕末の絵師・金蔵(1812~76)が描いた高知県指定有形文化財の屏風絵
びょうぶえ
5点を、貸出先の熊本市現代美術館が変色させていたと、同美術館を運営する熊本市美術文化振興財団が16日発表した。
殺虫作業で使った薬剤成分が原因とみられ、緑色の顔料が黒くなった。美術館側は、所蔵する高知県香南市の保存会など関係者に謝罪し、修復方法を検討するという。
発表によると、変色したのは「蘆屋道満大内鑑 葛の葉子別れ
あしやどうまんおおうちかがみくずはこわか
」「鎌倉三代記 三浦別れ」など、いずれも香南市赤岡町の「絵金蔵」が保管している絵金の芝居絵。着物、畳、コケなど、広範囲に黒くなっていた。
同財団は、美術館で開催する「小泉八雲 生誕160年記念・来日120年記念 へるんさんの秘めごと展」(6月26日~9月5日)に展示するため、絵金蔵から7月19日に借り受けた。専門業者に作品の殺菌、殺虫作業を委託し、27日に作品を開封したところ、一部が黒く変色しているのがみつかった。
東京文化財研究所が調査したところ、使用した薬剤成分の影響で、緑色の顔料に含まれる酸化銅と化学反応を起こし、黒変したことがわかった。
同財団は今月上旬、香南市を訪れて謝罪。作品は美術館で保管している。16日の記者会見で同美術館の桜井武館長は「大変申し訳ない。二度と同じことが起きないように注意したい」と陳謝した。
絵金は、赤を多用して血しぶきを描くなど、躍動的な芝居絵で知られる。5点の一つ「蝶花形名歌島台
ちょうはながためいかのしまだい
小坂部館
こさかべやかた
」は、軍略家の父を味方に付けるために姉妹が激しくつかみ合う浄瑠璃の場面を描いた作品。所蔵する赤岡町本町2区絵金屏風絵保存会の会長を務める米穀店経営島崎信将さん(65)は「先祖代々、引き継いできた絵は、町の文化そのもの。なんとか元通りに修復してほしい。このようなことがあっては、貸し出し方法も検討しなければならない」と残念がった。
香南市は「所蔵者にも申し訳ない気持ちでいっぱいだ。元の状態に戻るよう修復に最善を尽くしてほしい」とコメント。県教委文化財課は「たいへん残念。関係者と協力して、修復作業を支援していきたい」としている。
(2010年9月19日15時04分 読売新聞)
長崎
表敬訪問:ジョン万次郎直系5代目・中濱さん、長崎市長を きょうから講演会 /長崎
ジョン万次郎(中濱万次郎)直系5代目子孫の中濱京(なかはまきょう)さん(46)=名古屋市天白区=が18日、長崎市のグラバー園を訪れ、田上富久市長を表敬訪問した。
ジョン万次郎は1841(天保12)年、出漁して遭難し、米国捕鯨船に救助されてそのまま渡米。英語や航海術などを学び、帰国後、坂本龍馬ら幕末の志士たちに大きな影響を与えた。
中濱さんは19、20両日、県内で講演するために訪れ、「ジョン万次郎は龍馬と同じころ、長崎に滞在していた。万次郎と長崎との関係などを紹介したい」。田上市長は「『龍馬伝』放送をきっかけに、当時のつながりのある人たちが訪れてくれる」と喜んだ。
講演テーマは「ジョン万次郎のすべて」。19日は午前11時、長崎市立図書館多目的ホール(1000円)▽20日は午後2時、大村市のシーハットおおむらさくらホール(無料)で開かれる。【阿部義正】
やっと猛暑が収まり、いくらか過ごしやすくなって連休に突入なう。
薩長密約の龍馬の裏書き 公開
北海道
復元の箱館奉行所、開館50日目で入館10万人達成
箱館奉行所 オープン50日で10万人突破
東京
【TOKYOウオーク2010】2447人が日野市の歴史と自然満喫
長崎
くんち奉納の歴史といま 長崎、2カ所で展示
鹿児島
西南戦争の激戦地で『半次郎』プレミア上映。前売券5,000枚完売の大盛況
コラム
【龍馬を慕(おも)う】(24)京都・壬生 新選組が持つ魅力と魔力
【幕末から学ぶ現在(いま)】(79)東大教授・山内昌之 西郷隆盛(中)
薩長密約の龍馬の裏書き 公開
幕末の志士、坂本龍馬が薩長同盟の密約を保証した裏書きなど、宮内庁で保管されてきた貴重な図書や文書が18日から皇居で一般公開されます。
これは、皇室に伝わる図書や文書などを保管してきた宮内庁の書陵部が、45万点を超える所蔵品の中から、特に歴史的価値の高い古代から近代までの日記や絵巻、文書など、あわせて40点余りを選んで開くものです。このうち、幕末の志士、坂本龍馬自筆の書は、薩長同盟の密約の立会人となった龍馬が、長州藩の木戸孝允に密約を保証した裏書きで、最後に龍馬の名前の一部が記されています。また、今回初めて公開される、囲いを伴った家形の埴輪(はにわ)は、おととし大阪・堺市の百舌鳥陵墓(もずりょうぼ)参考地から出土したもので、古墳時代中期の5世紀に儀式などで使われていた建物を表したものとみられています。宮内庁で保管されてきた貴重な図書などがまとまった形で一般公開されるのは初めてで、皇居にある三の丸尚蔵館で、平日の月曜日と金曜日など一部の休館日を除いて来月17日まで開かれます。
北海道
復元の箱館奉行所、開館50日目で入館10万人達成
函館・五稜郭公園に復元された箱館奉行所の入館者が16日、10万人に達した。開館から50日目のスピード達成で、10万人目となった青森市の公務員小形圭史さん(27)に記念品が贈られた。
家族旅行で訪れた小形さんと妻洋子さん(29)、長男悠大ちゃん(2)に対し、奉行所の指定管理者である名美興業の阿相博志社長が記念品を手渡した。
小形さんは「良い思い出になりました。(幕末20件)当時のものに興味があり、奉行所に来たいと思っていました」と話していた。
7月29日の開館以来、入館者は予想を上回るペースで推移。初年度の目標14万7千人は10月中に達成できる見込みという。(渡辺創)
箱館奉行所 オープン50日で10万人突破
箱館奉行所(加納裕之館長)の入館者数が16日、7月29日のオープンからちょうど50日目で10万人を突破した。オープン効果や夏休み期間と重なったことなどが影響し、当初見込みよりも1週間早い達成となった。同奉行所は「和建築の趣ある雰囲気が来館者の心に響いているのでは」と好調な集客数の要因を分析する。
10万人目となったのは、青森市から来場した小形圭史さん(27)。妻の洋子さん(29)と長男の悠大ちゃん(2)と訪れた。小形さんは館内大広間の「壱之間」で、同奉行所の指定管理者「名美興業」の阿相博志社長から記念品の贈呈を受けた。小形さんは「記念すべき10万人目でびっくり。往時の姿を再現したと聞き、前から来てみたかった」と話していた。
同奉行所の来館者数は7月が6673人、8月は6万5843人だった。アンケートの調査結果によると、訪れた人の割合は道外が約37.5%、道内が約35%、市内居住者が約28%。
9月は修学旅行など団体利用が大きく伸びたほか、遠足などで市内の小学生が訪れる姿が目立つという。初年度の入館見込み数は14万7000人としており、同奉行所は「現在も多くの人が来館してくれている。見込み数も10月中には達成可能」と話す。
同奉行所は国の特別史跡「五稜郭跡」に、2006年から4年の工期を経て完成。解体前の古写真や発掘調査、古図面、文献資料を基に、当時の資材や工法をできる限り使用。総工費は約28億円。幕末当時、約2700平方メートルあった同奉行所の3分の1に当たる、約1000平方メートルが復元された。
東京
【TOKYOウオーク2010】2447人が日野市の歴史と自然満喫
東京都内の名所を巡る「TOKYOウオーク2010」(共催・産経新聞社、特別協賛・ライオン、協賛・アシックス)の第4回大会が11日、日野エリアで行われた。
正午前に30度を超える厳しい残暑となったが、2447人が約7~20キロの3コースを歩き、歴史を感じさせる日野市立新選組歴史博物館や高幡不動尊、多摩川、浅川の水辺の自然などを楽しんだ。
調布市の主婦、星野美矢子さん(45)は暑さ対策でペットボトルの水を凍らせて持参。小学3年の長男と約7キロを完歩した埼玉県所沢市の会社員、吉田康隆さん(39)は「厳しい暑さの中、親子で歩く貴重な体験を共有できた」と話した。
次回は11月20日に神宮外苑エリアで行われる。
長崎
くんち奉納の歴史といま 長崎、2カ所で展示
長崎くんち(10月7~9日)に合わせ、「くんち376年展」が長崎市立山1丁目の長崎歴史文化博物館で、「くんち資料展」が同市平野町の市歴史民俗資料館で開かれている。
376年展では、主に江戸時代のくんち奉納に使われていた衣装や傘鉾(かさぼこ)の垂れなどが並ぶ。幕末の茶輸出商人の大浦慶が油屋町に寄進した朱色に波が描かれた傘鉾の垂れ、上野彦馬撮影局が1891年に撮影したくんちの写真も展示されている。また、常設展示室のくんちコーナーには、今年の踊町の馬町の傘鉾が飾られている。10月18日まで。入場料一般500円、高校生以下250円。
資料展では、江戸時代から昭和にかけて奉納に使われた太鼓や笛、衣装など約100点が見られる。今年の踊町の築町が御座船を初めて奉納した1932年の資料では、構想段階での船の絵図、完成した船や衣装を色彩豊かに描いた絵巻、実際の写真が並ぶ。10月17日まで。入館無料。
鹿児島
西南戦争の激戦地で『半次郎』プレミア上映。前売券5,000枚完売の大盛況
幕末維新、西郷隆盛の右腕として活躍した薩摩の侍、中村半次郎(後の桐野利秋)の生涯を描いた映画『半次郎』のプレミア上映会が、9月11日・12日の両日、西南戦争の激戦地・鹿児島県伊佐市にて開催された。
会場となったのは伊佐市文化会館大ホール。計6回上映のために用意された前売券5,000枚は完売。上映に際しては舞台挨拶も行われ、伊佐市出身で主演の榎木孝明、ヒロインの白石美帆らが登壇。会場を大いに沸かせた。
本作の企画者でもある主演の榎木孝明は「企画から13年、ついに完成した『半次郎』の披露上映を故郷・伊佐市で迎えることができ、感無量」とコメント。「日本人の良さ、精神文化の美しさが描かれたこの作品を、伊佐市から発信し日本全国さらには世界へと拡げていきたい」と語った。
半次郎を心を通わせる京都の商家の娘役で出演した白石美帆からは「撮影中は、地元の方々から、多くのお力をいただきました」という挨拶に続き「榎木さんをはじめ関わった方々の熱い想いが隅々にまでこもった作品で、観れば何か湧き出てくるものがある、大きな作品に仕上がりました」と語った。
本作は、西南戦争の大規模な会戦シーンや山中でのリアルな戦闘描写なども見どころの戦争スペクタクル大河ロマン。撮影は全て鹿児島・熊本・宮崎など南九州で行われ、実際の戦跡も数多く登場する。時代劇初挑戦となるEXILEのAKIRAが魅せる圧巻の殺陣にも注目が集まっている。
『半次郎』は、9月18日(土)より九州先行公開後、10月9日(土)より、シネマート六本木ほか全国にて上映される。
コラム
【龍馬を慕(おも)う】(24)京都・壬生 新選組が持つ魅力と魔力
壬生(みぶ)寺に入るとすぐ右手に、ちいさな池に包まれるようにして壬生塚があった。正面には、いかめしい表情をした近藤勇の銅像があった。
その右手には、勇像のスタンプが押された絵馬がびっしりと掲げられていた。これがおもしろい。
「尊敬する近藤さん、土方さん、沖田さんのような素敵(すてき)な方とめぐり会えますように」
「新選組が大好きです。刀一本に命と志をかけて生きた姿を見習いたい」
「沖田総司と結婚したい!! もう別人でもいい!! 沖田の名字が欲しい!!」
たいていは若い女性の文字である。だが龍馬暗殺もくわだてた新選組という異様な結社の歴史は、疑心と内訌(ないこう)と裏切りと残酷さに満ちていた。残念ながら、「素敵」とは、とても思えない。
●わずか17人で結成
浪士組という、幕府公認の奇妙な武士団が江戸から、二条城にちかい壬生寺周辺の郷士や豪農宅にやってきたのは、文久3(1863)年2月である。現存する八木邸や前川邸など3カ所が屯所とされた。総勢250人にのぼる大集団である。
リーダーは庄内藩出身の郷士、清河(きよかわ)八郎である。清河は徹底した尊王攘夷思想の持ち主であった。攘夷を曖昧(あいまい)にしておきたい幕府とは折りあいがつかず、翌3月にはほとんどの浪士たちとともに江戸に帰ってしまった。
だが芹沢鴨(かも)や近藤勇、土方歳三(としぞう)、沖田総司といったおなじみの面々は京に残った。その数はわずか17人であった。これが新選組のはじまりである。
身分上は守護職会津藩主御預り。職務は京都にいる不穏な分子を斬(き)れ、であった。いわば会津藩の私設治安部隊である。
壬生寺を出て、すぐ斜め向かいの前川邸に入った。邸内の見取り図が展示されていた。
土方が拉致した尊攘派の志士に拷問をくわえ、池田屋事件の謀議を自白させた「東の蔵」もあった。逆さ吊(つ)りにしたうえ、足の甲に五寸釘(くぎ)を打ちつけたというから、とても「素敵な方」のふるまいとは思えない。
邸内奥の6・5畳間の「ここで山南敬助(やまなみ・けいすけ)切腹」の説明文に目が引かれた。新選組副長でもあった山南の切腹にはナゾが多い。
表向きは手狭になった屯所を、尊攘派に通じているとされた西本願寺に移す計画について、西本願寺を見張るようで見苦しいと反対したとされる。移したのは慶応元(1865)年3月、山南の切腹はその直前である。
千葉道場出身で、坂本龍馬とも顔なじみでもあった山南は、龍馬に親近感を抱いていた。もう幕府はダメだと思っていたフシもある。司馬遼太郎の『竜馬がゆく』でも、山南にこう言わせている。
「私は、この時勢に対する考え方というものは、坂本さんと同じなつもりだ」
こういう考え方が、近藤らに勘(かん)づかれのではないだろうか。
●隊員の無惨な最期
何十年ぶりかで、堀川七条にある興正寺(こうしょうじ)との間の北小路門から、西本願寺の境内に入った。白い築地塀をしばらく行くと、奢(しゃ)を極めた唐門(からもん)がある。
さらに行くと本願寺中央幼稚園の入り口があった。中に入ると、左手には龍谷(りゅうこく)大学の図書館、中央にはビャクシンの大樹、そして右手は駐輪場になっていた。
この駐輪場付近には、かつて木造平屋建ての、古ぼけた宗教記者室があった。筆者も宗教記者として、2年間ほど、手前の入り口から、なんども靴を脱いで入った。
すぐ右手の窓際には、洋風の長椅子(いす)があった。だいぶ年季が入っており、布地は薄い緑色に褪色(たいしょく)していた。理髪店の長椅子のように頭部のほうが反りあがっているので、寝ころびながら本を読むには便利だった。
いつもそこで本を読んでいると、顔見知りの長老の宗会議員がフラリと顔を見せ、「最近、モノを書いている福田クンは元気かね」と訊(き)いてきた。首を傾(かし)げると、「福田クンもいつも、そこで本を読んでいたナ」となつかしそうに言った。
「福田クン」とは福田定一、筆名・司馬遼太郎である。「福田クン」と同じ新聞社につとめ、「福田クン」と同じ宗教記者となり、「福田クン」と同じように長椅子で本ばかり読んでいたが、とうとう「福田クン」のようにはなれなかった。
境内をぐるりとまわって、御影堂や阿弥陀堂の大伽藍(がらん)のまえを通った。境内をほぼ一周したが、新選組の屯所跡を示す碑などはなかった。
新選組が西本願寺を出て、京都駅ちかくの不動堂村に移ったのは慶応3年6月である。ここには屯所跡の碑はあった。
土地の確保から移転費用、新屯所の建物などは、すべて西本願寺が負担した。西本願寺の寺侍が書きのこした記録には、
「疫病神ヲ送リ出シタル心地シテ門主及ビ一家ノ歓喜カギリナシ」
と書かれていた。「疫病神」の最期は無惨(むざん)であった。近藤勇や土方歳三以下、多くの隊員はたいてい横死した。(文 福嶋敏雄)
◇
≪メモ≫
壬生寺(京都市中京区)は律宗の寺で奈良時代、鑑真が開いたとされる。鎌倉時代に円覚によって再興され、仏教の教えを説く無言劇の壬生大念仏狂言(国重要無形民俗文化財)で知られる。阪急京都線「大宮」駅下車3分。西本願寺(下京区)は浄土真宗本願寺派の本山で、広大な境内に大伽藍が並び、世界遺産にも登録されている。京都駅から徒歩約15分。
◇
≪きょうの龍馬伝≫
■NHK総合 午後8時~ ほか
寺田屋の襲撃で死のふちをさまよった龍馬(福山雅治)は、薩摩藩邸でお龍(真木よう子)の看病を受けて何とか動けるようになる。不自由な体で木戸(谷原章介)が送ってきた密約の文書に裏書きし、西郷(高橋克実)の勧めで安全な薩摩で療養することになる。龍馬はお龍に妻として一緒に行こうと言い、お龍はうなずく。長崎に立ち寄った2人。お龍は亀山社中の面々に紹介されたものの、龍馬はすぐ忙しく今後の相談を社中と始め、次は1人でグラバー邸に出掛けてしまう。グラバー邸には海外へひそかに行こうとする高杉(伊勢谷友介)がいて、これから2人で一緒に面白いことをやろうと誓うが、実はこの時、高杉の体は病魔にむしばまれていた。
【幕末から学ぶ現在(いま)】(79)東大教授・山内昌之 西郷隆盛(中)
手段よりも人物こそが宝
民主党代表選は、円高株安や尖閣諸島海域への中国漁船の不法侵入など内外情勢多難な折に行われたが、菅直人首相の選出でひとまず決着した。ともかく、この選挙は菅首相と小沢一郎氏にとり、それぞれの思惑で奇貨(きか)居(お)くべしと、つかみとった「機会」への挑戦であった。
菅首相は当初から追求してきたクリーンな政治確立につながる好機と考え、小沢氏は自民党幹事長を経験して以来掲げた官僚統治構造の改変を実現する「天命」の到来と理解したのである。2人の建前は美麗すぎるにしても、両者ともに今回を遇機(機会にあう)逸すべからずと鎬(しのぎ)を削った点は事実であろう。
その意味では、政治家らしい緊迫した対決であり、天与の機会を避けずに争っただけに、今後の民主党は分裂含みの対立がますますあらわになるはずだ。
◆2種類の機会
ところで、「天命」といえば、「天」と、その理と、その機会を信じた西郷隆盛をすぐに思いだす。西郷は政治家として機会をとらえる重要性を強調していた。
「事の上にて、機会といふべきもの二つあり。僥倖(ぎょうこう)の機会あり、又(また)設け起す機会あり。大丈夫僥倖を頼むべからず、大事に臨(のぞん)では是非機会は引起さずんばあるべからず。英雄のなしたる事を見るべし、設け起したる機会は、跡より見る時は僥倖のやうに見ゆ、気を付くべき所なり」(岩波文庫『西郷南洲遺訓』所収「南洲答」六)
西郷の言いたかったのは、機会に2種類あるということである。求めずに偶然に幸運が訪れる機会。或(あ)る目的のために人為的に作り出す機会。立派な男子たる者は、偶然の幸運を頼んではならないのだ。大事なときには、何としても機会を作り出さなければならない。歴史上の英雄が果たした事績を見なくてはならない。人為的に作り出した機会は、後世から見ると偶然の幸運のようにも見えるが、そうでないことに注意を払うべきだと西郷はいうのだ。
◆制度の論議は第一ではない
今回の民主党代表選は、偶然の機会でなく、時勢に応じ理にかなった人びとが行動することで訪れた真の機会と符合したといえるのかもしれない。しかし西郷のような見方からすれば、代表選の勝敗そのものが目的であるはずもない。
政治家は、制度をいくら変えいじくっても政治を動かすことにはならない。官僚統治構造の打破を謳(うた)い政治主導を賛美するなら、政治家は官僚に勝る知恵と政策力を身につけなくてはならない。これはすでに西郷が強調していた点でもあった。
「何程制度方法を論ずる共、其人に非(あら)ざれば行はれ難し。人有て後方法の行はるるものなれば、人は第一の宝にして、己れ其人に成るの心懸(こころが)け肝要なり」(同『西郷南洲遺訓』所収「遺訓」二〇)
どれほど政治の制度や手法のことを論じようとも、それを動かす能力をもつ人がいなければ駄目である。まず人物、次が手段手法のはたらきという順番になるので、人物こそ第一番目の宝物であり、我々(われわれ)はみな人物になるよう心がけることが重要である、と。
こうした観点から今回の民主党代表選を眺めると、ほとんど別個の政党に属するかのように主張も見紛(みまが)う2人の間で戦われた印象が強い。代表選が終わっても、曖昧(あいまい)な妥協や馴(な)れ合いで形式だけの挙党一致をはかるのがよいのか、それとも将来の福祉社会の安定化を睨(にら)んだ消費税問題や外交安全保障政策を基準とした政界再編成がよいのか。今回の代表選の余燼(よじん)はまだくすぶるだろう。
◆互いに探り合う妙手
〈敵を苦しめ 味方を愛することこそ
人たるものの生き方である〉
14世紀のイスラームの統治論、イブン・アッティクタカーの『アルファフリー』(平凡社東洋文庫)に見える詩である。西郷は大義の前に友人の大久保利通(としみち)と訣別(けつべつ)し、高杉晋作は寡勢(かぜい)をものともせず決起し俗論派の椋梨藤太(むくなし・とうた)らを失脚に追いこんだ。
この2人を尊敬する小沢氏と菅首相が打つ次の一手は何であろう。或(ある)いは何事もなかったかのように、挙党一致を演出する可能性もなくはない。確かにイブン・アッティクタカーも「罪を許し、過失をよく許すのも王者に望まれる性質のひとつである」と述べたものだ。碁敵(ごがたき)でもあった2人に妙手はあるのだろうか。興味の尽きないところである。(やまうち まさゆき)
後世に「紅葉坂の佐平次」と語り継がれることになるかも知れない談春師匠の高座の余韻がまだ残っている白牡丹です。
そういう時には、「幕末」という趣味と「落語」という趣味が見事にクロスオーバーするんですね。
落語家・立川談春の、猿でもわかる「桜田門外の変」!これを観れば、映画も試験もばっちりだ!?
うほー、談春師匠の「桜田門外の変」解説、導入部は完璧にわかりましたっ! 続きが楽しみです。
そういう時には、「幕末」という趣味と「落語」という趣味が見事にクロスオーバーするんですね。
落語家・立川談春の、猿でもわかる「桜田門外の変」!これを観れば、映画も試験もばっちりだ!?
[シネマトゥデイ映画ニュース] 映画『桜田門外ノ変』の公開に先立ち、落語家・立川談春が「立川談春の幕末通信」と題して、映画で扱われる事件・桜田門外の変をわかりやすく説明した約3分間の動画が先行独占解禁された。この動画は全5回の予定で、本作のオフィシャルサイト上で公開される。
猿でもよくわかる! 立川談春の幕末通信
桜田門外の変が、歴史の教科書に載っている大事件とはいっても忘れている人も多く、細かいところまで知っている人は少ないはず。でも、映画の前にこれだけは知っておいた方が絶対にもっと楽しめる! そんなイロイロを、高座同様、軽妙な語り口で談春師匠が送るのが「立川談春の幕末通信」だ。
先行独占解禁された今回の動画は、第1回ということもあって事件の概要が中心。それでも、わかりやすい例えを用いて説明してくれる談春師匠の話術に3分があっという間に過ぎてしまうので、こんな歴史の先生がいたらいいのに……と思う中学生や高校生もいるかもしれない。「なぜ起こったのか?」「日本の歴史にどんな影響を与えたのか」という素朴な疑問にもちゃんと答えてくれるところもうれしい。
映画の予習としてはもちろん、事件の因果関係までしっかりと押さえているので、歴史の試験勉強としても効果は抜群? 歴史は暗記ばかりだから嫌いだと思っていた人も談春師匠の説明を聞けば、歴史的大事件の理由や影響を知ることが重要ということがわかるはず。そうすれば、映画で描かれる事件の渦中にいた人々のことをもっと知りたくなること間違いなしだ。
映画『桜田門外ノ変』は10月16日より全国公開
うほー、談春師匠の「桜田門外の変」解説、導入部は完璧にわかりましたっ! 続きが楽しみです。
今年の1月からライブで落語を聴き始めた、駆け出しの落語好きなんだけど、凄いものを立ち会ってしまったという確信はある。
今年で今までに見た高座の中でダントツによかったと思うだけでなく、たぶん、これから先も落語を見ていく限り、「自分が生で見たライブベスト5」の中にランクインされるんじゃないかと思う。
それが、まさかライブで初めて聴けた「居残り佐平次」by談春師だなんて……あぁ、幸せ。
縦長で撮影したiPHONEの写真を送ると、横に寝てしまうようで^_^;。次回から気をつけます。

ほとんど毎月、横浜にぎわい座で談春師を聴いている自分ですが、8月の『船徳』を聴いた時に一皮剥けたように感じてました。噺がもともと巧いことに加えて、笑わせることが巧くなった、という感じです。というか、笑わせることを談春師匠が楽しんでいる、と感じます。
先日のJ亭ゲストでの『長短』も、さらっとゲストで登場しながら、長さんと短七さんの会話の絶妙な間と表情や仕草でもって笑わせてもらいました。前座噺でもずっと爆笑させ続けられるんじゃないか、という、イケイケのオーラがいっぱい出てました。
そんなわけで、今日は素敵な高座になるんじゃないかという予感をもって、紅葉坂をえっちらおっちら上って音楽堂に行きました……うぅ、マッサージ機能つきクッションなんてものを見つけて買ってしまった自分、自分の体重に加えて錘を持ってこの坂を上るなんて、お馬鹿です(; ;)。
おや、めくりに「開口一番」でなく「立川談春」と出ている。前座さんがお茶を座布団に置いた。そして、出囃子はのっけから「鞍馬」(笛がないと、ちょっと間が抜けて聞こえますなぁ。牛若丸がいない五条の橋みたい^_^;)。
黒羽織に袴の談春師匠、登場。紅葉坂がどんなにきつかったかと観客をねぎらいつつ、若い頃に音楽堂に前座で出たことがあるという思い出話はそこそこに、同じ紅葉坂に住んでいた団鬼六さんのところに家元のお供で行った時の思い出話を楽しそうに(苦笑)。
悪人の顔も見続けるとだんだん慣れてくると、小沢さんの話。今日はどうも「欲」によって悪の道に入った人の話に入りたいらしいのですが……1500人ほども収容できそうな大きなホールの割に観客の空気がよかったのか、「県立ホール落語会の前回は柳屋三三さんで一人で三席喋った(しかも実質的には四席分だったとか)。あいつは俺と同じで落語家の友達がいないのか」と毒舌を叩いてみせるとか、「今の観客のうち2割は今のマクラから何の噺が始まるかいろいろ考えてるでしょ」とからかうなどして、いつもより長めに席を温めてました。
一、「牡丹灯籠 お礼はがし」談春
志の輔さんの『牡丹灯籠』聴いててよかった。「根津の清水谷に供蔵とおみねの夫婦が」と聴いただけで、『牡丹灯籠』の「お札はがし」だってぴんと来ました。
怪談噺なんだけど、幽霊となったお露さんのお付きの女中でこれまた幽霊であるお米さんの「伴蔵さん」という声色をおみねが真似て伴蔵をおびえさせたり、けっこうくすぐりが入る感じ。
それでいて、やはり怖いところは怖いのですよ。萩原新三郎様が恋しいあまりに幽霊となって毎夜通ってくる幽霊のお露とお米も怖いのだけど、人並みの生活がしたいばかりに幽霊に主人を裏切る代金として百両を要求しろと伴蔵をそそのかすおみねの方がもっと怖い(苦笑)。
おみねだって、食うや食わずの生活から脱するべく、夜になると横になってごろごろしている亭主とは違って夜遅くまで針仕事をするような働き者の女なんだよね。でも、まぁ、それだけ頑張ってもワーキングプアの暮らしから脱出できないという現実。だから、伴蔵のもとに現れたお米の幽霊が、「お露お嬢様が新三郎様に会いたいと泣いてらっしゃる。その邪魔になっているお札をはがしてほしい」と嘆願しているのを聴いて、どうせ幽霊には用意できまいという条件として百両を揃えて出せと言えとそそのかす。この時までは、あまり現実性はないと思っていただろう。
ところが、幽霊が百両を揃えて用意すると答えてからは、欲の権化に変身。新三郎が魔除けに身につけている仏が金むくと知れば、それを奪って百両と合わせればどこかで商いでも興せるだろうと血眼。
……幽霊に取り殺される新三郎様は哀れだけど、幽霊より怖いのは欲に取り憑かれた人間だよなぁと思う一席でした。
(中入り)
一、「居残り佐平次」談春
マクラなしでいきなり、うとうとする若い衆を呼び止める声。「何ですかって、ここで青物横丁はどこですかと道を聞く奴がいるかっ」って、これは、まさかまさかっ。
遣り手のおばさんに質問する暇も与えず、自分以外の四人(よったり)を盛大にもてなして欲しいという今夜の宴会の趣向を伝える場面。やたー、『居残り佐平次』に違いない。会話だけで入る手法が斬新な気がする。
若い衆(発音的には「わかいし」だな)はもちろん、海千山千の遣り手も煙に巻いて、連れの四人が金に糸目をつけない遊び上手のお大尽と勘違いさせて、四人が先に品川宿を出ても、若い衆をおだてたり脅したりして、なかなか「お直し」の勘定をさせない。担当の若い衆が睡眠不足でふらふらになった時にやっと、四人は飲んだ時に知り合った相手で住所も名前も知らない、自分はこれまでの代金を払う金がないから居残ると宣言して、布団部屋に居座ってしまう。
談春さんの魅力が炸裂、なんだろうな。快活にジョークを言っていたと思うと、相手の呼吸を乱しつつ急に恫喝する、佐平次のそのタイミングが絶妙なのよ。1500人ほどの観客が、佐平次と若い衆(または牛)との一言二言で大笑い。『居残り佐平次』ってこんなに爆笑する噺だったかなと思う。
そこが談春さんの凄いところで。
「ちょいと、いのどーん! 13番でお座敷ですよ〜!」「へ〜い!」の後には談志家元のイントネーションで「よいしょ!」が聴きたかったのだけど、ちょっと違った。でも、とにかく、若い衆はもちろん主人も翻弄するワルな佐平次の魅力満載だった。
たぶん、平成の「佐平次」のスタンダードというか、比較対象になると思う。そんなライブに出会えて、何という幸せ……。
今年で今までに見た高座の中でダントツによかったと思うだけでなく、たぶん、これから先も落語を見ていく限り、「自分が生で見たライブベスト5」の中にランクインされるんじゃないかと思う。
それが、まさかライブで初めて聴けた「居残り佐平次」by談春師だなんて……あぁ、幸せ。
縦長で撮影したiPHONEの写真を送ると、横に寝てしまうようで^_^;。次回から気をつけます。
ほとんど毎月、横浜にぎわい座で談春師を聴いている自分ですが、8月の『船徳』を聴いた時に一皮剥けたように感じてました。噺がもともと巧いことに加えて、笑わせることが巧くなった、という感じです。というか、笑わせることを談春師匠が楽しんでいる、と感じます。
先日のJ亭ゲストでの『長短』も、さらっとゲストで登場しながら、長さんと短七さんの会話の絶妙な間と表情や仕草でもって笑わせてもらいました。前座噺でもずっと爆笑させ続けられるんじゃないか、という、イケイケのオーラがいっぱい出てました。
そんなわけで、今日は素敵な高座になるんじゃないかという予感をもって、紅葉坂をえっちらおっちら上って音楽堂に行きました……うぅ、マッサージ機能つきクッションなんてものを見つけて買ってしまった自分、自分の体重に加えて錘を持ってこの坂を上るなんて、お馬鹿です(; ;)。
おや、めくりに「開口一番」でなく「立川談春」と出ている。前座さんがお茶を座布団に置いた。そして、出囃子はのっけから「鞍馬」(笛がないと、ちょっと間が抜けて聞こえますなぁ。牛若丸がいない五条の橋みたい^_^;)。
黒羽織に袴の談春師匠、登場。紅葉坂がどんなにきつかったかと観客をねぎらいつつ、若い頃に音楽堂に前座で出たことがあるという思い出話はそこそこに、同じ紅葉坂に住んでいた団鬼六さんのところに家元のお供で行った時の思い出話を楽しそうに(苦笑)。
悪人の顔も見続けるとだんだん慣れてくると、小沢さんの話。今日はどうも「欲」によって悪の道に入った人の話に入りたいらしいのですが……1500人ほども収容できそうな大きなホールの割に観客の空気がよかったのか、「県立ホール落語会の前回は柳屋三三さんで一人で三席喋った(しかも実質的には四席分だったとか)。あいつは俺と同じで落語家の友達がいないのか」と毒舌を叩いてみせるとか、「今の観客のうち2割は今のマクラから何の噺が始まるかいろいろ考えてるでしょ」とからかうなどして、いつもより長めに席を温めてました。
一、「牡丹灯籠 お礼はがし」談春
志の輔さんの『牡丹灯籠』聴いててよかった。「根津の清水谷に供蔵とおみねの夫婦が」と聴いただけで、『牡丹灯籠』の「お札はがし」だってぴんと来ました。
怪談噺なんだけど、幽霊となったお露さんのお付きの女中でこれまた幽霊であるお米さんの「伴蔵さん」という声色をおみねが真似て伴蔵をおびえさせたり、けっこうくすぐりが入る感じ。
それでいて、やはり怖いところは怖いのですよ。萩原新三郎様が恋しいあまりに幽霊となって毎夜通ってくる幽霊のお露とお米も怖いのだけど、人並みの生活がしたいばかりに幽霊に主人を裏切る代金として百両を要求しろと伴蔵をそそのかすおみねの方がもっと怖い(苦笑)。
おみねだって、食うや食わずの生活から脱するべく、夜になると横になってごろごろしている亭主とは違って夜遅くまで針仕事をするような働き者の女なんだよね。でも、まぁ、それだけ頑張ってもワーキングプアの暮らしから脱出できないという現実。だから、伴蔵のもとに現れたお米の幽霊が、「お露お嬢様が新三郎様に会いたいと泣いてらっしゃる。その邪魔になっているお札をはがしてほしい」と嘆願しているのを聴いて、どうせ幽霊には用意できまいという条件として百両を揃えて出せと言えとそそのかす。この時までは、あまり現実性はないと思っていただろう。
ところが、幽霊が百両を揃えて用意すると答えてからは、欲の権化に変身。新三郎が魔除けに身につけている仏が金むくと知れば、それを奪って百両と合わせればどこかで商いでも興せるだろうと血眼。
……幽霊に取り殺される新三郎様は哀れだけど、幽霊より怖いのは欲に取り憑かれた人間だよなぁと思う一席でした。
(中入り)
一、「居残り佐平次」談春
マクラなしでいきなり、うとうとする若い衆を呼び止める声。「何ですかって、ここで青物横丁はどこですかと道を聞く奴がいるかっ」って、これは、まさかまさかっ。
遣り手のおばさんに質問する暇も与えず、自分以外の四人(よったり)を盛大にもてなして欲しいという今夜の宴会の趣向を伝える場面。やたー、『居残り佐平次』に違いない。会話だけで入る手法が斬新な気がする。
若い衆(発音的には「わかいし」だな)はもちろん、海千山千の遣り手も煙に巻いて、連れの四人が金に糸目をつけない遊び上手のお大尽と勘違いさせて、四人が先に品川宿を出ても、若い衆をおだてたり脅したりして、なかなか「お直し」の勘定をさせない。担当の若い衆が睡眠不足でふらふらになった時にやっと、四人は飲んだ時に知り合った相手で住所も名前も知らない、自分はこれまでの代金を払う金がないから居残ると宣言して、布団部屋に居座ってしまう。
談春さんの魅力が炸裂、なんだろうな。快活にジョークを言っていたと思うと、相手の呼吸を乱しつつ急に恫喝する、佐平次のそのタイミングが絶妙なのよ。1500人ほどの観客が、佐平次と若い衆(または牛)との一言二言で大笑い。『居残り佐平次』ってこんなに爆笑する噺だったかなと思う。
そこが談春さんの凄いところで。
「ちょいと、いのどーん! 13番でお座敷ですよ〜!」「へ〜い!」の後には談志家元のイントネーションで「よいしょ!」が聴きたかったのだけど、ちょっと違った。でも、とにかく、若い衆はもちろん主人も翻弄するワルな佐平次の魅力満載だった。
たぶん、平成の「佐平次」のスタンダードというか、比較対象になると思う。そんなライブに出会えて、何という幸せ……。
眉とまぶたの間に吹き出物ができました(汗)。腫れにまぶたが引っ張られて、ちょっと嫌な感じです……ごくわずかな違和感も、薄い皮膚には敏感に伝わりますね。
北海道
はこだて外国人居留地研 函館、中国の交流史一枚に あすの見学会でも活用
福島
坂下で戊辰戦争受難者の慰霊祭
栃木
幕末の酒蔵で10月コンサート 小山の若駒酒造が創業150年記念に
茨城
二の丸御殿調査用排水路跡など出土 茨城
東京
【TOKYOウオーク2010】2447人が日野市の歴史と自然満喫
漫画や映画の近藤勇に迫る! 調布市郷土博物館「近藤勇展」!!
京都
【龍馬を慕(おも)う】(23)京都・三条小橋 「池田屋事件」の舞台はいま
大阪
【関西あれこれアニバーサリー】緒方洪庵生誕200年 医者志す若者の聖地
兵庫
幕末ビールで景気づけ 三田の幸民まつり
高知
龍馬使用と同型銃、展示は銃刀法違反? 高知県立記念館
佐賀
九州創発塾最終日 出島などで事例体験学習
長崎
聖福寺:龍馬ゆかりの唐寺 大雄宝殿修復へ募金活動 /長崎
龍馬パフェ」観光客に人気 長崎のカフェオリンピック
鹿児島
雑記帳:ランタンの龍馬とお龍、鹿児島へ「新婚旅行」/霧島で展示へ
コラム
【幕末から学ぶ現在(いま)】(78)小沢氏と西郷隆盛の違い 東大教授・山内昌之
北海道
はこだて外国人居留地研 函館、中国の交流史一枚に あすの見学会でも活用
【函館】函館の歴史研究グループ、はこだて外国人居留地研究会(岸甫一代表)は、函館と中国の交流史について最新の研究成果をまとめたリーフレット「はこだてと外国人居留地 中国編」を作成した。12日の函館中華会館創立100周年記念シンポジウムに合わせ、11日に開かれる中華会館(函館市大町)の特別見学会などで活用する。
函館では1865年(慶応元年)、長崎会所が独占していた幕府専売の俵物と称される海産物の売買が自由にできるようになった。長崎の独占が崩れたことで幕末20件から明治にかけ、函館には多くの中国人が流入した。リーフレットでは、こうした函館と中国の交流史を詳しく解説。中華会館など西部地区にあるゆかりの地を紹介する地図や、写真を添えた各種エピソードも掲載した。
両面カラーで3千部印刷。市地域交流まちづくりセンターで無料配布している。
11日は午後1時から、シンポジウムの一環として函館華僑総会の任道治理事の案内で中華会館特別見学会と船見町の中華山荘(中国人墓地)の説明会を行う。
続いて、はこだて外国人居留地研究会が、1890年代に現在の弥生町に存在した清国領事館の跡地、大町の外国人居留地跡を紹介する散策会を開く。中華会館の入館料600円と、中華山荘までの路線バス代200円がかかる。
参加希望者は当日中華会館横の駐車場に集まればよい。
シンポジウムは12日午前10時~午後4時、函館市中央図書館で開催。曽士才(そうしさい)・法政大教授の記念講演や川嶋稔夫・公立はこだて未来大教授らの研究報告が行われ、リーフレットが配布される。参加無料。参加希望者は当日会場へ。(小森美香)
福島
坂下で戊辰戦争受難者の慰霊祭
戊辰戦争で会津藩の娘子(じょうし)軍隊長を務めた中野竹子の墓前祭と、同戦争の受難者の慰霊祭は10日、会津坂下町の法界寺で行われた。
竹子は、なぎなたを手に新政府軍と戦い亡くなった。
同寺に墓が残っていることから、町内の女性でつくる町小竹会が主催し毎年、実施している。
会員や関係者ら約100人が参列した。
竹子の生きざまを歌った「護領の若竹」を全員で合唱。
詩吟を奉詠する中、会員が花や茶をささげた。
山口金子会長が式辞を述べ、同寺の井上文雄住職はじめ町内各寺の住職が読経し、竹子や戊辰戦争の殉難者を慰霊した。
坂下婦人会の斎藤京子会長らが追悼の言葉を述べた。
焼香の後、舞踊団体のひだまり会の二瓶淑さん、スポーツ民踊の後藤操さんが舞を奉納した。
栃木
幕末の酒蔵で10月コンサート 小山の若駒酒造が創業150年記念に
【小山】創業150年を迎えた小薬の若駒酒造は10月9日、酒蔵で記念コンサートを開く。出演するのは、ともに同酒蔵とゆかりがある「アンサンブル・キャナライズ」と「パパ・サラ」。柏瀬福一郎社長は「国登録文化財にもなっている酒蔵で音楽とこだわりの酒を楽しんでほしい」と話している。
若駒酒造は幕末30件の1860(万延元)年創業。現存する建物は当時建てられたとされ、このうち煙突のある主屋など3棟が2007年、国登録文化財になった。同社は、人々が集う酒蔵を目指して旧貯蔵庫を多目的ホール「醸楽蔵」と名付け、音楽会や地元芸術家の作品展などを開いている。
今回出演する「キャナライズ」は、女性4人のフルートとピアノのアンサンブル。06年から毎年、「醸楽蔵」でコンサートを続け、07年にはオリジナルCDと同社の日本酒をセット販売したこともある。
「パパ・サラ」は南米アンデス地方の音楽「フォルクローレ」を日本語で歌い演奏するグループ。昨年春と秋の2回、「醸楽蔵」でコンサートを開いた。
記念コンサートは午後2時と同6時開演の2回。開場はそれぞれ1時間前。休憩時には同社の日本酒、仕込み水の試飲もできる。柏瀬社長は「昨年はここでテレビドラマの撮影も行われた。登録文化財にもなっている酒蔵をぜひ多くの人に見てもらいたい」と話している。
定員は各100人程度。チケットは前売り2000円、当日2500円。小中高生は1500円。事前に申し込めばJR思川駅まで送迎するという。申し込み、問い合わせは同社電話0285・37・0429。
茨城
二の丸御殿調査用排水路跡など出土 茨城
県教委が6月から行っている水戸城跡の二の丸御殿部分の初調査で、発掘調査を受託する県教育財団は10日、調査状況を報道陣に公開した。
県立水戸第三高校(水戸市三の丸)の敷地内を発掘。整地された地面が8層あることが分かったほか、石組みの用排水路や井戸の跡などが出土した。
同財団によると、時代の違う遺構が同じ位置に配置されていることから、前代の工事を活用した効率的な工事が行われたと推定されるという。領主が替わるなどして何度も建て替えられた御殿部分の変遷が確認された。発掘部分は図面から、幕末期には食堂や家老の部屋として使われた部分という。
東京
【TOKYOウオーク2010】2447人が日野市の歴史と自然満喫
東京都内の名所を巡る「TOKYOウオーク2010」(共催・産経新聞社、特別協賛・ライオン、協賛・アシックス)の第4回大会が11日、日野エリアで行われた。
正午前に30度を超える厳しい残暑となったが、2447人が約7~20キロの3コースを歩き、歴史を感じさせる日野市立新選組歴史博物館や高幡不動尊、多摩川、浅川の水辺の自然などを楽しんだ。
調布市の主婦、星野美矢子さん(45)は暑さ対策でペットボトルの水を凍らせて持参。小学3年の長男と約7キロを完歩した埼玉県所沢市の会社員、吉田康隆さん(39)は「厳しい暑さの中、親子で歩く貴重な体験を共有できた」と話した。
次回は11月20日に神宮外苑エリアで行われる。
漫画や映画の近藤勇に迫る! 調布市郷土博物館「近藤勇展」!!
皆さん、こんにちは。ぬらりひょん打田です。
今回は東京都調布市の郷土博物館による『映画や漫画に登場する近藤勇展』を紹介します。
東京都調布市は、かの有名な新選組局長「近藤勇」の出身地です。市内には近藤の生家跡があります。そんな調布市の郷土博物館が今回、近藤勇をテーマに展示を行っています。実在の近藤勇のほか、漫画や映画の中で活躍した近藤や新選組の姿を紹介しているんです。様々に描かれる近藤勇の姿が見られますよ!!
まずは展示室で、大きな近藤の像が出迎えてくれます。
古いものでは紙芝居の『鞍馬天狗』が展示されていますが、ここでは新選組は敵役として登場します。そして昭和に入り新しい解釈がなされ、昭和30年代以降に新選組ブームは広がりを見せたようです。
映画に関しては『新撰組血風録』などの古い映画の写真をはじめ、比較的新しい『御法度』などのパンフレットもあります。
漫画は、調布市にお住まいの水木しげる先生が描いた近藤勇関係の作品をはじめ、手塚治虫先生、石ノ森章太郎先生などの作品も展示されています。一部はその場で読むこともできますよ。
この展示を見てわかることは「どういう価値観や思想を軸にして考えるかで、新選組の見え方が変わってくる」ということです。大衆文化に現れ始めたときの新選組は悪役として描かれることが多かったようですし、占領下の昭和20年代、チャンバラ映画は封建的精神を助長するということで禁止されていました。娯楽も、やはり時代を映す鏡なんですね。…と、実は展示の漫画の絵を見ているだけで楽しかったので、そんな難しいことは考えていなかったんですが(笑)。
いろいろと権利関係で苦労があると思いますが、こういうテーマで歴史上の人物を扱う催しは珍しいと思います。他の人物の展示も見てみたいですね。「聖徳太子」「織田信長」「真田幸村」「伊達政宗」…などなど。昨今のゲームに登場するのも含めると、いっそう楽しいと思います!! どこかやってくれませんかね…?
「映画・漫画に登場する近藤勇」
2010年9月23日まで
会場:調布市郷土博物館
開館時間:午前9時から午後4時 入館無料
休館日:月曜(祝日の場合は翌日)
住所:東京都調布市小島町3-26-2
アクセス:京王線 京王多摩川駅下車 徒歩4分
(「妖怪コスプレ記者」ぬらりひょん打田 山口敏太郎事務所)
参照 山口敏太郎公式ブログ「妖怪王」
http://blog.goo.ne.jp/youkaiou
京都
【龍馬を慕(おも)う】(23)京都・三条小橋 「池田屋事件」の舞台はいま
河原町通を北上し、三条通を右に折れた。高瀬川にかかる三条小橋の手前まできたとき、ちょっと目をむいた。維新史のなかでももっとも血なまぐさい池田屋事件の跡地に、「池田屋」という海鮮茶屋ができていたのである。店のまえの、
「池田屋騒動之址(あと)」
という石碑は、むかしのままである。だがかつて、その石碑のまえには、パチンコ店があったはずである。なんどか斬(き)り込み、ほとんど負けたから、覚えている。
店頭には、事件のあらましを書いた解説文と、死んだ志士たちの名前、年齢、出身地の一覧表が掲げられていた。解説文の最後のほうに、「この事件で倒幕が一年遅れたといわれる」とあったが、これはちょっとおおげさであろう。
三条小橋周辺は、江戸期から旅宿が立ちならび、池田屋も昭和の初期まであったという。その池田屋がパチンコ店などを経て、旅宿ではないが、海鮮茶屋となって復活したことになる。思わず斬り込む、ではなく、入店してみようかと思ったが、ひとりで酒を飲むのも味気ないので、遠慮した。
●3藩のあやうい均衡
新選組による池田屋襲撃事件が起きたのは、元治元(1864)年6月5日午後10時ごろである。双方の斬り合いは、3時間も続いたという。
このころの京の政治情勢をざっと俯瞰(ふかん)すると、前年の文久3年までは、薩摩、会津、長州の3藩があやうい均衡をたもっていた。
だが長州系の公卿(くぎょう)、姉小路公知(きんとも)の暗殺事件が起き、薩摩の田中新兵衛が犯人と疑われた。薩摩は一時、京の政界から脱落した。
長州が朝廷を牛耳るようになり、同年8月には、孝明天皇の大和行幸(ぎょうこう)をくわだてた。神武天皇陵などに参拝し、いっきに攘夷を進めようという計画だった。これに呼応し、土佐・檮原(ゆすはら)村出身の吉村寅太郎がリーダーとなり、先鋒(せんぽう)隊を堺から奈良・五条まで進め、代官所を襲った。天誅組(てんちゅうぐみ)の乱である。
少々、無謀な計画に対し、薩摩は会津と軍事同盟を結び、宮中クーデターを起こし、尊王攘夷派の公卿たちを追放した。「8月18日の政変」である。
長州藩は追放され、公卿たちとともに、長州にのがれた。いわゆる「七卿(しちきょう)落ち」である。
このあたりの薩摩の政治的リアリズムは、すさまじい。なにしろ、その2年後には長州と軍事同盟を結び、会津と敵対することになるからだ。司馬遼太郎の『竜馬がゆく』でも、
「薩摩藩の眼からみれば、会津藩も長州藩もこどものようなものであった」
と書かれている。
●「こども」じみた計画
たしかに追い込まれた志士たちは、「こども」のようにラディカルになった。御所に火を放ち、幕府側の要人を暗殺したうえで、天皇を長州に連れさる--という「こども」じみた計画を立てた。無謀を通りこして、すでにパラノイア症状(妄想障害)を起こしていた。
この情報が新選組にもれた。志士たちが木屋町三条にある四国屋か、この池田屋のどちらかで謀議をしていることを突きとめ、近藤勇や沖田総司ら10人が池田屋、土方歳三ひきいる24人が四国屋にむかった。
近藤は表口と裏口に6人を配置させ、沖田ら4人とともに池田屋内に入った。『竜馬がゆく』によれば、近藤は、
「亭主はおるか、御用改めであるぞ」
と土間に入って呼びかけた。すると、2階から話し声が聞こえた。抜刀した近藤らは、土足のまま一気に2階にかけあがった。これ以降の大チャンバラは、あまりにも有名である。二十数人いた志士のうち、座長格であった肥後の宮部鼎蔵(ていぞう)ら9人が死んだ。
神戸海軍操練所に所属していた土佐の望月亀弥太は重傷を負いながら逃げ出したが、追っ手に追いつかれ、自害した。蓆(むしろ)をかけられた望月の遺骸(いがい)を、騒動を知って駆けつけたお龍は目撃している。坂本龍馬を通じ、望月とは顔見知りだった。後年の聞き取りでは、
「私は頭の髪か手足の指か、何かひとつ形見に切っておきたいと思いましたが、番人がいっぱいおって取れないのです」
と語っている。髪はわかるが、手足の指を切る、という発想にはたまげる。
事件のとき、龍馬は勝海舟に会うために、江戸に向かっていた。神戸に帰ってきた、おそらく6月末には事件を知ったはずだが、どんな反応を示したのかは分からない。6月28日付の姉、乙女への手紙のなかに、こんな一節がある。
「天下に事をなすものハ ねぶともよく●は(腫)れずてハ、はり(針)へハうみ(膿)をつけもふさず候」
幕府という腫れ物を倒すには、膿がもうすこしたまってからだ、という意であろう。ようするに時期尚早論である。
新選組の名前は京中に響きわたり、志士たちを畏怖(いふ)させた。この異様なテロリスト集団について考えるためには、屯所(とんしょ)のあった壬生に向かわなければならない。(文 福嶋敏雄)
◇
≪メモ≫
鴨川にかかる三条大橋は東海道の出発点で、京都への玄関口でもあった。現在も木製の欄干が残り、京情緒を感じさせる景観となっている。「池田屋騒動之址」の碑へは、京阪電鉄「三条」駅か、京都市営地下鉄東西線「京都市役所前」駅を下り、徒歩約2分。長州藩邸の跡や土佐藩邸跡、坂本龍馬と中岡慎太郎が見廻組に襲われ、暗殺された近江屋跡などもごく近い。
◇
≪きょうの龍馬伝≫
■NHK総合 午後8時~ ほか
薩長同盟を成し遂げ、寺田屋に戻った龍馬(福山雅治)は、弥太郎(香川照之)に薩長が手を結んだこと、そして日本の仕組みが大きく変わり、幕府の時代が終わりを告げるであろうこと、その中で弥太郎が何をすべきか考えろと告げる。西郷(高橋克実)が密約を文書にしなかったことを危ぶむ木戸(谷原章介)が、文書化を主張。龍馬は証明の裏書きをするまで、寺田屋に残ることになる。もう京へ戻ることはないという龍馬にお龍(真木よう子)は複雑な思いを抱き、龍馬もお龍が気になる。京都守護職・松平容保(長谷川朝晴)は、伏見奉行に龍馬を捕らえるよう命じる。深夜、風呂に入っていたお龍が寺田屋を囲む捕り方に気付き、風呂を飛び出して龍馬と三吉慎蔵(筧利夫)に知らせる。
●=くの字点
大阪
【関西あれこれアニバーサリー】緒方洪庵生誕200年 医者志す若者の聖地
医学者、蘭学者で、江戸時代の大坂に「適塾」を開いた緒方洪庵の生誕から、今年で200年。翻訳をもとに日本に西洋医学を伝え、天然痘やコレラの予防にも尽力する一方、適塾では自由闊達(かったつ)な雰囲気のもと、慶応義塾創始者の福沢諭吉、明治維新で活躍した大村益次郎ら、数々の有能な人材を輩出した。適塾には、洪庵の遺徳をしのび、今もたくさんの人が訪れている。(吉田智香)
洪庵は文化7(1810)年、備中足守藩(現在の岡山市)で生まれた。足守藩士の父が大坂蔵屋敷留守居役となったのを機に、16歳で大坂に出てきた。
体が丈夫でなかったことから医学を志し、知識を深めた。天保9(1838)年に大坂で医院を開業。腕は確かで、2年後には医師を格付けした番付表に名前が載るようになり、後に大関に上り詰める。
適塾を開いたのも開業の年。その名は「荘子」に由来するという洪庵の号の一つ「適々斎」にちなんだ。評判が高まるにつれて塾生が増えて手狭になり、7年後に現在の場所(大阪市中央区北浜)に移転した。
適塾には、最新の学問を身に付けたい若者が続々と集まった。オランダ語の原書を訳す会読が中心で、習熟度に応じて級分けされ、塾生は辞書を頼りに独力で翻訳し、正確さを競った。
蘭和辞書が置いてあるヅーフ部屋では、塾生が予習のために辞書を奪い合ったという逸話も。諭吉は自伝で「勉強ということについてはこのうえにしようもないほどに勉強した」と振り返っている。
「洪庵は直訳ではなく、文章の要旨をくんで訳すことを重視した。塾生は原書を正確に訳すだけではなく、解釈をめぐって議論を交わした」と、適塾記念会の橋本孝成資料専門員(38)。「それが個性を伸ばすことにつながり、能力も高まった」と話す。
一方で、適塾は他の蘭学塾に比べて規則が緩く、飲酒もとがめられなかったという。血気盛んな若者たちのこと。時には“暴走”もあったようで、塾生が寝起きした大部屋の柱には無数の刀傷が残っている。
洪庵はこのほか、天然痘予防のため種痘所を設けたり、医師向けにコレラの治療法の本を発刊したりして流行を防いだ。大阪大学大学院文学研究科の村田路人教授(55)=日本近世史=は「優れた蘭学者、医学者だっただけでなく、予防という医者の社会的責務を信念を持って実践し、多くの人の命を救った」と話す。
適塾は今も一般公開されており、昨年は約2万8千人が来館。社会見学の小学生らに交じり、医学部志望の受験生も訪れる。備え付けのノートには「洪庵先生のような医者になりたい」と決意が記されていた。
兵庫
幕末ビールで景気づけ 三田の幸民まつり
三田藩出身の蘭学者川本幸民(1810~71年)の業績に親しむ催し「幸民まつり」のプレイベントが10日、三田駅前のペデストリアンデッキ(三田市駅前町)で開かれた。幸民が日本で初めてビールを造ったことにちなみ、屋台を開催。会社帰りのサラリーマンら数百人が、郷土の歴史に思いをはせながら舌鼓を打った。(本田純一)
今年は幸民生誕200年を記念してまつりを2日間に延長し、前夜祭としてこの日、プレイベントを企画した。
露店やいすなどを設け、市内の飲食店などが出店した。小西酒造(伊丹市)が幸民のビールを再現した「幕末のビール復刻版 幸民麦酒」の生ビールを販売。地場野菜や三田牛、三田ポークなどをふんだんに用いたコロッケやギョーザ、鉄板焼き、焼きそばなども並んだ。
午後5時の開店直後から、サラリーマンや近隣住民らが次々に立ち寄り、ビアガーデン気分で盛り上がった。西宮市の主婦(50)は「日本初のビールなんてロマンチック。幸民を機に、三田の魅力を知りました。もっとPRしてほしい」と満面の笑み。神戸市北区道場町の妻(64)と妻(60)は「幸民まつり本番が楽しみです」と話していた。
まつりは11、12日に市内各地で開かれる。
高知
龍馬使用と同型銃、展示は銃刀法違反? 高知県立記念館
幕末に坂本龍馬が京都・寺田屋事件で使ったとされる拳銃と同型の古い銃が今夏見つかり、高知県立坂本龍馬記念館が一時展示したのち、高知県警から銃刀法違反(所持禁止)の疑いがあると指摘を受けて撤去した。警察庁は10日、記念館職員を県の職員とするなどの方法で展示が可能になるよう、県と県警の間で調整が進んでいることを明らかにした。
問題となった拳銃は、スミス&ウエッソン社製の回転式6連発「モデル2アーミー」(32口径)。幕末から明治にかけて製造されたとみられる。警察庁によると、市販している銃弾を詰めれば発射が可能で、銃刀法の規制対象となる。
松山市の民家で今夏見つかり、8月に高知県に寄贈された後、8月22日から5日間展示された。記念館の職員が地方公共団体の職員であれば展示に法的な問題はなかったが、財団法人の職員だったことから、県警から法令違反の疑いがあると指摘を受け、撤去された。菅内閣で進めている「日本を元気にする規制改革100」の中にこの問題が取り上げられ、内閣府から警察庁に相談があったため、同庁と県警、県で検討していた。
佐賀
九州創発塾最終日 出島などで事例体験学習
「九州が生み出す維新~イノベーションで明日を照らす」をテーマに長崎市で開かれていた「九州創発塾2010長崎大会」(佐賀新聞社など7新聞社主催、九州経済連合会・中小企業基盤整備機構九州支部共催、旭化成後援)は11日、五つの事例体験学習で地域活性化のヒントを学び、2日間の日程を終えた。総合コーディネーターで脳科学者の茂木健一郎氏が「みなさんの行動が歴史を作ることを知ってほしい」と総括した。
シュガーロードをテーマにした事例体験は出島を見学、江戸時代に輸入された砂糖が長崎街道を通じて全国に広がったことを学んだ。2008年から佐賀、福岡の自治体や菓子組合と地域活性化に取り組んでいる長崎市の担当者は「武雄市とのシンポジウム実施や、福岡でのアンテナショップ開店など成果が出てきた」と話した。
茂木さんは「幕末の志士や市民の行動なしには、明治維新やフランス革命は起きなかった。みなさんの行動が大きな変革につながることに気づいてほしい」と話した。
佐賀市職員の緒方玲子さん(32)は「地域づくりのヒントや元気をいっぱいもらった。新しい価値を生み出す仕事をしたい」と話した。
長崎
聖福寺:龍馬ゆかりの唐寺 大雄宝殿修復へ募金活動 /長崎
1677年に創建された黄檗(おうばく)宗の唐寺で、幕末の志士・坂本龍馬にもゆかりの深い聖福(しょうふく)寺(長崎市玉園町)が老朽化したため、市民有志が募金活動を今月から始めた。特に本堂「大雄宝殿(だいゆうほうでん)」(県指定有形文化財)の傷みが激しく、2年をかけて1億円を集め、修復を目指す。【錦織祐一】
◇長崎市民有志、「協力会」を設立
聖福寺は、長崎出身の禅僧・鉄心道胖(1641~1710年)が建立。黄檗宗の大本山・万福寺(京都府宇治市)にならった建築様式が貴重とされ、大雄宝殿▽天王殿▽山門が県の有形文化財に指定されている。1867年に、坂本龍馬の海援隊が運航し、瀬戸内海で紀州藩船と衝突して沈んだ蒸気船「いろは丸」の賠償交渉が解決した場となったことでも知られる。
だが、日中貿易で来日した広東省出身者が檀家の中心だったため、長崎での貿易が衰えた戦後は檀家が減少。寺勢も衰え、伽藍(がらん)も老朽化した。現在は、屋根が草むして崩れ出し、軒先は崩落寸前の状態だ。
このため、郷土史家ら市民有志が今月1日に「大雄宝殿修復協力会」を設立。募金活動を決めた。世話人代表の一人、原田博二・長崎史談会長(64)は「国の文化財になり得る貴重な名刹(さつ)。抜本的に改修したい」と話している。問い合わせは同会事務局(090・4992・5037)。
〔長崎版〕
龍馬パフェ」観光客に人気 長崎のカフェオリンピック
長崎市浜町のカフェオリンピックで、パフェの上面に幕末の志士、坂本龍馬の顔を描いた「龍馬パフェ」(788円)が観光客らに人気。
フルーツやパンナコッタ、アイスなどを詰め込み、その上にソフトクリームを。最後に龍馬の顔の型を乗せ、ココアパウダーを振り掛けると出来上がり。
龍馬ブームが高まる中、「自分も地元を盛り上げたい」と中山陽三店長(58)が考案。「これを食べると、日本の歴史を動かした龍馬の勇気にあやかれるかもしれませんね」
鹿児島
雑記帳:ランタンの龍馬とお龍、鹿児島へ「新婚旅行」/霧島で展示へ
長崎市が中心市街地に設置する幕末の志士、坂本龍馬と妻お龍のランタン(中国ちょうちん、高さ約2~2・5メートル)=写真=が10日、鹿児島県に向け、“特別派遣”された。
2人のランタンは大河ドラマ「龍馬伝」放映と、今年2月の長崎ランタンフェスティバルに合わせ、台湾で製作。鹿児島での長崎物産展(15~27日)を機に派遣が決まった。
ランタンは15~20日、2人が新婚旅行をした鹿児島県霧島市で展示される。長崎市の担当者は「2人が新婚生活を送った長崎に、鹿児島からもぜひ」とPRを忘れなかった。【錦織祐一】
コラム
【幕末から学ぶ現在(いま)】(78)小沢氏と西郷隆盛の違い 東大教授・山内昌之
■敬天愛人の政治
民主党内には代表選を西南戦争に擬(なぞら)える雰囲気があるらしい。実際に9月1日夜、菅直人首相は支持者の会合で「明治維新に西郷隆盛の力は必要だったが、西南戦争があって本格的な明治政府ができた」(産経新聞9月2日朝刊)と語っている。代表選は明治10年の西南戦争に相当し、小沢一郎氏の政治生命を絶ついくさになるというわけだ。
それにしても、「菅軍」なる音を官軍にかけるのは上品なたとえとはいえない。しかし小沢氏の政敵たちは、維新つまり政権交代の功労者、小沢氏の行く末を西郷の運命に重ねたかったのだろう。
確かに小沢氏自身も、5日のテレビ番組で「情的に好きな」人物として西郷を挙げ、その理由として「いかにも日本人的だから」(読売新聞9月6日朝刊)と答えている。
すべてを始動させる原動力
西郷隆盛は、無教会派キリスト者の内村鑑三でさえ日本史でいちばん偉大な人物と讃(たた)えたほどの人物である。維新後の西郷は経済改革について無能だったかもしれず、内政についても木戸孝允(たかよし)や大久保利通(としみち)の方が精通していたに相違ない。また、国家の平和的安定をはかる点では、公家の三条実美(さねとみ)や岩倉具視(ともみ)でさえ西郷よりも有能だったかもしれない。
内村も語るように、新たな明治国家はこの人びとの全員がいなくては、実現できなかったともいえる。
しかし、西郷がいなければ、“明治革命”そのものが不可能だったであろう。木戸や三条を欠いたとしても、革命は上首尾ではないにせよ、たぶん実現を見ていたという内村の見方は正しい。
「必要だったのは、すべてを始動させる原動力であり、運動を作り出し、『天』の全能の法にもとづき運動の方向を定める精神でありました」(内村鑑三著『代表的日本人』)。この内村の指摘をまつまでもなく、一度動き始め進路さえ決まれば、あとは比較的簡単に処理できるのも政治運動のメカニズムなのである。その多くは、西郷より器量が劣る人間でも自動的にできる仕事だという指摘も基本的に正しい。
犠牲最小、効果大の革命
江戸城の無血開城をクライマックスとする明治維新は、犠牲者の少ない歴史上いちばん「安価な革命」であったが、これを効果的に実現したのが西郷にほかならない。実際に、西郷の偉大さは、犠牲者を最小にしながら効果の大きい革命を実現した点にあるといってもよい。
現代の政治家たちが西郷を尊敬し好きだと公言するのはまだよいだろう。それは格別に自分を美化し顕示するわけでもないからだ。また、自らの経綸(けいりん)を西郷に重ねてアナロジー(類推)にするほどの自信家がいるとも思われない。他方、たとえ政敵批判のためであっても、小沢氏を西郷に擬えるアナロジーにも慎重でなくてはならない。
何よりも西郷には「敬天愛人」のような聖者や哲人めいた政治思想があった。天はすべての人を同一に愛するがゆえに、われわれも自分を愛するように人を愛さなければならない。こうした敬天愛人の思想、あるいはそれに匹敵する政治理念をもつ哲学的政治家が果たして現在いるのだろうか。
命もいらず、名もいらず
西郷には、「命もいらず、名もいらず、官位も金もいらぬ人は、始末に困るもの也」(『西郷南洲遺訓』)という有名な言葉がある。こういう人物でないと、悩みや苦しみを共にしながら国家の大業を果たすことはできないというのだ。
ひょっとして、小沢氏の周辺に集(つど)う議員のなかには、苟安(こうあん)(目先の安楽をむさぼること)を謀らない人がいるのかもしれない。しかし、当の小沢氏は果たして「命もいらず、名もいらず、官位も金もいらぬ人」といえるのだろうか。異論のある有権者も多いに違いない。(やまうち まさゆき)
◇
【プロフィル】西郷隆盛
さいごう・たかもり 文政10(1828)年、薩摩(鹿児島県)生まれ。薩摩藩主、島津斉彬(なりあきら)に取り立てられる。斉彬の死後、島津久光と折り合わず流罪に。禁門の変の後、大久保利通らとともに討幕運動の中心となり、薩長連合や王政復古を成し遂げ、勝海舟とともに江戸城無血開城を実現させた。新政府で陸軍大将・参議を務めるが、征韓論政変で下野。明治10(1877)年、私学校生徒に擁され挙兵する(西南戦争)が、政府軍に敗北し、城山(鹿児島市)で自刃した。49歳だった。
すみません、写真が90度傾いてます。今夜は直す手間をかけられないので、談笑師匠にはちょっと横になっていただいてます。
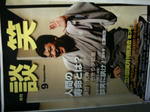
19時に下北沢で前座なしでスタートする高座に余裕をもって到着しておくには、17時ちょっと過ぎに勤め先を出なければなりません。自分は裁量労働ですが、残業必至のスタッフを残してオフィスを出るには少々気が引けます……(汗)。
でも、野球拳のお囃子が鳴る頃には、とりあえず日常のことを忘れて、作品に没頭してます。あらかじめネタはむ「死神」「ちきり伊勢屋」と知れていても、談笑師匠の落語はどこでどんな伏線があるかわかりませんので。
まずは「死神」。いくつかの作品を聞いてますが、医者になる前の主人公の職業とか名前を特定できるものは少ないです……白鳥さんのが医者だと特定されていて、死のうとしている主人公を死神が助けようとする理屈もちゃんと整理していますが、談笑版は幇間の一八が主人公。なぜ一八を死神が救おうとするのかは、この作品の大いなる伏線。
何というか、手塚治虫の『火の鳥』のいくつかの作品に通じるような、巡り巡るよ因果は巡る、というようなアレンジ。談笑さんがいうように、落語というよりは一人芝居の味わい。
さらに、中入り後の『ちきり伊勢屋』が、『死神』のエピソードワンになり、この独演会ではネタをちょっとばらまくだけだったけど『富久』がラストエピソードになるという、落語ファンにはとても楽しい複数作品のシリーズ構造。
『ちきり伊勢屋』、たぶん初視聴。圓生師匠の録音なら聴けるけど、並の落語家さんでは退屈な作品になるだろうなぁ。談笑さんはあちこちくすぐり入れてるから面白いし、『死神』とリンクする設定にしているから面白いわけで。
私服に着替えた談笑師匠と広瀬和生さんの対談が、また面白かった。広瀬さんは、談笑版『死神』にどういうバリエーションがあるかをよく知っているし、他の師匠たちのネタのバリエーションも知っている。その上で話の構造をこのように仕立てた談笑師匠の了見について聴き出す、というところが三倍美味しい。
次回は『居残り佐平次』『品川心中』なので、チケット争奪戦に参戦決定。談笑版の佐平次がとっても魅力的なのでライブで聴きたいのだ。
19時に下北沢で前座なしでスタートする高座に余裕をもって到着しておくには、17時ちょっと過ぎに勤め先を出なければなりません。自分は裁量労働ですが、残業必至のスタッフを残してオフィスを出るには少々気が引けます……(汗)。
でも、野球拳のお囃子が鳴る頃には、とりあえず日常のことを忘れて、作品に没頭してます。あらかじめネタはむ「死神」「ちきり伊勢屋」と知れていても、談笑師匠の落語はどこでどんな伏線があるかわかりませんので。
まずは「死神」。いくつかの作品を聞いてますが、医者になる前の主人公の職業とか名前を特定できるものは少ないです……白鳥さんのが医者だと特定されていて、死のうとしている主人公を死神が助けようとする理屈もちゃんと整理していますが、談笑版は幇間の一八が主人公。なぜ一八を死神が救おうとするのかは、この作品の大いなる伏線。
何というか、手塚治虫の『火の鳥』のいくつかの作品に通じるような、巡り巡るよ因果は巡る、というようなアレンジ。談笑さんがいうように、落語というよりは一人芝居の味わい。
さらに、中入り後の『ちきり伊勢屋』が、『死神』のエピソードワンになり、この独演会ではネタをちょっとばらまくだけだったけど『富久』がラストエピソードになるという、落語ファンにはとても楽しい複数作品のシリーズ構造。
『ちきり伊勢屋』、たぶん初視聴。圓生師匠の録音なら聴けるけど、並の落語家さんでは退屈な作品になるだろうなぁ。談笑さんはあちこちくすぐり入れてるから面白いし、『死神』とリンクする設定にしているから面白いわけで。
私服に着替えた談笑師匠と広瀬和生さんの対談が、また面白かった。広瀬さんは、談笑版『死神』にどういうバリエーションがあるかをよく知っているし、他の師匠たちのネタのバリエーションも知っている。その上で話の構造をこのように仕立てた談笑師匠の了見について聴き出す、というところが三倍美味しい。
次回は『居残り佐平次』『品川心中』なので、チケット争奪戦に参戦決定。談笑版の佐平次がとっても魅力的なのでライブで聴きたいのだ。
カレンダー
| 10 | 2025/11 | 12 |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
カテゴリー
最新記事
(10/19)
(09/13)
(07/16)
(03/25)
(03/24)
最新コメント
[11/26 จัดดอกไม้หน้าเมรุ]
[12/14 白牡丹(管理人)]
[12/14 ゆーじあむ]
[11/08 白牡丹(管理人)]
[11/07 れい]
[01/21 ゆーじあむ]
[11/15 白牡丹@管理人]
[11/15 ゆーじあむ]
[05/25 長谷川誠二郎]
[07/23 白牡丹@管理人]
最新TB
ブログ内検索
アーカイブ
最古記事
カウンター
プロフィール
HN:
白牡丹
性別:
非公開
自己紹介:
幕末、特に新選組や旧幕府関係者の歴史を追っかけています。連絡先はmariachi*dream.com(*印を@に置き換えてください)にて。
リンク
アクセス解析
Livedoor BlogRoll
本棚
