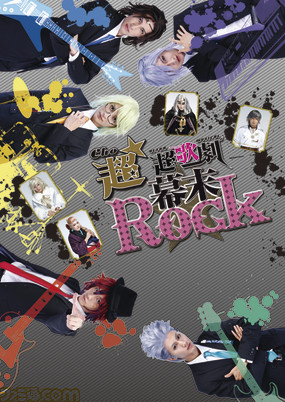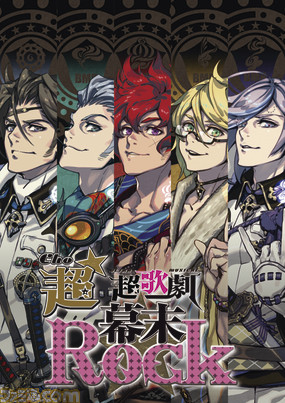東京
憧れの隊士役 45人が名乗り 日野「新選組まつり」きょうパレード
幕末に京都の治安維持に当たった「新選組」の副長、土方歳三(ひじかたとしぞう)ら主要な隊士の出身地である日野市で九日、恒例の「ひの新選組まつり」が始まった。十日のメーン行事「隊士パレード」の配役を決めるコンテストが高幡不動尊であり、土方役にはさいたま市の斉藤潤樹さん(27)、局長の近藤勇役には板橋区の佐々井隆文さん(38)がそれぞれ選ばれた。ブックレビュー
局長や副長、各隊を率いる隊長ら十人の隊士役を射止めようと、コンテストには四十五人が名乗りを上げた。応募者は居合の演武や隊士になりきった演技、フルート演奏など多様なパフォーマンスを披露してアピールした。
土方役に決まった斉藤さんは、表彰式で「パレードではいっぱい盛り上げるので、皆さん一緒に楽しみましょう」と呼び掛けた。一番隊組長の沖田総司役には、西東京市の色摩(しかま)亜美さん(27)が選ばれた。
この日はほかに、高幡参道通りで「高幡不動きものクイーンコンテスト」が開かれ、「土方歳三の恋人賞」のクイーンは日野市の手塚紗紀さん(23)に決定。手塚さんは隊士パレードに土方の恋人「お琴」役で加わるほか、高幡不動尊の行事などにクイーンとして一年間参加する。
新選組まつりは五月十一日の土方の命日に合わせて、毎年この時期に開催されている。十日は午前十時~午後四時、JR日野駅近くの日野駅前東交差点~川崎街道入り口の甲州街道五百メートル区間で車両通行止めになり、当時の衣装に身を包んだ隊士たちが練り歩く。 (林朋実)
土方歳三(上・下) [著]富樫倫太郎
[文]末國善己(文芸評論家) [掲載]2015年04月12日
■閉塞感打ち破るメッセージ
土方歳三を狂言回しにした〈土方歳三蝦夷血風録〉3部作を発表している著者が、土方を主人公にした大作を刊行した。エンターテインメント
ただ、本書は史料をなぞっただけの歴史小説ではない。時に大胆なフィクションを交え、魅力的な土方を描いているのだ。
太平の世が終わり、武士が再び武器を手に取ることを迫られた幕末に、土方、近藤勇を始めとする若者たちが、京で新選組を結成し、得意の剣を使って出世を目指す前半は、爽やかな青春小説としても楽しめるだろう。
だが新選組の名が高まると、近藤は同志を部下のように扱い、自分の大物ぶりを誇示しようと政治的なパフォーマンスに走るようになる。これに対し土方は、金にも地位にもこだわらず、ひたすら職務に邁進(まいしん)する。
時流に乗れば栄達ができた時代に、それに背を向け清廉な生きざまを貫いた土方の姿は、拝金主義に走った現代社会への批判になっているのである。
物語の後半、新選組は、薩長軍の新兵器の前に敗戦を重ね自信を失う。ところが土方は、最新の軍事教則本を熟読し、最後まで薩長軍に勝つ方法を模索する。負けても次があると考える土方の楽観性は、閉塞(へいそく)感を打ち破るには、再チャレンジが可能な社会を作る必要があるというメッセージに思えてならない。
◇
角川書店・各1620円
安西慎太郎、横浜流星ら注目の若手俳優が集結!舞台『武士白虎~もののふ白き虎~』上演決定!
幕末の揺れ動く時代を疾走した少年たちの激動の一生を描く舞台『武士白虎~もののふ白き虎~』が2015年9月17日(木)~9月27日(日)に東京・天王洲銀河劇場で上演されることがわかった。本作には、『テニスの王子様』2ndシーズンで人気を博した安西慎太郎やテレビ朝日系列『烈車戦隊トッキュウジャー』で人気急上昇の横浜流星ら、注目の若手俳優たちが白虎隊として出演する。
本作は、会津藩の武家の男子によって構成された少年兵部隊、白虎隊(びゃっこたい)の史実を基に、少年たちの儚い友情と人間ドラマを描いた書き下ろし作品。慶応元年(1864年)、若き少年達は藩校日新館に入学し、盟友たちと共に武士の心得を学んでいた。そんな中、彼らは“壬生狼(みぶろ)”と呼ばれた新撰組と出逢う。戦う事を知らぬ若者たちにとって、たたずむその男たちの背中は幼き目に強烈な印象を残していた。狼に憧れた若き虎たちは、命を懸けて会津を守ろうと固く心に誓うのだった。
白虎隊には、安西、横浜のほか、ミュージカル『テニスの王子様』2ndシーズンの手塚国光役で知られる和田琢磨、『海賊戦隊ゴーカイジャー』に出演していた小澤亮太、白又敦、河原田巧也ら若手注目株が並ぶ。さらに和田と同じく『テニスの王子様』2ndシーズンで脚光を浴びた青木玄徳、俳優だけでなくアーティストとしても注目されている荒木宏文が新撰組として出演する。また、淡く切ない恋をする娘役として元SUPER☆GIRLSの八坂沙織、会津藩の西郷頼母役として赤井英和が脇を固める。
白虎隊の飯沼貞吉を演じる安西は、「カンパニー一丸となり、胸に熱いもののふ魂を刻み込み、お客様の心に響く素敵な青春群像劇をお届けします。楽しみにしてて下さい!」と作品への思いを語っている。また、伊東悌次郎を演じる横浜は「殺陣は初挑戦ですが得意のアクションを活かして、悌次郎に負けないくらいカッコ良い殺陣を皆様に見せれたらと思います」と意気込んでいる。
舞台『武士白虎~もののふ白き虎~-幕末、「誠」に憧れ、白虎と呼ばれた若者達-』は2015年9月17日(木)~27日(日)に天王洲銀河劇場にて、10月1日(木)に名古屋・アートピアホールにて、10月3、4日(土・日)に大阪・梅田芸術劇場 シアター・ドラマシティにて上演。
新選組行進に熱視線 日野隊士などにふんし1000人
第十八回「ひの新選組まつり」最大のイベントである新選組隊士パレードが十日、日野市のJR日野駅東側の甲州街道周辺で行われ、約千人が隊士などにふんして行進した。会場では、新選組隊士の子孫らと記念撮影する若い女性の姿もみられ、新選組人気の高さをうかがわせた。 (榎本哲也)
パレードでは、九日の隊士コンテストで地元出身の副長・土方歳三(ひじかたとしぞう)役に選ばれた斉藤潤樹さん(27)=さいたま市=が白馬に乗って登場、歩道を埋め尽くした観客の声援に応えた。
斉藤さんは「声援がものすごく、土方人気は半端ないと思いました」と語った。
まつりは地元の実行委員会(三浦盛好委員長)主催で、土方の命日(五月十一日)に合わせて開催。新選組局長・近藤勇の五代目子孫、宮川清蔵さん(76)=茨城県牛久市、六番隊組長・井上源三郎の五代目子孫、井上雅雄さん(60)=日野市=らによる天然理心流勇武館演武も披露された。
井上さんは「市内の歴史館の来館者は75%が女性。幅広く新選組ファンが増えている」と話していた。
超★超歌劇『幕末Rock』8月に東京・大阪で再演決定!
●今度は東(とうきょう)で西(おおさか)でRockぜよ!
2014年に上演された“超歌劇(ウルトラミュージカル)『幕末Rock』”の再演が決定。“超★超歌劇(ちょう・ウルトラミュージカル)『幕末Rock』”として、2015年8月、東京・大阪にて上演される。
原作の『幕末Rock』は、2014年2月にマーベラスよりゲームがリリースされ、同年7月にテレビアニメ化も果たした人気コンテンツ。“幕末”という時代設定のもと、斬新で魅力的な志士(ロッカー)たちが音楽で新しい時代を創るという物語だ。
再演となる本作では、前作同様に吉谷光太郎氏が脚本・演出を手掛けるほか、良知真次(坂本龍馬役)、太田基裕(高杉晋作役)、矢田悠祐(桂小五郎役)ら初演のメインキャストがふたたび集結。新曲や新演出も追加されるという。8月8日(土)~9日(日)に大阪・梅田芸術劇場シアター・ドラマシティ、8月13日(木)~16日(日)に東京・Zeppブルーシアター六本木にて上演予定。
■公演概要
◆公演名:超★超歌劇(ちょう・ウルトラミュージカル)『幕末Rock』
◆原作:『幕末Rock』(マーベラス)
◆演出・脚本:吉谷光太郎
◆音楽制作:テレビ朝日ミュージック
◆公演期間・劇場:
大阪公演(梅田芸術劇場シアター・ドラマシティ):8月8日(土)~9日(日)
東京公演(Zeppブルーシアター六本木):8月13日(木)~16日(日)
◆キャスト:
坂本龍馬役:良知真次
高杉晋作役:太田基裕
桂小五郎役:矢田悠祐
土方歳三役:輝馬
沖田総司役:佐々木喜英
井伊直弼役:小谷嘉一
お登勢役:山岸拓生
近藤勇役:友常勇気
徳川慶喜 :Kimeru
ほか
◆主催:マーベラス/テレビ朝日ミュージック/NBCユニバーサルミュージック/NAS
◆協力:ギブソン
◆公演に関する問い合わせ
マーベラス ユーザーサポート
TEL:0120-57-7405 土日祝日 指定日除く11:00~17:00)
(C)2014 Marvelous Inc./幕末Rock製作委員会(C)2014 Marvelous Inc./超歌劇『幕末Rock』製作委員会
北海道
津軽海峡に眠る咸臨丸 地元住民「歴史知って」
幕末に勝海舟らを乗せて太平洋を横断したことで知られる「咸臨丸」は、明治初めに北海道木古内町沖の津軽海峡に沈んだ。今も海中に眠る船との縁に魅せられた町民らのグループが「多くの人に、町と咸臨丸の歴史を知ってほしい」と、活動を続けている。
咸臨丸は海軍創設を決めた江戸幕府が発注、1857年にオランダの造船所で完成した。長崎海軍伝習所の練習艦になった後、1860年には勝海舟や福沢諭吉らを乗せて太平洋を横断した。
戊辰戦争を経て北海道開拓使の輸送船になり、移住する旧仙台藩の家臣らを乗せていた1871年、木古内町の「サラキ岬」沖で座礁、沈没した。定説では、暴雨風が原因とされる。
町民らでつくる「咸臨丸とサラキ岬に夢みる会」は、咸臨丸との縁を観光や町づくりに生かそうと、2004年に結成、約400人の会員を抱える。サラキ岬に咸臨丸のモニュメントを設置、オランダにちなんで植えたチューリップが咲き誇る5月には、岬で祭りを開く。年に2回、咸臨丸の歴史を学ぶ研修会も開催している。
同会の事務局長で、住職の多田賢淳さん(63)は「太平洋を行き来するほどの活躍を見せたのに、最後は名もなき輸送船として沈んでいった。その歴史に翻弄された姿が魅力だ」と語る。
今年3月にオープンした木古内町郷土資料館には、咸臨丸のものとみられるいかりが展示されている。1984年にサラキ岬沖で引き揚げられ、19世紀の欧州製と判明したが、咸臨丸のいかりと断定はできなかった。
郷土資料館の学芸員の木元豊さん(50)は「北海道新幹線が走るようになれば、もっと多くの人が木古内を訪れる。咸臨丸のことを知り、町の観光を楽しんでもらいたい」と話している。〔共同〕
宮城
火縄銃演武:白石城開門記念 愛好者の鉄砲隊が披露 /宮城
白石城の開門(天守閣復元)20周年記念事業と白石市民春祭りの一環で、愛好者らで作る「片倉鉄砲隊」の火縄銃演武が3日、城の本丸広場であった。以下、有料記事です。
演武は、戊辰戦争中の1868(慶応4)年5月3日、薩摩・長州などの新政府に対抗し、東日本政府を樹立しようと、白石城で開かれた奥羽越列藩同盟会議にちなんだもの。白石城主だった片倉家の火縄銃鉄砲隊を模した。
大勢の観光客が... 続きを読む
福島
戊辰の役 鎮魂の舞 若松で奈与竹之碑碑前祭
戊辰戦争で亡くなった女性や子どもを慰霊する奈与竹(なよたけ)之碑碑前祭は1日、会津若松市北青木の善龍寺で行われた。
遺族と県内の支援者でつくる嫋竹(なよたけ)会の主催。約300人が参列した。吉田幸代会長が祭文を読み上げた。室井照平市長、戸川稔朗市議会議長が追悼の言葉を述べた。
献花、読経に続き国壮流会津日新吟詠会が詩吟を奉納した。葵高の舞踊部となぎなた部がそれぞれ女白虎隊と演武を披露した。
同寺には会津藩家老西郷頼母の自刃した一族21人の墓と妻千重子の辞世の句にちなむ「奈与竹之碑」がある。
( 2015/05/02 10:13 カテゴリー:主要 )
「女白虎隊」演武奉納 若松で「奈与竹之碑」碑前祭
戊辰戦争で命を落とした女性を顕彰し、慰霊する「奈与竹之碑(なよたけのひ)」碑前祭は1日、会津若松市北青木の善龍寺で開かれ、遺族や関係者が233人の霊を慰めた。東京
嫋竹(なよたけ)会の主催で、毎年5月1日に行っている。多くの市民が参列した。吉田幸代会長が「碑前祭を末永く続けることを誓い、御霊の安らかなることを祈る」と祭文を読み上げ、室井照平市長、戸川稔朗市議会議長が追悼の言葉を述べた。献花、読経に続いて、参列者が焼香した。
国壮流会津日新吟詠会の会員が詩吟を奉納したほか、葵高舞踊部の生徒6人が「女白虎隊」を演じ、同校なぎなた部の生徒たちが演武を披露、奉納した。大勢の市民が境内を囲み、生徒たちのりりしい姿を見守った。
(2015年5月2日 福島民友トピックス)
土方歳三資料館、新選組 土方歳三の愛刀「和泉守兼定」と近藤勇の愛刀「丹波守藤原照門」公開
公開日:2015年4月29日、5月2日~5日、9日~11日、17日
開館時間:12時~16時
入館料:500円
土方歳三資料館(東京都日野市)は、4月29日、5月2日~5日、9日~11日、17日に新選組 副長「土方歳三」が実際に使用した佩刀(はいとう)「和泉守兼定」と同局長「近藤勇」の佩刀「丹波守藤原照門」の刀身を公開している。2015年に刀身が公開されるのは、上記の期間のみとなる。入館料は500円、開館時間は12時~16時(4日、9日、10日は10時~16時)。
同資料館は、土方歳三の子孫である土方愛氏が運営しており、土方歳三の生まれ故郷でもある東京都日野市にある。資料館には、佩刀のほかに土方歳三が愛用した武具や遺品史料、書状など70点余りが展示されており、土方歳三に関する貴重な資料の数々を見ることができる。
なお、5月9日~10日には、日野市で「ひの新選組まつり」も開催される予定。土方歳三資料館ほか、各資料館での特別開館や「西洋砲術演武」などが行なわれる。
近藤勇の墓前に新選組隊士が集結!滝野川新選組まつり開催 /東京
第12回滝野川新選組まつりが5月3日、JR板橋駅東口駅前広場などで開かれた。江戸の幕末に活躍した新選組・近藤勇の墓所(滝野川7-8-10)が近くにあり、多くの申請組ファンが駆けつけて盛り上がった。
まつりのメインイベントのパレードでは、地元の新選組滝野川隊や新選組ガールズ、全国の新選組ファンなど総勢約120人が、新選組の衣装を身にまとい、約2時間かけて区内5つの商店街を回った。
パレードの途中で殺陣パフォーマンスも行われた。軽快な剣さばきに、観覧者の間から大きな歓声が上がっていた。
全国各地
23施設、世界遺産登録へ 各地で喜びの声
明治維新後、西洋の科学技術を熱心に取り入れた日本だが、その足跡が世界に認められた。4日夜、8つの県にある23か所の「産業革命遺産」が、世界遺産に登録される見通しになった。世界遺産登録が決まれば、国内19件目。登録の見通しが伝えられた自治体からは喜びの声が寄せられている。
4日夜、静岡県伊豆の国市役所。パソコンに向かっていた職員らが突然、一斉に立ち上がった。伊豆の国市にある韮山反射炉などが世界遺産登録に勧告されたとの一報がメールで届いたのだという。
伊豆の国市役所の職員「結果を読み上げます。推薦案件の名称を『明治日本の産業革命遺産』。製鉄・鉄鋼、造船、石炭産業と変更とした上で記載勧告が出された。23の構成機関すべてが本件遺産の構成要素として認められた」
緊張から解かれたのか、市の担当者からは笑みがこぼれた。
4日夜、世界遺産に登録される見通しとなった韮山反射炉などを含む「明治日本の産業革命遺産」。ユネスコ(=国連教育・科学・文化機関)の諮問機関・ICOMOSが「世界文化遺産への登録が適当」と勧告したのだ。
先月29日、韮山反射炉を取材。ゴールデンウイーク初日、多くの人でにぎわっていた。
観光客「昔の歴史的な良いものが残っているなと感じた」
韮山反射炉は幕末に大砲を造るのに活用され、世界で唯一、ほぼ完全な形で保存されているという反射炉。今回、世界遺産に登録される見通しとなったのは、幕末から明治時代にかけて日本の重工業の発展に貢献した、こうした一連の施設だ。
萩市歴史まちづくり部・植山幸三部長「大変うれしく思います。気を引き締めて、世界遺産登録に向けて頑張ってまいりたいと思う」
正式に登録されれば19件目となる日本の世界遺産。正式に登録されるかは来月の世界遺産委員会で決まる見通しだ。(05/05 00:56)
あと、新宿アルタで幕末rock土方歳三生誕祭やってるみたいです。誠仮面グッズもあるので、入手したい(汗)。
岩手
宮古港海戦、学び始動 児童生徒対象に歴史講座
今年の宮古港開港400周年に合わせて、宮古市の民間有志で組織する「宮古海戦組」の400周年事業実行委(佐々木芳江委員長)は18日、児童生徒を対象にした歴史講座を始めた。初回は1869(明治2)年の宮古港海戦をテーマにした紙芝居を披露し、新政府軍と旧幕府軍の死闘を伝えた。9月には講座参加者も加わった歴史劇やパレードも企画しており、節目の年を盛り上げる。
講座は同市山口1丁目の山口公民館で開かれ、約50人が参加。時代装束に身を包んだ海戦組の伊藤栄利子さん(29)が欧米列強に狙われた激動の幕末を読み解き、中高生による読み聞かせグループ「MYK48」が宮古港海戦の紙芝居を情感たっぷりに表現した。
日本初の近代海戦とされる宮古港海戦は、旧幕府軍の軍艦「回天」が新政府軍の軍艦「甲鉄」に接舷して乗っ取りを図る「アボルダージュ」戦法が採用された。新撰組(しんせんぐみ)副長の土方歳三も参戦したが、新兵器ガトリング砲を備えた新政府軍の圧勝に終わった。
海戦組のテーマソングも披露され、宮古小4年の女子児童は「衣装もかっこよく、海戦の歴史を分かりやすく教えてもらった」、津軽石中2年の女子生徒も「歴史に興味があり、新撰組が宮古に関わりのあることも理解できた」と関心を高めた。
【写真=宮古港海戦の紙芝居を披露する読み聞かせグループ「MYK48」のメンバー】
福島
小峰城跡修復4年ぶりに一般開放・白河
東日本大震災で石垣が崩落するなどした白河市の小峰城跡(国指定史跡)の修復工事が一部で完了し、市は19日、4年ぶりに城跡の一般開放を再開した。三重櫓(やぐら)までの見学ルートが通れるようになり、大勢の市民が市のシンボル復活を喜んだ。東京
JR白河駅北側にある小峰城跡を取り囲む石垣は総延長約2キロ。10カ所計160メートル(7000個)にわたり崩れたほか6カ所で石の隙間が広がるなどの被害を受けた。城郭の遺構を活用した公園として親しまれたが、本丸の敷地への立ち入りはできなくなった。
市は2011年12月に修復作業に着手し、本丸敷地内の三重櫓に至るルート付近3カ所を優先して実施した。昨年12月、最大の崩落箇所だった本丸南面(幅45メートル、高さ10メートル)の積み直しを終了。伝統工法を用いて崩れた石を積んだほか、新たに白河産の石も用いた。
1991年に復元された三重櫓も地震の被害を受け、壁などの修復が3月までに完了した。石垣の全面修復にはまだ時間を要するが、櫓までの散策ルートが復活したことで集客向上へ大きな弾みとなる。
同市の長田シゲ子さん(77)は「石垣が崩れた時は、言葉にならないぐらいしょんぼりしていた。立派に修復されて、街もにぎわってうれしい」と喜んだ。復興式典に出席した鈴木和夫市長は取材に「小峰城跡に再入場できるようになったことは、白河の復興のシンボルとなる」と語った。
小峰城は、初代白河藩主の丹羽長重が大改修をして完成。交通要衝の重要拠点として役割を担ったが、戊辰戦争で大部分を失った。
浅葱色のだんだら隊服を着て散策できる! ひの新選組まつり「日野宿隊服散策」開催日野宿本陣でプロによる撮影予定も。
5月9日に開催される「ひの新選組まつり」で、日野宿本陣近辺日野宿を「新選組隊士」になりきって散策できるようです。これは楽しそう!私はコスプレ趣味がないので遠慮しますが、帯刀しているのでご参加の方は周囲の方の安全には御配慮ください。
この企画では新撰組のイメージとして定着している浅葱(あさぎ)色のだんだら隊服を身にまとい、JR日野駅(東京都日野市)から八坂神社、本陣、井上源三郎資料館、佐藤彦五郎資料館近辺、日野宿のコースを散策するそうです。日野宿本陣での写真撮影会(有料)も予定されています。
しかし衣装は貸し出しではなく、上着物・下袴・浅葱色のだんだら隊服という参加規程に基づく和装を自分で用意し、持参する必要があります。着替え場所は確保されており、本陣・八坂神社境内では帯刀も検討中とのこと。
「日野宿隊服散策」は5月9日午前10時から午後4時まで実施。参加費用は800円(参加証の袖章・クローク代込)。事前申込み制で、応募締切は5月7日となっています。申し込み方法やその他注意事項は日野市観光協会公式ページを参照してください。
(高城歩)
静岡
幕末の史跡で歴史に触れる、レトロな「下田」で週末大人旅
史跡めぐりで黒船来航をしのぶ
伊豆半島南端の街、下田。夏は海水浴客で賑わい、冬はいち早く咲く水仙やアロエの花目当てに観光客が訪れます。しかし、意外と忘れられがちなのが、下田は史跡の街だということ。1854年の日米和親条約が締結された後、日本で函館と並んで初めて開港されたのがこの下田なのです。
【下田】幕末の史跡をたどる週末大人旅
(C)Flickr/bryan…
市街地の一角には、風情たっぷりのレトロな通りがあります。「ペリーロード」と呼ばれるこの道は、ペリーが日米和親条約を締結するために行進しました。現在では、この道沿いにカフェや土産物屋などが軒を連ねています。
【下田】幕末の史跡をたどる週末大人旅
(C)Flickr/Izu navi
そして、日米和親条約が締結された場所が、この了仙寺です。5月下旬には1000株のアメリカジャスミンが見ごろを迎え、境内は濃厚な甘い香りで包まれます。
ほかにも、米国総領事のハリスが滞在した玉泉寺や、日露和親条約が調印された長楽寺、ハリスに仕えて非業の死を遂げた唐人お吉の菩提寺である宝福寺など、史跡の見どころは満載。幕末ファンが訪れたくなるスポットが目白押しです。
毎年5月には黒船祭が開催され、パレードが行われるほか、時代衣装を着て街を散策することもできます。2015年は5月15~17日に開催されるので、イベントを狙って訪れてみるのもよいでしょう。
絶景そして海の幸
もちろん、下田は史跡以外にも観光スポットがたくさんあります。
【下田】幕末の史跡をたどる週末大人旅
(C)Flickr/hiro
爪木崎の灯台から望める雄大な大海原を前にすると、日常の疲れが吹き飛びそう。
【下田】幕末の史跡をたどる週末大人旅
(C)Flickr/bryan…
下田ロープウェイに乗り、寝姿山から見下ろす風景は、伊豆三景のひとつともいわる絶景です。頂上にある愛染堂は縁結びのパワースポットとしても知られています。
また、下田は海の幸がおいしいことでも有名です。名物のキンメダイは、煮つけで味わうのが定番ですが、ちょっと変わり種のメニューといえば、キンメダイのフライが入った「下田バーガー」です。
幕末の史跡で歴史に触れる、レトロな「下田」で週末大人旅
(C)Flickr/Yamaguchi Yoshiaki
くせのないキンメダイが、ソースとよく合います。ふわふわの食感で幸せな気分になりますよ!下田バーガーは、道の駅開国みなと内にある「Ra-maru」で味わうことができます。
史跡に絶景に食にと、さまざまな観光資源に恵まれた下田。5月の下田も魅力満載です。
[伊豆下田観光ガイド]
(今井明子)
福井
幕末偉人の活躍しのぶ 福井、ゆかりの料亭で歴史講座
幕末を中心とした福井の歴史を学ぶ講座が二十六日、福井市加茂河原一丁目の料亭「丹巌洞」で開かれた。福井藩主の松平春嶽や、橋本左内らが密談したと伝わる場所で、約三十人の参加者は幕末の偉人たちの活躍に思いをはせた。
歴史愛好者でつくるグループ「福井あすわ歴史道場」と福井商工会議所青年部が、ふくい春まつりの関連イベントとして共催。歴史道場の松下敬一会長が講師となり、幕末の動乱期に福井藩が果たした役割を解説した。
松下会長は、左内が春嶽の懐刀として、国の政治体制を変革するために活動していたことを紹介。福井などの有能な藩主を中心とした政治を目指し、議会政治の先駆となる構想を練っていたことを強調した。
昨年発見された坂本龍馬の手紙で、福井藩士で五箇条の御誓文の起草に関わった三岡八郎(のちの由利公正)を新政府の財政担当者にふさわしい、と評していたことも指摘。「龍馬は福井藩の国家構想などの影響を大きく受けていた。それを発信していかなくてはならない」と訴えた。
(桂知之)
福岡
『福岡県の幕末維新』 アクロス福岡文化誌 編纂委員会編 (海鳥社・1944円)
ペリー来航から明治維新にかけての激動期。時代の中心にいた薩摩藩や長州藩ではなく、現在の福岡県内にあった福岡藩、小倉藩、久留米藩、柳川藩の動向に目を向けた。福岡県の歴史や文化が地域性に富んでいる遠因が見えてくる。
尊皇攘夷(じょうい)か、公武合体か。佐幕か、倒幕か。各藩は揺れた。久留米藩で尊攘派志士の真木和泉が一時活躍した一方で、佐幕派の小倉藩は第2次長州戦争で長州藩に敗れた。戊辰戦争で財政が悪化した福岡藩は「贋札・贋金事件」に手を染め、事実上の廃藩に。柳川藩は明治維新後の士族の反乱を巧みに抑えた。ひとくくりにできない複雑な歴史が福岡県にはある。
各藩で活躍した人物を紹介するコラムも載せた。福岡藩における明治維新の語り部となった早川勇。新選組を離脱し、後に実業家となった久留米藩の篠原泰之進。あまり知られていない人物にも光を当てた。
アクロス福岡文化誌の第9巻。同誌編纂(へんさん)委員会長を務める丸山雍成・九州大学名誉教授(日本近世史)ら県内の研究者や学芸員計12人が執筆を担当した
=2015/04/26付 西日本新聞朝刊=
ブックレビュー
「ラ・ミッション」佐藤賢一著
幕末期に徳川幕府に軍事顧問として雇われたフランス軍人ブリュネ。新選組の土方歳三が会津藩にも頼らずに「てめえが抱える了見に、てめえの命をかけて殉じる。その潔さが士道ってもんだ」と言うのを聞いて感銘を受ける。なるほど、士道(エスプリ)か。やがてブリュネは軍事顧問団を率いて、エゾ共和国独立を目指す土方や榎本釜次郎(武揚)らとともに函館の五稜郭に立てこもった。そんな彼にフランスから帰国命令が出されるが、それに反して戦いを続けようとする。
映画「ラストサムライ」の主人公、オールグレン大佐のモデルとされるフランス軍人を描いた歴史小説。(文藝春秋 1850円+税)
北海道
軍艦「開陽丸」進水150年、江差で特別展
【江差】幕末期に江差沖で沈んだ旧幕府軍の軍艦、開陽丸が今年で進水から150年となるのを記念した特別展が21日、町内の開陽丸青少年センターの今季のオープンに合わせ、同センターロビーで始まった。同船の歴史を紹介している。
同船は1865年(慶応元年)にオランダ・ドルトレヒト市で進水し、1868年(明治元年)に沈没した。1974年から海中発掘調査が行われ、発見された砲弾など多数の遺物は、同センター近くに原寸大で復元された「開陽丸記念館」に展示されている。
特別展では、進水式の様子を撮影した写真の複製や同船の構造図など解説パネル60枚が中心の構成だが、分解された状態の米国製拳銃や軍靴など同記念館で常設公開していない実物資料も展示した。特別展は今季営業中開催。同センターは入場無料。記念館は大人500円、小中学・高校生250円。(山田一輝)
会津魂の結晶“緋の衣” 「マッサン」ゆかりの余市リンゴ
28日に最終回を迎える連続テレビ小説「マッサン」の舞台の一つ北海道・余市は旧会津藩士が明治期に入植し、国内初のリンゴの民間栽培に成功した地。藩士が苦難の末に実らせた品種「緋(ひ)の衣(ころも)」は現在、会津のリンゴ生産農家が栽培し、ジュースに加工している。生産農家は「会津人の苦労を知って」と思いを込める。
緋の衣は明治初期、産業振興のため米国から輸入され、開拓使が入植者に与えた品種。苦難にもあきらめずに栽培を続けた赤羽源八が初めて結実させた。品種名は藩主・松平容保が孝明天皇から賜った「緋の御衣」に由来。戊辰戦争で賊軍とされた藩士にとって”栄光の証し”といえる。ドラマでは亀山政春が興した会社が会津ゆかりの農家から買い取ってジュースにした。
緋の衣は現在、会津地方の生産農家6戸でつくる「会津平成りんご研究会」が栽培する。北海道で唯一原木が残る会津ゆかりの農園から譲り受けた枝約30本を接ぎ木して2000(平成12)年に栽培を開始。試行錯誤の末に結実させ、年々収量を増やしている。研究会の白井康友会長(56)=会津若松市、しらい農園園主=は「ドラマで緋の衣が全国に知られた」と喜び、「学校給食に使われることが目標。食を通じて子どもたちに伝えられれば」と思いを語る。
(2015年3月28日 福島民友トピックス)
福島
鶴ケ城の郷土博物館改修終える 1日、全面オープン
会津若松市・鶴ケ城の若松城天守閣郷土博物館の改修工事が終わり27日、内覧会が開かれた。新たに幕末の会津藩の動向や明治以降に活躍した会津の偉人など、今に伝わる会津武家文化を紹介する。大型観光企画「ふくしまデスティネーションキャンペーン(DC)」開幕に合わせ1日に全面オープンする。
鶴ケ城天守閣再建50周年記念事業で、これまで入場を規制していた三層(3階)と四層(4階)の改装が終わり細部の調整を進めている。三層では「幕末の動乱と会津」をテーマに、京都守護職就任や鶴ケ城籠城戦など会津藩のたどった幕末の歴史を当時の写真や資料などで解説する。四層には、新島八重や山本覚馬などの偉人20人のパネルを展示した。
東京
近代の「謎」を秘めた山
魚住昭の誌上デモ「わき道をゆく」第117回
1月につづいてまた上野のお山に行った。取り立てて言うほどの目的があったわけではない。西荻のわが家の窓から白い富士の嶺を眺めるうち、上野公園をほっつき歩いてみたくなったのである。
富士山と上野公園に何の関係があるかって? そんなことを訊かれても私にもよくわからない。しいて共通点を挙げるなら、どちらも畏敬の念をこめて“お山”と呼ばれることぐらいだろう。
まだ風が寒い。でも午後の日差しは暖かかった。売店で買ったお握りで腹ごしらえをした後、広さ53haの上野公園を1時間、2時間、3時間と夢中で歩き回った。
30分も歩けばへとへとになるはずなのになぜか平気だ。いつもの足腰の重さをまったく感じない。私はお山の混沌とした魅力に取り憑かれてしまったらしい。
その魅力とは何だと訊かれると、これまた答えにくい。突きつめていくと、近代日本の勝者と敗者の明暗ということになるのだが、それではあまりに漠としている。もう少し具体的にご説明したい。
上野公園にはモニュメントが数多ある。有名なものだけ挙げても西郷隆盛像、彰義隊墓碑、正岡子規記念球場、野口英世像、上野公園の生みの親と言われるオランダ人医師ボードワンの胸像・・・・・・。
それだけではない。不忍池の中の弁天島には石碑がぎっしり並んでいる。ふぐ供養碑、スッポン感謝之塔、暦塚、庖丁塚、鳥塚、魚塚、幕末の剣豪碑、めがね之碑など数え上げると切りがない。
歌川広重の不忍の池の浮世絵---〔PHOTO〕gettyimages
たぶん上野公園は日本一モニュメントの多い場所だ。それだけ人々の思い入れが強いということだろう。その理由は公園の歴史を繙くとわかる。中世の上野の山は忍の岡や忍の森と呼ばれ、多くの歌に詠われた名勝の地だった。
それが1603年の徳川幕府の成立後、江戸の聖地になる。江戸城の東北の鬼門を守り、天下太平を祈願する寛永寺(天台宗)が建立されたからだ。起工から74年後に落成した根本中堂は瑠璃殿と呼ばれる壮麗な大伽藍で、上野の山全域が寛永寺の境内になった。
全山に桜の木が植えられたため花見の名所となり、酒宴を張る人々でごった返した。不忍池畔には今のラブホテルにあたる出合茶屋が軒を連ね、町人だけでなく身分を隠した武士も通った。こうして上野界隈は聖と俗が混在するサンクチュアリと化した。
そのほとんどが幕末の戊辰戦争の最中に1日で灰燼に帰する。1868年、旧幕臣らの彰義隊が上野の山に立て籠もった。長州の大村益次郎が率いる官軍は、不忍池越しに砲弾をぶち込んで彰義隊を撃破、大伽藍を焼失させた。
上野の山が日本初の公園の一つに指定されるのはそれから5年後のことだ。以来、内国勧業博覧会などの国家的行事がたびたび催される一方、関東大震災では住民の避難場所、東京大空襲では焼死体の仮埋葬所になり、戦後は戦災者のバラックで埋まった。上野公園は戦火や震災とともに有為転変を重ねてきたのである。
page: 2
午後4時を過ぎ、園内の人影も少なくなりだしたころ、公園西側の東照宮境内に入ったら、意外なものが目に入った。鳩の彫像の中でちろちろと火が燃えている。
被爆者の一人が広島の焼け跡から故郷に持ち帰った「広島の火」と長崎の「原爆瓦」から採火した火を合わせたものだった。壁面には「核兵器をなくし永遠に平和を誓う広島・長崎の火」とあった。
東照宮を出てしばらく歩くと、初代林家三平の妻・海老名香葉子さんらが建てた「時忘れじの塔」にぶつかった。時計の下で遠くの空を見る母子3人の像が立っていた。東京大空襲で亡くなった海老名さんの家族がモデルらしい。
東京大空襲の主力となった戦略爆撃機B29---〔PHOTO〕gettyimages
「関東大震災(大正十二年)東京大空襲(昭和二十年) 東京にも、現在からは想像もできない悲しい歴史があります。今、緑美しい上野の山を行き交う人々に、そのような出来事を思い起こしてもらうとともに、平和な時代へと時をつなげる心の目印として、この時計台を寄贈しました」と記されていた。
上野は、戦争や震災で無念の死を遂げた人々の鎮魂の山だった。
東照宮からここに来る途中のパゴダ(仏塔)の丘にはかつて上野大仏が鎮座していたそうだ。関東大震災でその首が転げ落ち、胴体は戦中の金属類回収令で供出させられた。顔だけは寛永寺の僧侶が境内の檜にくくりつけて隠したので鋳つぶされずにすみ、今もパゴダの脇に安置されている。
このエピソードが語るのは官の統制においそれとは従わない寛永寺の性格だろう。上野の山には国家にまつろわぬ民や旧武士、僧侶らの精神が根付いている。それは、政府が消そうとしても消せなかった歴史の刻印にちがいない。
あまり知られていない話だが、後に靖国神社と呼ばれる東京招魂社は当初、上野の山に創建される案が有力だった。長州閥の木戸孝允が寛永寺の焼け跡を通りかかった際、この「土地を清浄して招魂場と為さんと欲す」(『木戸孝允日記』)との意向を示したからだ。
だが、大村益次郎が自ら指揮した彰義隊との戦の記憶が生々しい上野を「亡魂の地」と敬遠した。結局、幕府の歩兵調練場跡地だった九段坂上が選ばれ、1869(明治2)年6月、仮本殿が落成し、戊辰戦争の官軍戦没者約3600人が合祀された。
それから5年後、上野公園には彰義隊の墓碑が建てられた。以降、旧幕臣の「亡魂の地」であると同時に国家的行事の場でもあるという複雑な性格を帯びながら都市公園として整備されていく。
この日の散策の締めくくりは西郷サンである。彰義隊慰霊碑の前方に立つ高村光雲作の銅像は、身長3・7m、胸囲2・6m。実物(推定身長178㎝)の2倍も大きい。毛ずねの見える単衣に脇差し、愛犬ツンを従え、大きな目玉で虚空をにらんでいる。
西郷ほど民衆の信望を集めた政治家はいない。彼が西南戦争に敗れて自死した後も、人々は夜空に輝く火星を「西郷星」と呼び、彼が中国やインドやシベリアで生きているという噂を信じた。
伝説の英雄をいつまでも野に放っておくのは得策ではないと政府は判断したのだろう。1889(明治22)年の憲法発布にともなう明治天皇の特旨で西郷の賊名が解かれ、正三位が追贈された。
それを契機に薩摩閥を中心に銅像建設に向けた動きが始まり、9年後に完成した。当初案は軍服姿だったが、「逆徒」の経歴ゆえに撤回され、設置場所も皇居前から上野公園に変更された。上野公園は「逆徒」を無害化して「官」の側に取り込む格好の装置としても機能してきたのである。
それにしても、と私は思う。維新最大の功労者・西郷は自ら樹立した政府になぜ反旗を翻したのか。どんな日本を作りたかったのか。夕空に屹立する巨大な銅像が、近代史の謎の塊のように見えた。
*参考:『靖国神社と幕末維新の祭神たち』(吉原康和著・吉川弘文館刊)、『上野公園』(小林安茂著・郷学舎刊)、『西南戦争』(小川原正道著・中公新書)、『地図と愉しむ東京歴史散歩』(竹内正浩著・中公新書)
まつろわぬ者たちの上野
魚住昭の誌上デモ「わき道をゆく」第118回
お花見などで上野のお山に行かれることがあったら、是非、彰義隊の墓を御覧になるといい。西郷サンの銅像の裏手に建っているからすぐに見つかるはずだ。
そこはもともと1868(慶応4)年5月の上野戦争で死んだ彰義隊員(計266人)の遺体を荼毘に付したところだ。16年後に彰義隊生き残りの小川興郷(将軍慶喜の元家臣)らの手で今の墓が建立され、以来120年余、小川一族の手で守られてきた。
墓守の一族の苦労は並大抵のものではなかったらしい。何しろ彰義隊は靖国神社に合祀もされない賊軍だ。西郷隆盛のように没後の名誉回復もなされなかった。「朝敵」の汚名を背負ったまま生きなければならなかったからだ。
彼らが政府から受けた冷遇は墓碑銘が如実に示している。高さ6・7mの大墓石には旧幕臣・山岡鉄舟の筆で「戦死之墓」と刻まれているだけで肝心の彰義隊の3文字がない。つまり上野戦争から16年たっても彰義隊の名を書くことがはばかられたのである。
小川一族にとって救いがあるとすれば、それは彰義隊とともに壊滅的な打撃を被った寛永寺の僧侶たちの配慮だったろう。「戦死之墓」の前に置かれた高さ60cmの小さな墓石を見てほしい。上野戦争の翌年、寛永寺の子院の住職2人が密かに付近の地中に埋納したもので、後に掘り起こされ、今の位置に据えられた。
「慶応戊辰五月十五日 彰義隊戦死之墓」などと記された墓石の裏にはこんな漢詩が刻まれている。
昔時布金地 昔時金地を布く
今日草茫々 今日草茫々たり
誰笑千年後 誰か笑う千年後
却憐古戦場 劫て憐む古戦場
昔は絢爛たる伽藍だったところが、今は草ぼうぼうだ。この変わりようを誰か1000年後に笑うだろうか。いや、かえって古戦場として憐れんでくれるにちがいない―。
漢詩の読みも意訳も私の勝手な解釈だから誤っているかもしれないが、切々とした心情がこめられていることだけは間違いない。
吉村昭さんの『彰義隊』(新潮文庫)によると、上野戦争後、上野の山は彰義隊反乱の地として僧はもとより寺男も出入りを禁じられた。わずかに焼け残った寺が大名家に返還され、住職が帰山届を出し、明治2年2月に許されたが、彰義隊の墓に遺族が参ることは禁じられ、それが許されたのは明治6年末だったという。
いくら何でも酷すぎる仕打ちである。が、裏を返せば、それだけ政府が上野の山を恐れたということだろう。それは一体なぜか。
その訳を探るため上野戦争の歴史を繙いてみよう。始まりは鳥羽伏見の戦いに敗れた将軍慶喜が慶応4年2月、朝廷に恭順の意を示すため寛永寺に入って謹慎したことだ。寛永寺を選んだのは、貫首の輪王寺宮が明治天皇の叔父にあたり、朝廷に一定の影響力を持つと考えられたからだ。
慶喜の期待通り、輪王寺宮は慶喜の助命嘆願に奔走した。が、朝廷軍は強硬姿勢を崩さない。それに憤激した旧幕臣らが結成したのが彰義隊である。彼らは慶喜のいる寛永寺に集結し、その数は1000人余りに上った。
page: 2
この彰義隊の存在に困り果てたのが旧幕府の重臣・勝海舟らだ。彰義隊を解散させ、官軍を穏やかに江戸に迎え入れるのが最も望ましい。かといって解散を命じたら、彼らは暴発し、徳川家に恩義を抱く市民も合流して江戸は大混乱に陥る恐れがあった。
そこで彼らを江戸の治安を守るため利用すべきだという意見が出され、重臣一同が賛成した。彰義隊もこの要請に応え、江戸で横行する略奪や辻斬りなどから市民を守るため巡回することになった。
彼らは夜になると、数名ずつ組んで、円に彰の字を描いた提灯を掲げて上野の山を降り、江戸の町々に散っていった。その成果はめざましいものだったらしい。
〈犯罪は激減し、安らいだ夜を持つことを得た市民は感謝し、主立った者が、連れ立って上野の山の屯所に来て金品を差し出すことも多くなった。(中略)町民たちは円提灯をかかげてやってくる隊員たちに茶菓を出し、酒をすすめる者もいる。隊員と町民たちの結びつきは、日増しに強くなっていた〉と吉村さんは書いている。
同年3月14日、江戸に入った西郷と勝海舟の会談で江戸城の無血開城が決まり、慶喜は水戸に隠退謹慎することになった。西郷は江戸の治安維持を勝らに委ねた。
それから江戸に入った朝廷軍と彰義隊の衝突があちこちで起きるようになる。市民らは、乱暴狼藉を働く朝廷軍に敵意を抱き、治安維持の任にあたる彰義隊に喝采を送った。朝廷軍側の首脳は、やがて2000人以上に膨らんだ彰義隊を危険な集団と判断し、治安維持を託した勝に解散を命じた。
だが、彰義隊を支持する寛永寺がこれを拒んだ。寛永寺は単なる寺ではない。上野の山全域を境内とし、その他に寺領1万2000石を持つ大名並みの勢力だ。さらに彰義隊の背後には江戸市民の絶大な支持がある。彼らは彰義隊の屯所に食糧や金品を続々と届けた。
朝廷軍は江戸城を掌中におさめ、江戸に入る諸街道を封鎖していたものの、広大な町は町民のもので権勢は及ばず、完全占拠にほど遠かった。町の治安は彰義隊の力で維持され、その彰義隊を寛永寺と民心が守っていた。端的に言うと、江戸は朝廷軍と彰義隊+寛永寺の二重権力状態だったのである。
こうなると、朝廷軍にとっての最終的な解決策は武力制圧しかない。放置しておけば、同じような事態が全国に広がりかねない。
同年5月3日、奥羽25藩の家老らが集まり、奥羽列藩同盟を結成。その後、越後の6藩も加盟して徹底抗戦を決議した。これをきっかけに朝廷軍は上野への総攻撃を決める。5月15日の上野戦争の結果を改めて書く必要はないだろう。彰義隊+寛永寺勢力は近代兵器を装備した朝廷軍の猛攻を受け、たった1日の戦闘で瓦解した。
上野一帯に散乱した彰義隊員の遺体は見せしめのため野ざらしにされた。長雨で出水した水の中に沈んだり、浮かんだりした。〈やがて梅雨が明け、それらの死体は耕地や道に露出した。すべてが腐乱していて、蝿におおわれ烏や野犬がむらがり、悲惨な様相を呈していた〉(『彰義隊』)という。
国にまつろわぬ民の心を体現した彰義隊は、政府にとって憎むべき存在だった。江戸に潜在する反逆の気運は、彰義隊の記憶とともに上野の山に徹底的に封じ込めなければならない。だから5年半も出入りが規制されたのである。
「戦死之墓」の小墓石にはこんな和歌が刻まれ、当時の上野の山の寂寥とした風景を伝えている。
あはれとて尋ぬる人もなきたまのあとをし忍ぶ岡の辺の塚
(哀れだと思って訪ねて来る人もない魂の跡をこそ偲ばれる、忍の岡=上野の山の墓)
兵庫
姫路城400年、人の力と幸運と 廃城の危機や戦災越えて
「平成の大修理」を終えた世界文化遺産・国宝姫路城(兵庫県姫路市)の大天守内部が27日から、5年ぶりに一般公開される。築城からおよそ400年。廃城の危機、火災、空襲…。白鷺(しらさぎ)に例えられる美しい姿は、多くの人の尽力と幸運によって守られてきた。今、平成の職人たちの手でよみがえった白亜の城が、未来へと受け継がれる。
現存する大天守は関ケ原の合戦後の1601年、“西国将軍”と呼ばれた池田輝政が築造に着手した。その8年後、日本城郭建築の最高峰と称される城が姿を現す。
「継続的な修理で伝統技術が伝えられ、城は維持された」。26日の完成記念式典。文化庁の青柳正規長官がそう強調したように、城の歴史はまさに「修理の歴史」だった。
当初の姫路城は、優れた防御の工夫で「難攻不落」とされたが、大天守は構造的な弱点を抱えた。基礎の地盤沈下に加え、骨格ともいえる心柱の根元が腐食。完成から約50年後には大規模な修理が行われた。天守の傾きがうわさとなって城下に広まったほどで、歴代城主は修理に腐心した。
幕末。姫路藩は朝敵となり、西の備前藩の砲撃を受ける。廃城は免れたが、建物の傷みは目を覆うばかりだったという。
明治期には、地元市民らが「白鷺城保存期成同盟会」を結成。1910~11年、城を管轄する陸軍が緊急修理を行った。34年には本格的な「昭和の大修理」が始まる。
ところが、日本は戦争に突入し、修理は中断。45年、姫路城下は空襲にさらされ、焼け野原となった。その中で、奇跡的に被害を免れた城を「不死鳥のように見えた」と語ったのは、姫路の詩人大塚徹。その感動を「あゝ白鷺城」などの詩に託した。
「昭和の大修理」は再開され、大天守を全解体し復元した。今回の「平成の大修理」では、風雨で傷んだ瓦をふき直し、壁の漆喰(しっくい)などを塗り直した。
「修理を繰り返し、当初の姿を守ったことで世界文化遺産にも選ばれた。世界に、日本の『木の文化』を理解してもらう大きな役割を果たした」。姫路城の歴史に詳しい兵庫県立大特任教授の中元孝迪さん(74)は、そうたたえる。「まさに、永遠の城だ」(仲井雅史)
山口
松陰の自筆史料68点発見 山口・萩
幕末の思想家、吉田松陰の手紙やメモなど、未発表のものを含む自筆の史料68点が山口県萩市で見つかり、松陰の活動や人柄を知る貴重な史料として注目されます。
萩博物館によりますと、萩市に住む女性からおととし以降、市に託されたおよそ1500点の史料の中に、吉田松陰が書いたとみられる手紙などが見つかったということです。
このため明治維新史が専門で広島大学大学院の三宅紹宣教授に詳しい調査を依頼したところ、筆跡などから手紙やメモなど68点が松陰の自筆のものだと分かったということです。
このうち、「写本録」は松陰みずからが松下村塾で写本をして資金を集めていたことが分かる貴重な資料です。
また、松陰らが萩藩主を通じて朝廷を動かし、尊皇攘夷を実行させる計画を書いた草稿は、紙の余白にまで文字が書き込まれていて、紙を大切にする松陰の人柄や、尊皇攘夷に向けて具体策を練っていた様子がうかがえます。
萩博物館によりますと、女性の先祖が松陰の兄の杉民治と交流があり、杉家が保管していた松陰の史料が今回、見つかったとみられるということです。
萩博物館の樋口尚樹学芸専門監は「68点もの大量の吉田松陰の史料が出てきたことに大変驚いている。多くは『吉田松陰全集』にも載ってなく、非常に貴重なものだと思う」と話しています。
沖縄
幕末展、週末にぎわう 浦添市美術館
浦添市美術館で開かれている「琉球・幕末・明治維新 沖縄特別展」(主催・沖縄産業計画、琉球新報社、共催・浦添市教育委員会)は日曜日の15日、大勢の家族連れや友人同士でにぎわった。
琉球王国が1850年代にアメリカ、フランス、オランダのそれぞれと締結した琉米・琉仏・琉蘭の3修好条約原本が注目を集めていた。条約原本の展示に熱心に見入っていた照喜名直子さん(67)=那覇市=は「新聞で見ていたが実物を目にして感激した。昔の物が残っていたことがすごい」と語った。
同展は29日まで。開館は午前9時半~午後5時(月曜休館、金曜は午後7時まで)。入場料は大人千円、高校・大学生700円、小・中学生500円。問い合わせは琉球新報社事業局、電話098(865)5200。
福島
【復元促進の出発点に】天守閣再建50周年(1月26日)
会津若松市の鶴ケ城天守閣は今年、再建50周年を迎えた。4月に内部が改装オープンし、9月予定の記念式典まで行事が続く。成功を願う。
東日本最大級の城郭であり、歴史の興亡に彩られた名城だ。本県観光の目玉、市民のシンボルとして愛されている。復元整備は道半ばであり、前向きな議論はあまり聞かない。城の将来を語り合う「市民会議」のような場を設けてはどうか。復元促進の機運を熟成し、城の魅力をさらに高める出発の年としたい。
葦名氏時代の14世紀創建とされる。天正18(1590)年に領主となった蒲生氏郷が天守閣を建て、城下町を整える。現在の市街地の元となった。建造物は戊辰戦争後に壊されたが、天守閣、走り長屋、鉄門は昭和40(1965)年9月に再建された。
再建を前に「全会津の悲願」と推進論の一方、「文化財の破壊」「復古調」の批判が起こる。市議会で39年7月に可決された再建事業特別会計補正予算は18対16の僅差だった。市民を巻き込む激論が再建のエネルギーを生んだことを思い起こしたい。
市は天守閣内の改装に約1億2千万円を投じた。1階の企画展示室、2階の常設展示室を整備する。管理運営する会津若松観光ビューローは展示品を充実させる。記念式典は9月19日の予定だ。21日から始まる会津まつりと相乗効果を上げてほしい。
ただ、再建50周年をお祭りに終わらせてはならない。歴史遺産、観光地としての価値を磨く取り組みを進める契機にすべきだ。市が天守閣再建50周年記念事業方針で掲げた御三階[ごさんかい]の復元は実現していない。天守閣の赤瓦へのふき替えと外壁の塗り替えが完了しただけだ。平成8年度策定の史跡若松城跡総合整備計画で示された干飯櫓[ほしいやぐら]と南走[みなみはしり]長屋復元は13年に実現したものの、裏門、月見櫓、塀などの復元は手付かずだ。
計画をたなざらしにしないためにも議論を喚起する必要がある。「予算がない」「政策的な優先順位が低い」などの意見がある。しかし、復元は地域活性化に直結するはずだ。賛否を含め意見を出し合えば課題が浮き彫りとなり、解決策を講じる一助となる。議論を尽くし、城の将来展望を描くことに意義がある。
東日本大震災、東京電力福島第一原発事故で減った観光客を呼び戻すためにも魅力向上は欠かせない。熊本城、名古屋城などは建造物を次々と復元している。増加する外国人観光客の誘客合戦にも負けてしまう。手をこまぬいてはいられない。(鞍田 炎)
神奈川
幕末の偉人しのぶ 中島三郎助まつり/浦賀
1853年のペリー提督来航時に黒船へ乗船して対応した浦賀奉行所与力、中島三郎助をしのぶ催しが25日、横須賀市浦賀の住友重機械工業機関工場で開かれた。三郎助を描いた垂れ幕の下、多くの家族連れらが幕末の偉人に思いをめぐらせた。
地元住民らでつくる中島三郎助と遊ぶ会の主催で21回目。
三郎助は日本初の西洋式軍艦を浦賀で建造し、桂小五郎(木戸孝允)に造船術を教えた。戊辰戦争では箱館(函館)で新政府軍と戦い、息子とともに戦死。終焉(しゅうえん)の地である函館市中島町は「父子の忠節にちなんで名付けられた」とされる。
会場では三郎助の足跡をたどるパネル展が開かれ、ひ孫の中島恒英さん(69)=海老名市=も来場。展示に見入っていた女性(67)=横須賀市港が丘=は「ペリーとの交渉役を務めたのは有名だが、函館まで行って戦っていたのは初めて知った。勉強になった」と話していた。
模擬店や市立浦賀中学校による吹奏楽演奏、ゴスペルソングなども会場に花を添えた。遊ぶ会会長の大内透さん(68)は「こうして子どもたちや地域住民が集う場をつくることで、浦賀の町を愛していた三郎助の思いを継ぐことにつながってほしい」としていた。
テレビ
負けても生き残れ!波瀾万丈な人生を送った榎本武揚の思いとは?『先人たちの底力 知恵泉』
人々が組織や社会の中で直面している様々な課題、実はそれらは先人たちが取り組んできたものと通底する。現代人の課題や関心事項を毎月1テーマずつ設定し、解決へのヒントを歴史上の人物の知恵と行動から探っていく番組『先人たちの底力 知恵泉(ちえいず)』(NHK Eテレ)。
1月27日(火)は、「負けても生き残れ!」をテーマに、「だから、生きる 榎本武揚 敗北からの復活劇」を放送する。今回取り上げる榎本武揚ほど波瀾万丈の人生を送った人物も少ないのでは? 幕府の御家人として、最後まで明治新政府に抵抗した榎本。その後、一転して政府の高官となったことから、後世からの誤解や批判も多い。しかし実は、その博覧強記ぶりから国に多大な貢献をした人物。これまで光が当たりにくかった榎本の業績を掘り起こしていく。
幕府の旗本の家に生まれ、12歳で昌平坂学問所に入り、長崎の海軍伝習所に学び、さらには、幕府に派遣されてオランダに約4年間留学。その間、儒学、砲術、航海術、数学、化学、国際法、経済、蘭・英・仏・独の各国語など、文系・理系をとわず、あらゆる学問を身につけた、まさに博覧強記の人物だ。
ところが、榎本が1867年に帰国したとき、日本は動乱の真っ最中。将軍・徳川慶喜による大政奉還、翌年には戊辰戦争が勃発する。榎本は江戸城の無血開城に抗し、八隻の艦隊を引き連れ、蝦夷地に向かう。しかし新政府軍によって陥落。榎本も自害しようとするが、官軍総参謀・黒田清隆らに必死で止められる。その後、榎本は以後一転、明治政府の高官として外交や殖産興業に尽力する。なぜ黒田は榎本を生かそうとしたのか。榎本はなぜそれを受けたのか……。榎本の生き方から見えてくるものは?
■『先人たちの底力 知恵泉(ちえいず)』
毎週火曜 23:00~23:24(NHK Eテレ)
山形県
酒井家から盗まれた重文の名刀見つかる(山形県)
見つかったのは、国の重要文化財に指定されている日本刀「備州長船住元重」だ。鎌倉時代末期に作られたとされる名刀で、酒井家から戊辰戦争で指揮をとった重鎮に贈られ、その後、再び酒井家に戻されていた。しかし、1986年8月、刀を保管していた酒井家の収納庫に2人組の男が入り口を壊して侵入し、ほかの刀など15点とともに盗み出し、そのまま行方が分からなくなっていた。去年9月、酒井家18代当主で、致道博物館の館長でもある酒井忠久さんのもとに、大阪府のコレクターの男性から「刀を買い取った」と連絡があった。刀は転売が繰り返されたとみられていて、現在も大阪府の男性が所有している。民法では、無償で返還を請求できるのは、盗難・紛失から2年までで、再び酒井家で所有するには刀を買い戻す必要があり、1億円近くかかるという。酒井さんは、国宝や重要文化財などが時効にかかわらずに無償で返還できるような法整備を求めている。酒井さんは買い戻しはしない予定で、今後、コレクターの男性から刀を借り受けるなどして博物館に展示したいと話していた。
福島
現代版「二本松少年隊」結成 古里PR いざ出陣!
ふくしまデスティネーションキャンペーン(DC)に向け、二本松市推進委員会(二本松おもてなし隊)は市をPRする現代版「二本松少年隊」を結成した。10日、推進委員会長の新野洋市長が記者会見し、メンバーを発表した。
「二本松少年隊」は二本松、郡山両市と大玉村の16歳から31歳までの男女11人。声優を目指す学生や演劇部に所属する高校生、国際協力機構(JICA)二本松青年海外協力隊訓練所の職員らで構成している。
新野市長は「戊辰戦争で郷土を守るため若くして散った『二本松少年隊』の志を酌み、しっかりと市をPRするためのパフォーマンス集団にする。DCを盛り上げたい」と抱負を述べた。安斎文彦二本松観光協会長も同席し、メンバーを激励した。
メンバーは今後、毎週土曜日を中心に、戊辰戦争や二本松少年隊などについての座学や殺陣の練習に取り組む。市内の劇団HEROS ACTION CLUB代表の広瀬和重さん(50)が殺陣などアクションを指導し、3月29日に同市市民交流センターでお披露目会を開く。DC期間後も年間を通じて活動し「二本松の菊人形」などのイベントにも参加する。メンバーは次の通り。
中嶋哲也(二本松、JICA二本松)渡辺晴香(大玉、NOKエラストマー)栗城千鶴(郡山、郡山萌世高一年)鹿野ひとみ(二本松、MTS&プランニング)斎藤倫明(二本松、福島大四年)斎藤葵(二本松、安達高二年)鹿野康平(二本松、福島西高二年)菅野純麗(二本松、ケイセンビジネス公務員カレッジ)渡辺芽斐(二本松、二本松市臨時職員)斎藤美祐紀(二本松、障害者福祉施設・すばる)菅野愛華(二本松、安達高二年)
( 2015/01/11 08:22 カテゴリー:今日の撮れたて )
112歳90日 県内長寿記録更新 若松の佐藤ステさん
県内最高齢の会津若松市の佐藤ステさんは13日、112歳90日となった。統計がある昭和45年以降での県内最高長寿記録だった112歳88日を突破した。
佐藤さんは、明治35(1902)年、二本松市生まれ。実家の山岡家は二本松藩士の家柄で、佐藤さんの大叔父に当たる山岡栄治は戊辰戦争時、青山助之丞とともに薩摩の部隊に切り込んで奮戦し「大壇口の二勇士」とたたえられた。
佐藤さんは現在会津若松市の老人ホームに入所している。佐藤さんの孫で日本精測社長の佐藤光信さん(65)は「会話は難しいが、食欲も旺盛で歌も時折口ずさむなど元気。今年も誕生日を迎えられると思う。長寿日本一を目指してほしい」と話している。
これまでの最長寿記録者は平成10年に死去した川俣町の古和田チヨさんだった。
福井県
歴博開館1周年、幕末の福井語る
福井市立郷土歴史博物館の開館一周年を記念した講演会が二十三日、同市宝永三丁目の県国際交流会館で開かれた。専門家が新説を交えながら、幕末の福井藩の藩政改革について話した。
講師には、幕末の福井藩に詳しい大妻女子大短大部の高木不二教授を招いた。高木教授は▽幕末の藩士、三岡八郎(後の由利公正)による経済政策▽薩摩、福井両藩の交易▽藩士・日下部太郎のアメリカ留学―について、最新の研究成果を織り込んで講演した。
三岡八郎の経済改革では、生糸など藩内の産物の生産、管理、販売をつかさどる「制産方」という部門が設置されたことを指摘。大きな成果を上げたとした。
また高木教授は、福井藩が当時は禁じられていた他藩との交易を、薩摩藩と行っていた事実を披露。薩摩藩から英国の商社を通じ、ひそかに中国へ福井産の生糸や茶を輸出、利益を得ていたことを明かした。
山口県
講演会:晋作の“語り人” 幕末振り返る−−下関 /山口
下関の歴史や文化を語り合う下関夜話会が21日、下関市中之町の亀山八幡宮儀式殿であった。幕末の志士、高杉晋作の“語り人”として活動している福岡市の亀田真砂子さん(55)が「高杉晋作と下関〜長府・清末藩の人々と関わり〜」と題して講演し、約50人が耳を傾けた。
亀田さんは晋作にまつわる人物のプロフィルや年表を示しながら幕末を振り返り、「下関はまさに維新の舞台。大..(以下有料記事)
コラム
『明治維新と幕臣 「ノンキャリア」の底力』
レビュアー:麻木 久仁子
来年の大河ドラマは『花燃ゆ』。吉田松陰の妹・文を主人公に、松蔭はもちろん、久坂玄瑞や高杉晋作など長州の志士たちが、その生き様をたっぷりと魅せてくれるであろう。大河ドラマで幕末物は当たらないなどというジンクスはいつのことやら、『篤姫』『龍馬伝』『八重の桜』、そして今回の『花燃ゆ』とつづくのも、近代日本の立ち上がりを振り返り、このところの閉塞感を打破するヒントを得たいという空気があるのだろうか。ちなみに長州が舞台となるのは1977年の『花神』以来、38年ぶりだそうである。明治維新以来、現総理も含めてもっとも多くの総理大臣を輩出した地である。地元の皆さんはさぞかし期待しているに違いない。
さて、となればまた維新と「志士」の本はたくさん出版されることだろうと思うのだが、今回ご紹介する本は維新と「幕臣」の本である。
旧態依然とした幕府と、保身に汲々とするのみで時代の流れに取り残された幕臣。それに対して進取の気風に富み時代を読み、日本を近代化すべく戦った薩長をはじめとする西南雄藩と志士たち。
しかしこうしたイメージは修正されつつある。
たとえば戊辰戦争における鳥羽・伏見の戦いのイメージはどうだろう。三分の一の兵力しか持たなかった倒幕軍に敗れたことから「幕府軍は数ばかりで、装備は古くさい鎧兜」だったのかと思いきや。実際には洋式装備の歩兵隊が八個連隊・9800人もおり、フランス軍事顧問団の指導を受けた精鋭部隊も擁していたという。海軍ともなれば幕府軍が圧倒的で、主力艦の「開陽丸」も当時世界最大級の軍艦だったし装備も極めて優秀だった。薩長ふくめ、対抗できる戦力は国内には存在しなかったのである。幕府も時代の変化には充分に危機感をもち、軍制や税制、そのほか様々な改革をすこしずつ積み重ねてはいた。そもそも開国・近代化を目指したのは幕府の方がさきだったではないか。だが残念ながら幕府はガバナンスに失敗し、蓄えた優秀かつ大切なリソースも生かしきれず、明治維新となる。
では幕府がそれまでに積み重ねたものはすべて無駄になったのかというと、じつはそうではない、というのが本書のテーマである。明治維新は非常に大きな政治変動ゆえに、その変化ばかりに目を奪われがちだが、「いかにして統治したか」という行政の面からみると、江戸から明治への連続性が見えてくるというのである。
"明治維新に際して、戊辰戦争において戦地となった場所は例外として、全国津々浦々が混乱を極め、略奪や暴行が横行したという事態に至っていないということは、少なくとも社会生活を維持できるような秩序が保たれていたということになる。つまり、行政が機能しない状態にはほとんどならなかったということになろう。"
例えば大災害のときなどでも、日本人は秩序正しくふるまうことが折々話題になるが、道徳心もさることながら、行政に対する信頼感が実はとても大きいのである。行政がきっと対応する、援助がくると信じられるからこそ、暴動や略奪にはならない。
page: 2
天下の体制ががらりと変わっても、幕末の人々が落ち着いていられたのも、日常生活に直結する行政が機能し続けていたからなのである。
新政府による旧幕臣の登用というと、勝海舟や榎本武揚、渋沢栄一などの大物の名前を思い浮かべるが、ここで頑張ったのは旗本や御家人などの幕臣たちであった。今風にいえばノンキャリの官僚たちである。薩長土肥や越前・尾張などの雄藩は、藩の規模、いわば地方自治の規模での統治の経験しかなく、全国規模の統治は未経験だった。そのノウハウや人材を持っていたのは幕府のみだったのだ。明治政府による旧幕臣の登用については「国難にあたり、敵味方の分け隔てなく優秀な人材を登用した明治政府の度量」という見方もあるが、実情は徳川400万石の幕領を統治する行政組織をそのまま活用しなければどうにも事が動かない、というのが実情だったようだ。
"見方によっては皮肉ではあるが、明治政府は、江戸幕府という前政権が有効に機能していたからこそ、全国政権としての体裁を為すことができたともいえよう。"
「岩倉使節団」は、欧米の制度や法制を視察・研究するために派遣された専門官のほかに、実務にあたる書記官を多数含んでいたが、書記官の多くが幕末期の外交交渉にあたった旧幕臣であったという。それゆえにかれらは、使節団における地位は低くとも知識や経験は豊富だった。現実の外交交渉の場ではかれらに頼らざるをえず、岩倉さえも頭が上がらない始末。しまいにはホテルの部屋割りにいたるまでバチッと仕切ってしまったという。260年にわたりこの国を平穏に運営してきた幕府の官僚たちの意地を感じるエピソードである。
変革の時、人々はヒーローを求める。新しいビジョンを示す人物を求める。しかし、どんな優秀な人物がどれほど素晴らしいビジョンを描こうとも、それを実現するためには組織が必要であり、最前線で実行していく力をもつ人材が不可欠なのだ。その人材の層にどれほどの厚みがあるかが、その社会の力、基礎体力ともいうべきものだろう。それがしっかりしていれば、どんな社会変動があっても乗り越えてゆけることを、幕臣たちの働きが教えてくれる。
明治政府の改革をささえた無名の幕臣たちを思いながら、「人」の力の大切さを軽んじるような世の中になりませんようにと願うのである。
『明治維新と幕臣 - 「ノンキャリア」の底力 (中公新書)』
作者:門松 秀樹
出版社:中央公論新社
内容紹介
幕府は本当に組織が劣化し、すぐれた人材を欠いていたのか? 行政実務に通じ、新政府に継続登用された中・下級官僚層に光を当てる。
岩手
宮古港400年、歩み発信へ 「新撰組ゆかり」PRも
岩手県内で最も歴史の古い港として発展してきた宮古市の宮古港は2015年、開港400周年を迎えた。1611(慶長16)年の慶長津波の被害から復興するため、1615(元和元)年に2代盛岡藩主・南部利直公によって藩港として定められ、漁業や交易を中心に発展してきた。400年後の今、くしくも東日本大震災からの復興に歩む姿と重なる。今春から数々の記念事業を展開し、本県沿岸の拠点都市として、海の恩恵を生かしたまちづくりを全国に発信する。
宮古港400年の歴史の中には、新たな時代をひらく命がけの戦いがあった。1869(明治2)年、新政府軍と旧幕府軍が激突した「宮古港海戦」。145年余りの時を経て、宮古市では有志団体「宮古海戦組」が宮古の知名度向上や観光振興につなげようと、当時を思わせるいでたちでPR活動を展開している。
海戦では旧幕府軍が新政府軍の軍艦「甲鉄」奪取を狙ったが敗北した。旧幕府軍には新撰組(しんせんぐみ)の土方歳三が参戦したとされ、全国に根強くいる新撰組ファンにとって同港は名所の一つだ。
同団体は400周年に合わせ、今年9月19、20の両日、新撰組ゆかりの地で毎年開く「全国新選組サミット」を宮古に誘致。宮古秋まつりのパレードへの参加やミスター土方コンテストなどを企画する。
【写真=宮古港開港400周年をPRする宮古海戦組のメンバー。軍服を着て市内外のイベントに参加している】
福島
記念イベント続々 鶴ヶ城天守閣50周年
会津若松市のシンボル、鶴ケ城の天守閣がことし、再建から50周年を迎え、市は記念行事の実行委員会を設け、節目の年を祝うイベントを企画、誘客を図る。
鶴ケ城は戊辰戦争で戦場となり、天守閣は1874年に取り壊された。戦後、市民の要望を受け、1965年9月に再建された。
市は50周年を記念し、総工費1億2000万円をかけ、内装の一新に取り組む。天守閣内の展示を充実させるほか、夜間照明を発光ダイオード(LED)に替え、4月1日に改装オープンする。
次世代へ再建の意義を伝えようと、9月19日には市内の幼稚園児らを招いてイベントを企画、記念講演会やトークショーを開催する。
4月から6月に福島県内で「ディスティネーションキャンペーン」が実施されるのに合わせ、地域団体の多彩なイベントを展開。各種出店が並ぶ「會津十楽(あいづじゅうらく)」を土日祝日に開く。会津青年会議所は5月22日、全国城下町シンポジウムを企画する。
市観光課は、記念イヤーを盛り上げるため、公募でロゴマークも作成、市民や企業に活用を呼び掛けている。
東京
東京・丸の内で、英国人も愛した幕末明治のスター絵師・暁斎と弟子コンドルの展覧会
2015年6月27日(土)から9月6日(日)までの期間、展覧会「画鬼・暁斎-KYOSAI 幕末明治のスター絵師と弟子コンドル」が、東京・丸の内の三菱一号館美術館にて開催される。
河鍋暁斎(かわなべ きょうさい、1831〜1889年)は、幕末に生まれ、6歳で浮世絵師歌川国芳に入門、9歳で狩野派に転じてその正統的な修業を終え、幕末明治に絶大な人気を博した絵師のひとり。一方、三菱一号館を設計した英国人建築家ジョサイア・コンドル(Josiah Conder、1852〜1920年)は、日本美術愛好家であり、暁斎に弟子入りして絵を学び、師の作品を海外に紹介。本展では、2人の交流やコンドルの業績と、彼の敬愛する暁斎のユーモラスで型破りな画業を、展示替えを行いながら、国内外の名品約120点を通して紹介する。
みどころのひとつは、暁斎とコンドルの師弟愛。2人の交流はとても親密なもので、暁斎の《日光地 取絵巻》をみると、様々な名所旧跡を回り、何度か写生旅行にも出かけるほどだったという。屏風絵《大和美人図屏風》は、弟子のコンドルが自国に持ち帰ることを想定し、暁斎が「およそ6ヶ月もの間精力を集中して描き上げたもの」(コンドル著「河鍋暁斎」)。背景の屏風には、日本の稲作の様子が丁寧に描かれ、漆器や畳など日本独特の文化が余すところなく描き込まれている。
また、狩野派を引き継ぎながら、浮世絵や江戸期の諸派にも取り込み、「画鬼」と称された暁斎の画業を展示。2歳ですでに蛙を写生するなど、絵に早熟な才能を示した周三郎(暁斎の幼名)は、6歳で浮世絵師の歌川国芳に弟子入り。その後2年ほどで国芳の許を離れるが、西洋画に至るまで貪欲にとりこんで旺盛に制作する態度、写生の重視、絵師としての反骨の姿勢などが垣間見れる。
さらに、現在はニューヨークのメトロポリタン美術館に所蔵されている、英国人が愛した暁斎の作品がおよそ100年ぶりに里帰り。58歳で亡くなる2年程前に描かれたものと推定されている作品が展示され、晩年を迎えた暁斎の卓越した筆さばきと大胆な構図をみることができる。
河鍋暁斎《うずくまる猿》明治21(1881)年頃/
メトロポリタン美術館蔵
©Metropolitan Museum of Art
【開催概要】
画鬼・暁斎-KYOSAI 幕末明治のスター絵師と弟子コンドル
会期:2015年6月27日(土)〜9月6日(日) ※一部展示替えあり。前期は6月27日〜8月2日、後期は8月4日〜9月6日。
開館時間:10:00〜18:00(祝日・振替休日除く金曜のみ20:00まで) ※入館は閉館の30分前まで。
休館日:月曜休館(但し、祝日の場合は開館/8月31日は18時まで開館)
会 場:三菱一号館美術館
住所:東京都千代田区丸の内2-6-2
入 館 料:当日券 一般 1,500円、 高校・大学生 1,000円、小・中学生 500円
前売券 一般 1,300円 ※大学生以下の設定はない。
※前売券以下の期間、以下の場所にて発売する。
・2015年2月7日(土)〜6月26日(金)
ローソンチケット(34200)、チケットぴあ(766-491)、セブンチケット(034-467)、イープラス、ちけっとぽーと 関東各店、三菱一号館美術館チケット購入サイトWEBKET(展覧会ウェブサイトからアクセス)
・2015年2月7日(土)〜5月24日(日)
Store1894(三菱一号館美術館内・休業日は美術館に準ずる)
※ちけっとぽーと、Store1894では絵柄入りのチケットを販売。
※詳細は展覧会サイトにて。
コラム
この記事、面白かったです。
明治維新の成功を違う角度から見てみよう維新ヒーローの陰に旧幕臣がいた!
今年の大河ドラマは『花燃ゆ』。吉田松陰の妹・文を主人公に、松蔭はもちろん、久坂玄瑞や高杉晋作など長州の志士たちが、その生き様をたっぷりと魅せてくれるであろう。大河ドラマで幕末物は当たらないなどというジンクスはいつのことやら、『篤姫』『龍馬伝』『八重の桜』、そして今回の『花燃ゆ』と続くのも、近代日本の立ち上がりを振り返り、このところの閉塞感を打破するヒントを得たいという空気があるのだろうか。
ちなみに長州が舞台となるのは1977年の『花神』以来、38年ぶりだそうである。明治維新以来、現総理も含めてもっとも多くの総理大臣を輩出した地である。地元の皆さんはさぞかし期待しているに違いない。
覆される幕末のイメージ
さて、となればまた維新と「志士」の本はたくさん出版されることだろうと思うのだが、今回ご紹介する本は維新と「幕臣」の本である。
旧態依然とした幕府と、保身に汲々(きゅうきゅう)とするのみで時代の流れに取り残された幕臣。それに対して進取の気風に富み時代を読み、日本を近代化すべく戦った薩長をはじめとする西南雄藩と志士たち。しかしこうしたイメージは修正されつつある。
たとえば戊辰戦争における鳥羽・伏見の戦いのイメージはどうだろう。3分の1の兵力しか持たなかった倒幕軍に敗れたことから「幕府軍は数ばかりで、装備は古くさい鎧兜」だったのかと思いきや。実際には洋式装備の歩兵隊が八個連隊・9800人もおり、フランス軍事顧問団の指導を受けた精鋭部隊も擁していたという。
海軍ともなれば幕府軍が圧倒的で、主力艦の「開陽丸」も、当時、世界最大級の軍艦だったし装備も極めて優秀だった。薩長含め、対抗できる戦力は国内には存在しなかったのである。
page: 2
幕府も時代の変化には充分に危機感をもち、軍制や税制、そのほかさまざまな改革を少しずつ積み重ねてはいた。そもそも開国・近代化を目指したのは幕府の方が先だったではないか。だが残念ながら幕府はガバナンスに失敗し、蓄えた優秀かつ大切なリソースも生かしきれず、明治維新となる。
維新時に秩序が保たれていたことは、幕府のおかげ
では幕府がそれまでに積み重ねたものはすべて無駄になったのかというと、実はそうではない、というのが本書『明治維新と幕臣』のテーマである。
明治維新は非常に大きな政治変動ゆえに、その変化ばかりに目を奪われがちだが、「いかにして統治したか」という行政の面からみると、江戸から明治への連続性が見えてくるというのである。
“明治維新に際して、戊辰戦争において戦地となった場所は例外として、全国津々浦々が混乱を極め、略奪や暴行が横行したという事態に至っていないということは、少なくとも社会生活を維持できるような秩序が保たれていたということになる。つまり、行政が機能しない状態にはほとんどならなかったということになろう”
たとえば大災害のときなどでも、日本人は秩序正しくふるまうことが折々話題になるが、道徳心もさることながら、行政に対する信頼感が実はとても大きいのである。行政がきっと対応する、援助がくると信じられるからこそ、暴動や略奪にはならない。
天下の体制ががらりと変わっても、幕末の人々が落ち着いていられたのも、日常生活に直結する行政が機能し続けていたからなのである。
新政府による旧幕臣の登用というと、勝海舟や榎本武揚、渋沢栄一などの大物の名前を思い浮かべるが、ここで頑張ったのは旗本や御家人などの幕臣たちであった。今風にいえばノンキャリの官僚たちである。
薩長土肥や越前・尾張などの雄藩は、藩の規模、いわば地方自治の規模での統治の経験しかなく、全国規模の統治は未経験だった。そのノウハウや人材を持っていたのは幕府のみだったのだ。
page: 3
明治政府による旧幕臣の登用については「国難にあたり、敵味方の分け隔てなく優秀な人材を登用した明治政府の度量」という見方もあるが、実情は徳川400万石の幕領を統治する行政組織をそのまま活用しなければどうにも事が動かない、というのが実情だったようだ。
“見方によっては皮肉ではあるが、明治政府は、江戸幕府という前政権が有効に機能していたからこそ、全国政権としての体裁を為すことができたともいえよう”
「岩倉使節団」は、欧米の制度や法制を視察・研究するために派遣された専門官のほかに、実務にあたる書記官を多数含んでいたが、書記官の多くが幕末期の外交交渉にあたった旧幕臣であったという。それゆえに彼らは、使節団における地位は低くとも知識や経験は豊富だった。
現実の外交交渉の場ではかれらに頼らざるをえず、岩倉さえも頭が上がらない始末。しまいにはホテルの部屋割りに至るまでバチッと仕切ってしまったという。260年にわたりこの国を平穏に運営してきた幕府の官僚たちの意地を感じるエピソードである。
いつの時代も組織力が重要
変革の時、人々はヒーローを求める。新しいビジョンを示す人物を求める。しかし、どんな優秀な人物がどれほどすばらしいビジョンを描こうとも、それを実現するためには組織が必要であり、最前線で実行していく力をもつ人材が不可欠なのだ。
その人材の層にどれほどの厚みがあるかが、その社会の力、基礎体力ともいうべきものだろう。それがしっかりしていれば、どんな社会変動があっても乗り越えてゆけることを、幕臣たちの働きが教えてくれる。
明治政府の改革を支えた無名の幕臣たちを思いながら、「人」の力の大切さを軽んじるような世の中になりませんようにと願うのである。
【幕末女傑烈伝】要人の愛人となり、密偵活動した中西君尾
2015年NHK大河ドラマ「花燃ゆ」のヒロインで、吉田松陰の妹・杉文。文はいま、激動の時代をしたたかに生き抜いた女性として注目されているが、彼女の他にも、幕末から明治維新にかけて逞しく生きた女傑はいる! 今回は、中西君尾の波瀾万丈ヒストリーを追う!!
中西君尾(1844~1918年)は、京都府船井郡八木町に生まれた。京都市街の西側を流れる桂川を20kmほど上流にいったところにある山間の町である。父は武士だったが殺害され、家が没落。彼女は19歳で祇園の芸者となる。
座敷に出ていた「魚品」というお茶屋には、高杉晋作が長州の志士たちを連れてよくやって来た。あるとき、高杉に連れられて来た井上馨は、君尾を見て一目惚れ。やがて、2人は愛人関係になる。
この店には、安政の大獄の際、井伊直弼の指示で多くの志士たちを弾圧した島田左近も飲みに来ていた。島田も君尾を口説いていたが、彼女はなびかなかった。
それを聞いた井上は、長州藩の同志を彼女のもとに行かせ、「島田と肉体関係を結び、密偵になってほしい」と頼んだ。その頼みを聞いた彼女は、島田の愛人となり、その動向を長州藩士に伝達。島田はその後、尊皇攘夷派の過激派で構成されていた天誅組に殺された。
また、新撰組の近藤勇も君尾を口説いた。彼女が「あなたが天子様の味方をされるなら」と答えると、近藤は「それはできぬ」と答え、あっさり引き下がったという。
1863年(文久3)5月、井上馨は伊藤博文ら5人でロンドンに留学。その間、長州藩の志士で松陰の弟子でもある品川弥二郎の愛人になり、子供を生んだ。
彼女は明治時代になっても芸者を続け、明治政府の高官になったかつての志士たちが遊びに来るなどの交流が続いた。もし、島田左近や近藤勇など幕府側の人間の愛人になり、志士たちの情報を幕府側に漏らしていたとしたら、彼女の運命も変わっていたかもしれない。
【幕末女傑烈伝】50歳を過ぎて志士たちの連絡役に…松尾多勢子
2015年NHK大河ドラマ「花燃ゆ」のヒロインで、吉田松陰の妹・杉文。文はいま、激動の時代をしたたかに生き抜いた女性として注目されているが、彼女の他にも、幕末から明治維新にかけて逞しく生きた女傑はいる! 今回は、松尾多勢子の波瀾万丈ヒストリーを追う!!
信濃伊那谷の豊かな農家に生まれ、豪農に嫁いだ松尾多勢子(1811~1894年)。農家の主婦として4男3女を産み育てるいっぽうで、もともと学問が好きで、和歌や平田学派の国学の勉強も続けた。
国学というのは平田篤胤が提唱したもので、王政復古、つまり天皇を中心とした政治にすべきと主張。尊王の志士たちの考えにも近い。京都では、その志士たちが華々しい働きをしているとの噂が田舎の伊那谷にも聞こえ、彼女も京都に行きたいと願っていた。
子育てを終え、50歳を過ぎた彼女は一大決心、1862年(文久2)に京都の染物店に勤める若者に同行してもらい、京都に上る。そして、平田学派の薩摩藩士や長州藩士と交流するようになった。
吉田松陰門下生の久坂玄瑞(杉文の最初の夫)や、品川弥二郎(のちの明治政府の内相)、楫取素彦(杉文の2番目の夫)などとも親しく交流、志士たちの密談の場にも同席。50歳過ぎの田舎の農婦っぽい彼女は、幕府側にも怪しまれないということで、志士たちの連絡役を務めるようになった。倒幕をひそかに狙う公家の岩倉具視(のち明治の元勲)の知遇も得る。
しかし京都は、日増しに物騒になってきた。彼女も幕府側に目をつけられ、長州藩邸にかくまわれたりしながら生きる日々が続く。文久3年、心配した息子たちが京都に出てきて、彼女を田舎に連れて帰った。
その後、彼女は伊那谷で長寿をまっとうした。彼女は、やる気さえあれば50歳を過ぎた女性でも好きなことができる、という見本ではないだろうか。
【幕末女傑烈伝】高杉晋作の最期を看取った正妻・高杉雅子
2015年NHK大河ドラマ「花燃ゆ」のヒロインで、吉田松陰の妹・杉文。文はいま、激動の時代をしたたかに生き抜いた女性として注目されているが、彼女の他にも、幕末から明治維新にかけて逞しく生きた女傑はいる! 今回は、高杉雅子の波瀾万丈ヒストリーを追う!!
長州藩士の娘として萩に生まれた高杉雅子(1845~1922年)。父は山口町奉行という、藩内では身分の高い武士である。
1860年、雅子が16歳のとき、20歳の高杉晋作と結婚。新居は萩に構え、4年後には二人の間に息子も生まれた。ところが、高杉は幕末の政治活動に熱中し、家を飛び出したきり、めったに帰ってこない。
じつは、雅子に息子が生まれる頃、高杉は愛人のおうのと下関で暮らしていたのだ。萩から60kmほど離れた下関で、夫が愛人と暮らしていることは雅子の耳にも入っていたが、取り乱したりせず、一人息子を育てながらじっと家を守っていた。
しかし、夫が結核で重病だと聞き、下関まで出かけた。そこで初めて、夫の愛人・おうのと顔を合わせたのである。雅子は、おうのに代わり、自分が高杉の看病をすることにした。そして1867年(慶応3)、高杉の死を看取った。
雅子は1871年(明治4)、息子の教育のため、東京に出て麻布に住んだ。その後は、死ぬまでここで暮らしている。この間も、おうのとの交流は続いていた。おうのは雅子の東京の家を訪ね、泊まったりしたという。
高杉の思い出を語り合ったのだろうか。一人の天才的な男に関わった二人の女性。そのニ人が語り合う姿を、高杉は天国からどんな思いで眺めたのだろうか。
【幕末女傑烈伝】裸のまま飛び出し、坂本龍馬の窮地を救った楢崎龍
2015年NHK大河ドラマ「花燃ゆ」のヒロインで、吉田松陰の妹・杉文。文はいま、激動の時代をしたたかに生き抜いた女性として注目されているが、彼女の他にも、幕末から明治維新にかけて逞しく生きた女傑たちがいる! 今回は、楢崎龍の波瀾万丈ヒストリーを追う!!
長州藩士の流れを汲む医師の娘として京都に生まれた楢崎龍(ならざき りょう 1841~1906年)。裕福な家庭で、生け花、香道、茶道などを習って育つ。
しかし、父が安政の大獄(1858年)で牢に入れられ、その後、赦免になったものの、牢で受けた拷問のため、1962年に死亡。一家はたちまち困窮した。
母は方広寺大仏殿(東山区)の近くの、土佐尊王攘夷派が集まる隠れ家で炊事の仕事、21歳の龍も七条の旅館で働いた。
その母の縁で、坂本龍馬と龍は知り合う。龍馬に名前を聞かれた龍が自分の名前を告げると、「わしと同じ名だな」と龍馬は微笑んだという。
龍馬は、龍を伏見の寺田屋の女将・登勢に預けた。ある晩、夜中の3時頃、龍が風呂に入っていると、外で物音。刺客が龍馬を殺しに来た、とピンときた龍は、裸のまま2階に駆け上がり、寝ていた龍馬を起こした。龍の機転のおかげで、龍馬は傷を負いつつも逃げのびた。
その後、龍馬と龍は結婚、西郷隆盛の勧めで鹿児島まで船旅をし、温泉につかったりして50日間ほど過ごした。
1867年、京都河原町の近江屋で龍馬が暗殺されると、龍は一時的に高知の龍馬の実家に身を寄せる。
その後、東京に出て、明治8年に横浜で商人と再婚。晩年は酒浸りとなり、酔うと「わたしゃ、龍馬の妻だ」と呂律の回らない口調で言っていたという。強烈な個性を持った龍馬という男に惚れたため、一生忘れられなかったのだろう。これも女の業か。
【幕末女傑烈伝】拷問されても口を割らず!桂小五郎の妻・木戸松子
2015年NHK大河ドラマ「花燃ゆ」のヒロインで、吉田松陰の妹・杉文。文はいま、激動の時代をしたたかに生き抜いた女性として注目されているが、彼女の他にも、幕末から明治維新にかけて逞しく生きた女傑たちがいる! 今回は、木戸松子の波瀾万丈ヒストリーを追う!!
木戸松子(1843~1886年)は若狭小浜藩士の家に生まれたが、幼い頃に一家は離散。彼女は9歳で舞妓となり、14歳で京都の花街・三本木の芸者になった。
笛と踊りがうまく、美人で機転もきいた彼女は売れっ子に。彼女が籍を置いていた「吉田屋」には、吉田松陰の門下生・桂小五郎(明治になって木戸孝允に改名)も通い、京都での活動の拠点にするようになる。桂と松子は愛人関係となり、桂の後輩の伊藤博文の働きかけで松子は桂に身請けされた。
ところが、1863年に起きた「8・18の政変」で、長州勢は会津・薩摩連合勢力の手により、京都から追放された。桂は京都に潜伏し、情報収集につとめた。松子は同志に秘密の手紙を届けたり、密会の手引きを引き受けたりした。
それが新撰組にばれ、捕らえられて壬生の屯所に連行された。襦袢1枚にされ、青竹で叩かれ、桂の潜伏先を吐くように責められた。しかし、彼女は口を割らなかった。明治2年、桂は明治政府の高官となり、松子もその夫人として東京で暮らした。こんな女性に惚れられた男は果報者だ。
【幕末女傑烈伝】かの有名な「寺田屋」を切り盛りした寺田屋登勢
2015年NHK大河ドラマ「花燃ゆ」のヒロインで、吉田松陰の妹・杉文。文はいま、激動の時代をしたたかに生き抜いた女性として注目されているが、彼女の他にも、幕末から明治維新にかけて逞しく生きた女傑たちがいる! 今回は、寺田屋登勢の波瀾万丈ヒストリーを追う!!
寺田屋登勢(てらだやとせ 1829~1877年)は大津の米問屋の娘に生まれ、18歳で京都伏見の船宿「寺田屋」に嫁いだ。20人からの奉公人を抱える船宿だったものの、亭主はおとなしいが、どうしようもない遊び人。おまけに、口うるさい姑や小姑もいて、登勢は苦労を重ねたのである。
船宿の経営は、登勢に任された。彼女は女将としての才能を発揮。姉御肌でテキパキと働き、奉公人にも慕われ、客も増えて繁盛した。
寺田屋は薩摩藩士たちの定宿でもある。1862年(文久2)には、薩摩藩士同士が尊攘派と公武合体派に分裂し、寺田屋で殺傷事件を起こして9人が死亡した(寺田屋騒動)。登勢はその9人の位牌を寺田屋の仏壇に置き、供養した。
1866年(慶応2)には、薩長同盟締結を見届けるべく、京都に来た坂本龍馬が寺田屋に逗留。そこへ、午前3時ごろ、伏見奉行所の役人50人あまりが龍馬を捕らえるため、寺田屋にやってきた。龍馬の愛人・お龍の機転で、龍馬はかろうじて逃げるという事件も起きている。
龍馬は登勢のことを「おかあ」と慕い、勝海舟も彼女を「頭がいい」と褒めていたという。現代にも、こういう女性がいるといいのだが……。
【幕末女傑烈伝】井伊直弼の愛人&スパイとして暗躍・村山たか
2015年NHK大河ドラマ「花燃ゆ」のヒロインで、吉田松陰の妹・杉文。文はいま、激動の時代をしたたかに生き抜いた女性として注目されているが、彼女の他にも、幕末から明治維新にかけて逞しく生きた女傑たちがいる! 今回は、村山たかの波瀾万丈ヒストリーを追う!!
村山たか(1809~1876年)は彦根の寺の娘に生まれた。幼少より和歌、三味線、茶道、華道を学び、18歳で彦根藩主・井伊直亮の侍女となるが、20歳で京都に出て、祇園で芸妓となった。
金閣寺の僧に身請けされ、男児・帯刀を生んだ。その後、彦根に戻り、6歳下の井伊直弼と知り合い、愛人になる。直弼は部屋住みの身だったが、藩主の跡継ぎに決まっていた兄が1846年に急死したため、直弼が藩主を継ぐことになり、江戸藩邸に呼ばれた。
たかと直弼は別れざるを得なくなったが、今度は直弼の家来・長野主膳の妾となる。
1850年(嘉永3)に直弼は彦根藩主となり、幕政にも参加。世の中は、開国派や尊王攘夷派が入り乱れ争っていた。直弼は長野主膳に命じて、京都の志士たちの動向を探らせた。主膳の手足となって動いたのが、たかだったのである。その情報は直弼に送られ、安政の大獄の判断材料の一つとなった。
1862年に直弼が桜田門外で暗殺されると、主膳と、たかの息子・帯刀は反直弼派に捕まり、斬首。彼女は三条河原で柱に縛りつけられ、3日3晩飲まず食わずの晒し者に。その後、尼僧に助けられ、京都の金福寺で余生を送った。男のためなら危険をかえりみない、しぶとくて強い女性の手本だ。
【幕末女傑烈伝】坂本龍馬や大隈重信も頼りにした大浦慶
2015年NHK大河ドラマ「花燃ゆ」のヒロインで、吉田松陰の妹・杉文。文はいま、激動の時代をしたたかに生き抜いた女性として注目されているが、彼女の他にも、幕末から明治維新にかけて逞しく生きた女傑はいる! 今回は、大浦慶の波瀾万丈ヒストリーを追う!!
大浦慶(1828~1884年)は、長崎油屋町の油商の家に生まれた。老舗の商家だったが、1843年(天保14)、慶が15歳のとき、近辺の家500戸あまりが焼ける火事があり、慶の家も被害に遭う。慶は傾いた家業を再興させる決心をする。
翌年、長崎に蘭学の勉強に来ていた天草の庄屋の息子と結婚するが、この男が気に入らず、祝言の翌日には追い出してしまう。以後、死ぬまで独身を通す。
慶は1856年(安政3)から、イギリス人の貿易商を通じて日本茶の輸出を始めたところ、これが当たった。以後、10年間は大いに儲けた。
慶より7歳下の坂本龍馬が慶の屋敷を訪れ、300両の資金援助を頼んだこともある。慶は引き受けた。陸奥宗光、大隈重信、松方正義なども、慶の屋敷に居候して世話になったという。
【幕末女傑烈伝】大河ドラマ「花燃ゆ」の主人公・杉文
2015年NHK大河ドラマ「花燃ゆ」のヒロインで、吉田松陰の妹・杉文。文はいま、激動の時代をしたたかに生き抜いた女性として注目されているが、彼女の他にも、幕末から明治維新にかけて逞しく生きた女傑たちがいる! 今回は、杉文の波瀾万丈ヒストリーを追う!!
吉田松陰の妹・杉文。2015年NHK大河ドラマ「花燃ゆ」(主演:井上真央)のヒロインとしてもクローズアップされている文は、1843年(天保14年)、長州藩主・毛利家に仕える下級武士の家に、6人兄弟の4女として生まれた。
13歳上の兄が吉田松陰。松陰が松下村塾で講義を始めると、高杉晋作、伊藤博文、山県有朋など、のちに活躍する有能な人材が集まった。彼女は塾生たちの世話をして「女幹事」と呼ばれ、親しまれたのである。
そして、塾生のひとりが久坂玄瑞で、松陰は久坂の才能に惚れ込み、文との結婚を勧めた。文15歳、久坂18歳のときだ。
結婚した2人が落ち着いて暮らしたのは、新婚からわずか3カ月ほど。久坂は松陰が唱える尊王攘夷運動にのめり込み、京都や江戸などを飛び回った。
1859年(安政6年)に、兄の松陰が安政の大獄で斬首。5年後には夫の久坂が禁門の変で自決。文は22歳で未亡人となってしまう。その後、毛利家に奉公し、子供の教育係などを勤めた。
1883年(明治16年)、41歳の文は楫取素彦(55)と再婚した。文の姉・寿の夫だった人物で、姉が病死して再婚した形である。楫取は群馬県令(知事)で、のちに貴族院議員や男爵になっている。
文は華族夫人として夫を支えて過ごし、1921年(大正10年)に山口県で没した。そんな彼女はいま、幕末から明治維新に至る激動の時代をしたたかに生き抜いた女性として、注目を浴びている。
今年の大河ドラマ『花燃ゆ』はやっぱり「幕末版 花より男子」って印象……たぶん途中で脱落すると思います。。
1. 太田姫稲荷神社
御茶ノ水駅前で集合して、池田坂を下りて太田姫稲荷神社へ。今は小さな神社だが、もとは太田道灌が娘の天然痘の快癒を祈って京都の一口稲荷神社(いもあらいいなり)に願をかけて通じたことにより、江戸時代には天然痘よけの神社として大いに信仰を集めたそうだ。
日本でも天然痘は30年ほどの周期で大流行しており、古くは「もがさ」と呼ばれた。天然痘は飛沫感染する伝染病で死亡率は20~50%で、特効薬はない。運良く快癒できたとしても顔にあばたが残った(「痘瘡は器量定め はしかは命定め」と呼ばれた。幕末から明治にかけてあばたが残る有名人は吉田松陰、夏目漱石)。一口稲荷神社の「いもあらい」も、顔にできる瘡「いも」を洗う=快癒する、という祈りが語源らしい。
平安時代には藤原不比等の息子達で栄華を極めた四兄弟(武智麻呂・房前・宇合・麻呂)が天然痘でバタバタと亡くなっている(伝染病の知識がなかった当時、藤原家と対立したために一族ともども自死に追い込まれた長屋王の祟りとも囁かれた)。
太田姫稲荷神社は徳川時代を通じて痘瘡よけの神社として信仰を集めた(逆にいえば、疫学の知識がなかった当時は願掛け・祈願する以外に感染発病を防ぐことができなかった)。
2. 神田お玉が池・初代種痘所跡
江戸時代、西洋の学問知識は「蛮学」とされ、18世紀後半にイギリスでジェンナーが開発した種痘法は安政5年(1858)伊藤玄朴や大槻俊斎ら江戸の蘭学者たち82名が資金を出し合って「種痘所」を開設することでやっと認められた。初代種痘所は洋楽に理解のある幕臣川路聖謨《かわじよしあきら》(最後には勘定奉行、江戸無血開城の折に拳銃自殺した)。
ただ種痘所は半年後に火事で焼失。
種痘所は日本の近代医学の研究治療センターのはじまりで後に東大医学部に発展した医学所のルーツでもあるのだけど、私有地のビルの一角にはめられたプレートと碑にその姿を残すだけで、見つけにくいこともあり、ちょっと寂しい。
3. 三井記念病院
神田和泉町、幕末には津藩藤堂家の下屋敷があったところ。明治42年に三井財閥が下谷和泉橋通り(現・東京都千代田区神田和泉町)の東京帝国大学医科大学附属第二医院跡地に開院した。
4. 神田和泉町 種痘所跡
神田和泉町、三井病院のそばにある二代目種痘所、後に幕府医学所。伊東玄朴の後は大槻俊齊、緒方洪庵、松本良順が頭取を務めた。
種痘とは関係ないが、鳥羽伏見の戦いで敗れた旧幕府軍に加わっていた新選組の近藤勇と沖田総司が、船で品川に入港した後に神田泉町の医学所で治療を受けたことになっているので、ここで近藤は銃創の、沖田は結核の治療を受けたのだろう。神田川にほど近く、近藤たちは品川から舟でこちらに移動してきたと思われるし、近藤が幕臣として初めて登城したのもここから舟か馬で移動したのだろうな。
種痘所の開設には箕作阮甫はじめ82人の医学洋学者が関わった。私の好きな幕臣にして代官江川太郎左衛門(第36代英龍)は種痘普及のために自分の子供達に積極的に接種させた。岩本町の隣は小伝馬町で、小伝馬町の牢には蛮社の獄に連座した高野長英が入牢し、牢獄の火災に乗じて脱走し、全国を逃亡した。
……大河歴史マンガ『風雲児たち』ファンにはおなじみの面々の名前を挙げた。疱瘡のあばたの残る吉田松陰はじめ、みなもとキャラが脳内を駆け巡った楽しい半日ツアーでした。
北海道
箱館戦争再現、迫真の殺陣 五稜郭祭で維新行列
【函館】幕末の箱館戦争を伝える第45回箱館五稜郭祭(実行委主催)のメーンイベントの維新行列が18日、行われた。函館市中島町から五稜郭公園の約2キロをペリーや榎本武揚、土方歳三などに扮(ふん)した市民ら約600人が歩き、旧幕府軍と明治新政府軍の戦いを再現した模擬戦闘に、沿道の観客は盛んに拍手を送っていた。
本町では、大砲の音を合図に、両軍が箱館戦争の戦闘を再現。観客は、眼前で繰り広げられる迫真の殺陣や、クライマックスに土方が銃弾に倒れる場面を固唾(かたず)をのんで見守った。
一行は引き続き、五稜郭公園まで行進。箱館奉行所近くの特設ステージでは、榎本が五稜郭を開城した場面を再現し、祝砲を響かせて幕を閉じた。
行列には、16日に入港した米海軍イージスミサイル巡洋艦シャイローのクルーシュ・モリス艦長ら24人のほか、国の華幼稚園(梁川町)の園児約60人も参加し、沿道からの声援に手を振って応えていた。
市内港町の佐野正敏さん(62)は「毎年、孫2人と戦闘シーンを見に来ることを楽しみにしている。今年は行列の人数も多く、迫力があった」と話していた。(松嶋加奈)
白兵戦に観客沸く…五稜郭祭最終日に維新行列
第45回箱館五稜郭祭(協賛会主催)の最終日は18日、函館市中島町―五稜郭町間でメーンイベントの維新行列などが行われた。沿道に集まった観客が、函館の幕末の歴史を表現した総勢1100人のパレードや箱館戦争の白兵戦パフォーマンスを楽しんだ。
維新行列は、榎本武揚率いる旧幕府軍と新政府軍の衣装に身を包んだ市民らが出演。中島廉売で出発式が行われ、黒田清隆役を務めた中野豊実行委員長が「今年は五稜郭築造150年の節目を迎えた。元気にパレードしていこう」とあいさつし、出発した。
開陽丸など艦船を模した山車には、片岡格副市長や渡島総合振興局の宮内孝局長らも幕末の志士役となって”乗船”。千代台運動公園からは市内の吹奏楽部やマーチングバンド10組が音楽パレードに参加した。
本町の行啓通では、恒例の白兵戦パフォーマンスを披露。大砲が打ち鳴らされると、刀を持った出演者が一斉に格闘シーンを展開。前日の土方歳三コンテストで優勝した小林良紀さん扮(ふん)する土方も登場し、華麗な殺陣と壮絶な討ち死の場面を見せ、盛り上げた。
その後、五稜郭公園内で、無血開城のシーンを再現した開城セレモニーが行われ、榎本が黒田に「海律全書」を手渡すシーンなどが再現された。
両親とともに来場した札幌市の東生野さん(56)は「函館が歴史のあるまちだということをあらためて実感した。ずっと続けてほしい」と感激していた。
土方歳三コンテスト 迫真の演技…五稜郭祭開幕
戊辰戦争終結の地、五稜郭を舞台にした「五稜郭築造150年記念第45回箱館五稜郭祭」(同協賛会主催)が17日、開幕した。五稜郭タワーアトリウムで開かれた恒例の「土方歳三コンテスト全国大会」では、東京都練馬区の会社員小林良紀さん(38)が優勝を飾った。
同コンテストは27回目。参加者は男性8人、女性7人の計15人で、東京や千葉、愛知からの参加もあった。今年は出陣を前にした土方が市村鉄之助に写真を託し、戦場で官軍に撃たれるシーンを再現。正統派の演技で殺陣を決める人や、スマートフォンで写真を撮りながら登場して笑いを取るなど、それぞれが工夫を凝らした演技を披露した。
優勝の小林さんは一昨年が準優勝、昨年が3位で、3年目で栄冠をつかんだ。近藤勇らへの思いをセリフに盛り込み、刀や拳銃を用いた迫真の演技を披露。小林さんは「昨年まではギャグ路線だったので、今年は土方がどう戦いを挑んでいったのか演出面を考えた。パレードでは沿道の人に応えながら、土方の格好良さが出せれば」と話した。
準優勝の市内の准看護師丸山彩さん(21)は、官軍に撃たれ、あおむけに倒れ込んで客席を沸かせ、「土方の仲間を思いやる優しさや守るべきものへの思いを表現した」と話した。3位の箱館五稜郭祭賞は、時事ネタを盛り込んだ名古屋市の宮崎準也さん(47)が受賞した。
この日は同コンテストに先立ち、市内4カ所で碑前祭が行われ、箱館戦争の戦没者をしのんだ。18日は維新行列のパレードが行われ、小林さんと丸山さんも参加。午後1時に中島廉売通りをスタートし、行啓通では戦闘シーンの再現、午後3時ごろには五稜郭公園特設ステージで開城セレモニーがある。
戊辰戦争当時を再現する「箱館五稜郭祭」- 土方歳三になりきるコンテストも
北海道函館市の五稜郭で、戊辰戦争の舞台となった五稜郭にまつわる歴史を後世に伝える「箱館五稜郭祭」が開催される。期間は5月17日~18日。
同祭りは、日本が近代国家に移行する最後の戦い「戊辰戦争」の舞台となった「五稜郭」について、史実と合わせ歴史的遺産として長く後世まで伝えることを目的とし、昭和45年(1970)にはじまった。
45回目となる今回は、17日に「中島三郎助父子最後之地」、「土方歳三最期之地」、「碧血碑」、「箱館戦争供養塔」など箱館戦争ゆかりの地を巡る「碑前祭」を開催。また、函館の地で最期を迎えた新選組副長・土方歳三を演じる「第27回 土方歳三コンテスト全国大会」を、五稜郭タワー1階アトリウムで実施する。
18日の「維新行列・音楽パレード」では、戊辰戦争当時の旧幕府軍・官軍に扮した行列が町を練り歩く。行啓通りで戦闘シーンのパフォーマンスを見ることができるほか、五稜郭公園特設ステージで、五稜郭明け渡しを再現する「開城セレモニー」も行われるとのこと。
五稜郭150年 節目の祭典、にぎやかに開幕 碑前祭130人しのぶ
160年前のペリー来航から箱館戦争終結までの15年間の歴史を伝える「第45回箱館五稜郭祭」が17日、函館市内で開幕した。初日は同戦争の戦没者を追悼する碑前祭や記念式典、土方歳三コンテスト全国大会を開催。18日は維新行列と音楽パレードが行われる。ショーアップされる土方歳三最期の姿に心を痛める土方ファンもいるようです。戦闘場面を迫力をもって伝えることで歴史に関心を持ってもらうことも大事ですが、戦争によって多くの血が流れたという史実が後世に伝わるようにしなければいけませんね。
碑前祭は碧血碑(谷地頭町)など市内4カ所で実施。旧幕府の幕臣中島三郎助と2人の息子を供養する「中島三郎助父子最後之地」碑前(中島町)の碑前祭には、地元の中島町会や三郎助のひ孫で神奈川県海老名市在住の中島恒英(つねふさ)さん(69)、出身地の横須賀から訪れた18人を含む約130人が参加。榎本武揚と黒田清隆に扮(ふん)した実行委関係者が花を供え、中島三郎助父子追悼の祭文を読み上げた。
五稜郭タワーアトリウムで行われた記念式典では、観光客ら約400人を前に、実行委員長の中野豊・五稜郭タワー社長が「今年は五稜郭築造150年という節目の年。午前の碑前祭では地域に愛され続けられるよう祈ってきました」とあいさつした。
また、新選組副長土方歳三らしさを競うコンテストでは、東京都練馬区の会社員小林良紀さん(38)が優勝。準優勝に函館市の准看護師丸山彩さん(21)が選ばれ「昨年に続く挑戦なので、とてもうれしい。優勝するまで頑張りたい」と笑顔を見せた。このほか市内の保育園児が寸劇を披露した。
最終日の18日は、維新行列が午後1時、中島町の中島廉売通りをスタートし、行啓通りで榎本軍と新政府軍が戦闘を繰り広げるパフォーマンスを行う。中高生らによる音楽パレードは午後1時に千代台公園を出発し、五稜郭タワーに向かう。(田中雅章)
栃木
戦争の痕跡訪ね 戦後の平和知る
かつて「軍都」と呼ばれた割にあまり知られていない、宇都宮市内の戦争の痕跡を訪ねるバスツアーが、今年も今月17日に催される。戦争の記憶を風化させない狙いで、今回で30回目の節目。主催する市民団体「宇都宮平和祈念館をつくる会」では、積極的な参加を呼び掛けている。 (後藤慎一)東京
宇都宮市にはかつて旧陸軍の師団司令部や飛行場、中島飛行機宇都宮製作所など多くの軍関連施設が置かれた。米軍機の空襲で多くの犠牲者も出した。
「ピースバス」と名付けられたツアーは、一九八七年から年一~二回実施。「軍都」としての宇都宮の横顔はあまり知られていないため、参加者から「こんなところがあったとは」と驚きの声が上がることが多い。
昨年のツアーでは、旧陸軍宇都宮飛行場(清原飛行場)で通信員を務めた奈良県の男性(83)が七十年ぶりに訪問。往時をしのび「すっきりした」と感想を残したという。
今年は午前九時半、宇都宮市役所をスタート。市中心部の清住町通りを歩き、戊辰(ぼしん)戦争など江戸時代も含めた戦争の痕跡を見学する。
その後、市西部にある旧陸軍師団司令部跡、地下軍事工場跡、射撃訓練場跡などを探訪。それらが病院や運動公園などに姿を変えたことを知ることで、戦後の平和都市への変貌を実感する。
佐藤信明(しんめい)事務局長は「宇都宮の戦跡を後世に残したい。ギョーザとカクテルの観光だけではない宇都宮を分かってもらえれば」と話している。
だれでも参加可。定員四十人。資料代五百円が必要。希望者は十三日までに、はがきか電話、ファクスで同会に申し込む。宛先は〒320 0037 宇都宮市清住3の1の14。電話は028(625)3266、ファクスは028(627)4216。
ひの新選組まつり」で都市農業PR!」 東京都日野市 2014年5月17日
新選組副長の土方歳三や六番隊長の井上源三郎が生まれ育った東京都日野市で、第17回ひの新選組まつりが開かれた。]新選組ゆかりの日野発祥グルメ「焼きカレーパン」1200 個登場/東京
市内の農業者とJA東京みなみ職員は農民に扮(ふん)して、大八車に地元野菜や市内産の野菜苗を載せ、都市農業をPR。大勢の見物客から注目を浴びた。総勢約800人の「隊士」が当時の衣装に身を包んで練り歩く「新選組隊士パレード」もあり、全国各地から参加者が集まった。まつりは1998年に市制35周年と土方歳三没後135周年を記念して始まった。
東京都日野市で5月11日に開かれる「第17回ひの新選組まつり」で、日野市内のパン店6店が、オリジナルの創作“焼きカレーパン“を披露、販売する。焼きカレーパンは、日野市の新たなご当地グルメとして注目が集まりつつあり、関係者は広くアピールする機会にしようと意気込んでいる。エンターテインメント
「ひののめぐみ焼きカレーパン」は、トマトやカキなど市内の特産物を使用。障害者と農家がコラボレーションして創作した一品で、油で揚げずに焼いて調理するためヘルシーだという。2013年11月に行われた「ニッポン全国ご当地おやつランキング」で高い評価を受け、準グランプリを獲得した。
催しは、5月11日(日)午前10時から午後3時、同市日野本町のJCN日野ケーブルテレビ社屋隣の第17回ひの新選組まつり会場内で開催。市内6店が独自の工夫を凝らした「焼きカレーパン」を計1200個を販売予定で、一個120~200円で食べ比べできる。
『半沢』続編に興味なし!? NHK大河、三谷幸喜・堺雅人“最強”タッグ結成の舞台裏
「NHKとしては、予想外の発表になったそうです。『女性自身』(光文社)に直撃された三谷さんが、否定しませんでしたからね。それで急きょ、発表することになったそうです」(スポーツ紙記者)『組!』出演者のゲスト出演も期待できるかな?
13日、2016年のNHK大河ドラマの脚本を三谷幸喜が手掛け、その主演に堺雅人が内定したと一斉に報じられた。
「『自身』に記事が出ることが分かり、題材が戦国武将・真田幸村ということも、主演が堺さんであることも、すべて発表することにしたそうです。話題性抜群の組み合わせだけに、NHKとしては独自に発表したかったみたいですが」(同)
NHKの内情はともあれ、確かに今、一番数字が取れる俳優である堺を押さえられたのは大きい。
「三谷さんが脚本を担当することは年明けには決まっていたのですが、三谷さんは“当て書き”といって、先に役者を決めてからその役者をイメージしながら台本を書くので、早急に主演を決める必要がありました」(NHK関係者)
NHKとしても、ここのところ低迷する大河の起爆剤となることを期待しての三谷起用だけに、確実に視聴率が取れる俳優を望んだという。そんな両者の思惑が一致した俳優が、堺だったというわけだ。
堺は昨年の『半沢直樹』(TBS系)での活躍は言うまでもないが、04年に放送された三谷脚本のNHK大河ドラマ『新撰組!』に新撰組総長・山南敬助役で出演したことで、一気に知名度をアップさせた。
「堺さん演じる山南が切腹する回は、視聴者から“助命嘆願書”が局に届くくらい、盛り上がりましたからね。年末には、大河ドラマ史上初めて、その回だけが再放送されるということもありました。その『新撰組!』から4年後、宮崎あおいさん主演の『篤姫』でも、徳川13代将軍の徳川家定役で出演し、話題を呼びました。もちろん、主演である宮崎さんの好演もあったのですが、それまで幕末モノは視聴率が取れないとされてきた大河で前評判を覆し、平均視聴率24.5%を獲得。幕末モノとしては、過去最高を記録しました。それに堺さんの存在があったことは間違いありません。これも、NHKとしては史上初めて、放送中に再放送するという、異例の人気を博しました」(芸能事務所関係者)
実は、『新撰組!』はNHK大河史上初めて続編が作られた作品でもある。
「NHKとしては、こうした“史上初”といった作品の中心に常に堺さんがいたことから、“いつか彼主演で大河を”と思っていたそうです。それで今回、堺さんの名前が挙がったというわけです」(前出・NHK関係者)
通常、大河の撮影は前年の夏から始まる。つまり、来年15年の夏から、出演者は大河に付きっきりということになる。となると、気になるのは『半沢直樹』の続編なのだが……。
「堺さん自身、続編にはあまり興味がないみたいですよ。事務所としては、“いつかできれば”というスタンスのようです」(前出・芸能事務所関係者)
“三谷組”の俳優、女優は人気者ばかり。8年ぶりに大河に主演としてカムバックする堺を中心に、豪華俳優陣による戦国絵巻が展開されそうだ。
北海道
五稜郭築造150年祭開幕
特別史跡「五稜郭」築造150年を記念するイベントが26日、開幕した。箱館奉行所前でオープニングセレモニーと箱館戦争の激戦の様子を再現する「箱館戦争抜刀隊」があり、熱のこもった演技を披露。集まった観光客らから拍手喝采を浴びた。来年2月までさまざまな催しを繰り広げ、観光客や市民を楽しませる。
市内の団体、企業でつくる実行委の主催。オープニングセレモニーで小笠原勇人実行委員長が「五稜郭築造150年は歴史的にもまちづくりの観点からも大きな意義がある。イベントを観光の目玉にし、五稜郭を全国、世界へ発信する機会にしたい」と述べた。
「抜刀隊」に出演したのは箱館五稜郭祭で殺陣を担当する箱館稜雲社と函館野外劇の殺陣チームのメンバー約20人。軍服に身を包み、両軍入り乱れた白兵戦を展開。銃撃シーンや土方歳三の最後、旧幕府軍の降伏などの見せ場で観客を楽しませた。
神奈川県から訪れた樋渡敏雄さん(66)と頴子(えいこ)さんの夫婦は「タイミングよくイベントを見ることができてよかった。演技は迫力満点、面白かった」と満足そうに話した。ゴールデンウイーク期間中は27、29日、5月3~5日も午前11時と午後2時からの2回披露する。
また、幕末の衣装を着て観光客をもてなす「幕末見廻隊」もあり、好評だった。10月19日まで土、日、祝日に行う。
幕末の戦い再現 北海道・五稜郭で築造150年祭
【函館】箱館戦争の舞台となった函館市の五稜郭の築造150年祭(実行委主催)が26日、開幕した。
箱館戦争当時の黒い軍服などの衣装を身に着けた市民ボランティアが、五稜郭公園内で記念写真の撮影や観光案内の「おもてなし」をしたほか、旧幕府軍と新政府軍に分かれての戦闘シーンを再現し、観光客を喜ばせた。長野県松本市から訪れた宮沢隆昭さん(48)は「幕末の雰囲気が演出されていて、とても楽しめました」と満足そうだった。
来年2月28日まで。市民ボランティアによる「おもてなし」は10月19日までの週末や祝日に行われ、戦闘シーンはゴールデンウイーク期間中を中心に10月まで計18日間、披露される。<北海道新聞4月26日夕刊掲載>
函館ゆかりの偉人、楽しく紹介 円柱の掲示塔、市内に30基設置
【函館】26日に開幕する五稜郭築造150年祭に合わせ、幕末の函館ゆかりの人物を紹介する円柱の掲示塔「ヒストリア ハコダディ」が函館市内17カ所に計30基設置され、市民や観光客の注目を集めている。
掲示塔は、民間企業などでつくる150年祭の実行委が制作。実行委事務局長の中野晋・五稜郭タワー常務が、ドイツのイベントから発想を得て2月末から設置を進めた。強化プラスチックや防水加工の紙製で直径80センチ、高さ2・5メートル。当時のモノクロ写真を掲示し、解説文が読めるようになっている。
このうち、JR函館駅構内の掲示塔は、新選組副長土方歳三を紹介。函館出身のロックバンドGLAYが昨年、野外ライブを行った緑の島には、同志社大を創設した新島襄らを説明する3基が並んだ。
市内元町のペリー広場で、ペリー提督の掲示塔解説を読んでいた市内末広町の会社員村上進さん(66)は「観光の名物になりそう。説明が詳しくて市民にも参考になる」と話していた。
実行委は、30基の設置場所が分かる案内地図も作製。市内の観光案内所などで近く配布を始める予定。中野事務局長は「函館の歴史を作った大勢の人物を知る手がかりにしてほしい」と話している。掲示塔の設置は11月3日まで。(内山岳志)
函館・五稜郭築造150年 あすから「祭り」開幕 6月にギネス挑戦イベントも
【函館】五稜郭築造150年祭が26日、五稜郭で来年2月28日までの日程で開幕する。10月19日までの週末や祝日には、幕末期の衣装を着た「幕末見廻(みまわり)隊」が観光客をもてなし、「箱館戦争抜刀隊」が戦闘シーンを再現するほか、築造記念日の6月15日には、市民ら1500人が手をつなぎ人文字で「150」を表現、ギネス世界記録更新を目指す記念イベントも開催される。
見廻隊は土日と祝日の57日間、午前10時から午後3時まで登場。道案内をしたり、記念撮影に応じたりして、観光客にサービスする。抜刀隊はゴールデンウイーク期間中の土日、祝日を中心に18日間、午前11時と午後2時の2回、旧幕府脱走軍と新政府軍に分かれて殺陣などを披露する。
見廻隊が出ている日は、箱館奉行所の中央にそびえる太鼓櫓(やぐら)で午前10時から午後3時まで1時間ごとに計6回、時報の太鼓を打ち鳴らす。26日は午前11時から小笠原勇人実行委会長のあいさつなど簡単な開会式が予定されている。
市民1500人による人文字は6月15日の記念イベントの目玉。郭内の広場を会場に、隣の人の手首を握って人の鎖をつくり、「150」を表現する。
実行委によると、これまでのギネス世界記録は、2年前に群馬県の東洋大板倉キャンパスで学生たちによって樹立された1026人。当日はギネスワールドレコーズの公式認定員を招く予定で、1500人が実現すれば、ギネス記録更新は確実だ。
記念イベントではこのほか、幕末コスプレフェスティバルや江差追分など道南の伝統芸能のステージ、道南各地のご当地グルメを提供するコーナーを予定している。(大内聡顕)
江差・開陽丸 12年ぶり化粧直し マストや煙突を塗装
【江差】幕末期、江差沖に沈んだ旧幕府軍の軍艦「開陽丸」を実寸大に復元した施設「開陽丸記念館」(姥神町)で、マストなどの塗装が行われている。観光シーズンが本格化する前の12年ぶりの化粧直しで、今月下旬までに完了させ、観光客を迎える。
記念館は全長73メートル、幅13メートルの船形施設で、内部には海底から引き上げた開陽丸の遺物などを展示している。1990年にオープンし、2002年に全体の塗装を直しているが、今回は白色のマスト3本と煙突のさびが目立ってきたため、きれいにすることにした。
高さ35~45メートルのマストの下の方の部分と、同6メートルの煙突全体が対象。さびを落としてからさび止めを塗り、白色ペンキで仕上げている。補修費用は約300万円。施設を運営する開陽丸青少年センターの須藤公徳館長は「装いを新たにして、多くの観光客を迎え入れたい」と話している。施設は10月末まで無休、11、12月は月曜と祝日の翌日が休館。入館料は大人500円、小中学・高校生250円。(山田一輝)
「榎本武揚の書」寄贈のお礼へ墓参り 江差の石橋さん、25日に岩手入り
【江差】箱館戦争当時に江差沖で沈没した旧幕府軍の軍艦・開陽丸の発掘調査に尽力した、元江差町教育長の石橋藤雄さん(89)が25日、岩手県陸前高田市に入り、活動を支えた恩人の墓前に手を合わせる。約40年前、石橋教育長宛てに「何かに役立ててもらえれば」と榎本武揚の書を寄贈した人物で、石橋さんは「じかに会ってお礼したいとずっと思っていた。書を大事に持っていた理由や意味合いを確かめたい」としている。
書(縦1・4㍍×幅31・5㌢)を寄贈したのは、岩渕としみさん。1976年8月に4枚の書を江差に贈った。同じ文で1枚には印が押してあり、残りの3枚は下書きの可能性が高い。
印のある書は、江差の開陽丸記念館で展示中だが、これまで脚光を浴びることはなかったという。
石橋さんによると、この書は榎本武揚が仙台や石巻に約50日間滞在したときにしたためたものと分析。「奥羽越列藩同盟の結束が崩れ、頼りの仙台藩も和平論に傾きかけるなど徳川家の再興を願っていた榎本の意に反する時代の流れや、悩みの心情を表現したものに違いない。自分の行く末を予感してしたためたのでは」とみる。
寄贈当時、江差での発掘事業が全国ニュースだった。石橋さんは「毎日発掘事業に追われて、礼状を出したつもりだが、忙しさを理由にしっかりとしたお礼ができていなかった。こればかりが心残りだった」という。
そして2011年、東日本大震災が発生。連日、陸前高田市の報道に「あのおばあちゃんが心配だ…」と市役所に電話を入れた。岩渕さんは大震災前に亡くなっていたことが分かった。その後親族の情報も把握し、「どうしても会ってお礼を伝えたい」と岩渕さんの寄贈を紹介している石橋さんの著書を関係機関に贈るなどし、今年に入り訪問の段取りが一気についた。
石橋さんは「岩渕さんのお墓参りと大震災の被災者への供養などもしっかりしてきたい。江差のようかんを持っていく」と話している。
27日には東京で開陽丸子孫の会(榎本隆充会長)総会があり、石橋さんも出席して書の意味合いの解明に関係者の協力を呼び掛ける。
提供 - 函館新聞社
箱館戦争の激闘 ご覧あれ 五稜郭築造150年祭26日開幕
26日に開幕する「五稜郭築造150年祭」(実行委主催)の中の催しのひとつ「箱館抜刀隊」の総練習が20日、箱館奉行所前で行われた。箱館戦争の激闘の様子を再現、披露するというもので、この日は本番同様、衣装を身につけて練習に臨んだ。
抜刀隊は五稜郭築造150年祭のオープニングを飾る催しで、10月まで全18日間の予定。26日を皮切りにゴールデンウィーク期間は27、29日、5月3~5日に行う。
出演するのは箱館五稜郭祭で殺陣を担当する箱館稜雲社と函館野外劇の殺陣チームのメンバー。総練習には約20人が参加し、白兵戦の殺陣や動きなどを確認した。五稜郭を訪れていた観光客らは迫真の演技を興味深そうに見つめ、拍手を送っていた。
土方役を務める箱館稜雲社の佐藤竜也さん(55)は「観光客に喜んでもらえるようなパフォーマンスを披露したい。市民、特に若い人たちに五稜郭150年の歴史を伝えたい」と話した。
時間は午前11時から午後2時からの2回。ほかにも幕末の衣装を着たスタッフが観光客をもてなす「幕末見廻隊」なども予定している。
あっ榎本だ、斐三郎だ 五稜郭150年祭実行委、箱館奉行所前にも掲示塔
【函館】五稜郭築造150年祭実行委は12日、円柱状の掲示塔「ヒストリアハコダディ」を五稜郭内の箱館奉行所前に設置した。幕末から明治初期の五稜郭ゆかりの人物を描いた高さ2・5メートル、直径80センチの柱が並び、市民や観光客らを圧倒した。
登場したのは、蝦夷(えぞ)共和国を設立した榎本武揚や江戸時代末期に五稜郭を設計した武田斐三郎などを紹介した6基。硬質プラスチック製の筒に印刷したシートを貼り、中に270キロの重りを入れた。実行委の野寺正樹さんは「目を引く塔の存在で、函館市民にも歴史ある五稜郭を持つ函館というマチの良さを再認識してもらいたい」と話す。
これとは別に1基の掲示塔は2月28日に五稜郭タワー内に設置済み。五稜郭150年祭初日の今月26日までに、計30基が置かれ、来年2月末まで続ける予定。終了後は「北海道新幹線開業仕様に変えるなど函館のPRに一役買いたい」と活用も検討している。(野村佳南)
福島
平成26年6月14日に会津米沢街道ウォーク 5月23日まで参加者募集
「会津米沢街道歴史ウォーク」は平成26年6月14日に北塩原村活性化センター集合で行われる。23日まで参加者を受け付けている。
実行委員会と福島県北塩原村の主催、北塩原村教委、福島民報社などの後援。新島八重と新島襄が歩いた「会津米沢街道」や新選組の土方歳三副長らが集結したといわれる旧大塩村などを歩く。5キロ、10キロ、15キロの3コースを用意した。ゴール後にはステージイベントや抽選会なども開かれる。定員は各コース合わせて500人で参加料は1000円。
申し込みは村教委 電話0241(23)5236へ。
◇ ◇
北塩原村の佐藤信寛教育長と武藤聖文教育課副主査、菊地あゆみ商工観光課主事は30日、福島民報社を訪れ、裏磐梯春まつりと会津米沢街道歴史ウォークをPRした。
(2014/05/01 10:28カテゴリー:歴史・伝統)
「會津十楽」に来らんしょ 若松で400年前の自由市を再現
ゴールデンウイーク後半の4連休が3日、始まった。県内有数の観光地・会津若松市は昨年、大河ドラマ効果で大きな盛り上がりを見せたが、風評はぬぐえず今年に入り観光客は昨年を下回る。「全国が注目するようなイベントを」。大型観光企画「デスティネーションキャンペーン(DC)」のプレDCに合わせて同市の経営者が立ち上がり、会津が華やいだ約400年前の「南蛮文化」を紹介するイベント「會津十楽(じゅうらく)」を企画。同日から町なかで繰り広げ、会津観光の復活につなげる。
「会津と言えば幕末の歴史が注目されがちだが魅力はもっとある。会津の新たな一面を紹介したい」。事業を主催するサムライシティプロジェクト実行委員長で、同市の不動産賃貸業岸敏恵さん(43)は、会津に南蛮文化を取り入れた武将蒲生氏郷が着用した甲冑(かっちゅう)に似せた衣装を身に着け、外国人をはじめ観光客一人一人に会津の魅力を紹介するため会場を駆け回った。
実行委は会津青年会議所OB、OGからなる40~50代の地元経営者が中心となって2012(平成24)年に組織。東京電力福島第1原発事故の影響が色濃く残る中、「会津の文化や武士道精神が注目されるイベントを手掛けよう」と始まった。戊辰戦争、白虎隊に代表される幕末以外からテーマを探し、南蛮文化で華やいだ約400年前の會津十楽にたどり着いた。
「400年前の雰囲気づくりと出店企業の協力依頼に苦労した。それだけに昨年の結果は悔しい」。試行錯誤を繰り返しながら実行委は昨年9月、鶴ケ城で會津十楽を初開催したが、台風で3日間のうち2日目以降を中止せざるを得なかった。しかし、地域振興の思いは途切れず、今回の開催につなげ、プレDCに合わせ会場を町なかに移した。
「會津十楽をきっかけに観光客も市民も会津が良い町だと知ってもらえればいい。それが観光復活や地域振興につながっていく」と岸さんは熱い思いを語った。
白虎隊士しのび剣舞奉納 若松・飯盛山で「春季祭典」
戊辰戦争で散った会津藩戦死者を慰霊し、藩士の功績を顕彰している会津弔霊義(ちょうれいぎ)会(芳賀公平理事長)は24日、会津若松市の飯盛山で白虎隊士墓前春季祭典を行い、郷土のため若い命を犠牲にした少年をしのんだ。
会員や白虎隊士遺族、関係者ら約200人が参列。芳賀理事長が「主君と藩のために命を捨てた少年たちの行動は会津士魂の象徴。時代は変わるが白虎隊は後世に残していかなければならない」と祭文を読み上げた。芳賀理事長、室井照平市長、戸川稔朗市議会議長らが玉串をささげた。
剣舞奉納では、会津高剣舞委員会(村岡亜美委員長)20人による剣舞が披露。白虎隊と同世代の男子生徒のりりしい表情と機敏な動きに、観客が見入っていた。
水戸藩の志士しのぶ 殉難者恩光碑保存会が慰霊式
戊辰戦争の鶴ケ城籠城戦で、会津藩士とともに戦った水戸藩諸生党の志士をしのぶ団体「水戸殉難者恩光碑保存会」は21日、福島県会津若松市の白虎隊記念館敷地内にある諸生党鎮魂碑前で慰霊式を行った。
「諸生党」は、尊皇攘夷(じょうい)派「天狗(てんぐ)党」と藩内で激しい抗争を繰り広げた保守派で、北陸戦争でも会津藩や長岡藩と奮戦したという。
慰霊式は、平成12年5月に鎮魂碑が建立されてから同会が定期的に行っている。今回は4年ぶりの来県で、約30人が訪れた。
小雨が降る中、川上有文会長が追悼の辞を読み上げ、関係者が花を供えて供養した。本県からは早川広中白虎隊記念館長、畑敬之助秋月悌次郎顕彰会長、坂内実会津史談会長、野口信一会津歴史考房主宰らも出席した。
「八十里越」再び 新潟につながる古道を只見町が整備へ
新潟・福島豪雨災害からの復興を目指す福島県只見町は、町内から新潟県につながる国内有数の長さ(約32キロ)の峠道「八十里越」を調査・補修して「復活」させ、歴史と自然の名所として活用する。江戸時代などに両県の交易を支えた「古道」とされる。ブナの天然林を散策できる区間でもあり、今年登録を予定するエコパークの目玉の一つにする。
町が調査、整備する「古道」は、江戸時代の天保14(1843)年に幕府が改修し、明治初期まで使われていた。しかし、明治14年に「中道」、同27年に「新道」が整備されて以降、一部を登山道に利用する以外は人の往来が途絶え、「幻の道」となっていた。20年ほど前に存在が再確認された。現在は通れない状態で、町が活用を検討していた。
「古道」の詳細な調査は、町が平成26年度当初予算で確保した300万円を使い、今春から始める。町教委の担当者や有識者らが草木が生い茂る道を調べ、歴史上貴重な石橋跡や石垣跡、ほこらや排水路などの現状を確認する。豪雨災害による土砂崩れなど道が途切れている部分も点検する。調査後は危険な部分の補修などを検討し、安全に通行しながら史跡を見学できるようにする。ただ、保護が必要な国有林などもあり、補修地点は国、県と慎重に協議する。
「古道」は歴史と自然の愛好家から整備を求める声があった。会津藩とゆかりがあり、戊辰戦争で新潟県から峠を抜けて只見町で死去した長岡藩家老の河井継之助が「八十里 腰抜け武士の 越す峠」と自嘲する句を詠んだエピソードがある。
また、今夏にユネスコの制度「エコパーク」に登録される予定の町内の中で、八十里越周辺のブナ林などは原生に近く、評価が高いという。町は歴史ファンや観光客が古道を歩きながら只見の魅力を知り、新潟県側まで歩く「ロングトレイル」の開催も視野に入れる。
町内は若者の減少や高齢化に加え、豪雨被害からの復興の課題もある。斎藤修一町教育長は「地域の歴史に光を当てることで町民の郷土愛を育みたい。教育にも活用することでエコパークを象徴する場所の一つになるはず」と話し、10年後ごろを目標に国指定史跡の登録を目指す考えだ。
東京
新選組ゆかりの日野発祥グルメ「焼きカレーパン」1200 個登場/東京
東京都日野市で5月11日に開かれる「第17回ひの新選組まつり」で、日野市内のパン店6店が、オリジナルの創作“焼きカレーパン“を披露、販売する。焼きカレーパンは、日野市の新たなご当地グルメとして注目が集まりつつあり、関係者は広くアピールする機会にしようと意気込んでいる。
「ひののめぐみ焼きカレーパン」は、トマトやカキなど市内の特産物を使用。障害者と農家がコラボレーションして創作した一品で、油で揚げずに焼いて調理するためヘルシーだという。2013年11月に行われた「ニッポン全国ご当地おやつランキング」で高い評価を受け、準グランプリを獲得した。
催しは、5月11日(日)午前10時から午後3時、同市日野本町のJCN日野ケーブルテレビ社屋隣の第17回ひの新選組まつり会場内で開催。市内6店が独自の工夫を凝らした「焼きカレーパン」を計1200個を販売予定で、一個120~200円で食べ比べできる。
日野の味をPR 焼きカレーパン 食べ比べてみて 来月の「新選組まつり」で
五月十、十一日に日野市内で開かれる「第十七回ひの新選組まつり」で、来場者に地元グルメを味わってもらおうと、日野生まれの「焼きカレーパン」が登場する。市内のパン店が自慢の逸品を出し、食べ比べを楽しめる。関係者は知名度がさらに向上し、商業活性化につながることを期待する。 (小松田健一)
焼きカレーパンは、日野市で障害者施設の仕事開拓に取り組んでいる「日野わーく・わーく」(程久保)が考案。市内農家から提供された地元産トマトと柿を使い、知的障害者施設「工房夢ふうせん」(旭が丘二)が調理した。
柿が辛みを抑えて独特の食感を出し、油で揚げずオーブンで焼くため低カロリーも売り物。昨年十一月に池袋で開かれた「ニッポン全国ご当地おやつランキング」に東京代表として出場、準グランプリを獲得した。
全国の強豪を抑えての上位入賞は大きな反響を呼んだ。これを機に市や市商工会は、地元グルメとしてさらに盛り上げようと、市最大規模のイベントである新選組まつりへの出品を市内のパン店へ呼び掛け、六店舗が参加を決めた。
当初は共通レシピとして日野市で生産された野菜の使用を条件にしようとしたが、春先は収穫される野菜が少ないため、揚げずに焼き、一個の価格は百二十~二百円にすることだけを求める。
「元祖」である日野わーく・わーくや、工房夢ふうせんも参加する。わーく・わーくの小島一明さん(38)は「地域活性化に貢献する目標ができ、障害のある人たちが働く励みにもなる」と話す。
市産業振興課の小松利夫さん(45)は「農業、商業、観光関係者が一体となって『日野ブランド』として育てていきたい」と熱意がこもる。
出品はまつり二日目の十一日午前十時から。甲州街道沿いの日野ケーブルテレビ(日野本町四)隣にブースを設け、計千二百個を販売する予定だ。
問い合わせは同課=電話042(585)1111、内線3440=へ。
千葉
江戸時代、東京湾で迫力のクジラ漁? 勝山で200年以上続いた分業制
江戸前といえば穴子、アサリ。アジやコハダもいける。しかし、江戸の昔、東京湾でクジラが潮を吹いていたのは知られていない。
体長10メートルのツチクジラの漁で栄えたのは千葉県鋸南町勝山漁港である。連休の谷間。まずは鋸南町商工会を訪ねた。
「クジラは食文化といいますが、季節のものでおいしいから食べるんです」
経営指導員主査の伊藤聖二さんは同県袖ケ浦市出身で、10年ほど前に鋸南に来て初めてクジラを食べた。夏場は冷凍でない商品が出回るので煮るか揚げてごちそうにするという。
鋸南町は鋸山の南にある。クジラが回遊していた理由は海底の地形にある。鋸山や周囲の海岸線の切り立った崖の下には太古の昔にできた水深500メートル以上の海底谷が続く。
「鯨道」。クジラが黒潮に乗って太平洋から餌を求めてやってくる海底谷の通り道をこう呼んだ。
携帯電話も無線もない時代。クジラの動きをどう伝えたのか。
勝山漁港を臨む大黒山(標高76メートル)に登った。近くをトビが舞う展望台からは大(たい)房(ぶさ)岬(同県南房総市)、洲崎(同県館山市)が見えた。「山見方」と呼ばれた見張り役がのろしをみて船に旗で様子を伝えた。
浮島付近で潮を吹くのを静かに待ち構え、6メートルの銛で突く。麻縄をつけて疲れさせ、海に飛び込んで太刀で仕留める。口を縄で縛り、船で港に運ぶ。その様子が万祝(まいわい)と呼ばれる丈の長いはんてんのような郷土衣装の背に描かれている。
世襲による500人ほどの分業制で漁は行われた。獲ったあとは「出刃組」が解体。元締めが油や肥料をとるための骨や尾を買い取り、肉は配分された。「江戸時代には他にない」仕組み。明暦元(1655)年に確立したのが房総捕鯨の祖、醍醐新兵衛である。代々、新兵衛を名乗り、初代の墓は大黒山にある。
〈いさなとる 安房の浜辺は魚篇に 京という字の 都なるらん〉
「いさな」は勇魚と書き、クジラの別名。危険を伴う代わりにもうけも大きく、墓の隣にある捕鯨繁栄の碑には文化2(1805)年に詠まれた歌が刻まれている。漁港の通りの1つは「いさな通り」と名付けられている。
醍醐組が組織化されて200年以上たった幕末。捕鯨船の寄港地を求めてペリー提督が来航したが、米国の乱獲でクジラは獲れなくなった。明治4(1871)年、醍醐組は解散する。調査捕鯨の対象外である小型捕鯨は南房総市和田町で今も続けられている。
だが、元祖であるはずの「勝山の捕鯨」は忘れられる寸前だった。漁を祝った「鯨唄」と大正時代に作られた「勝山小唄」。勝山港通り商店会が修復してCDにしたのは平成21年だ。これを知ることができたのは人情のおかげだった。
「まちかど博物館」は休業中の薬店の棚に漁の道具などを展示している。そこの女性に化粧品店経営の松岡弘子さんを紹介された。地域活性化へ向けた女性グループ「ドリームK」のメンバーで港通りおかみさん会会長だ。
「鯨唄が消えてしまう。何とか残せないかと思いました。いろいろな問題があって鯨は難しいですが」
ドリームKは捕鯨を伝える活動の1つとして紙芝居を作った。2月には勝山小(現・鋸南小)の3年生に授業をして好評だった。
最後に訪ねたのは鯨塚。カエルの大合唱のなか、田んぼの脇を行く。たとえ殺生しても恵みに感謝し、翌年の豊漁を願う-。出刃組が石碑を1年に1基建てた。供養塔だ。残っているのは52基。こうした自然との向き合い方は日本人の心情を示す証しである。そこに供え物はある。ただ、手入れは行き届いていない。
「地元のことを知らない大人と子供がいっぱい。地元に目を向けない…」
松岡さんの言葉がこだました。 (羽成哲郎)
神奈川
横須賀・浦賀に70mの坂本龍馬立像を建立! 幕末・維新の志士群像&歴史記念館も
坂本龍馬をはじめとする幕末・維新の志士たちの功績や理念を広める活動を行う日本龍馬会が2日、神奈川・横須賀の浦賀(愛宕山)に高さ70mの「坂本龍馬立像」を建立し、「幕末・維新の志士群像」および「幕末・維新の歴史記念館」も建設することを発表した。
【もっとほかの写真をみる】
日本龍馬会は、現在、日本や世界を取り巻く情勢が混迷を深めているとし、幕末・維新の志士たちの歴史観、理念、行動を学び、具現化して、改革を断行する必要があると表明。
現状打開を目指し、勇気ある行動を実行するための精神的シンボルとして、黒船来航の地・浦賀の愛宕山に「坂本龍馬立像」「幕末・維新の志士群像」「幕末・維新の歴史記念館」を建設することを決意した。さらに、その研究、実践行動組織の「平成龍馬維新塾・平成龍馬海援隊」を創立する。
なお、横須賀市の「建設開発許認可」が得られ次第、建設に着手する予定で、工期は2016年4月(開発許認可の取得後)~2019年3月を予定している。
鳥取
幕末・維新期に活躍の河田佐久馬描いた歴史漫画、倉吉で原画展 鳥取
鳥取藩の尊王攘夷派の中核として幕末から維新期に活躍した河田佐久馬(1828~97年)を描いた歴史漫画「河田佐久馬 倉吉淀屋と因幡二十士」の原画展が、鳥取県倉吉市の倉吉淀屋で開かれている。
河田は尊攘派藩士と、穏健派重臣を斬殺する本圀寺(ほんこくじ)事件を起こす。その後、坂本龍馬の蝦夷地開拓計画に関わり、戊辰戦争で功をあげるなど、激動期の日本を駆け抜けた。鳥取出身の漫画家、藤原芳秀さんが、豪商淀屋の陰の倒幕支援などの伏線とともに河田の生涯を漫画化。「コミック乱TWINS」(リイド社)4月号に掲載された。
淀屋ゆかりで漫画にも登場する江戸期の町屋、倉吉淀屋での原画展には、約30枚を展示。手描きの迫力ある線で描かれた登場人物たちが歴史ある町屋で息づき、観光客ら多くの人が興味深く見入っていた。同展は11日まで。
山口
大河ドラマ「花燃ゆ」で観光客誘致 ゆかりの防府、萩など3市連携 山口
■準主役「楫取素彦(かとり・もとひこ)」って誰? 知名度アップが鍵
井上真央さんが吉田松陰の妹、文(ふみ)役を演じる来年のNHK大河ドラマ「花燃ゆ」。文役以外はこれまでに、後に文と夫婦となる準主役の楫取素彦役の大沢たかおさんだけが決定している。楫取は松陰投獄後に松下村塾を任され、明治維新後は群馬県などの地方振興に尽力した人物だが、歴史ファンでも楫取を知る人は少ない。ゆかりの山口県萩市と防府市、そして前橋市の3市は大河ドラマを観光客誘致につなげようと、連携して楫取の知名度アップを目指す。(将口泰浩)
◇
楫取は江戸後期の文政12(1829)年、藩医松島家の次男として萩で生まれ、儒家、小田村家の養子となって小田村伊之助と名乗った。後に幕府からの追及を逃れるため、藩命で「楫取」に改名した。
藩校明倫館で学ぶ中で松陰と親交を深め、江戸に出て佐藤一斎らに師事し、萩に戻った後は明倫館で後進を指導した。
その人柄を松陰は「正直者すぎて困る」「気力・詩力・酒力は自分より上」と評した。
楫取は松陰の妹、寿(次女)と結婚する。安政の大獄によって松蔭が江戸に送られるときには、松下村塾を託されるほど信頼が厚かった。藩主の毛利敬親(たかちか)の側近として薩長同盟を推進し、維新を迎える。
新政府に出仕し、伊藤博文や薩摩の大久保利通らと同じ参与職に就くが、藩主の頼みで毛利邸建設推進のため三田尻管事役(市長)として防府に居を移した。
その後、群馬県の初代県令(現在の県知事)に任じられる。楫取は在任中に県庁を高崎から前橋に移し、さらに蚕糸業の発展、教育の振興など群馬の近代化に寄与した。
このころ、楫取の私生活では明治14(1881)年に妻の寿が43歳で亡くなり、16年に寿の妹、文(美和子)と再婚した。文は松陰門下の俊英、久坂玄瑞と結婚していたが、久坂は幕末の元治元(1864)年、禁門の変に敗れ、自刃していたのだ。
萩から始まり、群馬、防府と巡り、松陰の志を受け継ぎ、生き抜いた楫取。文との約30年間の結婚生活を経て、大正元(1912)年に防府で没する。享年84だった。
これほどの人物であるが、なぜか楫取の存在はほとんど知られていない。
大河ドラマで楫取を演じる大沢さんも「お話を頂いたときに初めてその存在を知りました。幕末に登場した多くの英雄の陰には、小田村伊之助(楫取)のように信じられないほどの力で英雄たちを支え、共に激動の時代を生きた人たちがいたということを知り、歴史とはその時代に生きるすべての人たちによって作られるものなのだと強く感じました」とコメントしたほどだった。
だが、楫取ゆかりの地にとって、大河ドラマ効果を最大限に生かすためにも、楫取の知名度向上が欠かせない。
夫婦が眠る墓碑が残る山口県防府市は4月に「花燃ゆ推進室」を新設し、早速、楫取の知名度アップの作戦を練っている。
楫取邸宅跡に石碑や看板を設置、墓碑がある大楽寺の近くに大型バス待機場も設けた。防府駅前の商業施設ルルサスに「ドラマ館」をオープンする。
松浦正人市長は「以前の大河『毛利元就』の時は観光振興策が後手に回りました。今回は先手先手で対応し、観光客を増やしたい」と述べる。
明倫館や松下村塾があった萩市は、昭和52(1977)年の「花神」以来の大河の舞台となる。昨年7月の集中豪雨災害によって、平成25年の観光客数が前年比6・1%減、宿泊客数も同6・7%減と厳しい状況だけに、花燃ゆへの期待は大きい。
萩市は4月、明倫館跡地に建つ明倫小学校の旧校舎に、市観光課や観光協会を移した。ここを拠点に「ドラマ館」などを整備する。大河ドラマ推進室の松原功氏は「平成30年の明治維新150年に向け、ホップ・ステップ・ジャンプで弾みをつけたい」と期待を込めた。
一方、楫取を「前橋の恩人」と位置づける前橋市。同市は広報紙で「初代群馬県令、楫取素彦の妻、文が主人公です」と紹介する。こちらも今回の大河を前橋が脚光を浴びる機会ととらえるが、知名度不足が悩みの種だ。
「龍馬伝」(平成22年)が放映された高知県では、県外からの観光客が4割近くも増加した。経済効果は535億円とする試算もある。
大河を観光振興の起爆剤とするには、放送前に少しでも楫取素彦の知名度をアップさせる必要がある。防府市おもてなし観光課の杉江純一課長補佐は「来年を観光客誘致の好機ととらえ、萩や前橋と連携を取りながらアピールしていきたい」と語った。
エンターテインメント
るろうに剣心」志々雄真実描く前後編読切、SQ.8月号より
和月伸宏「るろうに剣心 -明治剣客浪漫譚-」の新作読み切りが、7月発売のジャンプスクエア8月号(集英社)より前後編で掲載される。これは本日5月2日発売の同誌6月号にて告知されたもの。
【この記事の関連画像をもっと見る】
「るろうに剣心」は、幕末に「人斬り抜刀斎」として恐れられた剣客・緋村剣心が宿敵との戦いを通じ、生き方を模索していく剣劇マンガ。同作を原作にした実写映画「るろうに剣心 京都大火編」と「るろうに剣心 伝説の最期編」がそれぞれ8月1日、9月13日に全国の劇場にて封切られる。
読み切りとして描かれるのは、映画にも登場する志々雄真実のエピソード。本編では「弱肉強食」を信条に掲げ国取りを目指した志々雄が、新作でどのような活躍を見せるのか期待しよう。
TVアニメ「幕末 Rock」 キャラ設定公開 公式サイトもリニューアルで革命まであと2ヵ月!
「Rockで日本を革命せよ!」、そんなコンセプトで新撰組と熱き志士たちが幕末を舞台に音楽で戦う、それが『幕末 Rock』だ。今年2月にPSP用ゲームソフトが発売、さらに2014年7月からのテレビアニメも決まっている。すでに多くの女性ファンを獲得、ブームの兆しをみせている。
この『幕末 Rock』のテレビアニメのメインキャラクターのキャラ設定が、このほど公開された。坂本龍馬、高杉晋作、桂小五郎、土方歳三、沖田総司の5人である。アニメでは一体、どう描かれるのか?ファンであれば見逃せないだろう。
テレビアニメのスタッフも注目されている。アニメ制作は、女性向けの作品に定評があるスタジオディーンが手がけている。そして、キャラクターデザインは石井明治さんが務めている。監督は『戦国BASARA』や『レンタルマギカ』の川崎逸朗さん、こちらも期待を高めるのに十分だ。
作品は徳川幕府の「天歌(ヘブンズ・ソング)」により、泰平の世から民心が奪われた時代から始まる。「天歌」を歌う最高愛獲(トップ・アイドル)新選組、しかし幕府の支配を快く思わない者たちは、ロック魂を胸に立ち上がる。その中心に坂本龍馬がいた。
4月28日には、テレビアニメ公式サイトも一挙にリニューアルした。今後、7月の公開に向けて、情報発信をすることになる。ファンであれば、チェックを欠かせない。
そして、リニューアルに合わせて、電子瓦版の第1号配信を開始した。今後毎月配信を予定する。さらにCD発売記念として、ミュージックビデオの限定再公開も行っている。テレビ放送開始前に、これを楽しみたい。
『幕末 Rock』
http://bakumatsu.maql.co.jp/
[キャスト]
坂本龍馬: 谷山紀章
高杉晋作: 鈴木達央
桂小五郎: 森久保祥太郎
土方歳三: 森川智之
沖田総司: 小野賢章 ほか
『幕末 Rock』
(c)2014 MarvelousAQL Inc./幕末Rock製作委員会
| 10 | 2025/11 | 12 |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |